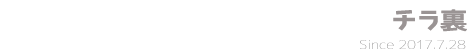上鳴
釣ったサカナ
釣ったサカナ
ナンパするお話。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
何もやることがない日曜日の昼の話。
正確には手つかずの課題がまだ一つ残っていたがこの場合の『やること』には含まれない。夜になってから眠たい目を擦ってこなさなければいけなくなると分かっていても、貴重な日曜日を課題で潰すというのは健全な高校生男子としては考えられないことだ。
そんなこんなで繰り出した、アミューズメントスポット。老若男女の主に若と女が集まる場所。
隣には相棒の峰田。
分かりやすく言えば、ナンパに来ている。
「なんでこんだけ女がいるのに、逆ナンが起きねえんだ」
峰田がぼやいた。
すでに連戦連敗を喫して身も心もボロボロ。吹きすさぶ冷たい風に鼻を啜って上鳴も乾いた笑いを浮かべた。峰田の言う『なんで』っていう問いの先は考えないようにした。答えが分かると絶望しか待っていないということだけは確かだからだ。
「……ていうかな、上鳴」
植え込みのレンガの上で平らになってしまいそうになっている尻をもぞもぞ動かしていると、峰田の声が意味ありげに途切れる。
「あそこでよ、さっきからずーーーーーっとナンパされてる奴さあ」
見れば峰田の視線は目の前の広場に力なく投げ出されている。広場には沢山の人が行き交っていてあそこと言われても峰田が指示しているものがどれなのかすぐには分からず、ぐるぐると視線を彷徨わせながら続きを待った。
「あれ、西岐じゃね?」
「――……は!?」
峰田の口から出た名前に脳みそが急速に回転し、目が本気を出して人混みを掻き分けた。
どうしてこんなに分かりやすい人物を見落としていたのやら。
確かにいる。
店の看板でやや影になっているところに。
そして、二人連れの男に手首を掴まれて何やら話しかけられている。
「――あぁもう、なぁにやってんだよ」
気付いた時には尻が浮き上がり人混みの中にダイブしていた。左右からの流れを真っ直ぐにぶった切る形で進む上鳴は、何人かと肩をぶつけて舌打ちされるが構わず看板の影へと急いだ。
長い前髪のせいで困っているんだかいないんだか分からない西岐が今にもどこかに連れ去られそうになっている。
自分でも自覚していない焦燥のようなものに突き動かされて手を伸ばした。
上鳴の指が細い腕をぐるっと一周。
初めて触れたその細さに、指先から痺れのようなものが伝播する。が、それは一瞬で、耳に雑踏の騒音が戻り西岐と男二人から視線を浴びる。
「すんません、こいつ俺のツレなんすけど、なにか?」
力を込めて引き寄せると、男二人はあからさまにゲッと嫌そうな顔をして互いに目配せするなり足早に立ち去った。心境はよーく分かる。ナンパしていた相手に連れが現れた時の気まずさと言ったら、もう……喩えようがない。
テリトリーを主張されて追い払われた二人の背中を哀れな目で見送りつつも、せいせいしてるもう一人の自分が唇を皮肉げにつり上げさせる。
「コッチ側って気持ちいいなあ〜」
腕を掴んでからこちら、ずっとぼんやり上鳴を見ていた西岐がやっと『上鳴を認識できました』とばかりに小さく「あ」と声を漏らす。
「でんきくん……」
「電気くんですよ、なにしてんの、れぇちゃん」
「えっと、参考書買いに……」
「そっかそっか。じゃあこっちおいで」
ひとまず峰田がいる元の場所へ連れて行こうと掴んでいる腕を引っ張る。参考書が入っているだろう本屋の袋がすでに手にぶら下がっているし、ここで別れればまた誰ぞに声をかけられるかもしれない。そう思ってのことだったが別段西岐も断るつもりはないらしく大人しく引っ張られて後ろを歩く。人の流れを横切る間、流されないように上鳴の腕に縋るように身を寄せられて、らしくもなく心臓が飛び跳ねた。
「あ、みねたくん」
「よお。男のくせに男にナンパされるって、もう才能だな」
「ほんとそれな」
植え込みに腰かけている峰田の姿が見えると西岐は小走りで駆けていく。
手から離れてしまったことに寂しさのようなものを感じて指をすり合わせながら峰田の調子に合わせて笑う。
とりわけ女に見えるという訳でもないし、絶世の美少年というほどでもないのにどういうわけか同性に好かれる傾向にある西岐。いや、正確には男女隔たり無く好かれるわけだが。男から言い寄られる時の熱は女性からのそれより高い。
「どうせなら女連れてこいって」
数少ない西岐にときめかない男・峰田はつまらなさそうに頬杖で頬を押しつぶしている。
だが、自分の言った言葉で何か思い至ったらしく、その丸い目をパチパチと瞬かせて西岐を見上げた。
「あ、そうだよ。お前、女連れてこい」
「おいおい、峰田。何言って……」
「西岐ならナンパくらいチョロいだろうがよ!」
名案だとばかりにだんだんと興奮して峰田の鼻息が荒くなっていく。いつもながら制御不能の欲望マシンと化して西岐に指を突きつけグイグイと迫る。
「な、なんぱ?」
「女の子に一緒にお茶しましょーっつって連れてくればいいんだよ!」
「え、で、でも、なんで」
「仲良ししたいからに決まってんだろ? お前もオスなら分かれ」
峰田の勢いに押されて西岐はすっかりたじたじになり、持っている本屋の袋をグシャッと抱きかかえて後ずさった。
「で……で、でも、俺」
「でもでもでもでもウルセーな」
「し、知らない人……に、話しかけるの、こわい」
及び腰になった西岐を追いかけるように峰田が植え込みから飛び降りて再び指さす。
「おい、オイラ達はヒーロー志望だろ。こんなことが苦手でどうすんだ。知らない奴に話しかけてコミュニケーションを取らなきゃなんねぇ場面なんてヒーローやってりゃザラだろうが。何気なく訪れた知らない土地で事件が起きて知らないヒーローとチームアップしなきゃならねぇってなったらどうする? プルスウルトラしろよ」
こういう時の峰田は本当にきれっきれだ。それっぽい内容をそれっぽい口調で語ってみせている。その語り口調は存外説得力があるものだから、理解力の乏しい西岐なぞあっさりと丸め込まれてしまう。
「そ……そっか」
「れぇちゃん、ただのナンパだからね、騙されちゃいけない」
「上鳴ぃいッ、裏切る気か」
「あのなぁ……さすがに多方面から殺されるぜ」
西岐の保護者は多い。もしバレでもしたらタダでは済まないだろう。
後先考えずに突っ走っては毎度痛い目を見ているのに、いまだに学習しないのか、学習したら負けと思っているのか。欲望への忠誠心は見事だがさすがに上鳴にはそこまで見習えない。
ただ、この時の上鳴は、少し西岐の素直さを侮っていた。
「うん、わかった。俺、行ってくる」
「……へ?」
「お!」
止める暇もなくバッと身を翻して西岐が人混みの中へと消えていった。
上鳴の情けない声と、峰田の期待に満ちた声だけがその場に残されていた。
およそ数分後。
戻ってきた西岐と共に女性三人組が連れ立って歩いてきた。西岐をよく知らない者でも一目でアンバランスに思うほど、見るからにきつそうで年上であろう美人な三人だ。よくこの人たちに声をかけたなと感心してしまう。
ぎりぎり高校生なのか、大学生なのか。化粧のせいで判別がつかない。
「すげー上玉じゃねえか。よくやった西岐」
「う、うん」
「どっか店入ろうぜ」
峰田は大喜びで食いついて近くの店へと促す。ファーストフード店で特に異論はないらしく女性三人はニコニコ愛想よくついてきた。
入口からすぐの注文カウンターを見て西岐が僅かにたじろいだ。
「れぇちゃん、何食べたい?」
「あ……えっと……あ」
「プレミアムチョコパイがあるよ」
「あ、うん……」
「じゃ、俺が買うかられぇちゃんは席とっといて」
「わかった」
西岐の困惑を見越した上鳴が助け船を出すと素直にコクコクと頷いて賑わう店内へと足を向けた。ほっと安心した気配が背中から感じ取れて上鳴の頬も緩む。
「え、なになに? 西岐くん、だっけ、どうしたの?」
もう早々に名前を把握しているらしい巻き毛の女の子が、注文もせず席へと向かった西岐を不思議そうに目で追いかける。
「れぇちゃん、こういう店に慣れてなくってさ」
「アイツ箱入りだもんなぁ」
細かい家庭の事情は把握していなくとも西岐が世間知らずだということは最早クラス全員が知るところとなっている。女の子たちに弁明する上鳴の言葉を拾って峰田が呆れたように溜息をついた。
箱入りという言葉に女の子たちのボルテージが上がるのが手に取るように分かる。
「あの子、お金持ちなんだ」
「多分なあ〜、金銭感覚もおかしいぜ」
適当に言葉を投げてから空いたカウンターに注文すべく向かった峰田の背後で、女の子たちが目の色を変えているのを上鳴だけは見ていた。
「雄英体育祭トップ!」
「お金持ち!」
「しかもチョロそう!」
口々に呟く声が上鳴には丸聞こえだ。
なるほど、雄英体育祭の活躍を知っていてホイホイついてきたらしい。
というか隣に上鳴がいるというのにこんなあからさまな態度をとるということは上鳴はまるっきり眼中にないということだろう。上鳴にしても全く好みのタイプではなかったから構わないが。
何故かさっきから胸のあたりがムカムカして仕方がない。
注文を終え、チョコパイとハンバーガーとミルクティーとコーラをトレーに載せて西岐がちょこんと座っている窓際の席に向かう。ベンチシートがL字型になっていて長いほうへ女の子が三人横並びに座り、短い方には西岐、峰田と上鳴は個別の椅子へと腰を下ろした。
「ねえねえ、西岐くんってれぇちゃんって呼ばれてるの?」
「あたしらもれぇちゃんって呼びたーい」
「いいよねー?」
席に座るなり臨戦態勢になる三人から逃れようと、西岐はベンチから落ちそうなほど横にずれ、それでも断る理由が見つけられなかったのか黙って頷きを返している。
「れぇちゃんは彼女いる?」
なんて直球なんだ。
口いっぱいに含んだコーラを一気に飲み込んでしまいグビリと喉が音を立てた。
そんなの自分だって知らない。
咳き込む上鳴に女の子たちの煩わし気な視線が向けられるが、上鳴は西岐だけを凝視していた。
「い、いない、けど……」
「そーなんだーっ!」
「オイラも今フリーだぜ」
「ソーナンダー」
西岐と峰田への返事の温度差が顕著だ。西岐の手前もあってか峰田を無視したりはしないものの相手にしていませんというのが態度に出すぎているのだが、ただ、雑な扱いに慣れている峰田はそんな態度も気にならないのかニヤニヤデレデレと表情が崩れ切っている。
「どういう子が好きなの?」
「そうだな、しいて言えばムチムチがタイプ」
「年上好き?」
「大好物だぜ」
全くへこたれる様子もなく女の子たちが西岐へ投げる質問に答えていく峰田。彼の鋼の精神はある種の尊敬に値する。合いの手のように峰田が口を挟むものだから女の子たちも無視できずにグッと口をつぐんで睨みつける。
西岐は集中砲火を免れてチョコパイへと手を伸ばした。
ぼろぼろと崩れやすいパイがテーブルに零れてしまわないようにトレーへと身を寄せて齧っている姿はこの場にいる誰より可愛い。
「いやいや、そんな馬鹿な」
パタパタと宙を掻く。
美人揃い踏みを目の前にしてこの考えは危うい。
「暖房あつい?」
「あー……うん、ちょっとな、トイレ行ってくるわ」
不審そうな三対の目と不思議そうな西岐の目に晒されて上鳴は苦笑を浮かべて立ち上がった。峰田は一瞥もくれない。さすがだ。
特に催したわけでもないからトイレには向かわず、店の外に出てビルの端に寄り掛かって外気で頭を冷やす。上着なしでは結構こたえる寒さだが身を縮こませて暖房で温められた息を深々と吐き出した。
折角ナンパに繰り出したというのになんとも情けない。気持ちが女の子の方に全く傾かないだなんて。
窓際の席は上鳴が立っている場所からも遠目だがよく見える。必死に西岐へアプローチをかける女の子たちとそこへ食いつく峰田がどうにも笑える。それぞれが全然噛み合ってない。しかも西岐はチョコパイとミルクティーでほっこりし始めて多分女の子たちの話の半分も聞いていないだろう。
「あーー……くっそ……可愛いんだよなあもう」
湧きたつ衝動に耐え切れずガシガシと髪を掻き混ぜる。
ステータスでしか見ていないような女の子たちがいちいち西岐に話しかけるたびにイライラとするのは一体なんでなのか、分かるようで分かりたくない。これでは西岐の一挙一動に右往左往するクラスメイト達を笑えないではないか。
「……て、あれ?」
わずかに目を離した間に窓から見える席に座る人物が三人消えている。峰田と女の子二人が足りない。近くにある入り口から聞き覚えのある声が聞こえる。レジで女の子二人に挟まれてデレデレしながら峰田が何やら注文していた。
もう一度席に目をやって、西岐の肩に女の子の手が置かれているのが見えて、あ、これは駄目なやつだと察したときには女の子の唇が西岐に触れた。
バチッと火花が散って思考がショートする。
大股で店内を突っ切り席へと戻り、呆けている西岐の腕を掴んで引っ張り上げる。
「――悪いっすけど、俺ら用事思い出したんですんません」
投げつけてやりたかった罵詈雑言をどうにか飲み込んで笑顔を取り繕う。驚いている西岐と二人分の上着と荷物を掴んで、西岐の足がもつれるのも気遣う余裕もなく店を出た。
ずんずんと真っ直ぐ歩く上鳴と引きずられるようにしてついてくる西岐に周りが避けて道を作る。
別にどこに向かっているという訳でもなかったのだが、人通りの少ない細い道まで来て、西岐の痛そうな声がやっと耳に届いて立ち止まり、手を離した。あんな細い腕を遠慮なしに掴んで引っ張ったからもしかしたら痕になってしまったかもしれない。それくらい加減が出来てなかった。
「ごめん、なんか俺、頭キテ……なんかもう、ほんとごめんなんだけど……なんだあのオンナッ」
謝っているのにどんどん苛立ちが募っていく。本人にぶつけられなかった分までもが口から噴き出す。
「あ……あの、ごめん、ね?」
「や、れぇちゃん悪くないから。まあ無防備すぎだけど……でもそれがいいっていうか、ツケ込むほうが悪いっていうか」
珍しく毒吐く上鳴に驚きつつも気遣わしげに謝ってくる西岐を見て、首を振って暴れている感情を黙らせようと試みる。
そうして視線を下に向けたことで西岐の上着も自分が持っていることを思い出し、手荷物と共に手渡す。西岐は大き目の服が好きなのかいつもサイズが合っていない。今羽織ってファスナーを締めている上着もまた然りで、そのダボダボ感が上鳴の感情を煽る。
「れぇちゃんが可愛いからさぁ、俺嫉妬とかしちゃうんだよ……困るわ」
もう、自覚せざるを得ない。
余裕ぶって冷やかす側にいたはずなのに、いつの間にこんな深みに嵌まっていたのやら。
不思議そうにきょとんとしないでくれ、可愛い。
「れぇちゃん、ごめん、先に謝るね」
他人に怒っておきながら同じことをしようとしている。分かっていても衝動が押さえられない。
大きめの上着に包まれた西岐の身体を更に包むように腕の中に引っ張り込んで、「えっ」と小さく開いた口を塞ぐ。さっき女の子が触れたものを上書きする。ただ触れているだけだというのにその柔らかい感触に頭がくらくらする。
もっとあれやこれやしたいという欲望が渦巻くが、今いる場所が往来だということは忘れていなかった。
数秒にも数分にも感じられたキスは触れるだけにとどまって、そっと離れる。
「れぇちゃん、あのさ」
ああ、どう言おう。どう取り繕おう。
ぐるぐると考えが頭を駆け巡る。
腕から解放しても西岐ははくはくと口を開閉するだけで何もリアクションが取れていない。きっと今身に起きたことが理解しきれていないに違いない。
ならばここはこう言っておこう。
言葉を選び、上鳴は目を細めて西岐の顔を覗き込む。
「俺と一緒にお茶しませんか」
多分、きっと、今までで一番うまくナンパできる気がしていた。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
何もやることがない日曜日の昼の話。
正確には手つかずの課題がまだ一つ残っていたがこの場合の『やること』には含まれない。夜になってから眠たい目を擦ってこなさなければいけなくなると分かっていても、貴重な日曜日を課題で潰すというのは健全な高校生男子としては考えられないことだ。
そんなこんなで繰り出した、アミューズメントスポット。老若男女の主に若と女が集まる場所。
隣には相棒の峰田。
分かりやすく言えば、ナンパに来ている。
「なんでこんだけ女がいるのに、逆ナンが起きねえんだ」
峰田がぼやいた。
すでに連戦連敗を喫して身も心もボロボロ。吹きすさぶ冷たい風に鼻を啜って上鳴も乾いた笑いを浮かべた。峰田の言う『なんで』っていう問いの先は考えないようにした。答えが分かると絶望しか待っていないということだけは確かだからだ。
「……ていうかな、上鳴」
植え込みのレンガの上で平らになってしまいそうになっている尻をもぞもぞ動かしていると、峰田の声が意味ありげに途切れる。
「あそこでよ、さっきからずーーーーーっとナンパされてる奴さあ」
見れば峰田の視線は目の前の広場に力なく投げ出されている。広場には沢山の人が行き交っていてあそこと言われても峰田が指示しているものがどれなのかすぐには分からず、ぐるぐると視線を彷徨わせながら続きを待った。
「あれ、西岐じゃね?」
「――……は!?」
峰田の口から出た名前に脳みそが急速に回転し、目が本気を出して人混みを掻き分けた。
どうしてこんなに分かりやすい人物を見落としていたのやら。
確かにいる。
店の看板でやや影になっているところに。
そして、二人連れの男に手首を掴まれて何やら話しかけられている。
「――あぁもう、なぁにやってんだよ」
気付いた時には尻が浮き上がり人混みの中にダイブしていた。左右からの流れを真っ直ぐにぶった切る形で進む上鳴は、何人かと肩をぶつけて舌打ちされるが構わず看板の影へと急いだ。
長い前髪のせいで困っているんだかいないんだか分からない西岐が今にもどこかに連れ去られそうになっている。
自分でも自覚していない焦燥のようなものに突き動かされて手を伸ばした。
上鳴の指が細い腕をぐるっと一周。
初めて触れたその細さに、指先から痺れのようなものが伝播する。が、それは一瞬で、耳に雑踏の騒音が戻り西岐と男二人から視線を浴びる。
「すんません、こいつ俺のツレなんすけど、なにか?」
力を込めて引き寄せると、男二人はあからさまにゲッと嫌そうな顔をして互いに目配せするなり足早に立ち去った。心境はよーく分かる。ナンパしていた相手に連れが現れた時の気まずさと言ったら、もう……喩えようがない。
テリトリーを主張されて追い払われた二人の背中を哀れな目で見送りつつも、せいせいしてるもう一人の自分が唇を皮肉げにつり上げさせる。
「コッチ側って気持ちいいなあ〜」
腕を掴んでからこちら、ずっとぼんやり上鳴を見ていた西岐がやっと『上鳴を認識できました』とばかりに小さく「あ」と声を漏らす。
「でんきくん……」
「電気くんですよ、なにしてんの、れぇちゃん」
「えっと、参考書買いに……」
「そっかそっか。じゃあこっちおいで」
ひとまず峰田がいる元の場所へ連れて行こうと掴んでいる腕を引っ張る。参考書が入っているだろう本屋の袋がすでに手にぶら下がっているし、ここで別れればまた誰ぞに声をかけられるかもしれない。そう思ってのことだったが別段西岐も断るつもりはないらしく大人しく引っ張られて後ろを歩く。人の流れを横切る間、流されないように上鳴の腕に縋るように身を寄せられて、らしくもなく心臓が飛び跳ねた。
「あ、みねたくん」
「よお。男のくせに男にナンパされるって、もう才能だな」
「ほんとそれな」
植え込みに腰かけている峰田の姿が見えると西岐は小走りで駆けていく。
手から離れてしまったことに寂しさのようなものを感じて指をすり合わせながら峰田の調子に合わせて笑う。
とりわけ女に見えるという訳でもないし、絶世の美少年というほどでもないのにどういうわけか同性に好かれる傾向にある西岐。いや、正確には男女隔たり無く好かれるわけだが。男から言い寄られる時の熱は女性からのそれより高い。
「どうせなら女連れてこいって」
数少ない西岐にときめかない男・峰田はつまらなさそうに頬杖で頬を押しつぶしている。
だが、自分の言った言葉で何か思い至ったらしく、その丸い目をパチパチと瞬かせて西岐を見上げた。
「あ、そうだよ。お前、女連れてこい」
「おいおい、峰田。何言って……」
「西岐ならナンパくらいチョロいだろうがよ!」
名案だとばかりにだんだんと興奮して峰田の鼻息が荒くなっていく。いつもながら制御不能の欲望マシンと化して西岐に指を突きつけグイグイと迫る。
「な、なんぱ?」
「女の子に一緒にお茶しましょーっつって連れてくればいいんだよ!」
「え、で、でも、なんで」
「仲良ししたいからに決まってんだろ? お前もオスなら分かれ」
峰田の勢いに押されて西岐はすっかりたじたじになり、持っている本屋の袋をグシャッと抱きかかえて後ずさった。
「で……で、でも、俺」
「でもでもでもでもウルセーな」
「し、知らない人……に、話しかけるの、こわい」
及び腰になった西岐を追いかけるように峰田が植え込みから飛び降りて再び指さす。
「おい、オイラ達はヒーロー志望だろ。こんなことが苦手でどうすんだ。知らない奴に話しかけてコミュニケーションを取らなきゃなんねぇ場面なんてヒーローやってりゃザラだろうが。何気なく訪れた知らない土地で事件が起きて知らないヒーローとチームアップしなきゃならねぇってなったらどうする? プルスウルトラしろよ」
こういう時の峰田は本当にきれっきれだ。それっぽい内容をそれっぽい口調で語ってみせている。その語り口調は存外説得力があるものだから、理解力の乏しい西岐なぞあっさりと丸め込まれてしまう。
「そ……そっか」
「れぇちゃん、ただのナンパだからね、騙されちゃいけない」
「上鳴ぃいッ、裏切る気か」
「あのなぁ……さすがに多方面から殺されるぜ」
西岐の保護者は多い。もしバレでもしたらタダでは済まないだろう。
後先考えずに突っ走っては毎度痛い目を見ているのに、いまだに学習しないのか、学習したら負けと思っているのか。欲望への忠誠心は見事だがさすがに上鳴にはそこまで見習えない。
ただ、この時の上鳴は、少し西岐の素直さを侮っていた。
「うん、わかった。俺、行ってくる」
「……へ?」
「お!」
止める暇もなくバッと身を翻して西岐が人混みの中へと消えていった。
上鳴の情けない声と、峰田の期待に満ちた声だけがその場に残されていた。
およそ数分後。
戻ってきた西岐と共に女性三人組が連れ立って歩いてきた。西岐をよく知らない者でも一目でアンバランスに思うほど、見るからにきつそうで年上であろう美人な三人だ。よくこの人たちに声をかけたなと感心してしまう。
ぎりぎり高校生なのか、大学生なのか。化粧のせいで判別がつかない。
「すげー上玉じゃねえか。よくやった西岐」
「う、うん」
「どっか店入ろうぜ」
峰田は大喜びで食いついて近くの店へと促す。ファーストフード店で特に異論はないらしく女性三人はニコニコ愛想よくついてきた。
入口からすぐの注文カウンターを見て西岐が僅かにたじろいだ。
「れぇちゃん、何食べたい?」
「あ……えっと……あ」
「プレミアムチョコパイがあるよ」
「あ、うん……」
「じゃ、俺が買うかられぇちゃんは席とっといて」
「わかった」
西岐の困惑を見越した上鳴が助け船を出すと素直にコクコクと頷いて賑わう店内へと足を向けた。ほっと安心した気配が背中から感じ取れて上鳴の頬も緩む。
「え、なになに? 西岐くん、だっけ、どうしたの?」
もう早々に名前を把握しているらしい巻き毛の女の子が、注文もせず席へと向かった西岐を不思議そうに目で追いかける。
「れぇちゃん、こういう店に慣れてなくってさ」
「アイツ箱入りだもんなぁ」
細かい家庭の事情は把握していなくとも西岐が世間知らずだということは最早クラス全員が知るところとなっている。女の子たちに弁明する上鳴の言葉を拾って峰田が呆れたように溜息をついた。
箱入りという言葉に女の子たちのボルテージが上がるのが手に取るように分かる。
「あの子、お金持ちなんだ」
「多分なあ〜、金銭感覚もおかしいぜ」
適当に言葉を投げてから空いたカウンターに注文すべく向かった峰田の背後で、女の子たちが目の色を変えているのを上鳴だけは見ていた。
「雄英体育祭トップ!」
「お金持ち!」
「しかもチョロそう!」
口々に呟く声が上鳴には丸聞こえだ。
なるほど、雄英体育祭の活躍を知っていてホイホイついてきたらしい。
というか隣に上鳴がいるというのにこんなあからさまな態度をとるということは上鳴はまるっきり眼中にないということだろう。上鳴にしても全く好みのタイプではなかったから構わないが。
何故かさっきから胸のあたりがムカムカして仕方がない。
注文を終え、チョコパイとハンバーガーとミルクティーとコーラをトレーに載せて西岐がちょこんと座っている窓際の席に向かう。ベンチシートがL字型になっていて長いほうへ女の子が三人横並びに座り、短い方には西岐、峰田と上鳴は個別の椅子へと腰を下ろした。
「ねえねえ、西岐くんってれぇちゃんって呼ばれてるの?」
「あたしらもれぇちゃんって呼びたーい」
「いいよねー?」
席に座るなり臨戦態勢になる三人から逃れようと、西岐はベンチから落ちそうなほど横にずれ、それでも断る理由が見つけられなかったのか黙って頷きを返している。
「れぇちゃんは彼女いる?」
なんて直球なんだ。
口いっぱいに含んだコーラを一気に飲み込んでしまいグビリと喉が音を立てた。
そんなの自分だって知らない。
咳き込む上鳴に女の子たちの煩わし気な視線が向けられるが、上鳴は西岐だけを凝視していた。
「い、いない、けど……」
「そーなんだーっ!」
「オイラも今フリーだぜ」
「ソーナンダー」
西岐と峰田への返事の温度差が顕著だ。西岐の手前もあってか峰田を無視したりはしないものの相手にしていませんというのが態度に出すぎているのだが、ただ、雑な扱いに慣れている峰田はそんな態度も気にならないのかニヤニヤデレデレと表情が崩れ切っている。
「どういう子が好きなの?」
「そうだな、しいて言えばムチムチがタイプ」
「年上好き?」
「大好物だぜ」
全くへこたれる様子もなく女の子たちが西岐へ投げる質問に答えていく峰田。彼の鋼の精神はある種の尊敬に値する。合いの手のように峰田が口を挟むものだから女の子たちも無視できずにグッと口をつぐんで睨みつける。
西岐は集中砲火を免れてチョコパイへと手を伸ばした。
ぼろぼろと崩れやすいパイがテーブルに零れてしまわないようにトレーへと身を寄せて齧っている姿はこの場にいる誰より可愛い。
「いやいや、そんな馬鹿な」
パタパタと宙を掻く。
美人揃い踏みを目の前にしてこの考えは危うい。
「暖房あつい?」
「あー……うん、ちょっとな、トイレ行ってくるわ」
不審そうな三対の目と不思議そうな西岐の目に晒されて上鳴は苦笑を浮かべて立ち上がった。峰田は一瞥もくれない。さすがだ。
特に催したわけでもないからトイレには向かわず、店の外に出てビルの端に寄り掛かって外気で頭を冷やす。上着なしでは結構こたえる寒さだが身を縮こませて暖房で温められた息を深々と吐き出した。
折角ナンパに繰り出したというのになんとも情けない。気持ちが女の子の方に全く傾かないだなんて。
窓際の席は上鳴が立っている場所からも遠目だがよく見える。必死に西岐へアプローチをかける女の子たちとそこへ食いつく峰田がどうにも笑える。それぞれが全然噛み合ってない。しかも西岐はチョコパイとミルクティーでほっこりし始めて多分女の子たちの話の半分も聞いていないだろう。
「あーー……くっそ……可愛いんだよなあもう」
湧きたつ衝動に耐え切れずガシガシと髪を掻き混ぜる。
ステータスでしか見ていないような女の子たちがいちいち西岐に話しかけるたびにイライラとするのは一体なんでなのか、分かるようで分かりたくない。これでは西岐の一挙一動に右往左往するクラスメイト達を笑えないではないか。
「……て、あれ?」
わずかに目を離した間に窓から見える席に座る人物が三人消えている。峰田と女の子二人が足りない。近くにある入り口から聞き覚えのある声が聞こえる。レジで女の子二人に挟まれてデレデレしながら峰田が何やら注文していた。
もう一度席に目をやって、西岐の肩に女の子の手が置かれているのが見えて、あ、これは駄目なやつだと察したときには女の子の唇が西岐に触れた。
バチッと火花が散って思考がショートする。
大股で店内を突っ切り席へと戻り、呆けている西岐の腕を掴んで引っ張り上げる。
「――悪いっすけど、俺ら用事思い出したんですんません」
投げつけてやりたかった罵詈雑言をどうにか飲み込んで笑顔を取り繕う。驚いている西岐と二人分の上着と荷物を掴んで、西岐の足がもつれるのも気遣う余裕もなく店を出た。
ずんずんと真っ直ぐ歩く上鳴と引きずられるようにしてついてくる西岐に周りが避けて道を作る。
別にどこに向かっているという訳でもなかったのだが、人通りの少ない細い道まで来て、西岐の痛そうな声がやっと耳に届いて立ち止まり、手を離した。あんな細い腕を遠慮なしに掴んで引っ張ったからもしかしたら痕になってしまったかもしれない。それくらい加減が出来てなかった。
「ごめん、なんか俺、頭キテ……なんかもう、ほんとごめんなんだけど……なんだあのオンナッ」
謝っているのにどんどん苛立ちが募っていく。本人にぶつけられなかった分までもが口から噴き出す。
「あ……あの、ごめん、ね?」
「や、れぇちゃん悪くないから。まあ無防備すぎだけど……でもそれがいいっていうか、ツケ込むほうが悪いっていうか」
珍しく毒吐く上鳴に驚きつつも気遣わしげに謝ってくる西岐を見て、首を振って暴れている感情を黙らせようと試みる。
そうして視線を下に向けたことで西岐の上着も自分が持っていることを思い出し、手荷物と共に手渡す。西岐は大き目の服が好きなのかいつもサイズが合っていない。今羽織ってファスナーを締めている上着もまた然りで、そのダボダボ感が上鳴の感情を煽る。
「れぇちゃんが可愛いからさぁ、俺嫉妬とかしちゃうんだよ……困るわ」
もう、自覚せざるを得ない。
余裕ぶって冷やかす側にいたはずなのに、いつの間にこんな深みに嵌まっていたのやら。
不思議そうにきょとんとしないでくれ、可愛い。
「れぇちゃん、ごめん、先に謝るね」
他人に怒っておきながら同じことをしようとしている。分かっていても衝動が押さえられない。
大きめの上着に包まれた西岐の身体を更に包むように腕の中に引っ張り込んで、「えっ」と小さく開いた口を塞ぐ。さっき女の子が触れたものを上書きする。ただ触れているだけだというのにその柔らかい感触に頭がくらくらする。
もっとあれやこれやしたいという欲望が渦巻くが、今いる場所が往来だということは忘れていなかった。
数秒にも数分にも感じられたキスは触れるだけにとどまって、そっと離れる。
「れぇちゃん、あのさ」
ああ、どう言おう。どう取り繕おう。
ぐるぐると考えが頭を駆け巡る。
腕から解放しても西岐ははくはくと口を開閉するだけで何もリアクションが取れていない。きっと今身に起きたことが理解しきれていないに違いない。
ならばここはこう言っておこう。
言葉を選び、上鳴は目を細めて西岐の顔を覗き込む。
「俺と一緒にお茶しませんか」
多分、きっと、今までで一番うまくナンパできる気がしていた。
create 2018/02/15
update 2018/02/15
update 2018/02/15