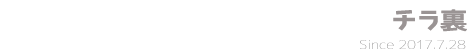轟
カタバミ
カタバミ
お母さんのお見舞いに行くお話。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
雄英体育祭の後、何年も会っていなかった母の見舞いに行った。謝りたいとか救けたいとか前に進みたいとか色々、全部が嘘という訳ではないけど、本当のところは単純に会いたくなったからだった。我慢するのが辛いほど会いたいという気持ちが膨らんだ理由は二つ。
緑谷に揺さぶられた、ヒーローになりたいという情熱。
そして……――。
時間の確認と連絡待ちを担っていたスマホが小刻みに震えて、指をスライドさせてから耳に当てる。
「……ああ、おはよう。……うん、……じゃあそこに行くから、待ってろ」
挨拶と道に迷っているということが耳に伝えられて、轟は手短に言葉を返すと通話を繋げたまま今聞いた場所へと足を向けた。駅の階段を足早に駆け上り、いくつもの出口に分岐している広いコンコースの真ん中のエスカレータの横、そこに立っている西岐が轟の姿を見つけて手を振る。
互いが足を前に出して距離を縮め、似たような動作で繋がっていた通話が切られた。
「おはよぉ、待たせたかな」
「いや……俺が早く着きすぎた」
まるで恋人同士のデートの待ち合わせのような会話だ、と一瞬思って熱くなる耳を掻いて誤魔化す。
病院のある方の出口へ身体を向けると西岐も横に並んで歩きだし、西岐の手にぶら下がっている紙袋がカサカサと音を立てた。
体育祭で揺り動かされて数年ぶりに顔を合わせた母に話したのは、家のこと、学校のこと。重苦しいような緊張のある沈黙を何度も挟んで、ぽつり、ぽつり、と時間をかけて色々なことを話した。言わなくてもいいことまで言った気がするし、言いたかったことが言えなかった気もする。
その中で、思わず口から零れ落ちたのが、西岐の名前だった。
何かを話す端々に西岐が出てくる。
轟の中の父の呪縛を解いてくれたのは西岐じゃない。緑谷だ。緑谷の真っ直ぐな声が轟を揺さぶってここに連れてきてくれた。だけど、母と対峙した時、手が震える轟の背を押すように心の中に一緒にいてくれたのは西岐だった。
『大丈夫……って言ってもらったんだ』
どういう顔でそう呟いたのか。聞きながらしばらく噛みしめるように微笑んでいた母が轟の言葉が途切れると、会ってみたいと言った。
そうしてそれを轟が西岐に伝えて、西岐は快く頷いてくれて、職場体験を経て一か月後に期末試験を控えた今日、やっと実現することとなったのだ。この間に轟は何度も見舞いに訪れていて、いつ西岐は来られるのかと聞かれていたのが、やっと会ってもらえる。いつもは緊張してしまう病室までの足取りがいくらか軽い。
「あ、待って……どうしよう、緊張する」
病室の扉に手をかけた轟を西岐が隣で制止する。紙袋を両手で必要以上にギュウっと握ってしまっている。
「……大丈夫」
いつか、西岐が掛けてくれた言葉を返すように言って肩に手を置く。きっと轟が口にした言葉の意味は伝わらないのだろうけれど。
扉を開いた先に、いつもどおり待ち構えていた母が笑みを向けてくれる。けれどそれが、隣に並び立つ西岐を見て僅かによそ行きの表情へと変化した。自然な、"母親"らしい変化だった。
「もしかして、西岐くん?」
「はい、あの……西岐れぇです」
「うっそ、西岐くん? 体育祭で優勝してた?」
扉の陰になった洗面台の前から姉の明るい声が聞こえる。扉が閉じられると案の定、母にそっくりな姉が顔を覗かせる。キラキラと目が輝いて見えるのは目の錯覚ではない。興奮気味に拳を握っている。
「焦凍、蹴られて場外になったよね」
「……やめろ」
あれが心底痛快だったらしい。録画した映像を繰り返し見ては死ぬほど笑われた。
蹴った本人は轟の家族を前にして焦ったようで、うまく言葉に出来ず口をパクパクと開閉しては紙袋がより一層歪んでベキッと音を立てる。
「気にしなくていいから」
西岐の肩を押して奥に促す。
ベッドに腰かけた母の正面にはいつも轟が使っている丸椅子が置かれていて西岐に座るように勧めた。
「あ……の、これ」
緊張して引き攣った口が普段の何倍も聞き取りにくい小さな声を紡ぐ。表面が折れ曲がり皺になった紙袋から平たい箱を取り出して母へと差し出した。包装紙には有名和菓子店の名前と『くず餅』の文字が書かれている。以前、保須の病院に見舞いに訪れた時、同じものを選んで手渡されたということがあった。ぶら下げていた紙袋からして何となく嫌な予感がしていたが、よもや未だ父に囚われているのであろう母に対して父の好物を持ってこられるとは……。
母の反応を想像して凍り付く轟の視界の先で、母は笑みを深くした。
「ありがとう」
社交辞令なのか本当に気にしていないのか判断の難しい、静かな笑顔で箱を受け取る。
西岐は一度きゅっと口を引き結ぶ。
「俺、くず餅すきなんです」
今度はしっかりとした声で告げられた言葉に、轟は何故西岐がそれを選んだのか分かってしまった。母も同じだったのか、小さく頷く。
「ええ、私もよ」
その答えを聞いて轟の胸がギュッと締め付けられる。
心の底から嬉しそうな笑みを浮かべた西岐は丸椅子ではなく母の隣に腰かけ、母と姉から投げられる問いに答えを返しては寒々しい病室の空気を変えていく。
「ほんとに、とどろきくんって凄くって、一瞬で凍らせちゃったからオールマイトさんがこれじゃ訓練にならないなあって」
「……まあ」
「とどろきくんはね、お昼ごはんいっつも、お蕎麦で」
「……あら」
「それでね昨日はね」
「……なんだこれ、物凄く恥ずかしいぞ……」
このメンツで話す話題となれば大体は轟自身のことになる。問われるまでもなく西岐は次々と学校での轟の様子を語って聞かせる。話すつもりがなかったこと、自覚していなかったことまで母の耳に入っていく。纏まりがなくて、要領を得ない話し方でも母と姉は楽しいのか、どんどんと引き込まれるように表情が崩れていく。
西岐には不思議な魅力がある。そこにいて、言葉を発して、表情を変える。その一つ一つが周りの心を揺らす。
そんな彼が自分のことを我が事のように嬉しそうに話すのだから照れるやら恥ずかしいやら、居たたまれない。身の置き場のなさに轟は壁へめり込むように寄り掛かった。
結局、誰も座らず空いていた丸椅子に腰かけた姉が轟にからかうような視線を向ける。
「焦凍、そんなに凄いんだ?」
「はい」
「じゃあクラスで一番凄いのって誰?」
「は? 何聞いてんだ」
唐突に投げられた姉の問いに轟は目を瞠った。
西岐の口が素直に開く。
けたたましい音を立てて足を踏み込み開いたその口を手で覆う。
「――ッんぐ」
「それは駄目だ……さすがに」
誰の名前が出ても平静でいられない。たとえそれが自分の名前だったとしても、だ。
発音しそこなった声が手のひらの中で潰れる。もう片方の手が西岐の丸い後頭部を押さえ、勢い余って膝がベッドの縁にぶつかる。
さらっと前髪が流れて隙間から驚きに丸くなった西岐の目が覗く。
同じく丸い目が二人分、向けられている。
「……あ、悪い」
ぎこちない動作で手のひらを剥がし後ろに後ずさる。誰かの名前を出される云々以前にすでにこれが失態だ。
西岐の口を塞ごうと足を踏み出したことで母との距離もいつになく近くなってしまい、じっと見上げてはクスッと笑われて頬が熱を持つ。
「ちょっと、落ち着きなよ」
「……変なこと聞くからだろ」
姉からもニヤニヤした笑みを向けられて完全に顔から火を噴く。
壁と一体化したい気持ちになってへばりつく。ヒヤリとした壁が熱くなった顔には心地いい。
それでも視線が西岐に向けられているのは彼が母と接するところをしっかり見ていたいという思いがあるからだ。自分が大切に思う存在に母がどういう顔をするのか見てみたかった。小さな子供が自分のとっておきを自慢するような気持ち。
轟のさっきの行動はあっさりと押し流されて、何事も無かったかのように三人の会話が再開される。
自分のことをあまり話すことのない西岐だが聞かれれば何でも淀みなく答え、絶え間なく楽しそうな笑みを口元に浮かべていた。
どれほど経ったのか、不意に西岐が自分の喉に手を当てた。
「あ……俺、ちょっと飲み物買ってきます」
言うが早いか立ち上がり扉へ向かう西岐に母が「それなら」と声をかけようとした。冷蔵庫に買い置きがあると言おうとしたのだろう。それを轟は手のひらをかざすことで制して西岐を見送る。
「疲れたのかもしれない。あいつ、あんなに喋るほうじゃないんだ」
西岐なりにいろいろと気を遣ってくれていることはずっと伝わってきていた。ベッドの端に置かれたままになっているくず餅の箱を見て目を細めると、その視界の中で母の手が優しい手つきで包装紙の文字をなぞる。
「……やさしい子ね」
「そうだね」
母の言葉を姉が拾って頷く。
「あんな焦凍の顔、はじめて見た」
すっと睫毛を伏せるように細めた目が弓なりになって、儚げな母の顔立ちが柔らかく穏やかに彩られる。こういう表情をきっと"慈しみ"というのだろうと思った。
程なくして西岐が病室に戻ってくる。どうやら売店まで行って全員分を買ってきたらしい。手にぶら下げた袋からお茶のペットボトルを取り出して母と姉にそれぞれ手渡す。壁に寄り掛かった轟の前に来てお茶のペットボトルを持ったまま、もう一度手を袋に突っ込む。出てきたのは見覚えのある牛のイラストが描かれた紙パック。以前、母がお見舞いに来る轟の為に買っていてくれた乳酸飲料だ。幼少の頃に好んで飲んでいたらしいというそれが西岐の顔の横にかざされている。
「どっちがいい?」
お茶と乳酸飲料どちらか選べと。
笑みを浮かべて小首をかしげる西岐に轟は情けないほど眉尻を下げてしまった。
プッと、何かの封が切られるような音が聞こえた。
「――っあは」
控えめな笑い声が耳をかすめる。
もうずっと記憶の遠くに行ってしまっていた、母の笑った声だ。口に手を当てて顔をくしゃくしゃにして笑っている。
目の奥がじんと熱くなる。
姉もまた、声をあげて笑う母を泣きそうな顔で……それでも笑ってみている。
「俺ね、これ好きなの」
「…………俺もだ」
まだ轟が選んでいないのに待ちきれなくなったのか轟の手にはお茶を押し付けてパックにストローを突き刺している。ちゅっと吸い上げる音を聞きながら、西岐がたまたまこれを好きでたまたまこれを見つけて選んだのだとしたら本当に凄いことだと心が震えそうになっていた。たった数秒だけれど笑って、その後は微笑まし気に轟と西岐のやり取りを眺めている母の、こんな顔を見られるとは思っていなかった。
「半分飲む?」
「……俺はよく飲むから」
母が用意してくれているから。
首を横に振ると西岐は安心してパックの中身を吸い上げる。子供向けの小さな紙パックはあっという間に空になって、ベコッと音を立ててへこんだ。軽くなったそれを指先で弄びながら西岐は母の隣へと座り直した。
「……あのね、おかあさん」
小さな子が自分の母親を呼ぶようなそんな呼び方に、母は我が子への返事のように「なあに」と返す。
「ぎゅって、してもらえませんか」
母の笑みが深くなって西岐の願いはすぐに聞き入れられる。少しの躊躇いもなく隣に座る西岐の身体をやんわりと抱きしめた。
おずおずと西岐の手が持ち上がり、しばらく迷うそぶりを見せた後で、母の背に回して縋った。
轟も姉も何も言わない。
随分長い時間そうしていたが小さく身じろぎして母から離れる。気恥ずかしさからか顔を俯けてきゅっと口を結び、髪の隙間から見える耳が赤く染まっていた。
西岐に肉親がいないという話は、母にも姉にもしてある。西岐がお見舞いに訪れた時、不用意に傷付けてしまわないようにと。
どんな気持ちで轟の母に縋っていたのだろうと考えて胸が痛んだ。
「あ……そろそろ帰ります。また来てもいいですか」
「もちろんよ」
耳を赤くしたまま立ち上がった西岐に母と姉が揃って頷きを返す。
窓の外に目を向けると日が傾き始めて遠くの空がオレンジ色になっている。もうこんなに時間が経っていたのか。時間という概念を今やっと思い出したかのような顔で、凭れかかっていた壁から体を起こした。
「じゃあ、俺も送っていくから……今日はこれで……」
「ええ、またね」
二人に見送られて病室を後にした。
耳が痛くなるような静寂と微かな人の気配が併存している奇妙なフロアを抜けてエレベーターに乗り込む。一階のロビーでは打って変わって外来の会計や処方箋の受け取りの患者でごった返している。通りがかった柱の傍にあるごみ箱へ、西岐が飲み終えた紙パックとベコベコになった紙袋を捨てた。さすがに見舞いに訪れた先の病室のごみ箱に捨てるのは気が引けたのかもしれない。
轟はもらったお茶のペットボトルを未開封のままカバンに押し込んだ。
「疲れたか?」
「………………え?」
病院を出て通りを歩いているさなか、どこを見るでもなく視線を正面に投げ出してふらふら歩く西岐に問いかけると、かなりの間が空いてから何かを言われたという事実だけを脳が認識したらしく轟を振り返った。やはりかなり疲れさせてしまったのだと思って轟が眉を顰めたことをどう受け止めたのか、西岐は足を止めた。
道の真ん中で唐突に立ち止まったものだから、後ろから来た人が戸惑った様子で二人を避けていく。
「あ、え……っと、何か駄目だった?」
「何かって?」
言葉足らずの西岐と理解力不足の轟が互いに疑問符を浮かべる。
西岐はそれ以上の言葉がうまく探せないようで言い淀む。
「俺は疲れたかって聞いた」
「あ、うん……え、あ、ぜんぜん」
少なくない人通りの中で流れを堰き止めてしまっている西岐を道の端に促して、改めて問いかけてやれば、一度頷いてしまってから大きく首を振った。
「嘘下手だな」
「ち、ちがうよ、あのね、なんか……気が抜けて、頭ぼーっとしてたから」
「それを疲れたっていうんだと思う」
不器用な気遣いを轟に一刀両断されて西岐は口をつぐんだ。
「なんか俺たちの都合でいろいろ気を遣わせたな」
母の要望があったとはいえ西岐を母に会わせたのはほとんど轟の我儘だ。轟家のごたごたに西岐は全く関係ないというのに。
「……でも、俺楽しかったから」
沈みかけた轟の気持ちを西岐の声が掬い上げる。嘘の下手な西岐の言葉は真っ直ぐ轟の心の深いところまで届いて強く響く。
「あ…………とどろきくん、今日、うちに寄っていけるかな?」
脈絡のない西岐の誘いに不意打ちを食らい、昂っていた心がひときわドキンと高鳴った。
「……ああ」
短い返事を聞くなり西岐は轟の手を取り遠くへと視線を投げだす。何を見ているのか轟には分からないほど遠くへと向いた視線が恐らく目的の物を捉え、次の瞬間には周りの景色が一変していた。
幅の広い歩道や植えられていた街路樹、大きな白い建物、通りの向こうに見える沢山のビル、道路を行き交う車の音、それらがすべて消え去って、キンと耳鳴りを覚えるような静寂が急に襲い掛かってきた。背に扉があって足元は綺麗な石のタイル、正面には薄暗い廊下が伸びている。訪れたのは初めてだがここが西岐のマンションの玄関なのだろう。
「……凄いな」
初めて味わう瞬間移動というものに驚けばいいのか、初めて踏み入れたプライベート空間にときめけばいいのか。とにかく胸が騒がしい。
西岐は廊下に進むことも明かりをつけることもせず広い玄関で轟に向かって両手を広げた。
「とどろきくん、ぎゅってしていい?」
予想できるはずもないその一言に轟は今度こそ返す言葉を失った。いや、それよりどう呼吸をするんだったか忘れそうになった。轟の世界の全てが時を止めたように頭が真っ白になる。
轟の返事を待たずに西岐の腕が背中に回される。
肩が、頬が、髪が触れる。
シャツ越しに体温が伝わる。
だいぶ遅れて実感が轟を襲い掛かってきた。急激に上がる体温と心拍数に頭がくらくらする。どうしていいか分からず棒立ちでされるがままになっている轟の胸元で西岐が笑みを浮かべたのが気配だけで分かった。
「もうずっと、おかあさんにぎゅっとされてないでしょ」
働いていなかった思考回路が西岐の声を拾うなり冷静さを取り戻して、弾き出した"行動の理由"にまさかという思いが沸く。
「……このために、さっき頼んだのか?」
まさかと思いながらももう轟は自分の考えが間違っていないと分かっていた。
西岐は答えないが背中に回した腕がいっそう強く轟を抱きしめる。手のひらが優しくトン、トンと安心を与えるようにリズムを刻む。
轟は勘違いしていたのだ。病室で西岐が母に抱擁を強請ったのは西岐自身の為ではなかった。幼少の時に離されてから何年も経ち、今更抱きしめてほしいとは言えない年齢になってしまった轟の為。母の抱きしめ方を覚えようとしたのだ。
ああ、なんで分からなかったのか。
こんなにいろんなことを想わせてしまった。
「……西岐」
目頭が熱い。
喉に何かが詰まって声が掠れる。
溢れ出す感情をどうしたらいいか分からなくて自分を抱いてくれる身体を抱きしめ返した。少し下にある頭に頬を摺り寄せ腰に回した手に力を込めて引き寄せる。より強く触れ合おうとしたことで西岐の背が仰け反り轟に縋りつくような形になる。
「全然……こんなの……母じゃない」
母なわけがない。
母に抱きしめられてこんなふうに苦しくはならないだろう。
「ん、そっか。……どうやったらおかあさんっぽいかな」
「いい、西岐でいい」
柔らかな髪に鼻先を埋める。
「西岐がいい、西岐が抱きしめてくれれば……俺はそれでいい」
吐息がかかる距離で耳へ声をそっと吹き込む。擽ったかったのか少し逃げかけるが腕に閉じ込めて逃がさない。シャンプーの香りがふんわりと鼻孔を擽って轟を心地いいような落ち着かないような気分にさせる。
「西岐……好きだ。俺は西岐が好きだ」
抑えきれない想いが口をついた。
言葉にすればするだけどんどん想いが膨らんで募っていく。西岐を想う気持ちで胸が破裂してしまいそうだ。
「俺もとどろきくん好きだよぉ」
明らかに意味の違う"好き"が西岐の口から出てくる。
「なあ、西岐。俺はどうしてもお前が欲しい。手に入れたいって思った。母と会ってもらってそれが強くなった。……だから…………いいよな」
それは了承を得るための言葉ではない。告白とも違う。ただの免罪符のようなもの。
意味を一ミリも理解していないだろう西岐が腕の中で身じろぎするが解放してやることはなく、逆に膝裏に腕を回して抱き上げた。小さくあがった驚きの声を聞き流して靴を脱ぎ部屋へと上がり込む。リビングの扉を開け、ざっと見渡してからラグの上へと西岐を下した。勿論、逃がさぬよう肩を手で押さえて。
横たわる西岐の前髪が重力に従って零れ、轟を見上げている瞳が不安に揺れている。
溢れて止まらない衝動に突き動かされている。それを止める理性は元から持ち合わせていないようだ。
西岐の理解を待たず、顎を掬いとる。
「まずは……『好き』の言葉がどう違うのか……知ってもらう」
言いながらゆっくりと西岐の身体に覆いかぶさっていく。戸惑いの声が耳を掠るが聞こえないふりをする。
こんな存在は初めてだった。
どうしても欲しいと思ってしまう。
目を逸らすことが出来ないのに真っ直ぐ見つめるには眩しすぎる。触れたいのに触れるのが怖くなる。それでも誰かに掠め取られたくないから迷わず手を伸ばす。
いつだって西岐は轟から躊躇いという言葉を剥ぎとっていく。
喉の渇きを覚えて唾を飲み込んだ。
――あと少しで息が触れる。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
雄英体育祭の後、何年も会っていなかった母の見舞いに行った。謝りたいとか救けたいとか前に進みたいとか色々、全部が嘘という訳ではないけど、本当のところは単純に会いたくなったからだった。我慢するのが辛いほど会いたいという気持ちが膨らんだ理由は二つ。
緑谷に揺さぶられた、ヒーローになりたいという情熱。
そして……――。
時間の確認と連絡待ちを担っていたスマホが小刻みに震えて、指をスライドさせてから耳に当てる。
「……ああ、おはよう。……うん、……じゃあそこに行くから、待ってろ」
挨拶と道に迷っているということが耳に伝えられて、轟は手短に言葉を返すと通話を繋げたまま今聞いた場所へと足を向けた。駅の階段を足早に駆け上り、いくつもの出口に分岐している広いコンコースの真ん中のエスカレータの横、そこに立っている西岐が轟の姿を見つけて手を振る。
互いが足を前に出して距離を縮め、似たような動作で繋がっていた通話が切られた。
「おはよぉ、待たせたかな」
「いや……俺が早く着きすぎた」
まるで恋人同士のデートの待ち合わせのような会話だ、と一瞬思って熱くなる耳を掻いて誤魔化す。
病院のある方の出口へ身体を向けると西岐も横に並んで歩きだし、西岐の手にぶら下がっている紙袋がカサカサと音を立てた。
体育祭で揺り動かされて数年ぶりに顔を合わせた母に話したのは、家のこと、学校のこと。重苦しいような緊張のある沈黙を何度も挟んで、ぽつり、ぽつり、と時間をかけて色々なことを話した。言わなくてもいいことまで言った気がするし、言いたかったことが言えなかった気もする。
その中で、思わず口から零れ落ちたのが、西岐の名前だった。
何かを話す端々に西岐が出てくる。
轟の中の父の呪縛を解いてくれたのは西岐じゃない。緑谷だ。緑谷の真っ直ぐな声が轟を揺さぶってここに連れてきてくれた。だけど、母と対峙した時、手が震える轟の背を押すように心の中に一緒にいてくれたのは西岐だった。
『大丈夫……って言ってもらったんだ』
どういう顔でそう呟いたのか。聞きながらしばらく噛みしめるように微笑んでいた母が轟の言葉が途切れると、会ってみたいと言った。
そうしてそれを轟が西岐に伝えて、西岐は快く頷いてくれて、職場体験を経て一か月後に期末試験を控えた今日、やっと実現することとなったのだ。この間に轟は何度も見舞いに訪れていて、いつ西岐は来られるのかと聞かれていたのが、やっと会ってもらえる。いつもは緊張してしまう病室までの足取りがいくらか軽い。
「あ、待って……どうしよう、緊張する」
病室の扉に手をかけた轟を西岐が隣で制止する。紙袋を両手で必要以上にギュウっと握ってしまっている。
「……大丈夫」
いつか、西岐が掛けてくれた言葉を返すように言って肩に手を置く。きっと轟が口にした言葉の意味は伝わらないのだろうけれど。
扉を開いた先に、いつもどおり待ち構えていた母が笑みを向けてくれる。けれどそれが、隣に並び立つ西岐を見て僅かによそ行きの表情へと変化した。自然な、"母親"らしい変化だった。
「もしかして、西岐くん?」
「はい、あの……西岐れぇです」
「うっそ、西岐くん? 体育祭で優勝してた?」
扉の陰になった洗面台の前から姉の明るい声が聞こえる。扉が閉じられると案の定、母にそっくりな姉が顔を覗かせる。キラキラと目が輝いて見えるのは目の錯覚ではない。興奮気味に拳を握っている。
「焦凍、蹴られて場外になったよね」
「……やめろ」
あれが心底痛快だったらしい。録画した映像を繰り返し見ては死ぬほど笑われた。
蹴った本人は轟の家族を前にして焦ったようで、うまく言葉に出来ず口をパクパクと開閉しては紙袋がより一層歪んでベキッと音を立てる。
「気にしなくていいから」
西岐の肩を押して奥に促す。
ベッドに腰かけた母の正面にはいつも轟が使っている丸椅子が置かれていて西岐に座るように勧めた。
「あ……の、これ」
緊張して引き攣った口が普段の何倍も聞き取りにくい小さな声を紡ぐ。表面が折れ曲がり皺になった紙袋から平たい箱を取り出して母へと差し出した。包装紙には有名和菓子店の名前と『くず餅』の文字が書かれている。以前、保須の病院に見舞いに訪れた時、同じものを選んで手渡されたということがあった。ぶら下げていた紙袋からして何となく嫌な予感がしていたが、よもや未だ父に囚われているのであろう母に対して父の好物を持ってこられるとは……。
母の反応を想像して凍り付く轟の視界の先で、母は笑みを深くした。
「ありがとう」
社交辞令なのか本当に気にしていないのか判断の難しい、静かな笑顔で箱を受け取る。
西岐は一度きゅっと口を引き結ぶ。
「俺、くず餅すきなんです」
今度はしっかりとした声で告げられた言葉に、轟は何故西岐がそれを選んだのか分かってしまった。母も同じだったのか、小さく頷く。
「ええ、私もよ」
その答えを聞いて轟の胸がギュッと締め付けられる。
心の底から嬉しそうな笑みを浮かべた西岐は丸椅子ではなく母の隣に腰かけ、母と姉から投げられる問いに答えを返しては寒々しい病室の空気を変えていく。
「ほんとに、とどろきくんって凄くって、一瞬で凍らせちゃったからオールマイトさんがこれじゃ訓練にならないなあって」
「……まあ」
「とどろきくんはね、お昼ごはんいっつも、お蕎麦で」
「……あら」
「それでね昨日はね」
「……なんだこれ、物凄く恥ずかしいぞ……」
このメンツで話す話題となれば大体は轟自身のことになる。問われるまでもなく西岐は次々と学校での轟の様子を語って聞かせる。話すつもりがなかったこと、自覚していなかったことまで母の耳に入っていく。纏まりがなくて、要領を得ない話し方でも母と姉は楽しいのか、どんどんと引き込まれるように表情が崩れていく。
西岐には不思議な魅力がある。そこにいて、言葉を発して、表情を変える。その一つ一つが周りの心を揺らす。
そんな彼が自分のことを我が事のように嬉しそうに話すのだから照れるやら恥ずかしいやら、居たたまれない。身の置き場のなさに轟は壁へめり込むように寄り掛かった。
結局、誰も座らず空いていた丸椅子に腰かけた姉が轟にからかうような視線を向ける。
「焦凍、そんなに凄いんだ?」
「はい」
「じゃあクラスで一番凄いのって誰?」
「は? 何聞いてんだ」
唐突に投げられた姉の問いに轟は目を瞠った。
西岐の口が素直に開く。
けたたましい音を立てて足を踏み込み開いたその口を手で覆う。
「――ッんぐ」
「それは駄目だ……さすがに」
誰の名前が出ても平静でいられない。たとえそれが自分の名前だったとしても、だ。
発音しそこなった声が手のひらの中で潰れる。もう片方の手が西岐の丸い後頭部を押さえ、勢い余って膝がベッドの縁にぶつかる。
さらっと前髪が流れて隙間から驚きに丸くなった西岐の目が覗く。
同じく丸い目が二人分、向けられている。
「……あ、悪い」
ぎこちない動作で手のひらを剥がし後ろに後ずさる。誰かの名前を出される云々以前にすでにこれが失態だ。
西岐の口を塞ごうと足を踏み出したことで母との距離もいつになく近くなってしまい、じっと見上げてはクスッと笑われて頬が熱を持つ。
「ちょっと、落ち着きなよ」
「……変なこと聞くからだろ」
姉からもニヤニヤした笑みを向けられて完全に顔から火を噴く。
壁と一体化したい気持ちになってへばりつく。ヒヤリとした壁が熱くなった顔には心地いい。
それでも視線が西岐に向けられているのは彼が母と接するところをしっかり見ていたいという思いがあるからだ。自分が大切に思う存在に母がどういう顔をするのか見てみたかった。小さな子供が自分のとっておきを自慢するような気持ち。
轟のさっきの行動はあっさりと押し流されて、何事も無かったかのように三人の会話が再開される。
自分のことをあまり話すことのない西岐だが聞かれれば何でも淀みなく答え、絶え間なく楽しそうな笑みを口元に浮かべていた。
どれほど経ったのか、不意に西岐が自分の喉に手を当てた。
「あ……俺、ちょっと飲み物買ってきます」
言うが早いか立ち上がり扉へ向かう西岐に母が「それなら」と声をかけようとした。冷蔵庫に買い置きがあると言おうとしたのだろう。それを轟は手のひらをかざすことで制して西岐を見送る。
「疲れたのかもしれない。あいつ、あんなに喋るほうじゃないんだ」
西岐なりにいろいろと気を遣ってくれていることはずっと伝わってきていた。ベッドの端に置かれたままになっているくず餅の箱を見て目を細めると、その視界の中で母の手が優しい手つきで包装紙の文字をなぞる。
「……やさしい子ね」
「そうだね」
母の言葉を姉が拾って頷く。
「あんな焦凍の顔、はじめて見た」
すっと睫毛を伏せるように細めた目が弓なりになって、儚げな母の顔立ちが柔らかく穏やかに彩られる。こういう表情をきっと"慈しみ"というのだろうと思った。
程なくして西岐が病室に戻ってくる。どうやら売店まで行って全員分を買ってきたらしい。手にぶら下げた袋からお茶のペットボトルを取り出して母と姉にそれぞれ手渡す。壁に寄り掛かった轟の前に来てお茶のペットボトルを持ったまま、もう一度手を袋に突っ込む。出てきたのは見覚えのある牛のイラストが描かれた紙パック。以前、母がお見舞いに来る轟の為に買っていてくれた乳酸飲料だ。幼少の頃に好んで飲んでいたらしいというそれが西岐の顔の横にかざされている。
「どっちがいい?」
お茶と乳酸飲料どちらか選べと。
笑みを浮かべて小首をかしげる西岐に轟は情けないほど眉尻を下げてしまった。
プッと、何かの封が切られるような音が聞こえた。
「――っあは」
控えめな笑い声が耳をかすめる。
もうずっと記憶の遠くに行ってしまっていた、母の笑った声だ。口に手を当てて顔をくしゃくしゃにして笑っている。
目の奥がじんと熱くなる。
姉もまた、声をあげて笑う母を泣きそうな顔で……それでも笑ってみている。
「俺ね、これ好きなの」
「…………俺もだ」
まだ轟が選んでいないのに待ちきれなくなったのか轟の手にはお茶を押し付けてパックにストローを突き刺している。ちゅっと吸い上げる音を聞きながら、西岐がたまたまこれを好きでたまたまこれを見つけて選んだのだとしたら本当に凄いことだと心が震えそうになっていた。たった数秒だけれど笑って、その後は微笑まし気に轟と西岐のやり取りを眺めている母の、こんな顔を見られるとは思っていなかった。
「半分飲む?」
「……俺はよく飲むから」
母が用意してくれているから。
首を横に振ると西岐は安心してパックの中身を吸い上げる。子供向けの小さな紙パックはあっという間に空になって、ベコッと音を立ててへこんだ。軽くなったそれを指先で弄びながら西岐は母の隣へと座り直した。
「……あのね、おかあさん」
小さな子が自分の母親を呼ぶようなそんな呼び方に、母は我が子への返事のように「なあに」と返す。
「ぎゅって、してもらえませんか」
母の笑みが深くなって西岐の願いはすぐに聞き入れられる。少しの躊躇いもなく隣に座る西岐の身体をやんわりと抱きしめた。
おずおずと西岐の手が持ち上がり、しばらく迷うそぶりを見せた後で、母の背に回して縋った。
轟も姉も何も言わない。
随分長い時間そうしていたが小さく身じろぎして母から離れる。気恥ずかしさからか顔を俯けてきゅっと口を結び、髪の隙間から見える耳が赤く染まっていた。
西岐に肉親がいないという話は、母にも姉にもしてある。西岐がお見舞いに訪れた時、不用意に傷付けてしまわないようにと。
どんな気持ちで轟の母に縋っていたのだろうと考えて胸が痛んだ。
「あ……そろそろ帰ります。また来てもいいですか」
「もちろんよ」
耳を赤くしたまま立ち上がった西岐に母と姉が揃って頷きを返す。
窓の外に目を向けると日が傾き始めて遠くの空がオレンジ色になっている。もうこんなに時間が経っていたのか。時間という概念を今やっと思い出したかのような顔で、凭れかかっていた壁から体を起こした。
「じゃあ、俺も送っていくから……今日はこれで……」
「ええ、またね」
二人に見送られて病室を後にした。
耳が痛くなるような静寂と微かな人の気配が併存している奇妙なフロアを抜けてエレベーターに乗り込む。一階のロビーでは打って変わって外来の会計や処方箋の受け取りの患者でごった返している。通りがかった柱の傍にあるごみ箱へ、西岐が飲み終えた紙パックとベコベコになった紙袋を捨てた。さすがに見舞いに訪れた先の病室のごみ箱に捨てるのは気が引けたのかもしれない。
轟はもらったお茶のペットボトルを未開封のままカバンに押し込んだ。
「疲れたか?」
「………………え?」
病院を出て通りを歩いているさなか、どこを見るでもなく視線を正面に投げ出してふらふら歩く西岐に問いかけると、かなりの間が空いてから何かを言われたという事実だけを脳が認識したらしく轟を振り返った。やはりかなり疲れさせてしまったのだと思って轟が眉を顰めたことをどう受け止めたのか、西岐は足を止めた。
道の真ん中で唐突に立ち止まったものだから、後ろから来た人が戸惑った様子で二人を避けていく。
「あ、え……っと、何か駄目だった?」
「何かって?」
言葉足らずの西岐と理解力不足の轟が互いに疑問符を浮かべる。
西岐はそれ以上の言葉がうまく探せないようで言い淀む。
「俺は疲れたかって聞いた」
「あ、うん……え、あ、ぜんぜん」
少なくない人通りの中で流れを堰き止めてしまっている西岐を道の端に促して、改めて問いかけてやれば、一度頷いてしまってから大きく首を振った。
「嘘下手だな」
「ち、ちがうよ、あのね、なんか……気が抜けて、頭ぼーっとしてたから」
「それを疲れたっていうんだと思う」
不器用な気遣いを轟に一刀両断されて西岐は口をつぐんだ。
「なんか俺たちの都合でいろいろ気を遣わせたな」
母の要望があったとはいえ西岐を母に会わせたのはほとんど轟の我儘だ。轟家のごたごたに西岐は全く関係ないというのに。
「……でも、俺楽しかったから」
沈みかけた轟の気持ちを西岐の声が掬い上げる。嘘の下手な西岐の言葉は真っ直ぐ轟の心の深いところまで届いて強く響く。
「あ…………とどろきくん、今日、うちに寄っていけるかな?」
脈絡のない西岐の誘いに不意打ちを食らい、昂っていた心がひときわドキンと高鳴った。
「……ああ」
短い返事を聞くなり西岐は轟の手を取り遠くへと視線を投げだす。何を見ているのか轟には分からないほど遠くへと向いた視線が恐らく目的の物を捉え、次の瞬間には周りの景色が一変していた。
幅の広い歩道や植えられていた街路樹、大きな白い建物、通りの向こうに見える沢山のビル、道路を行き交う車の音、それらがすべて消え去って、キンと耳鳴りを覚えるような静寂が急に襲い掛かってきた。背に扉があって足元は綺麗な石のタイル、正面には薄暗い廊下が伸びている。訪れたのは初めてだがここが西岐のマンションの玄関なのだろう。
「……凄いな」
初めて味わう瞬間移動というものに驚けばいいのか、初めて踏み入れたプライベート空間にときめけばいいのか。とにかく胸が騒がしい。
西岐は廊下に進むことも明かりをつけることもせず広い玄関で轟に向かって両手を広げた。
「とどろきくん、ぎゅってしていい?」
予想できるはずもないその一言に轟は今度こそ返す言葉を失った。いや、それよりどう呼吸をするんだったか忘れそうになった。轟の世界の全てが時を止めたように頭が真っ白になる。
轟の返事を待たずに西岐の腕が背中に回される。
肩が、頬が、髪が触れる。
シャツ越しに体温が伝わる。
だいぶ遅れて実感が轟を襲い掛かってきた。急激に上がる体温と心拍数に頭がくらくらする。どうしていいか分からず棒立ちでされるがままになっている轟の胸元で西岐が笑みを浮かべたのが気配だけで分かった。
「もうずっと、おかあさんにぎゅっとされてないでしょ」
働いていなかった思考回路が西岐の声を拾うなり冷静さを取り戻して、弾き出した"行動の理由"にまさかという思いが沸く。
「……このために、さっき頼んだのか?」
まさかと思いながらももう轟は自分の考えが間違っていないと分かっていた。
西岐は答えないが背中に回した腕がいっそう強く轟を抱きしめる。手のひらが優しくトン、トンと安心を与えるようにリズムを刻む。
轟は勘違いしていたのだ。病室で西岐が母に抱擁を強請ったのは西岐自身の為ではなかった。幼少の時に離されてから何年も経ち、今更抱きしめてほしいとは言えない年齢になってしまった轟の為。母の抱きしめ方を覚えようとしたのだ。
ああ、なんで分からなかったのか。
こんなにいろんなことを想わせてしまった。
「……西岐」
目頭が熱い。
喉に何かが詰まって声が掠れる。
溢れ出す感情をどうしたらいいか分からなくて自分を抱いてくれる身体を抱きしめ返した。少し下にある頭に頬を摺り寄せ腰に回した手に力を込めて引き寄せる。より強く触れ合おうとしたことで西岐の背が仰け反り轟に縋りつくような形になる。
「全然……こんなの……母じゃない」
母なわけがない。
母に抱きしめられてこんなふうに苦しくはならないだろう。
「ん、そっか。……どうやったらおかあさんっぽいかな」
「いい、西岐でいい」
柔らかな髪に鼻先を埋める。
「西岐がいい、西岐が抱きしめてくれれば……俺はそれでいい」
吐息がかかる距離で耳へ声をそっと吹き込む。擽ったかったのか少し逃げかけるが腕に閉じ込めて逃がさない。シャンプーの香りがふんわりと鼻孔を擽って轟を心地いいような落ち着かないような気分にさせる。
「西岐……好きだ。俺は西岐が好きだ」
抑えきれない想いが口をついた。
言葉にすればするだけどんどん想いが膨らんで募っていく。西岐を想う気持ちで胸が破裂してしまいそうだ。
「俺もとどろきくん好きだよぉ」
明らかに意味の違う"好き"が西岐の口から出てくる。
「なあ、西岐。俺はどうしてもお前が欲しい。手に入れたいって思った。母と会ってもらってそれが強くなった。……だから…………いいよな」
それは了承を得るための言葉ではない。告白とも違う。ただの免罪符のようなもの。
意味を一ミリも理解していないだろう西岐が腕の中で身じろぎするが解放してやることはなく、逆に膝裏に腕を回して抱き上げた。小さくあがった驚きの声を聞き流して靴を脱ぎ部屋へと上がり込む。リビングの扉を開け、ざっと見渡してからラグの上へと西岐を下した。勿論、逃がさぬよう肩を手で押さえて。
横たわる西岐の前髪が重力に従って零れ、轟を見上げている瞳が不安に揺れている。
溢れて止まらない衝動に突き動かされている。それを止める理性は元から持ち合わせていないようだ。
西岐の理解を待たず、顎を掬いとる。
「まずは……『好き』の言葉がどう違うのか……知ってもらう」
言いながらゆっくりと西岐の身体に覆いかぶさっていく。戸惑いの声が耳を掠るが聞こえないふりをする。
こんな存在は初めてだった。
どうしても欲しいと思ってしまう。
目を逸らすことが出来ないのに真っ直ぐ見つめるには眩しすぎる。触れたいのに触れるのが怖くなる。それでも誰かに掠め取られたくないから迷わず手を伸ばす。
いつだって西岐は轟から躊躇いという言葉を剥ぎとっていく。
喉の渇きを覚えて唾を飲み込んだ。
――あと少しで息が触れる。
create 2018/02/21
update 2018/02/21
update 2018/02/21