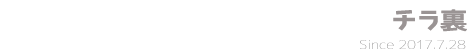相澤
ハローヒーロー
ハローヒーロー
『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 〜2人の英雄〜』で相澤先生と一緒に夢主が《Iアイランド》に行っていたらというお話。
ネタバレを含みますので劇場版をご覧になっていない方はご注意ください。
劇場版を見ていないと内容がよく分からないと思います。
メリッサとデヴィットとは接触なし。メインキャラ達ともほぼ接触ないです。ずっと相澤先生のターンです。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。(本編の時期より早い段階で相澤先生と暗間が接触している等、時間軸での矛盾がありますが別時空だと思っていただけると幸いです。)
IアイランドでIエキスポが行われるというニュースや特番は随分前からテレビで流れていたし、夏休みが近付くにつれてクラスメイト達が大いに盛り上がっていたのは知っていた。ただ、西岐はそれをどこか他人事に感じていた。世界的に盛り上がるようなイベントと『イチ高校生の自分』とは国境以上の隔たりがあって、関わることなどないと思っていたのだ。
招待状が自宅に届くまでは……。
ポストに投函されていた封書にはプレオープンのチケットとレセプションへの招待状が同封されていて、案内状によると体育祭の上位入賞者に向けて贈られたという旨が書かれていた。
「ゆ、雄英ってすごい……」
学校行事のはずの体育祭で活躍したというだけで、あのサイエンスハリウッド、巨大人口移動都市に招待されるのだから本当に雄英というところは凄い。雄英に入学していなければ手にすることもなかったであろう招待状を握り締めて震えていると、相澤が横から覗き込んで短く嘆息した。
「タイミングだな。そうあることじゃない。今期の雄英生は無駄に引きが強い。良くも悪くも当たり年ってやつだ」
「……褒めてます?」
「褒めてるだろ」
相澤の物言いだとあまり褒めているようには聞こえないが普段より幾らか口角が緩んでいるところをみると割と機嫌がよさそうだ。
「い……行きたい」
遥か遠くのものだと思っていた場所へ招待されたのだ、行きたいに決まっている。
思わず口に出して、しかし、自分が今謹慎中だったことを思い出して、相澤に伺いの目を向けた。
期末試験を終えた先日、クラスメイトと一緒に訪れたショッピングモールで死柄木と遭遇し、立ち去ろうとする死柄木を追いかけた西岐。怪我を負うこともなく相澤によって無事救出されたが、勝手に危険な行動をとったことを怒られ、林間合宿まで自宅謹慎をするように言い渡されていた。二週間後の終業式もその後のIエキスポの開催期間も"謹慎中"だ。
この相澤に『例外』がある気がしない。
ダメと言われるに決まっている。
そう勝手に結論付けて項垂れる西岐の横で相澤は未だ招待状を眺めつつ、ぽつりと言う。
「行くか」
意外な一言をすぐには理解できず西岐は『そうですね』と項垂れたまま返事をした。
「世界的に活躍しているヒーローが警備やら招待やらで集まるし、何より一流の科学者の生み出す最新鋭のヒーローアイテムを目にする機会ってのはそうそうあることじゃない。さっきも言ったろ。これはお前の引きだ。得られる経験値は得たほうがいい」
まさかの『例外』が存在した。
ゆっくりと顔を上げてまじまじと相澤を見る。
「いいの……?」
「ああ、ただし俺も同伴する」
相澤の指が招待状の一部をとんと叩く。
『本状にて同伴者一名様までご参加いただけます』との一文。
勿論、相澤の同伴は大歓迎だ。というより一人で海外に行く勇気はない。
じわじわと西岐の表情に嬉しさが滲み始め、噛みしめるように招待状の端を摘まむ手に力を込める。
だが相澤は西岐の手から航空チケットを抜き取り、ぽりっと頬を掻く。
「ただ……お前、…………保護者の許可は下りるのか?」
相澤からの問いかけに西岐は「あ」と小さく零す。
はらりと招待状が滑り落ちた。
遠足、社会科見学、キャンプに修学旅行。
学校行事に必ずある校外学習のありとあらゆるものを西岐は経験をしたことがなかった。
それというのも西岐の後見人である叔父がことごとく『長距離移動を伴う行事へは参加しないように』と却下してくるからだ。正確に言うと叔父ではなく叔父の秘書が『駄目です』と一刀両断し、さっさと学校に不参加の連絡を入れてくれるわけだ。
実は林間合宿に行くことにも少々渋られた。電話越しの声があからさまに低くなり『林間合宿……わざわざ山に行く理由は何でしょう』と淡々と説明を求めてきたのは記憶に新しい。あの時は本当に苦労した。だって西岐にも山に行く理由なんて分からない訳で、説明のしようがない。ただどうしても行きたいという熱意だけは必死に伝えようと頑張って、なんとか渋々ながらも承諾を得られた。
その林間合宿に行く前に、今度は海外に行きたいだなんて、どう言えばいいのか。
テーブルに置いたスマホを緊張の面持ちで眺める。
ハンズフリーにしているのでスピーカーからコール音が聞こえてくる。
いっそ出なければいいのにと思うくらい緊張が高まった頃、プツリと途切れて柔らかな声が聞こえた。
「はい。暗間でございます」
彼の恭しげな話し方はいつもこちらを恐縮させる。
「れぇです」
「はい」
西岐が名乗ると存じておりますとばかりに丁寧な返事が返ってきて、一度開いたはずの口をきゅっと結んでしまった。
こうしたい、と自分の想いを伝えるのが本当に苦手だ。だって今までしてこなかった。思ったこともなかった。それがヒーローを目指すと決めたあの日からどんどん溢れてきて、心の内ばかりがまるで欲張りな人間のように変わってしまい、心の変化に行動力やら何やらが追いついていない状態だった。
それでも、相澤が口を出そうとする前にと声を絞り出す。
「あ、Iアイランド、行きたい……です。あのっ、体育祭、頑張ったから……招待状がきて、それで、俺行きたいんです」
こんなことくらい自分で言えないようではだめだと思った。緊張で声がひしゃげたが何とか思っていることを言葉に出来た。
「駄目です」
案の定、即答だ。
「な、なんで?」
「危険だからです」
あくまで柔らかな物言いだが西岐に有無を言わせない強さがあって、うまく切り返すだけの言葉が出てこなくなってしまう。
「Iアイランドは特殊拘置所タルタロスに匹敵するセキュリティを誇ります。危険ということはないはずです」
「……貴方は、相澤先生でしょうか」
「担任の相澤です」
「挨拶が遅れました。私、西岐の秘書をしています暗間と申します」
見兼ねてか相澤が口を挟み、それに対して暗間は丁寧すぎるくらいに挨拶を返した。
そうしてからスピーカーからフッと息が吹きかかったような微かな音がする。
「優秀なセキュリティ……そういうものが覆された時ほど凄惨なことになるとは思いませんか。それに航路での安全は保障されませんよね」
「……もっともです」
「っ、あ、俺、危ないことはしない。自分で自分を守る、だから」
何故か相澤が責めたてられているような具合になってきて西岐は二人の会話に声を被せた。学校関連のことでもないのに相澤に責任を向けるのはおかしな話だ。
しかし暗間は西岐の意見をぶった切る。
「自分で自分を守ってはいけません」
あまりのきっぱりした物言いに西岐は今何の話をしているのか見失いかけた。
「え、……え?……なんで?」
「なんででもです」
答えになっていない。相変わらずこの人の話は一方的だ。
「……私が同伴して護ります」
静かに、何でもないことのように相澤が言う。
「それはヒーローとしてですか、それとも担任としてですか」
「両方、あるいはイチ一般人の知人としてです」
迷いのない相澤の言葉を受けて暗間はしばらく沈黙した。何か考え込んでいるのか、それとも不快感を得たのか。声だけが頼りのこのやり取りの中で彼が何を考えているのかさっぱり分からない。
やけに沈黙が長く感じた。
「同伴している間、一切のヒーロー活動を放棄できますか?」
やっと言葉を発したと思うなり、彼が提示したのはとんでもない条件だった。
「どんな状況になっても、誰が窮地に立っていても……救けに行かず闘いにも行かず、その子から片時も離れず護ってもらえるのなら容認しましょう」
「――だめっ」
反射的に声を荒げていた。
プロヒーローに向かって誰も救けるなだなんて、そんな条件飲めるはずがない。
そこまでして行きたいなんて思わない。
そう続くはずだった言葉が相澤の手の中でもごもごと籠る。相澤がすかさず西岐の口を塞いだのだ。
「分かりました、約束します」
藻掻く西岐を押さえ込みながら相澤は少しも揺らがず答える。まるでそこに暗間がいるかのようにスマホへ真っ直ぐな視線を向けていた。
同伴中は一切のヒーロー活動を放棄すること。
片時も離れないこと。
目立つ行動はしないこと。
レセプションには参加しないこと。
以上が暗間からの承諾の条件だ。万が一破ることがあれば全責任は相澤がとるということになった。
西岐はしばらくの間この条件に猛反発していたが、そのうちに「何事も起きなければいいんだ」と考えを軌道修正したらしく「イレイザーさんには絶対迷惑はかけませんから」と息巻いていた。
正直、相澤は迷惑をかけられるとか責任を負うということ自体に胸が高揚していたので西岐の気遣いは余計だった。
保護責任者に挨拶して、ちゃんと護れるのかと値踏みされ、絶対に護ると誓う。この流れ、どう考えても"あの流れ"そのものにしか思えない。そもそも、一般的にはレセプションの同伴者は"そういう"間柄の相手と相場が決まっている。レセプション自体の参加は暗間に却下されてしまったが、Iアイランドへの同行が将来のリハーサルのようなものと思えば、是が非でも全責任を請け負いたかった。
何はともあれ承諾を得られて早三週間弱。
相澤は西岐と共にIアイランドに入国していた。
「わあ……わああああ……!」
出入国管理局を出て眼前に広がる景色に西岐の目がキラキラと輝く。
噴水が文字を綴ったり、音楽がカラフルな音符になって風船のようにふわふわ浮かび上がったり、透明なカプセルに乗った観光客が宙に浮かんだり、さながら一昔前のSF映画のような光景だ。
今日は未だプレオープンだというのに随分と賑わっていて、景色を見るのに夢中になっている西岐は右にフラフラ、左にフラフラと危なっかしい足取りで、人ごみに揉まれている間にうっかり見失っても可笑しくない。
相澤は大股で歩み寄って西岐の腕を掴み引き寄せる。
「"片時も離れるな"……だったよな」
そう言うと我に返ったのかハッと息を吸い込む口を手で押さえ、西岐の方からもツツツッと身を寄せてくる。
ただ重心がフラフラしているうえに、すぐ上の空になる西岐が身を寄せた程度ではぐれないように気を付けるのは難しいように思える。
だから相澤は手のひらを空に向けて西岐の脇に差し出す。
「……?」
それだけでは意図が伝わらなかったらしい。
視線が二度ほど相澤の手と顔を往復した。
「お手」
短く言い放つ。
すると反射的に手が持ち上がりパシッと軽い音を立てて重なった。
考えての行動ではなかったのだろう。相澤の手に自分の手を乗せてから驚いたように手を引っ込めようとして、相澤はその手を握りこんだ。逃げられないように指一本一本を股にくぐらせてがっちりと固定すれば、西岐は何が起きたのか分からないとばかりに瞠目する。
はぐれないように手を繋ぐという概念が彼にはなかったらしい。しばらくキョトンとしているが、じわじわと頬が紅潮していく。
「ち、ちっちゃい子じゃないから」
酷く子ども扱いされたと受け取ったようで手を揺すって逃げようを試みる。
どちらかといえばこれは所謂『恋人繋ぎ』というやつなのだが。その辺の認識は更にないようだ。
繋いだ手をグッと引き寄せると西岐の軽い身体が簡単に引き寄せられて一層ぴったりと寄り添う。指から手のひら、腕が絡まるように触れた状態で歩くことになる。そういうことを理解していない西岐を間近に見下ろして可笑しいやら愛おしいやら。自然と笑いがこみ上げてくる。
「小さい子供より手がかかる」
鼻で笑い飛ばして揶揄うとムウとむくれる。
「そんなこと……ないです」
「だったら大人しく繋がれてろ」
こんな役得をおいそれと手放すわけがない。西岐の微々たる抵抗を物ともせず繋いだままエキスポ会場を目指して歩き始める。
暫く納得がいかないような顔でくっついていた西岐だが、段々と周りに景色の方に気を取られていく。
あちらこちらを走り回っているロボットだとか、案内係のスタッフだとか、ファンにサービスしているヒーローだとか。見るものが多すぎて目が追いつかないのか足取りが怪しくなってきた。相澤が誘導していなければ何度か引き返したり方向転換したりしていたに違いない。
相澤たちが向かう数メートル先から大きな地響きのような足音と恐竜に似た咆哮が聞こえる。怪獣ヒーローゴジラだ。実績はともかく知名度と人気は世界トップクラスで、目の当たりにした西岐も目を輝かせた。
「すごぉい……ほんものだあ……」
感激のあまり空いていた手を添えて相澤に縋るようにぎゅうと抱きついてきた。
頭上のゴジラを見上げてはピコピコと踵が跳ねる。
死ぬほど可愛い。
「さ、サインしてくれないかなあ……」
「……無理じゃないか」
とはいえ自分以外のヒーローにやたら夢中になられているのも面白くない。延々とゴジラを眺めていそうな西岐を引き摺るようにパビリオンへ向かうのだった。
ここIアイランドに来た目的の一つ、最新のヒーローアイテムが展示されているパビリオン。
その建物の中は想像以上に凄い光景が広がっていた。
西岐の身近なヒーローが纏うスーツやアイテムといえば補助的な機能が多少はあれどどちらかといえばデザイン性が優先されているような感じだが、ここに展示されているものはどれも『身に着ける個性』とも言えるほどの機能を備えている。飛行潜水両用の多目的ビークル、深海七千メートルまで耐えられる潜水スーツ、三十六種類のセンサーが内蔵されたゴーグル、ありとあらゆるものが西岐の想像を遥かに超えて、しかし現物としてそこに存在していた。タルタロスに相当する警備システムによって守られているだけのことはある。
「でも、ちょっと怖いですね。……科学がヒーローを凌駕しそう」
科学の凄さに圧倒され、胸に広がった不安感がそんなふうに呟かせて、隣の相澤がしんなりと眉を顰めた。
「科学、バケ学、医学、生物学、そういうもんは時折人間を大きく超える。諸刃の智慧だな」
まるで映画の世界だ。
人間の偉大な智慧が人間のキャパシティを超えて牙を剥くようになったらと考えると空恐ろしい。
しかし圧倒的な科学を目の前にしても雄英の、いや、相澤の教えは揺るがない。
「けど、それを更に超えるのが、ヒーローってもんだ」
相変わらず叩き込まれる"校訓"に西岐は強張っていたものがフッと解けるのを自覚した。
「それにな、やっぱりヒーローに発明家ってのはつきものだろ。俺の捕縛武器だってあんな合理的なのをよく作ってくれたと思うよ」
「ふは……っ、そうですね」
細長いきしめんのようなデザイン性皆無の捕縛武器を思い出して堪らず肩を震わせる。あんなアイテムはきっと相澤以外に需要がないだろう。
ヒーロー一人一人がそれぞれに違う個性を持っていて、アイテムにそれぞれが違うサポートを求めるのなら技術が過ぎるということもないのかもしれない。
パビリオンを一通り見終えた後は、外のアトラクションを見て回る。
ふわふわ浮き上がるだけの乗り物の類はかったるいと却下され、三百六十度パノラマのプラネタリウムでは欠伸され、微妙に盛り上がりきらない。何か目が覚めるようなものはと視界を巡らせている中で、スピーカーを通したお姉さんの実況が耳に滑り込んできた。
どうやら参加型のアトラクションゲームのようだ。
ヴィランと想定されたロボットをどれだけの時間で打破できるかというシンプルなルール。
「一般入試と似た内容だな」
観客席の後ろから覗き込みながら相澤の一言を拾い上げて西岐は少々落ち着かなくなる。
入試内容。
体育祭で見たあの仮想ヴィランのロボットのやつか。
入試を受けていない身としては気になる。
自分がどれくらいの実力なのか。
「ってか、参加者……おいおい、うちの生徒ばっかじゃねえか」
モニターに映し出されているランキングとアトラクション敷地内にいる人影、それらが見知った名前・顔ぶれと分かるや渋い表情になっていく。
「一位……かつきくんか」
対ヴィラン向きのあの個性だ。
参加しているとなればこの順位は頷ける。
そしてどういうわけか観客席にいた緑谷に向かってがなり立てて、緑谷が飛び入り参加する流れになったらしい。職場体験以降、目にするようになった全身に走る電撃のようなもの、それらを纏ってヴィランを叩き潰していく。
結果は爆豪のタイムより一秒下回り、二位に。
「……すごい」
続いての参加者もまた見知った顔。
轟の氷結が一気に岩山を覆い隠すように広がって爆豪のタイムを超え一位に成り上がった。相変わらずの瞬殺ぶりに会場が大きくどよめいている。
海を渡って世界のヒーローやアイテムを見に来たというのに、こんなところでもクラスメイトの凄さを突きつけられようとは。激しい羨望と無視できないほどの張り合う気持ちが胸の中で膨らんできた。
「イレイザーさん……」
「おい」
ざわざわとする気持ちが西岐を前のめりにさせる。
今にもアトラクション敷地内へ降り立ちそうな西岐を相澤の手が押しとどめる。
「駄目だ。目立つなって言われただろ」
「……目立たなきゃいいですよね」
今着ているのはクラスメイトたちみたいなヒーロースーツではなく私服だ。羽織っているパーカーのフードを頭に被せてそう示すと、相澤の顔色が悪くなる。
「そういう屁理屈は通用しない」
「常にトップを取りに行くくらいの気持ちじゃなきゃダメなんですよね。俺、今トップ取りたいです」
「あのな、そんなことすればめちゃくちゃ目立つだろうが」
繋がれている手により力が込められて痛いくらいに軋んだ。
こうと思ったら考えを曲げられない上に、ルールや戒めというものから時折どうしてか外れていってしまう性質が西岐にはあって、暗間と交わした約束や相澤に降りかかる責任というものが思考から薄れてしまう。
「大丈夫、今はプレオープンで中継もされていない。バレませんよ」
昂る闘争心とは裏腹にやけに冷静な部分があって、ざっと辺りを見渡してカメラがないことは確認済みだ。
もう、抑制を放って相澤を振り切ろうかと思いかけた西岐を、恐らく察したのだろう。相澤の髪がざわっと僅かに浮き上がりいつでも抹消できる構えになって、これまで以上に厳しい声音を放った。
「ヒーロースーツなしのお前がどうやってあれを潰すつもりだ?」
「……抑制で」
「離したらまた動き出すだろ。一体だけじゃないんだぞ」
「……うっ」
相澤のズバリな指摘が盛り上がっていた気持ちを引き戻す。
もっともすぎて反論が出ない。
ロボット相手では幻影も効かないし個性を封印することもかなわない。あれだけやる気になっておきながらまさか勝算がないなんて……。
「帰ったら似たような授業やってやるから、その意欲はぜひ学校で発揮しろ」
西岐の気持ちが萎んだところで相澤がにたりと意地の悪い笑みを浮かべたのだった。
人工島とは思えない広大な敷地内には今回のエキスポ会場もさることながらさまざまな施設が充実していて、とても一日で周回することはかなわず、日が傾いた頃にホテルへ入った。
学生への招待にしては随分と豪華な部屋だ。この島のホテル自体がこの基準なのか、西岐への招待が特別なものなのか。少なくともこの部屋がホテルの最上階にあるということはそれなりの特別扱いを受けているのだろう。体育祭での西岐の活躍に余程の関心が寄せられたのか、もしくは彼の保護者が何かしたのか。
ぼんやりと夜景を眺めては何とはなしに考えを巡らせていると、バスルームの扉が開く音に続いて、パタンパタンとスリッパを踏み鳴らす音が聞こえてきた。そちらを見ないよう頑なに窓の外を凝視していたのだが、ガラスに湯上り姿の西岐が映りこんで、相澤はゴンッと額をガラスにぶつける。
「だ、だいじょうぶ?」
西岐は相澤が自ら頭部に打撃を加えたなどと露ほども思わずに近付いてくる。
手のひらを翳して大丈夫だということと来なくていいという意思表示をすると不思議そうにしつつも、方向転換して冷蔵庫からドリンクを取り出している。
それを横目でちらっと覗き見して息を吐く。
ホッとしたのではない、重い溜息だ。
チェックインして部屋に入った時も、ラウンジで食事した時もあまり気にしていなかったのだが、同じ部屋で一晩過ごすということがここにきてじわじわと苛み始めていた。
これまでも西岐宅に泊まることはあったし、風呂上りや寝起きの顔だって見慣れている。しかしこう"特別な空間"を演出した部屋にいると、教師という立場を忘れて暴走してしまいそうになるのだ。
この島に来た動機も割と邪だったし、今日一日連れ歩いているさなかも"そういう"気分に浸りきっていたが、でもあれはあくまで"ごっこ"の域を出ない、所詮は戯れ程度のことだった筈だ。それがよもや本当に"そう"なってしまいかねない酷く危うい状況に陥ろうとは……。
だというのに、西岐はいつものごとく自分の格好がどうなっているのかなどということには無頓着で、濡れた髪を肌に貼りつけたままソファーにちょこんと腰かけてテレビのリモコンをいじっている。フルーツウォーターのボトルを傾けるたびに水滴が白い喉を伝う。ガウンという腰ひもで纏めるだけの簡素な着衣が、何かするたびに捲れ、はだけ、着ているんだか引っ掛けているんだか分からない状態だ。ソファーの上で体育座りのように膝を抱えて座るものだから、うっかり見えてしまう。何がとは言わないが。
「……フロハイッテクル」
なるべく心を無にしようと努めた結果、片言になった相澤を西岐が戸惑いの目で見送る。
やたら広いバスルームとバスタブ。これ二人で入れるんじゃないかと考えてから何を馬鹿なと自嘲しつつ、シャワーブースに足を向けた。雑念を洗い流すべく勢いよくお湯を頭からかぶる。気分は滝行だ。長い髪と湯の滝の内側で何度目か分からなくなった溜息をついた。
やたら無意味に全身隈なく綺麗に洗いバスルームを出ると、西岐の姿が見当たらない。先程のソファーにはリモコンとドリンクのボトルが転がっていて、つけっぱなしのテレビからアニメーション映画が流れている。窓辺の椅子にも、違うソファーにも、姿がない。
寝室の扉を静かに開く。
相澤の想像通り、ベッドの真ん中で丸くなって眠っている。
シーツと一緒に下敷きにされているのは相澤の着ていたシャツだ。慣れないホテルの中でそれに安心を求めたのだろうか。
眠りに落ちる直前まで握っていたのか手の近くにスマホが転がっていて、ピロンピロンと電子音を途切れ途切れ鳴り響かせている。ディスプレイにはクラスメイト達の名前が見えた。
「あーあ……」
零れ落ちた乾いた声。
「これだもんなあ……」
全然これっぽっちも意識されていない。
全力で油断されている。
信頼の証と言えば聞こえがいいが西岐の中で相澤は保護者なのだ。
そして心の拠り所はいまやクラスメイト全員に分散している。特別でも何でもない。
けれど、今はまだそれでいい。
目指すものの途中にいる"生徒"を導いてやる"教師"という立場を未だ手放すつもりはなかった。
音を立てないようにそっと傍らに腰かけ、西岐の髪を撫でる。サラサラと指から逃げていくのを絡め取り、感触を味わいつつ頬に滑り落とす。擽ったそうにイヤイヤと首を振るあどけない横顔に、相澤の眼差しが和らぐ。
つけっぱなしのテレビでも消してくるか、と腰を上げたその時。
唐突に警報が鳴り響いた。
『Iアイランド管理システムよりお知らせします。警備システムによりIエキスポエリアに爆発物が仕掛けられたという情報を入手しました。Iアイランドは現時刻を以って厳重警戒モードに移行します』
室内のスピーカーから聞こえてくる不穏なアナウンスに相澤が身構え、西岐もまた何事だと飛び起きた。
「……ばくだん」
明らかに寝惚けた声音で、しかし迷いなくベッドから飛び降りて手荷物を入れたクローゼットに向かう。キャリーを開いて着替えを引っ張り出すのを見て相澤は西岐の肩を掴んだ。
「外出するなって指示だ。ここの警備システムに任せればいい」
西岐の行動が逃げる為でも備えでもなく、爆弾というイレギュラーを解決しようとするべくなのは考えるまでもない。
反射行動。
呆れるほど、彼は常に『ヒーロー』で居る。
「でも、こんな格好じゃ……いざとなったら」
「いざとはならない」
「……なるかもしれないでしょ」
相澤の言うことも素直に聞きはしない。
しかし非常事態なのは間違いなく、実際に避難や何かでいざということは起こりうるかもしれない。結局、相澤も西岐と共にガウンからいつもの私服に手早く着替え、ソファーに移動した。
スマホやネットが繋がらないのはともかくテレビまで映らなくなっている。情報という情報すべてがシャットアウトされているのだろうか。
「……なんか……街中、警備ロボットが……」
何もないはずの壁や斜め下の床に西岐の目が向く。
「警備しているっていうより……制圧してるように見えるけど」
手で鼻と口を軽く覆い、困惑を隠すことなく呟く。そうすることで自分を落ち着かせ、窓ガラスの向こう側にそびえたつ、島で一番高い建物を見上げた。西岐の目がどういうものなのか知らなければ一種異様に見えるに違いない。
「……警備システム」
まるでそこにあることを"把握"しているかのように真っ直ぐ見つめる西岐を、相澤は止めるべきなのか迷いながら、しかし現状を知りたい気持ちが制止の言葉を飲み込ませた。
二百もの階層を視線で探っているのだろう。少しの間沈黙が続き、時折辛そうに眉間を拳で叩く。
「…………あ」
何かに視線が到達したらしい。
表情が一層強張ったと思うなり身体を縮こませた。
「オールマイト……さん」
タワービルに目を向けた状態のまま引き攣った声で名前を呼ぶ。
西岐が心の拠り所にしている一人であり、雄英の教師、そして平和の象徴と呼ばれるNo.1ヒーロー、オールマイト。彼なら高い確率で来ているとは思っていた。
ただ、今の声は知り合いを見つけたという類の調子ではない。
鋭利になった西岐の纏う空気が、隣にいる相澤の肌をざらざらと撫でる。
ぱち、ぱちと数秒おきに繰り返す瞬き。目蓋が開くごとに見える瞳が張り詰めていく。ソファーに座ってはいるものの今にも飛び出していきそうな表情に、相澤は堪らず再び肩を押さえつける。
「……ヴィランに警備システムごとレセプション会場が占拠されていて、一般人を人質に取られてオールマイトさんは動けません。デクくんたちが警備システムを正常に戻すために最上階に向かっているそうです」
いやに落ち着いた声で相澤に説明する。こういう時ほど感情的な状態に近い。
「なんで分かる」
「え、と……聞こえて」
目で"視"ただけでは知り得ない情報までつらつらと妙に詳しく説明して見せる様に相澤は眉間を寄せ、怪訝に問いを向ける。すると急に言葉を詰まらせ、一瞬だけ視線が相澤のほうに戻った。感心するほど嘘や誤魔化しが下手だ。
それにしても、レセプション会場が占拠とは。
なんだろう、この符合。
暗間が言っていた"危険"がまさに参加するなと言われていたレセプション会場で起きているのだ。ひょっとしてあの人はこうなることを知っていたのではないのか。しかし、だとすれば普通の立場の人間では到底あり得ない。
「イレイザーさん、デクくんたちが……」
どんどん緊迫していく西岐の声音。
相澤とて受け持ちの生徒が関わっていると知って心穏やかではない。視線で問い返す。だが返事を聞かずとも耳にした名前で状況は何となく想像がついてはいた。
ビルの上層階で何人もの生徒たちがヴィランと、或いは警備ロボットと戦闘していると。西岐が言う。
それもそうスムーズではないのだろう。見知った姿を見つけるたびに西岐は息を詰まらせる。
今すぐ行けるのに、行きたいのに、暗間との約束が枷になっていて、ソファーから立ち上がれもしない。
なるほど。
あの約束は相澤ではなく西岐を動かさないためのものだったわけだ。
タワービルの最上階でヴィランを食い止める緑谷と、警備システムのある部屋へ走る少女。彼女はオールマイトの話によればメリッサという名前で親友の娘らしい。
警備システムが正常に戻され人質という枷から解放されたオールマイトはメリッサからの電話を受けながら最上階に向かう。
オールマイトの焦りや怒りが西岐の胸に流れ込む。
このテロ行為はオールマイトの親友、デヴィットが仕組んだということ。そのデヴィットがヴィランに連れ去られようとしていること。今、それをデクが食い止めるべく一人奮闘していること。
西岐は心でオールマイトからの声を聞きながら、目はヘリから突き落とされる緑谷を捉え、耳が複数の音を拾い上げている。
「っ……」
地面に叩きつけられる緑谷。
遠ざかるヘリのなかで血を擦り付けながら倒れるのがオールマイトの親友デヴィットか。
何もしなくていいのか。
ここでじっと見ているだけなのか。
自問自答がずっとぐるぐる巡っている。
ここは個性の使用が認められている特殊な人工島Iアイランド。ヴィランと戦うことに何の縛りもないはずだ。だから緑谷たちは闘っている。
けれど西岐には暗間との約束がある。けしてヒーロー活動をしないこと。何が起きても、誰がピンチになっても救けにはいけない。
「…………」
あれ、と首を傾げる。
――いや、違う。
「ヒーロー活動を放棄したのは……イレイザーさんだ」
西岐自身は何の制約も受けていない。ただ離れるなというだけのことだ。闘うなとも救けるなともいわれてはいない。
はたと思い至って相澤の神妙な顔を見る。長いこと遠くへと視線を投げていたせいで上手くピントが合わせられずパチパチと瞬いた。視界が鮮明になるにつれ、西岐の心も晴れていく。
「離れさえしなきゃ、俺は救けていい」
肩に乗せられている大きな手に自分の手を重ねる。
「……屁理屈だ」
アトラクションゲームに参加しようとした時と同じセリフが相澤の口から出てくるが、あの時とはかなり意味合いが違う。相澤も生徒たちの安否を懸念していたのだ。『良し』とははっきり言わないが口端がグッとつり上がって明らかに賛同している。
意識と視線が逸れていたタワービルから、聴覚へ直に叩きつけるような騒音が鳴り響いた。
もう、遠目遠耳を駆使しなくても分かる。
振動でバリバリと音を立てるガラスの向こうに、到底人間とは思えない様相のヴィランがタワービルの屋上に纏わりついている。触手のごとく蠢く金属と複雑に絡まっては自身とデヴィットを匿う本体部分。もうあんなもの、ヒトの領域を超えている。
昼間パビリオンで感じた脅威があそこにある。
ふう、と息を吐く。
キンと頭の奥が冷たく張り詰める。
「……金属」
――あれは金属。
「イレイザーさん、俺を掴んでて」
言うが早いか西岐と相澤の身体は一瞬でホテルの部屋から空中に移動していた。
タワービルの屋上、それより遥か上空。
濃紺の空と真下に街の明かり。
物凄く強い風が身体を煽り持っていかれそうになる。ただ、宙を使って自身の動きをコントロールするのは西岐の常套手段だ。器用にバランスを取り滑空していく。
オールマイトと緑谷に気を取られこちらに気付く様子もないヴィランの頭上に降り立つ。金属を纏っているせいで感覚が遮断されているのか、乗られていることにさえ気づかない。
この分厚い装甲。
これが金属なのであれば抑制が効く。
ヴィラン自身にも届くはず。
「ただし、それなりのエネルギーが要る」
ぽいぽいとスリッパを脱ぎ捨てる。
抑制。
体内にある無数の蓄電細胞を部分的に直列加算して放出している。
スイッチと放出口は両手、そして両足。
脳から一番遠い場所にある足の裏は全身の蓄電細胞を直列加算にして放出することが出来る。正確に言えば、手よりも耐えられる。
つまり電圧が上がり、放出できる電気の量も勢いも増す。
素足でヴィランの纏う鉄を踏みつけ、パチと小さな火花が散る。
それを皮切りに飛び散る火花が大きく激しくなり、足の裏が一気に熱を帯びた。
「――ッ」
相澤が息を飲む。
手のスイッチを入れていないから繋いでいるそこから通電することはないが、ホテルのスリッパでは絶縁しきれなかったらしく、足を付けている金属を介して抑制を受けてしまったらしい。
申し訳なく思いながらも、放電を弱めることはなく、寧ろ増していく。
オールマイトと緑谷に降りかかる金属の攻撃が止まっていない。
末端まですべて通電する必要はない。
本体に届きさえすればいい。
「っう、あ、ああ」
接触している足の裏が熱いを通り越して痛い。
頭が痺れていく。
鼻と喉の奥がツンと痛い。
止めなければ。
止めなければ。
自分だってヒーローだ。
誰かを救けたい。
止めなければ。
「あァあああ、ア゙ああ」
全身からエネルギーというエネルギーをこそぎ出す。
全身を駆け巡るエネルギーにぞわりぞわりと神経を撫でられ猛烈な吐き気がこみ上げてくる。
二つの拳が振りかざされるのが見える。
ギッと軋む音を最後にあれだけの騒音が止んだ。
一瞬の静寂。
それを叩き潰すように二つの拳がヴィラン目掛けて叩きつけられた。
勢い良く粉砕して吹き飛んでいく金属片。
吹き荒れる拳圧の風。
ヴィランの一部になっていた金属片と一緒に西岐と相澤が吹き飛んでいく。
あれだけ巨大に育った鉄の塊を吹き飛ばす一撃だ。
吹き飛ばされる勢いも凄まじい。
抑制が解け動けるようになった相澤が空中で西岐を抱きかかえる。
限界の限界を突き抜けたのだろう。空中に身を投げ出されたというのにぐったり目を閉じている。口と鼻から赤いものが伝い、吹き飛ばされていく二人の軌跡にぽつぽつと赤い点を残していく。
非常にまずい。
ここは二百階のタワービルのさらに上空だ。
身体能力に自信がある相澤とて流石に捕縛武器なしでこの高さを着地するのは難しい。
「西岐ッ、起きろ、西岐」
このままでは地面に叩きつけられミンチになってしまう。
こんなことなら、約束など捨てて自分が抹消を使ってしまえばよかった。ヴィランの顔は見えていた。一部でも見ればヴィランの個性は消せたはずだ。それでもそうしなかったのは、約束を交わした相手が西岐の保護者だったからに他ならない。『信頼を裏切る』という行為を西岐とその身内に晒すのが我慢ならなかったのだ。
ルールの中で生きるヒーロー、且つそれを叩き込む立場の教師、それを捨てられなかった。
「約束、守ってくださったんですね」
背後で声がしたと思うなり視界がホテルの一室に切り替わる。全身に受けていた風も夜明けの光も何もかもが消え失せ、バランスを崩して床にドカッと落ちた。
突然の移動に理解が追いつかず顔面を絨毯に貼りつけているすぐ間近に、品のいい革靴が見える。
相澤が顔を上げようとする前にその足はパッと消えた。
「……」
何が起きたのか混乱するまま、しかし腕の中でみじろぐ気配があって相澤は慌てて西岐を抱き起す。
ゆっくりと目を開き自分がホテルにいることをすぐ把握したのだろう。ちらっと窓の外を伺ってから、相澤を見上げる。
「……た、おせた?」
「ああ」
「やったあ……」
案外、いつもと同じ調子の声が出てきた。多少の疲労は見えるが、重症というほどではなさそうだ。ヴィランが倒せたと分かるなり小さく拳を握って嬉しそうに笑う。
「凄かった」
純粋に褒めてやるとより一層嬉しそうににやりと唇を吊り上げ、口周りの血の汚れを袖でグイッと拭いとる。
代償や後先考えない点は説教せねばとも思うのだが、西岐にしては珍しいその得意げな仕草があまりに胸をキュンとさせるものだから、相澤はまあいいかと嘆息して、ぽんぽんと西岐の頭を撫でた。
窓の向こう。
ボロボロになったタワービルに眩しいくらいの朝焼けが降り注いでいた。
「れぇちゃあああああん」
クラスメイト達とやっと顔を合わせた西岐は、数年ぶりの再会かと言わんばかりの大歓迎を受けた。女子からは代わる代わるハグされ、一部男子からもハグされ、つつかれ、肩を叩かれ、髪をぐしゃぐしゃ掻き混ぜられ、まあ人気だ。
ただし相澤が横にいることには疑問と不満を張り付けている。
暗間と交わした約束はIアイランドに滞在している間は変わらず有効で、片時も離れるわけにはいかないわけで。生徒たちの前でがっつり恋人繋ぎするのも問題があるので今は触れてもいないが、つかず離れず寄り添っている状態の相澤に痛いほど視線が突き刺さってくる。
開催予定だったIエキスポは破壊された施設の修復および安全確保の面から当分の間、開催が見送られることとなり、暇を持て余したA組一同はオールマイトとの『奢る』約束を果たすべく揃ってバーベキューに興じている。
野外で調理してその場で食べるというものにはじめは興味津々だった西岐だが、肉々しい食べ物を受け付けないのでドリンクだけ手にしてクラスメイト達と談笑している。
「れぇちゃん、あのさ」
会話がふと途切れたところで緑谷が控えめに声をかけた。
「あのさ……昨日、あのとき……あそこにいた?」
さすがの観察眼だと感心しつつ相澤は二人から少し視線をずらして、すっかり廃墟のようになったシンボルタワーを見上げる。
「……ううん。いなかったよ」
どこに、とも言われていないのに。
ゆるく首を振って否定する西岐に相澤は小さく笑う。
青い水平線。
吸い込まれそうなくらいの晴天。
ギラギラ照り付ける太陽。
夏の風がふわりと吹き抜けていった。
ネタバレを含みますので劇場版をご覧になっていない方はご注意ください。
劇場版を見ていないと内容がよく分からないと思います。
メリッサとデヴィットとは接触なし。メインキャラ達ともほぼ接触ないです。ずっと相澤先生のターンです。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。(本編の時期より早い段階で相澤先生と暗間が接触している等、時間軸での矛盾がありますが別時空だと思っていただけると幸いです。)
IアイランドでIエキスポが行われるというニュースや特番は随分前からテレビで流れていたし、夏休みが近付くにつれてクラスメイト達が大いに盛り上がっていたのは知っていた。ただ、西岐はそれをどこか他人事に感じていた。世界的に盛り上がるようなイベントと『イチ高校生の自分』とは国境以上の隔たりがあって、関わることなどないと思っていたのだ。
招待状が自宅に届くまでは……。
ポストに投函されていた封書にはプレオープンのチケットとレセプションへの招待状が同封されていて、案内状によると体育祭の上位入賞者に向けて贈られたという旨が書かれていた。
「ゆ、雄英ってすごい……」
学校行事のはずの体育祭で活躍したというだけで、あのサイエンスハリウッド、巨大人口移動都市に招待されるのだから本当に雄英というところは凄い。雄英に入学していなければ手にすることもなかったであろう招待状を握り締めて震えていると、相澤が横から覗き込んで短く嘆息した。
「タイミングだな。そうあることじゃない。今期の雄英生は無駄に引きが強い。良くも悪くも当たり年ってやつだ」
「……褒めてます?」
「褒めてるだろ」
相澤の物言いだとあまり褒めているようには聞こえないが普段より幾らか口角が緩んでいるところをみると割と機嫌がよさそうだ。
「い……行きたい」
遥か遠くのものだと思っていた場所へ招待されたのだ、行きたいに決まっている。
思わず口に出して、しかし、自分が今謹慎中だったことを思い出して、相澤に伺いの目を向けた。
期末試験を終えた先日、クラスメイトと一緒に訪れたショッピングモールで死柄木と遭遇し、立ち去ろうとする死柄木を追いかけた西岐。怪我を負うこともなく相澤によって無事救出されたが、勝手に危険な行動をとったことを怒られ、林間合宿まで自宅謹慎をするように言い渡されていた。二週間後の終業式もその後のIエキスポの開催期間も"謹慎中"だ。
この相澤に『例外』がある気がしない。
ダメと言われるに決まっている。
そう勝手に結論付けて項垂れる西岐の横で相澤は未だ招待状を眺めつつ、ぽつりと言う。
「行くか」
意外な一言をすぐには理解できず西岐は『そうですね』と項垂れたまま返事をした。
「世界的に活躍しているヒーローが警備やら招待やらで集まるし、何より一流の科学者の生み出す最新鋭のヒーローアイテムを目にする機会ってのはそうそうあることじゃない。さっきも言ったろ。これはお前の引きだ。得られる経験値は得たほうがいい」
まさかの『例外』が存在した。
ゆっくりと顔を上げてまじまじと相澤を見る。
「いいの……?」
「ああ、ただし俺も同伴する」
相澤の指が招待状の一部をとんと叩く。
『本状にて同伴者一名様までご参加いただけます』との一文。
勿論、相澤の同伴は大歓迎だ。というより一人で海外に行く勇気はない。
じわじわと西岐の表情に嬉しさが滲み始め、噛みしめるように招待状の端を摘まむ手に力を込める。
だが相澤は西岐の手から航空チケットを抜き取り、ぽりっと頬を掻く。
「ただ……お前、…………保護者の許可は下りるのか?」
相澤からの問いかけに西岐は「あ」と小さく零す。
はらりと招待状が滑り落ちた。
遠足、社会科見学、キャンプに修学旅行。
学校行事に必ずある校外学習のありとあらゆるものを西岐は経験をしたことがなかった。
それというのも西岐の後見人である叔父がことごとく『長距離移動を伴う行事へは参加しないように』と却下してくるからだ。正確に言うと叔父ではなく叔父の秘書が『駄目です』と一刀両断し、さっさと学校に不参加の連絡を入れてくれるわけだ。
実は林間合宿に行くことにも少々渋られた。電話越しの声があからさまに低くなり『林間合宿……わざわざ山に行く理由は何でしょう』と淡々と説明を求めてきたのは記憶に新しい。あの時は本当に苦労した。だって西岐にも山に行く理由なんて分からない訳で、説明のしようがない。ただどうしても行きたいという熱意だけは必死に伝えようと頑張って、なんとか渋々ながらも承諾を得られた。
その林間合宿に行く前に、今度は海外に行きたいだなんて、どう言えばいいのか。
テーブルに置いたスマホを緊張の面持ちで眺める。
ハンズフリーにしているのでスピーカーからコール音が聞こえてくる。
いっそ出なければいいのにと思うくらい緊張が高まった頃、プツリと途切れて柔らかな声が聞こえた。
「はい。暗間でございます」
彼の恭しげな話し方はいつもこちらを恐縮させる。
「れぇです」
「はい」
西岐が名乗ると存じておりますとばかりに丁寧な返事が返ってきて、一度開いたはずの口をきゅっと結んでしまった。
こうしたい、と自分の想いを伝えるのが本当に苦手だ。だって今までしてこなかった。思ったこともなかった。それがヒーローを目指すと決めたあの日からどんどん溢れてきて、心の内ばかりがまるで欲張りな人間のように変わってしまい、心の変化に行動力やら何やらが追いついていない状態だった。
それでも、相澤が口を出そうとする前にと声を絞り出す。
「あ、Iアイランド、行きたい……です。あのっ、体育祭、頑張ったから……招待状がきて、それで、俺行きたいんです」
こんなことくらい自分で言えないようではだめだと思った。緊張で声がひしゃげたが何とか思っていることを言葉に出来た。
「駄目です」
案の定、即答だ。
「な、なんで?」
「危険だからです」
あくまで柔らかな物言いだが西岐に有無を言わせない強さがあって、うまく切り返すだけの言葉が出てこなくなってしまう。
「Iアイランドは特殊拘置所タルタロスに匹敵するセキュリティを誇ります。危険ということはないはずです」
「……貴方は、相澤先生でしょうか」
「担任の相澤です」
「挨拶が遅れました。私、西岐の秘書をしています暗間と申します」
見兼ねてか相澤が口を挟み、それに対して暗間は丁寧すぎるくらいに挨拶を返した。
そうしてからスピーカーからフッと息が吹きかかったような微かな音がする。
「優秀なセキュリティ……そういうものが覆された時ほど凄惨なことになるとは思いませんか。それに航路での安全は保障されませんよね」
「……もっともです」
「っ、あ、俺、危ないことはしない。自分で自分を守る、だから」
何故か相澤が責めたてられているような具合になってきて西岐は二人の会話に声を被せた。学校関連のことでもないのに相澤に責任を向けるのはおかしな話だ。
しかし暗間は西岐の意見をぶった切る。
「自分で自分を守ってはいけません」
あまりのきっぱりした物言いに西岐は今何の話をしているのか見失いかけた。
「え、……え?……なんで?」
「なんででもです」
答えになっていない。相変わらずこの人の話は一方的だ。
「……私が同伴して護ります」
静かに、何でもないことのように相澤が言う。
「それはヒーローとしてですか、それとも担任としてですか」
「両方、あるいはイチ一般人の知人としてです」
迷いのない相澤の言葉を受けて暗間はしばらく沈黙した。何か考え込んでいるのか、それとも不快感を得たのか。声だけが頼りのこのやり取りの中で彼が何を考えているのかさっぱり分からない。
やけに沈黙が長く感じた。
「同伴している間、一切のヒーロー活動を放棄できますか?」
やっと言葉を発したと思うなり、彼が提示したのはとんでもない条件だった。
「どんな状況になっても、誰が窮地に立っていても……救けに行かず闘いにも行かず、その子から片時も離れず護ってもらえるのなら容認しましょう」
「――だめっ」
反射的に声を荒げていた。
プロヒーローに向かって誰も救けるなだなんて、そんな条件飲めるはずがない。
そこまでして行きたいなんて思わない。
そう続くはずだった言葉が相澤の手の中でもごもごと籠る。相澤がすかさず西岐の口を塞いだのだ。
「分かりました、約束します」
藻掻く西岐を押さえ込みながら相澤は少しも揺らがず答える。まるでそこに暗間がいるかのようにスマホへ真っ直ぐな視線を向けていた。
同伴中は一切のヒーロー活動を放棄すること。
片時も離れないこと。
目立つ行動はしないこと。
レセプションには参加しないこと。
以上が暗間からの承諾の条件だ。万が一破ることがあれば全責任は相澤がとるということになった。
西岐はしばらくの間この条件に猛反発していたが、そのうちに「何事も起きなければいいんだ」と考えを軌道修正したらしく「イレイザーさんには絶対迷惑はかけませんから」と息巻いていた。
正直、相澤は迷惑をかけられるとか責任を負うということ自体に胸が高揚していたので西岐の気遣いは余計だった。
保護責任者に挨拶して、ちゃんと護れるのかと値踏みされ、絶対に護ると誓う。この流れ、どう考えても"あの流れ"そのものにしか思えない。そもそも、一般的にはレセプションの同伴者は"そういう"間柄の相手と相場が決まっている。レセプション自体の参加は暗間に却下されてしまったが、Iアイランドへの同行が将来のリハーサルのようなものと思えば、是が非でも全責任を請け負いたかった。
何はともあれ承諾を得られて早三週間弱。
相澤は西岐と共にIアイランドに入国していた。
「わあ……わああああ……!」
出入国管理局を出て眼前に広がる景色に西岐の目がキラキラと輝く。
噴水が文字を綴ったり、音楽がカラフルな音符になって風船のようにふわふわ浮かび上がったり、透明なカプセルに乗った観光客が宙に浮かんだり、さながら一昔前のSF映画のような光景だ。
今日は未だプレオープンだというのに随分と賑わっていて、景色を見るのに夢中になっている西岐は右にフラフラ、左にフラフラと危なっかしい足取りで、人ごみに揉まれている間にうっかり見失っても可笑しくない。
相澤は大股で歩み寄って西岐の腕を掴み引き寄せる。
「"片時も離れるな"……だったよな」
そう言うと我に返ったのかハッと息を吸い込む口を手で押さえ、西岐の方からもツツツッと身を寄せてくる。
ただ重心がフラフラしているうえに、すぐ上の空になる西岐が身を寄せた程度ではぐれないように気を付けるのは難しいように思える。
だから相澤は手のひらを空に向けて西岐の脇に差し出す。
「……?」
それだけでは意図が伝わらなかったらしい。
視線が二度ほど相澤の手と顔を往復した。
「お手」
短く言い放つ。
すると反射的に手が持ち上がりパシッと軽い音を立てて重なった。
考えての行動ではなかったのだろう。相澤の手に自分の手を乗せてから驚いたように手を引っ込めようとして、相澤はその手を握りこんだ。逃げられないように指一本一本を股にくぐらせてがっちりと固定すれば、西岐は何が起きたのか分からないとばかりに瞠目する。
はぐれないように手を繋ぐという概念が彼にはなかったらしい。しばらくキョトンとしているが、じわじわと頬が紅潮していく。
「ち、ちっちゃい子じゃないから」
酷く子ども扱いされたと受け取ったようで手を揺すって逃げようを試みる。
どちらかといえばこれは所謂『恋人繋ぎ』というやつなのだが。その辺の認識は更にないようだ。
繋いだ手をグッと引き寄せると西岐の軽い身体が簡単に引き寄せられて一層ぴったりと寄り添う。指から手のひら、腕が絡まるように触れた状態で歩くことになる。そういうことを理解していない西岐を間近に見下ろして可笑しいやら愛おしいやら。自然と笑いがこみ上げてくる。
「小さい子供より手がかかる」
鼻で笑い飛ばして揶揄うとムウとむくれる。
「そんなこと……ないです」
「だったら大人しく繋がれてろ」
こんな役得をおいそれと手放すわけがない。西岐の微々たる抵抗を物ともせず繋いだままエキスポ会場を目指して歩き始める。
暫く納得がいかないような顔でくっついていた西岐だが、段々と周りに景色の方に気を取られていく。
あちらこちらを走り回っているロボットだとか、案内係のスタッフだとか、ファンにサービスしているヒーローだとか。見るものが多すぎて目が追いつかないのか足取りが怪しくなってきた。相澤が誘導していなければ何度か引き返したり方向転換したりしていたに違いない。
相澤たちが向かう数メートル先から大きな地響きのような足音と恐竜に似た咆哮が聞こえる。怪獣ヒーローゴジラだ。実績はともかく知名度と人気は世界トップクラスで、目の当たりにした西岐も目を輝かせた。
「すごぉい……ほんものだあ……」
感激のあまり空いていた手を添えて相澤に縋るようにぎゅうと抱きついてきた。
頭上のゴジラを見上げてはピコピコと踵が跳ねる。
死ぬほど可愛い。
「さ、サインしてくれないかなあ……」
「……無理じゃないか」
とはいえ自分以外のヒーローにやたら夢中になられているのも面白くない。延々とゴジラを眺めていそうな西岐を引き摺るようにパビリオンへ向かうのだった。
ここIアイランドに来た目的の一つ、最新のヒーローアイテムが展示されているパビリオン。
その建物の中は想像以上に凄い光景が広がっていた。
西岐の身近なヒーローが纏うスーツやアイテムといえば補助的な機能が多少はあれどどちらかといえばデザイン性が優先されているような感じだが、ここに展示されているものはどれも『身に着ける個性』とも言えるほどの機能を備えている。飛行潜水両用の多目的ビークル、深海七千メートルまで耐えられる潜水スーツ、三十六種類のセンサーが内蔵されたゴーグル、ありとあらゆるものが西岐の想像を遥かに超えて、しかし現物としてそこに存在していた。タルタロスに相当する警備システムによって守られているだけのことはある。
「でも、ちょっと怖いですね。……科学がヒーローを凌駕しそう」
科学の凄さに圧倒され、胸に広がった不安感がそんなふうに呟かせて、隣の相澤がしんなりと眉を顰めた。
「科学、バケ学、医学、生物学、そういうもんは時折人間を大きく超える。諸刃の智慧だな」
まるで映画の世界だ。
人間の偉大な智慧が人間のキャパシティを超えて牙を剥くようになったらと考えると空恐ろしい。
しかし圧倒的な科学を目の前にしても雄英の、いや、相澤の教えは揺るがない。
「けど、それを更に超えるのが、ヒーローってもんだ」
相変わらず叩き込まれる"校訓"に西岐は強張っていたものがフッと解けるのを自覚した。
「それにな、やっぱりヒーローに発明家ってのはつきものだろ。俺の捕縛武器だってあんな合理的なのをよく作ってくれたと思うよ」
「ふは……っ、そうですね」
細長いきしめんのようなデザイン性皆無の捕縛武器を思い出して堪らず肩を震わせる。あんなアイテムはきっと相澤以外に需要がないだろう。
ヒーロー一人一人がそれぞれに違う個性を持っていて、アイテムにそれぞれが違うサポートを求めるのなら技術が過ぎるということもないのかもしれない。
パビリオンを一通り見終えた後は、外のアトラクションを見て回る。
ふわふわ浮き上がるだけの乗り物の類はかったるいと却下され、三百六十度パノラマのプラネタリウムでは欠伸され、微妙に盛り上がりきらない。何か目が覚めるようなものはと視界を巡らせている中で、スピーカーを通したお姉さんの実況が耳に滑り込んできた。
どうやら参加型のアトラクションゲームのようだ。
ヴィランと想定されたロボットをどれだけの時間で打破できるかというシンプルなルール。
「一般入試と似た内容だな」
観客席の後ろから覗き込みながら相澤の一言を拾い上げて西岐は少々落ち着かなくなる。
入試内容。
体育祭で見たあの仮想ヴィランのロボットのやつか。
入試を受けていない身としては気になる。
自分がどれくらいの実力なのか。
「ってか、参加者……おいおい、うちの生徒ばっかじゃねえか」
モニターに映し出されているランキングとアトラクション敷地内にいる人影、それらが見知った名前・顔ぶれと分かるや渋い表情になっていく。
「一位……かつきくんか」
対ヴィラン向きのあの個性だ。
参加しているとなればこの順位は頷ける。
そしてどういうわけか観客席にいた緑谷に向かってがなり立てて、緑谷が飛び入り参加する流れになったらしい。職場体験以降、目にするようになった全身に走る電撃のようなもの、それらを纏ってヴィランを叩き潰していく。
結果は爆豪のタイムより一秒下回り、二位に。
「……すごい」
続いての参加者もまた見知った顔。
轟の氷結が一気に岩山を覆い隠すように広がって爆豪のタイムを超え一位に成り上がった。相変わらずの瞬殺ぶりに会場が大きくどよめいている。
海を渡って世界のヒーローやアイテムを見に来たというのに、こんなところでもクラスメイトの凄さを突きつけられようとは。激しい羨望と無視できないほどの張り合う気持ちが胸の中で膨らんできた。
「イレイザーさん……」
「おい」
ざわざわとする気持ちが西岐を前のめりにさせる。
今にもアトラクション敷地内へ降り立ちそうな西岐を相澤の手が押しとどめる。
「駄目だ。目立つなって言われただろ」
「……目立たなきゃいいですよね」
今着ているのはクラスメイトたちみたいなヒーロースーツではなく私服だ。羽織っているパーカーのフードを頭に被せてそう示すと、相澤の顔色が悪くなる。
「そういう屁理屈は通用しない」
「常にトップを取りに行くくらいの気持ちじゃなきゃダメなんですよね。俺、今トップ取りたいです」
「あのな、そんなことすればめちゃくちゃ目立つだろうが」
繋がれている手により力が込められて痛いくらいに軋んだ。
こうと思ったら考えを曲げられない上に、ルールや戒めというものから時折どうしてか外れていってしまう性質が西岐にはあって、暗間と交わした約束や相澤に降りかかる責任というものが思考から薄れてしまう。
「大丈夫、今はプレオープンで中継もされていない。バレませんよ」
昂る闘争心とは裏腹にやけに冷静な部分があって、ざっと辺りを見渡してカメラがないことは確認済みだ。
もう、抑制を放って相澤を振り切ろうかと思いかけた西岐を、恐らく察したのだろう。相澤の髪がざわっと僅かに浮き上がりいつでも抹消できる構えになって、これまで以上に厳しい声音を放った。
「ヒーロースーツなしのお前がどうやってあれを潰すつもりだ?」
「……抑制で」
「離したらまた動き出すだろ。一体だけじゃないんだぞ」
「……うっ」
相澤のズバリな指摘が盛り上がっていた気持ちを引き戻す。
もっともすぎて反論が出ない。
ロボット相手では幻影も効かないし個性を封印することもかなわない。あれだけやる気になっておきながらまさか勝算がないなんて……。
「帰ったら似たような授業やってやるから、その意欲はぜひ学校で発揮しろ」
西岐の気持ちが萎んだところで相澤がにたりと意地の悪い笑みを浮かべたのだった。
人工島とは思えない広大な敷地内には今回のエキスポ会場もさることながらさまざまな施設が充実していて、とても一日で周回することはかなわず、日が傾いた頃にホテルへ入った。
学生への招待にしては随分と豪華な部屋だ。この島のホテル自体がこの基準なのか、西岐への招待が特別なものなのか。少なくともこの部屋がホテルの最上階にあるということはそれなりの特別扱いを受けているのだろう。体育祭での西岐の活躍に余程の関心が寄せられたのか、もしくは彼の保護者が何かしたのか。
ぼんやりと夜景を眺めては何とはなしに考えを巡らせていると、バスルームの扉が開く音に続いて、パタンパタンとスリッパを踏み鳴らす音が聞こえてきた。そちらを見ないよう頑なに窓の外を凝視していたのだが、ガラスに湯上り姿の西岐が映りこんで、相澤はゴンッと額をガラスにぶつける。
「だ、だいじょうぶ?」
西岐は相澤が自ら頭部に打撃を加えたなどと露ほども思わずに近付いてくる。
手のひらを翳して大丈夫だということと来なくていいという意思表示をすると不思議そうにしつつも、方向転換して冷蔵庫からドリンクを取り出している。
それを横目でちらっと覗き見して息を吐く。
ホッとしたのではない、重い溜息だ。
チェックインして部屋に入った時も、ラウンジで食事した時もあまり気にしていなかったのだが、同じ部屋で一晩過ごすということがここにきてじわじわと苛み始めていた。
これまでも西岐宅に泊まることはあったし、風呂上りや寝起きの顔だって見慣れている。しかしこう"特別な空間"を演出した部屋にいると、教師という立場を忘れて暴走してしまいそうになるのだ。
この島に来た動機も割と邪だったし、今日一日連れ歩いているさなかも"そういう"気分に浸りきっていたが、でもあれはあくまで"ごっこ"の域を出ない、所詮は戯れ程度のことだった筈だ。それがよもや本当に"そう"なってしまいかねない酷く危うい状況に陥ろうとは……。
だというのに、西岐はいつものごとく自分の格好がどうなっているのかなどということには無頓着で、濡れた髪を肌に貼りつけたままソファーにちょこんと腰かけてテレビのリモコンをいじっている。フルーツウォーターのボトルを傾けるたびに水滴が白い喉を伝う。ガウンという腰ひもで纏めるだけの簡素な着衣が、何かするたびに捲れ、はだけ、着ているんだか引っ掛けているんだか分からない状態だ。ソファーの上で体育座りのように膝を抱えて座るものだから、うっかり見えてしまう。何がとは言わないが。
「……フロハイッテクル」
なるべく心を無にしようと努めた結果、片言になった相澤を西岐が戸惑いの目で見送る。
やたら広いバスルームとバスタブ。これ二人で入れるんじゃないかと考えてから何を馬鹿なと自嘲しつつ、シャワーブースに足を向けた。雑念を洗い流すべく勢いよくお湯を頭からかぶる。気分は滝行だ。長い髪と湯の滝の内側で何度目か分からなくなった溜息をついた。
やたら無意味に全身隈なく綺麗に洗いバスルームを出ると、西岐の姿が見当たらない。先程のソファーにはリモコンとドリンクのボトルが転がっていて、つけっぱなしのテレビからアニメーション映画が流れている。窓辺の椅子にも、違うソファーにも、姿がない。
寝室の扉を静かに開く。
相澤の想像通り、ベッドの真ん中で丸くなって眠っている。
シーツと一緒に下敷きにされているのは相澤の着ていたシャツだ。慣れないホテルの中でそれに安心を求めたのだろうか。
眠りに落ちる直前まで握っていたのか手の近くにスマホが転がっていて、ピロンピロンと電子音を途切れ途切れ鳴り響かせている。ディスプレイにはクラスメイト達の名前が見えた。
「あーあ……」
零れ落ちた乾いた声。
「これだもんなあ……」
全然これっぽっちも意識されていない。
全力で油断されている。
信頼の証と言えば聞こえがいいが西岐の中で相澤は保護者なのだ。
そして心の拠り所はいまやクラスメイト全員に分散している。特別でも何でもない。
けれど、今はまだそれでいい。
目指すものの途中にいる"生徒"を導いてやる"教師"という立場を未だ手放すつもりはなかった。
音を立てないようにそっと傍らに腰かけ、西岐の髪を撫でる。サラサラと指から逃げていくのを絡め取り、感触を味わいつつ頬に滑り落とす。擽ったそうにイヤイヤと首を振るあどけない横顔に、相澤の眼差しが和らぐ。
つけっぱなしのテレビでも消してくるか、と腰を上げたその時。
唐突に警報が鳴り響いた。
『Iアイランド管理システムよりお知らせします。警備システムによりIエキスポエリアに爆発物が仕掛けられたという情報を入手しました。Iアイランドは現時刻を以って厳重警戒モードに移行します』
室内のスピーカーから聞こえてくる不穏なアナウンスに相澤が身構え、西岐もまた何事だと飛び起きた。
「……ばくだん」
明らかに寝惚けた声音で、しかし迷いなくベッドから飛び降りて手荷物を入れたクローゼットに向かう。キャリーを開いて着替えを引っ張り出すのを見て相澤は西岐の肩を掴んだ。
「外出するなって指示だ。ここの警備システムに任せればいい」
西岐の行動が逃げる為でも備えでもなく、爆弾というイレギュラーを解決しようとするべくなのは考えるまでもない。
反射行動。
呆れるほど、彼は常に『ヒーロー』で居る。
「でも、こんな格好じゃ……いざとなったら」
「いざとはならない」
「……なるかもしれないでしょ」
相澤の言うことも素直に聞きはしない。
しかし非常事態なのは間違いなく、実際に避難や何かでいざということは起こりうるかもしれない。結局、相澤も西岐と共にガウンからいつもの私服に手早く着替え、ソファーに移動した。
スマホやネットが繋がらないのはともかくテレビまで映らなくなっている。情報という情報すべてがシャットアウトされているのだろうか。
「……なんか……街中、警備ロボットが……」
何もないはずの壁や斜め下の床に西岐の目が向く。
「警備しているっていうより……制圧してるように見えるけど」
手で鼻と口を軽く覆い、困惑を隠すことなく呟く。そうすることで自分を落ち着かせ、窓ガラスの向こう側にそびえたつ、島で一番高い建物を見上げた。西岐の目がどういうものなのか知らなければ一種異様に見えるに違いない。
「……警備システム」
まるでそこにあることを"把握"しているかのように真っ直ぐ見つめる西岐を、相澤は止めるべきなのか迷いながら、しかし現状を知りたい気持ちが制止の言葉を飲み込ませた。
二百もの階層を視線で探っているのだろう。少しの間沈黙が続き、時折辛そうに眉間を拳で叩く。
「…………あ」
何かに視線が到達したらしい。
表情が一層強張ったと思うなり身体を縮こませた。
「オールマイト……さん」
タワービルに目を向けた状態のまま引き攣った声で名前を呼ぶ。
西岐が心の拠り所にしている一人であり、雄英の教師、そして平和の象徴と呼ばれるNo.1ヒーロー、オールマイト。彼なら高い確率で来ているとは思っていた。
ただ、今の声は知り合いを見つけたという類の調子ではない。
鋭利になった西岐の纏う空気が、隣にいる相澤の肌をざらざらと撫でる。
ぱち、ぱちと数秒おきに繰り返す瞬き。目蓋が開くごとに見える瞳が張り詰めていく。ソファーに座ってはいるものの今にも飛び出していきそうな表情に、相澤は堪らず再び肩を押さえつける。
「……ヴィランに警備システムごとレセプション会場が占拠されていて、一般人を人質に取られてオールマイトさんは動けません。デクくんたちが警備システムを正常に戻すために最上階に向かっているそうです」
いやに落ち着いた声で相澤に説明する。こういう時ほど感情的な状態に近い。
「なんで分かる」
「え、と……聞こえて」
目で"視"ただけでは知り得ない情報までつらつらと妙に詳しく説明して見せる様に相澤は眉間を寄せ、怪訝に問いを向ける。すると急に言葉を詰まらせ、一瞬だけ視線が相澤のほうに戻った。感心するほど嘘や誤魔化しが下手だ。
それにしても、レセプション会場が占拠とは。
なんだろう、この符合。
暗間が言っていた"危険"がまさに参加するなと言われていたレセプション会場で起きているのだ。ひょっとしてあの人はこうなることを知っていたのではないのか。しかし、だとすれば普通の立場の人間では到底あり得ない。
「イレイザーさん、デクくんたちが……」
どんどん緊迫していく西岐の声音。
相澤とて受け持ちの生徒が関わっていると知って心穏やかではない。視線で問い返す。だが返事を聞かずとも耳にした名前で状況は何となく想像がついてはいた。
ビルの上層階で何人もの生徒たちがヴィランと、或いは警備ロボットと戦闘していると。西岐が言う。
それもそうスムーズではないのだろう。見知った姿を見つけるたびに西岐は息を詰まらせる。
今すぐ行けるのに、行きたいのに、暗間との約束が枷になっていて、ソファーから立ち上がれもしない。
なるほど。
あの約束は相澤ではなく西岐を動かさないためのものだったわけだ。
タワービルの最上階でヴィランを食い止める緑谷と、警備システムのある部屋へ走る少女。彼女はオールマイトの話によればメリッサという名前で親友の娘らしい。
警備システムが正常に戻され人質という枷から解放されたオールマイトはメリッサからの電話を受けながら最上階に向かう。
オールマイトの焦りや怒りが西岐の胸に流れ込む。
このテロ行為はオールマイトの親友、デヴィットが仕組んだということ。そのデヴィットがヴィランに連れ去られようとしていること。今、それをデクが食い止めるべく一人奮闘していること。
西岐は心でオールマイトからの声を聞きながら、目はヘリから突き落とされる緑谷を捉え、耳が複数の音を拾い上げている。
「っ……」
地面に叩きつけられる緑谷。
遠ざかるヘリのなかで血を擦り付けながら倒れるのがオールマイトの親友デヴィットか。
何もしなくていいのか。
ここでじっと見ているだけなのか。
自問自答がずっとぐるぐる巡っている。
ここは個性の使用が認められている特殊な人工島Iアイランド。ヴィランと戦うことに何の縛りもないはずだ。だから緑谷たちは闘っている。
けれど西岐には暗間との約束がある。けしてヒーロー活動をしないこと。何が起きても、誰がピンチになっても救けにはいけない。
「…………」
あれ、と首を傾げる。
――いや、違う。
「ヒーロー活動を放棄したのは……イレイザーさんだ」
西岐自身は何の制約も受けていない。ただ離れるなというだけのことだ。闘うなとも救けるなともいわれてはいない。
はたと思い至って相澤の神妙な顔を見る。長いこと遠くへと視線を投げていたせいで上手くピントが合わせられずパチパチと瞬いた。視界が鮮明になるにつれ、西岐の心も晴れていく。
「離れさえしなきゃ、俺は救けていい」
肩に乗せられている大きな手に自分の手を重ねる。
「……屁理屈だ」
アトラクションゲームに参加しようとした時と同じセリフが相澤の口から出てくるが、あの時とはかなり意味合いが違う。相澤も生徒たちの安否を懸念していたのだ。『良し』とははっきり言わないが口端がグッとつり上がって明らかに賛同している。
意識と視線が逸れていたタワービルから、聴覚へ直に叩きつけるような騒音が鳴り響いた。
もう、遠目遠耳を駆使しなくても分かる。
振動でバリバリと音を立てるガラスの向こうに、到底人間とは思えない様相のヴィランがタワービルの屋上に纏わりついている。触手のごとく蠢く金属と複雑に絡まっては自身とデヴィットを匿う本体部分。もうあんなもの、ヒトの領域を超えている。
昼間パビリオンで感じた脅威があそこにある。
ふう、と息を吐く。
キンと頭の奥が冷たく張り詰める。
「……金属」
――あれは金属。
「イレイザーさん、俺を掴んでて」
言うが早いか西岐と相澤の身体は一瞬でホテルの部屋から空中に移動していた。
タワービルの屋上、それより遥か上空。
濃紺の空と真下に街の明かり。
物凄く強い風が身体を煽り持っていかれそうになる。ただ、宙を使って自身の動きをコントロールするのは西岐の常套手段だ。器用にバランスを取り滑空していく。
オールマイトと緑谷に気を取られこちらに気付く様子もないヴィランの頭上に降り立つ。金属を纏っているせいで感覚が遮断されているのか、乗られていることにさえ気づかない。
この分厚い装甲。
これが金属なのであれば抑制が効く。
ヴィラン自身にも届くはず。
「ただし、それなりのエネルギーが要る」
ぽいぽいとスリッパを脱ぎ捨てる。
抑制。
体内にある無数の蓄電細胞を部分的に直列加算して放出している。
スイッチと放出口は両手、そして両足。
脳から一番遠い場所にある足の裏は全身の蓄電細胞を直列加算にして放出することが出来る。正確に言えば、手よりも耐えられる。
つまり電圧が上がり、放出できる電気の量も勢いも増す。
素足でヴィランの纏う鉄を踏みつけ、パチと小さな火花が散る。
それを皮切りに飛び散る火花が大きく激しくなり、足の裏が一気に熱を帯びた。
「――ッ」
相澤が息を飲む。
手のスイッチを入れていないから繋いでいるそこから通電することはないが、ホテルのスリッパでは絶縁しきれなかったらしく、足を付けている金属を介して抑制を受けてしまったらしい。
申し訳なく思いながらも、放電を弱めることはなく、寧ろ増していく。
オールマイトと緑谷に降りかかる金属の攻撃が止まっていない。
末端まですべて通電する必要はない。
本体に届きさえすればいい。
「っう、あ、ああ」
接触している足の裏が熱いを通り越して痛い。
頭が痺れていく。
鼻と喉の奥がツンと痛い。
止めなければ。
止めなければ。
自分だってヒーローだ。
誰かを救けたい。
止めなければ。
「あァあああ、ア゙ああ」
全身からエネルギーというエネルギーをこそぎ出す。
全身を駆け巡るエネルギーにぞわりぞわりと神経を撫でられ猛烈な吐き気がこみ上げてくる。
二つの拳が振りかざされるのが見える。
ギッと軋む音を最後にあれだけの騒音が止んだ。
一瞬の静寂。
それを叩き潰すように二つの拳がヴィラン目掛けて叩きつけられた。
勢い良く粉砕して吹き飛んでいく金属片。
吹き荒れる拳圧の風。
ヴィランの一部になっていた金属片と一緒に西岐と相澤が吹き飛んでいく。
あれだけ巨大に育った鉄の塊を吹き飛ばす一撃だ。
吹き飛ばされる勢いも凄まじい。
抑制が解け動けるようになった相澤が空中で西岐を抱きかかえる。
限界の限界を突き抜けたのだろう。空中に身を投げ出されたというのにぐったり目を閉じている。口と鼻から赤いものが伝い、吹き飛ばされていく二人の軌跡にぽつぽつと赤い点を残していく。
非常にまずい。
ここは二百階のタワービルのさらに上空だ。
身体能力に自信がある相澤とて流石に捕縛武器なしでこの高さを着地するのは難しい。
「西岐ッ、起きろ、西岐」
このままでは地面に叩きつけられミンチになってしまう。
こんなことなら、約束など捨てて自分が抹消を使ってしまえばよかった。ヴィランの顔は見えていた。一部でも見ればヴィランの個性は消せたはずだ。それでもそうしなかったのは、約束を交わした相手が西岐の保護者だったからに他ならない。『信頼を裏切る』という行為を西岐とその身内に晒すのが我慢ならなかったのだ。
ルールの中で生きるヒーロー、且つそれを叩き込む立場の教師、それを捨てられなかった。
「約束、守ってくださったんですね」
背後で声がしたと思うなり視界がホテルの一室に切り替わる。全身に受けていた風も夜明けの光も何もかもが消え失せ、バランスを崩して床にドカッと落ちた。
突然の移動に理解が追いつかず顔面を絨毯に貼りつけているすぐ間近に、品のいい革靴が見える。
相澤が顔を上げようとする前にその足はパッと消えた。
「……」
何が起きたのか混乱するまま、しかし腕の中でみじろぐ気配があって相澤は慌てて西岐を抱き起す。
ゆっくりと目を開き自分がホテルにいることをすぐ把握したのだろう。ちらっと窓の外を伺ってから、相澤を見上げる。
「……た、おせた?」
「ああ」
「やったあ……」
案外、いつもと同じ調子の声が出てきた。多少の疲労は見えるが、重症というほどではなさそうだ。ヴィランが倒せたと分かるなり小さく拳を握って嬉しそうに笑う。
「凄かった」
純粋に褒めてやるとより一層嬉しそうににやりと唇を吊り上げ、口周りの血の汚れを袖でグイッと拭いとる。
代償や後先考えない点は説教せねばとも思うのだが、西岐にしては珍しいその得意げな仕草があまりに胸をキュンとさせるものだから、相澤はまあいいかと嘆息して、ぽんぽんと西岐の頭を撫でた。
窓の向こう。
ボロボロになったタワービルに眩しいくらいの朝焼けが降り注いでいた。
「れぇちゃあああああん」
クラスメイト達とやっと顔を合わせた西岐は、数年ぶりの再会かと言わんばかりの大歓迎を受けた。女子からは代わる代わるハグされ、一部男子からもハグされ、つつかれ、肩を叩かれ、髪をぐしゃぐしゃ掻き混ぜられ、まあ人気だ。
ただし相澤が横にいることには疑問と不満を張り付けている。
暗間と交わした約束はIアイランドに滞在している間は変わらず有効で、片時も離れるわけにはいかないわけで。生徒たちの前でがっつり恋人繋ぎするのも問題があるので今は触れてもいないが、つかず離れず寄り添っている状態の相澤に痛いほど視線が突き刺さってくる。
開催予定だったIエキスポは破壊された施設の修復および安全確保の面から当分の間、開催が見送られることとなり、暇を持て余したA組一同はオールマイトとの『奢る』約束を果たすべく揃ってバーベキューに興じている。
野外で調理してその場で食べるというものにはじめは興味津々だった西岐だが、肉々しい食べ物を受け付けないのでドリンクだけ手にしてクラスメイト達と談笑している。
「れぇちゃん、あのさ」
会話がふと途切れたところで緑谷が控えめに声をかけた。
「あのさ……昨日、あのとき……あそこにいた?」
さすがの観察眼だと感心しつつ相澤は二人から少し視線をずらして、すっかり廃墟のようになったシンボルタワーを見上げる。
「……ううん。いなかったよ」
どこに、とも言われていないのに。
ゆるく首を振って否定する西岐に相澤は小さく笑う。
青い水平線。
吸い込まれそうなくらいの晴天。
ギラギラ照り付ける太陽。
夏の風がふわりと吹き抜けていった。
create 2018/08/05
update 2018/08/05
update 2018/08/05