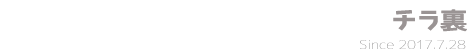治崎
甘やかな痛みをあなたの手で
甘やかな痛みをあなたの手で
ピアスをあけるお話。
短いです。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
薄い皮膚を針が貫く。
その感覚を想像して手が震える。
「ううう……やっぱり恐いよ……やめようよ……」
情けないほど弱気な声が滑り落ちた。取り繕う余裕など今はない。
怖い。
物凄く怖い。
こんなの絶対痛い。
堪えられない。
この場から逃げ出したくて仕方がない。
今にも泣きだしそうな顔で目の前の人物をじっと見つめていると、心底呆れたような溜息をつく。
「あのな……お前の耳に穴が開くわけじゃない」
「あ、あ、まって、動かないで、針刺さっちゃうから……っ」
おもむろに顔を上げた治崎の耳から宛がっていたピアッサーを慎重に遠ざけて、ひとまず安全な状態になってホッと息をつき、じっとりと汗が滲んだ手をきゅうと握った。
「刺さるも何も、当たってないからな」
ピアッサーのピアスとキャッチの間の空間に耳たぶを挟み込むというのがどうにも出来ず、数センチ離れたところでモダモダしていたことを指摘しては、うんざりと眉を顰める治崎に、だったら自分でやるか玄野にやらせるかすればいいのにと思いながら、西岐は『だって……』と項垂れる。
何がきっかけだったか。
治崎の左耳のピアスを見て『これって痛くないの?』と聞いたことだったか、正確には忘れてしまったが、久しぶりに会った今日、唐突にピアッサーを突きつけて開けろと言い放ってきたのだ。
いや、もう、……なんで自分に?と困惑しては散々逃げ回ったのだが、やらないなら西岐の耳に穴をあけるとまで言われて泣く泣くピアスを開けてあげるという状況になった訳だ。
身体に針で穴をあけるだなんてこんな恐ろしいことをただのファッションのために行うだなんて信じられなかった。
元々、痛みに強いわけでもなく、血を見るのも苦手だし、ヒーローを目指す中で怪我を負うことも増えたが自ら痛みを享受するというのはまた別の話だ。とんでもない。
なのに、……それなのに、この手で今まさに行おうとしているのだ。
信じられない。
もしかしてこれは新手の嫌がらせなのではないだろうかと思ってすらいる。ここまで全力で嫌がっているうえに失敗の確率の高そうな西岐にわざわざやらせるあたり嫌がらせという可能性は濃厚だ。
変なところに変な風に穴が開いてもいいというのだろうか。
責任……はとれなくはない。レストアという手がある。やり直しは効く……とはいえ冒険が過ぎる。
「……いいから早くしろ」
ぐるぐる思考の渦に飲まれている西岐に手厳しい声がかかった。
「やだあ……もう、こわいもん」
とてもではないが人様の耳に穴をあけるなんて出来ない。
もう一度ピアッサーを耳に宛がう気持ちにはなれず、すっかり怯えきっている西岐の頬に治崎の指が触れた。スルッと横髪を耳に引っ掛け、露わになった耳朶の柔らかな部分をツンと引っ張る。
「……っ」
恐怖を感じて身構える前に人工物の感触を受けた。
いつの間にか、手に持っていたはずのピアッサーが今、自分の耳に充てられている。
シュッと音が立つほど勢い良く息を吸い込みそのまま動けなくなる。治崎の耳に穴を開けようとしていた時の恐怖がそっくり自分の身に降りかかっているのだから、動けるはずがない。
「や……」
ハンドル部分に力が加わったのか仄かに軋んだ音がして恐怖が増幅した。
じわじわと視界が滲む。
「真っ直ぐになるように持って」
西岐にお手本でも示しているつもりなのか。
随分近いところで治崎の声がする。こめかみのあたりに吐息が吹きかかり少し唇が触れている気がする。
「あとは……躊躇わず一息に、押し込む」
ぐっと手に力を込めるような気配を感じた。
短く悲鳴が零れる。
やだ。
痛い。
痛いのがくる。
やだ。
恐怖にぎゅっと目を瞑って身構える。
いつくるのか、どれくらい痛いのか予想がつかない恐さが、西岐を何秒も何秒もじっと身構えさせた。
どれくらいそうしていただろうか。
随分経った気がするがまだ何も起きていない。
痛みがない。
何も音が立たない。
触れている人工物的な感覚に変わりがなく、しかも西岐が目を開くのと同時にそれが離れていった。
滲む視界に映るのは未使用のピアッサーで治崎はしれっとした顔で西岐の手に返してきた。
「っ……!!!」
脅かされただけだと察するなりカッと顔が熱くなる。
非常に腹立たしい。
ぽすんっとグーで治崎の胸を叩く。一度では気持ちが治まらず二度三度叩いては、うううっと低く唸る。全く効いてないという顔がより一層腹立たしい。
「もおっ、ばか、ばか」
腹立たしいやら怖かったやら腹立たしいやらで、返されたピアッサーを全力で部屋の隅に向けて放り投げる。壁に当たったそれが乾いた音を立てて床に転がるが治崎はニヤニヤと口角を吊り上げている。耳に穴をあける道具が床に転がっても気にしないところを見ると、使う気がなかったとしか思えない。やはり治崎の目的はピアッシングそのものではなかったらしい。
「お、俺をからかったな……!」
「面白いくらい怯えるから」
「うーーーっ、もお、もおっ怒るっ」
悪びれもなく白状する治崎にいよいよ膨れっ面になって、行き場のない怒りをぶつけるようにソファーのクッションにダイブし、バタバタと両手をクッションに叩きつけた。
その手を押さえつけるかのように覆い被さってくる。
耳たぶに吸い付く感触がある。
「お前にピアスを開けさせたいのは本当だ。それで、同じ場所にお前も開ける」
「やだ、こわい」
触れている個所からじんわりと熱くなっていくような気がする。
「顔を真っ赤にして泣きながらピアスを開けるって……なんかえろいだろ」
「…………へんたい」
「そういう事言うなら耳以外に開けるぞ」
あまりの変態的な思考が理解できなくてボソリと呟くと、耳に直接低い声が注がれた。
耳以外ってなんだ。
……耳以外ってなんだ!
「例えば、そうだな…………こういうところ、とか」
クッションと身体の間に手が滑りこんでスルスルと胸元を滑っていく。とある一点をとんとんとつつく。
「あと、こういうところ、とか」
もう片手が下腹部をなぞり、とんでもないところを強く押して示した。
少し混乱して何の話か分からなくなりかけているが、針で穴をあけるという話だった、筈。
まさか。まさか……だ。考えただけで背筋が凍る。
「……やだ」
もう少し反論の仕方というものがありそうなのだが『嫌だ』と言うこと以外思いつかない自分が恨めしい。
こうなると本格的に泣きが入る。
背後で身体をまさぐる治崎という男が西岐を泣かすことに悦びを見出す変態なのだと分かっていても泣くしかない。うううっと唸りながら身体を左右に揺らして剥がそうと試みてみるも、逆にやすやすと押さえ込まれてしまう。
「み、っみみでいい……」
ふにゃりと力の入っていない声で言うと閉じ込めていた腕の力が幾らか緩まった。
「開けるか?」
「……ん、あける」
また耳たぶに吸い付く感触がして、今度は硬く薄いものが触れる。力を込めたり緩めたりしては湿ったものがなぞって、ぞわぞわと肌が粟立つ。
やっていることは変わっていないのだが何となく治崎の纏う空気が柔らかくなった気がした。
ぐっと腕を突っぱねて起き上がろうとすると、すんなり背中から剥がれる。
「でも、あれ使えなくなっちゃったけど……どうするの?」
先程壁に叩きつけたピアッサーを指さす。針自体が床と接触していないだろうし、消毒し直せば問題ないのかもしれないが、潔癖症の治崎がそれを良しとはしなさそうだ。
新しいものを用意するまでもしかしたら猶予が生まれるのではという儚い期待が生まれるが、しかし治崎がソファー脇の小さなケースを開くことでその期待は本当に儚く散った。
「あれはお前でも扱えるかと思って用意したもので、本来はこっちを使う」
今まで彼が医療用のものを持ち出したときに何度かお目にかかったビニールの保護フィルム。その内側でキラリと光を反射している銀色の棒が見える。あれほど恐怖を煽られたピアッサーがプラスチックのオモチャに思えてくるほど、あの鋭利な針のようなものが与えてくる悪寒は凄まじい。
ここまでの流れは掌握のことだったのだろう。
治崎の口端が愉悦に歪んだ。
結局、悪い方向に有言実行な治崎から逃れられず、ニードルを持っては泣きを入れ、散々べそをかきながら治崎の耳を貫通させ終えた後、死ぬほど泣き喚く中、押さえ込まれて耳に穴をあけられたのだが。
その後、帰ってきた玄野が物凄く羨ましがって同じことをもう一度やる羽目になったのは、本当に最高に災難だった。
短いです。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
薄い皮膚を針が貫く。
その感覚を想像して手が震える。
「ううう……やっぱり恐いよ……やめようよ……」
情けないほど弱気な声が滑り落ちた。取り繕う余裕など今はない。
怖い。
物凄く怖い。
こんなの絶対痛い。
堪えられない。
この場から逃げ出したくて仕方がない。
今にも泣きだしそうな顔で目の前の人物をじっと見つめていると、心底呆れたような溜息をつく。
「あのな……お前の耳に穴が開くわけじゃない」
「あ、あ、まって、動かないで、針刺さっちゃうから……っ」
おもむろに顔を上げた治崎の耳から宛がっていたピアッサーを慎重に遠ざけて、ひとまず安全な状態になってホッと息をつき、じっとりと汗が滲んだ手をきゅうと握った。
「刺さるも何も、当たってないからな」
ピアッサーのピアスとキャッチの間の空間に耳たぶを挟み込むというのがどうにも出来ず、数センチ離れたところでモダモダしていたことを指摘しては、うんざりと眉を顰める治崎に、だったら自分でやるか玄野にやらせるかすればいいのにと思いながら、西岐は『だって……』と項垂れる。
何がきっかけだったか。
治崎の左耳のピアスを見て『これって痛くないの?』と聞いたことだったか、正確には忘れてしまったが、久しぶりに会った今日、唐突にピアッサーを突きつけて開けろと言い放ってきたのだ。
いや、もう、……なんで自分に?と困惑しては散々逃げ回ったのだが、やらないなら西岐の耳に穴をあけるとまで言われて泣く泣くピアスを開けてあげるという状況になった訳だ。
身体に針で穴をあけるだなんてこんな恐ろしいことをただのファッションのために行うだなんて信じられなかった。
元々、痛みに強いわけでもなく、血を見るのも苦手だし、ヒーローを目指す中で怪我を負うことも増えたが自ら痛みを享受するというのはまた別の話だ。とんでもない。
なのに、……それなのに、この手で今まさに行おうとしているのだ。
信じられない。
もしかしてこれは新手の嫌がらせなのではないだろうかと思ってすらいる。ここまで全力で嫌がっているうえに失敗の確率の高そうな西岐にわざわざやらせるあたり嫌がらせという可能性は濃厚だ。
変なところに変な風に穴が開いてもいいというのだろうか。
責任……はとれなくはない。レストアという手がある。やり直しは効く……とはいえ冒険が過ぎる。
「……いいから早くしろ」
ぐるぐる思考の渦に飲まれている西岐に手厳しい声がかかった。
「やだあ……もう、こわいもん」
とてもではないが人様の耳に穴をあけるなんて出来ない。
もう一度ピアッサーを耳に宛がう気持ちにはなれず、すっかり怯えきっている西岐の頬に治崎の指が触れた。スルッと横髪を耳に引っ掛け、露わになった耳朶の柔らかな部分をツンと引っ張る。
「……っ」
恐怖を感じて身構える前に人工物の感触を受けた。
いつの間にか、手に持っていたはずのピアッサーが今、自分の耳に充てられている。
シュッと音が立つほど勢い良く息を吸い込みそのまま動けなくなる。治崎の耳に穴を開けようとしていた時の恐怖がそっくり自分の身に降りかかっているのだから、動けるはずがない。
「や……」
ハンドル部分に力が加わったのか仄かに軋んだ音がして恐怖が増幅した。
じわじわと視界が滲む。
「真っ直ぐになるように持って」
西岐にお手本でも示しているつもりなのか。
随分近いところで治崎の声がする。こめかみのあたりに吐息が吹きかかり少し唇が触れている気がする。
「あとは……躊躇わず一息に、押し込む」
ぐっと手に力を込めるような気配を感じた。
短く悲鳴が零れる。
やだ。
痛い。
痛いのがくる。
やだ。
恐怖にぎゅっと目を瞑って身構える。
いつくるのか、どれくらい痛いのか予想がつかない恐さが、西岐を何秒も何秒もじっと身構えさせた。
どれくらいそうしていただろうか。
随分経った気がするがまだ何も起きていない。
痛みがない。
何も音が立たない。
触れている人工物的な感覚に変わりがなく、しかも西岐が目を開くのと同時にそれが離れていった。
滲む視界に映るのは未使用のピアッサーで治崎はしれっとした顔で西岐の手に返してきた。
「っ……!!!」
脅かされただけだと察するなりカッと顔が熱くなる。
非常に腹立たしい。
ぽすんっとグーで治崎の胸を叩く。一度では気持ちが治まらず二度三度叩いては、うううっと低く唸る。全く効いてないという顔がより一層腹立たしい。
「もおっ、ばか、ばか」
腹立たしいやら怖かったやら腹立たしいやらで、返されたピアッサーを全力で部屋の隅に向けて放り投げる。壁に当たったそれが乾いた音を立てて床に転がるが治崎はニヤニヤと口角を吊り上げている。耳に穴をあける道具が床に転がっても気にしないところを見ると、使う気がなかったとしか思えない。やはり治崎の目的はピアッシングそのものではなかったらしい。
「お、俺をからかったな……!」
「面白いくらい怯えるから」
「うーーーっ、もお、もおっ怒るっ」
悪びれもなく白状する治崎にいよいよ膨れっ面になって、行き場のない怒りをぶつけるようにソファーのクッションにダイブし、バタバタと両手をクッションに叩きつけた。
その手を押さえつけるかのように覆い被さってくる。
耳たぶに吸い付く感触がある。
「お前にピアスを開けさせたいのは本当だ。それで、同じ場所にお前も開ける」
「やだ、こわい」
触れている個所からじんわりと熱くなっていくような気がする。
「顔を真っ赤にして泣きながらピアスを開けるって……なんかえろいだろ」
「…………へんたい」
「そういう事言うなら耳以外に開けるぞ」
あまりの変態的な思考が理解できなくてボソリと呟くと、耳に直接低い声が注がれた。
耳以外ってなんだ。
……耳以外ってなんだ!
「例えば、そうだな…………こういうところ、とか」
クッションと身体の間に手が滑りこんでスルスルと胸元を滑っていく。とある一点をとんとんとつつく。
「あと、こういうところ、とか」
もう片手が下腹部をなぞり、とんでもないところを強く押して示した。
少し混乱して何の話か分からなくなりかけているが、針で穴をあけるという話だった、筈。
まさか。まさか……だ。考えただけで背筋が凍る。
「……やだ」
もう少し反論の仕方というものがありそうなのだが『嫌だ』と言うこと以外思いつかない自分が恨めしい。
こうなると本格的に泣きが入る。
背後で身体をまさぐる治崎という男が西岐を泣かすことに悦びを見出す変態なのだと分かっていても泣くしかない。うううっと唸りながら身体を左右に揺らして剥がそうと試みてみるも、逆にやすやすと押さえ込まれてしまう。
「み、っみみでいい……」
ふにゃりと力の入っていない声で言うと閉じ込めていた腕の力が幾らか緩まった。
「開けるか?」
「……ん、あける」
また耳たぶに吸い付く感触がして、今度は硬く薄いものが触れる。力を込めたり緩めたりしては湿ったものがなぞって、ぞわぞわと肌が粟立つ。
やっていることは変わっていないのだが何となく治崎の纏う空気が柔らかくなった気がした。
ぐっと腕を突っぱねて起き上がろうとすると、すんなり背中から剥がれる。
「でも、あれ使えなくなっちゃったけど……どうするの?」
先程壁に叩きつけたピアッサーを指さす。針自体が床と接触していないだろうし、消毒し直せば問題ないのかもしれないが、潔癖症の治崎がそれを良しとはしなさそうだ。
新しいものを用意するまでもしかしたら猶予が生まれるのではという儚い期待が生まれるが、しかし治崎がソファー脇の小さなケースを開くことでその期待は本当に儚く散った。
「あれはお前でも扱えるかと思って用意したもので、本来はこっちを使う」
今まで彼が医療用のものを持ち出したときに何度かお目にかかったビニールの保護フィルム。その内側でキラリと光を反射している銀色の棒が見える。あれほど恐怖を煽られたピアッサーがプラスチックのオモチャに思えてくるほど、あの鋭利な針のようなものが与えてくる悪寒は凄まじい。
ここまでの流れは掌握のことだったのだろう。
治崎の口端が愉悦に歪んだ。
結局、悪い方向に有言実行な治崎から逃れられず、ニードルを持っては泣きを入れ、散々べそをかきながら治崎の耳を貫通させ終えた後、死ぬほど泣き喚く中、押さえ込まれて耳に穴をあけられたのだが。
その後、帰ってきた玄野が物凄く羨ましがって同じことをもう一度やる羽目になったのは、本当に最高に災難だった。
create 2018/08/10
update 2018/08/10
update 2018/08/10