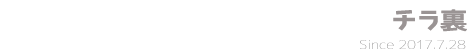爆豪派閥
夜も日も明けない
夜も日も明けない
カツアゲされる夢主を目撃してしまった爆豪派閥のお話です。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
珍しく課題も何もない週末。言い出したのは瀬呂だったか上鳴だったか、とにかく爆豪たち四人は暇を持て余して息抜きでもしようと街に繰り出していた。
とはいえ目的があるでもなく、適当に入ったゲームセンターでだらだらと時間と小銭を浪費する。
レーシングゲームで五回目となる負けを喫した上鳴が、最早悔しさも感じなくなったのか乾いた笑いを浮かべながらスマホを操作している。
「れぇちゃん、相変わらず未読なのな。今日何してんだろ」
「昼まではトレーニングしてるの見たけど気付いたらいなかったんだよな」
上鳴の言葉に同じくゲームに飽きましたという顔で瀬呂が返す。
本当なら西岐も一緒に誘いたかったのだろう。メッセージアプリに返信がないか何度も確かめては似たような会話を繰り返している。
「こんなことならまず最初にれぇの都合を聞くべきだったな」
「何で聞かなかったん」
「いや、普通に寮にいたから……って俺の責任かよ」
やり場のない不満が向けられて切島は傾けていたペットボトルを大きく揺らした。
「切島が絶対誘うと思ってたし」
「俺も」
みんなで遊ぶとなれば、普段から面倒見のいい切島が当然西岐を誘うだろうと思っていたのは、爆豪も同じだった。
「使えねえな」
「いやいやいやいや、自分で誘えよオマエラ」
わざと聞こえるように舌打ちをするとバシャバシャとペットボトルの中身を振りながら三人を指さす。切島の言い分はもっともだが、別に誘うのを躊躇って押し付けようとかそういう話ではない。役割として切島が誘うであろうと思っていたのに期待外れを食らわされた不平不満を吐いているわけで。
「どーする? 帰る?」
「……だなぁ」
思いのほか盛り上がりに欠けてしまった現状に全員が戸惑っていると言ってもいい。一人いないだけでこうも空気が変わってしまうとは。
惰性でプレイするにしてももうゲームに興味がわかず全員がのそのそと出口へと向かう。
"それ"が聞こえてきたのはちょうど店を出たタイミングだった。
「俺たち今困っててさ、ちょっとお金貸してくんない?」
なんというテンプレ通りなカツアゲの台詞なのだろうかとその場の全員が思ったことだろう。ただしその全員がヒーロー志望だ。カツアゲと分かって素通りはできない。
声が聞こえてきた細い路地に目と足を向ける。
数人の高校生くらいの男子に囲まれたひょろっとした人物に視線が吸い込まれる。
「うん、いいよ」
そこで少しの躊躇もなく財布を開こうとしているのは西岐だった。
なんと、カツアゲされていたのは西岐で。
それを理解した全員の目が据わる。
「――楽しそうなことしてんじゃねえか、なァオイ」
今にも辺り構わず爆破してしまいそうな勢いで拳を鳴らす爆豪に、
「俺らの連れに何の用だ?」
こちらはもう完全に腕を硬化させてしまっている切島、
「うちのボスこえーから早く謝っちゃった方がいいんじゃねーの?」
「そーそー、謝って許してくれるかは知らねーけど」
爆豪と切島の迫力に乗っかったような口ぶりのくせにけして穏やかではない表情の上鳴と瀬呂。
西岐に対しては強気だったカツアゲ連中は振り向いた途端委縮した。切島が真っ先に西岐の前で庇うように立ちはだかり、上鳴と瀬呂がそれに続き、爆豪が後ろから睨みを利かせれば呆気なく震えあがり、我先にと逃げていく。カツアゲをするような連中だ、小物と思っていたが想像以上の手応えのなさは呆れるほどだ。
連中の足音がすっかり遠ざかって消えると、硬化を解いた切島の腕がきょとんとしている西岐の肩に置かれた。
「なん、っで、こんなとこでカツアゲされちゃってんのかな」
深々と息を吐いて脱力しながら凭れ掛かる切島の身体を受け止めきれずよろける西岐は、未だにカツアゲということにピンときていない様子で、寧ろ急に登場した四人に驚いている。
「ダメだぜ、ああいうのにお金渡しちゃ」
「はい、お財布しまって」
それでも上鳴と瀬呂の言葉には素直に頷いて手にしていた財布をカバンに戻した。
不思議そうな西岐の表情は一番後ろに立っていた爆豪を見て一転する。ビクッと肩を跳ねさせてたじろぐ。切島の腕が乗っていなければ踵を返して逃げていたかもしれない。
怯えさせている自覚はあるものの怒りの表情を緩められぬまま爆豪は西岐へと近寄る。
スッと手を伸ばし、何をするのかと身構えた西岐の頭をグイグイと押さえつけるような手つきでこね回す。
「え、え、なに?」
やはり分かっていないらしいが分からなくていい。
誰にも悟られぬように静かに息を吐く。
今日一日、どこにいるのかと気を揉んでいれば、現れた途端知らない連中に囲まれて金を無心されていたのだ。怒るなというほうが無理な話だ。だがその怒りは西岐の顔を見たことで違う形に変わっていくから不思議なもので。
まあ、要は顔が見たかったわけで。
見れたわけで。
乾いた喉が潤うような感覚が全身を満たしていく。
「あー腹減ったな」
「飯でも食いに行くか」
「マック行こうぜ」
戸惑っている西岐をよそに仕切り直し始める三人。はじめから頭数には西岐が含まれていて当然一緒に行くだろうと言わんばかりの視線が向けられる。
爆豪も揺さぶっていた手を放して同意の言葉のみを待つ。
今日一日のだれていた空気が、西岐の頷き一つで好転するのを感じながら、爆豪は口角を緩めるのだった。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
珍しく課題も何もない週末。言い出したのは瀬呂だったか上鳴だったか、とにかく爆豪たち四人は暇を持て余して息抜きでもしようと街に繰り出していた。
とはいえ目的があるでもなく、適当に入ったゲームセンターでだらだらと時間と小銭を浪費する。
レーシングゲームで五回目となる負けを喫した上鳴が、最早悔しさも感じなくなったのか乾いた笑いを浮かべながらスマホを操作している。
「れぇちゃん、相変わらず未読なのな。今日何してんだろ」
「昼まではトレーニングしてるの見たけど気付いたらいなかったんだよな」
上鳴の言葉に同じくゲームに飽きましたという顔で瀬呂が返す。
本当なら西岐も一緒に誘いたかったのだろう。メッセージアプリに返信がないか何度も確かめては似たような会話を繰り返している。
「こんなことならまず最初にれぇの都合を聞くべきだったな」
「何で聞かなかったん」
「いや、普通に寮にいたから……って俺の責任かよ」
やり場のない不満が向けられて切島は傾けていたペットボトルを大きく揺らした。
「切島が絶対誘うと思ってたし」
「俺も」
みんなで遊ぶとなれば、普段から面倒見のいい切島が当然西岐を誘うだろうと思っていたのは、爆豪も同じだった。
「使えねえな」
「いやいやいやいや、自分で誘えよオマエラ」
わざと聞こえるように舌打ちをするとバシャバシャとペットボトルの中身を振りながら三人を指さす。切島の言い分はもっともだが、別に誘うのを躊躇って押し付けようとかそういう話ではない。役割として切島が誘うであろうと思っていたのに期待外れを食らわされた不平不満を吐いているわけで。
「どーする? 帰る?」
「……だなぁ」
思いのほか盛り上がりに欠けてしまった現状に全員が戸惑っていると言ってもいい。一人いないだけでこうも空気が変わってしまうとは。
惰性でプレイするにしてももうゲームに興味がわかず全員がのそのそと出口へと向かう。
"それ"が聞こえてきたのはちょうど店を出たタイミングだった。
「俺たち今困っててさ、ちょっとお金貸してくんない?」
なんというテンプレ通りなカツアゲの台詞なのだろうかとその場の全員が思ったことだろう。ただしその全員がヒーロー志望だ。カツアゲと分かって素通りはできない。
声が聞こえてきた細い路地に目と足を向ける。
数人の高校生くらいの男子に囲まれたひょろっとした人物に視線が吸い込まれる。
「うん、いいよ」
そこで少しの躊躇もなく財布を開こうとしているのは西岐だった。
なんと、カツアゲされていたのは西岐で。
それを理解した全員の目が据わる。
「――楽しそうなことしてんじゃねえか、なァオイ」
今にも辺り構わず爆破してしまいそうな勢いで拳を鳴らす爆豪に、
「俺らの連れに何の用だ?」
こちらはもう完全に腕を硬化させてしまっている切島、
「うちのボスこえーから早く謝っちゃった方がいいんじゃねーの?」
「そーそー、謝って許してくれるかは知らねーけど」
爆豪と切島の迫力に乗っかったような口ぶりのくせにけして穏やかではない表情の上鳴と瀬呂。
西岐に対しては強気だったカツアゲ連中は振り向いた途端委縮した。切島が真っ先に西岐の前で庇うように立ちはだかり、上鳴と瀬呂がそれに続き、爆豪が後ろから睨みを利かせれば呆気なく震えあがり、我先にと逃げていく。カツアゲをするような連中だ、小物と思っていたが想像以上の手応えのなさは呆れるほどだ。
連中の足音がすっかり遠ざかって消えると、硬化を解いた切島の腕がきょとんとしている西岐の肩に置かれた。
「なん、っで、こんなとこでカツアゲされちゃってんのかな」
深々と息を吐いて脱力しながら凭れ掛かる切島の身体を受け止めきれずよろける西岐は、未だにカツアゲということにピンときていない様子で、寧ろ急に登場した四人に驚いている。
「ダメだぜ、ああいうのにお金渡しちゃ」
「はい、お財布しまって」
それでも上鳴と瀬呂の言葉には素直に頷いて手にしていた財布をカバンに戻した。
不思議そうな西岐の表情は一番後ろに立っていた爆豪を見て一転する。ビクッと肩を跳ねさせてたじろぐ。切島の腕が乗っていなければ踵を返して逃げていたかもしれない。
怯えさせている自覚はあるものの怒りの表情を緩められぬまま爆豪は西岐へと近寄る。
スッと手を伸ばし、何をするのかと身構えた西岐の頭をグイグイと押さえつけるような手つきでこね回す。
「え、え、なに?」
やはり分かっていないらしいが分からなくていい。
誰にも悟られぬように静かに息を吐く。
今日一日、どこにいるのかと気を揉んでいれば、現れた途端知らない連中に囲まれて金を無心されていたのだ。怒るなというほうが無理な話だ。だがその怒りは西岐の顔を見たことで違う形に変わっていくから不思議なもので。
まあ、要は顔が見たかったわけで。
見れたわけで。
乾いた喉が潤うような感覚が全身を満たしていく。
「あー腹減ったな」
「飯でも食いに行くか」
「マック行こうぜ」
戸惑っている西岐をよそに仕切り直し始める三人。はじめから頭数には西岐が含まれていて当然一緒に行くだろうと言わんばかりの視線が向けられる。
爆豪も揺さぶっていた手を放して同意の言葉のみを待つ。
今日一日のだれていた空気が、西岐の頷き一つで好転するのを感じながら、爆豪は口角を緩めるのだった。
create 2017/12/22
update 2017/12/22
update 2017/12/22