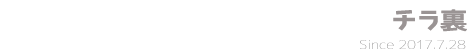爆豪
jinx
jinx
年齢制限のある作品です。
1日1アンケの結果により『爆豪と一緒にTDLに行く』お話を書きました。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
ネズミの国にカップルで行くと別れるなんてジンクスがあるらしいが、きっとこういうことではないと思う。
後ろを歩いていたはずの西岐がいない。
振り返った先にはとても戻る気にはなれそうにもないほどの人混み。
ひょこひょことオレンジ色の髪が見えてどうにかかき分けて追いかけてきた。
「は……ひと、すごい……」
混雑した一角を抜け出してきた西岐に爆豪はあからさまな不機嫌を顔に貼りつける。
もう何度はぐれそうになったか分からない。
「だからな、それをしまえって言ってんだろうが」
原因は分かっている。
爆豪が示した"それ"を両手で握りしめて西岐の口がへの字に曲がる。
「……せっかく調べたのに」
「今のペースだとそもそもチェックしたところ回れないから意味ねえんだよ」
ただでさえふらふら歩くせいでいつでも人にぶつかりそうになるのに、数日前に買ったガイドブックに夢中になっているから前が見えていない。
ついでにいうと爆豪も見えていない。
だから気が付くと違う人について行っていたり流れに飲み込まれたりしていなくなるわけだ。
「……次は気をつける、から」
何度同じことを言ったか分からないのだが、それでも西岐はガイドブックを手放そうとはしなくて、結局何度も見失っている。今更その言葉は信用できない。
というかはぐれるのも問題だが、そもそもそこにガイドブックがあること自体が問題で、でもそれを言えるほど爆豪は人間が出来ておらず、ひたすらフラストレーションを溜め込む。結果うなぎ上りに不機嫌が増して歩調も早まり、一層はぐれる確率が増していった。
しかも、
「あの、ね、これ行きたい」
「……うそだろ、そこに行くにはここ引き返すんだぞ」
ガイドブックがガイドブックの役割を果たしておらず無駄足も多い。どうして地図があるのに効率よく回れないのか。
イライラする頭を押さえる。
なるほど、確かにカップルが別れる気がした。
数日前の夜。
いつものメンバーでソファースペースのテレビを見ていた時。
この時期特有のイルミネーションに包まれたネズミの国のCMを見て西岐が『行ったことないんだよね』『一度行ってみたいなあ』と何気なく言ったのを聞いて、爆豪はすぐ部屋に戻ってネットでチケットを買った。
あんなことをあんな場で言えば絶対誰かが誘うし、他の男と行かれるなんて絶対に嫌だったからだ。
プリントアウトしたチケットを見せて誘うと西岐は嬉しそうに目を輝かせ、さっそくガイドブックを買ってあれこれ行きたいところなどを考え始めた。普段のんびりまったりのほほんとしている西岐がそこまで喜んでいるのは気分がよかったし、二人きりで遠出するのは爆豪も楽しみだった。
そう、現地に到着するまではよかったのだ。
実際に目の当たりにしたネズミの国。
想像以上の人混み。
想像以上の浮かれた空気。
想像以上のファンシーさ。
訪れたタイミングなのか右を見ても左を見てもネズミの国コーデをしたカップルだらけ。
一歩踏み入れただけでここは自分の来るべき場所ではなかったと思った。
そんないたたまれない気持ちに耐えているというのにだ、西岐は開園前からずっとガイドブックに夢中で爆豪を見ることはなく、話を聞いていないのか会話はかみ合わず、振り返ったら大体いない。
そろそろ本気で怒っていいやつかなとも思うが、嬉しそうに限定スイーツというものを頬張っているのを見るとそれも出来なくなる。
今日は我ながらよく耐えているほうだ。
「あとどれくらい?」
「……二時間」
スマホで時間を確かめると並び始めてまだ三分の一しか経っていない。
「じゃあねぇ、次は俺ね。……えっと」
気が遠くなりそうな待ち時間だが西岐は待ち疲れた様子もなく、アトラクションに並んでからは数時間移動もないからかガイドブックをバッグにしまい、列に並ぶ前に買ったスイーツを頬張っていて、暇つぶしに始めたヒーロー情報学や歴史学の出題と回答に勤しんでいる。
現金なもので自分に西岐の意識が戻ると幾らか気分もよくなる。
それにしても、栄養という点では食事に興味を示さないくせに、ジャンクフードやスイーツの類は本当に美味しそうに食べる。
「……ひとくち食べる?」
じっと顔を見ていたのを勘違いしたらしく食べかけのスイーツを差し出してくる。
「いらねーよ。つーか食いたいもんがちげえ」
「からいやつ?」
「……からくはない」
どちらかといえば甘そう。とは言えず、まさかこんな大人数のひしめき合う場所で美味しく頂くわけにもいかないので誤魔化すと、西岐はカバンの中に手を突っ込む。
「どの辺のお店?」
「いい、やめろ、出すな、しまえ」
折角しまったガイドブックを取り出そうとする仕草に爆豪は慌てた。またガイドブックに夢中になられては困る。
西岐の手首を掴んで引っ張り出す。
「そんなもん要らねえだろッ、いい加減鬱陶しいんだよ!」
つるっと。
思わず出た本音。苛立ち。
「でも……」
西岐が何か言い淀む。
「なんだよ」
一日分の不満だ。声も顔もいつになく不機嫌になっているのだろう。
西岐から怯えた空気が伝わってくる。
片手に食べかけのスイーツ、もう片手は爆豪に掴まれ、前後はアトラクションに並ぶ人で埋まっている、逃げ場はない。
長い前髪の隙間からチラッと伺うような目が向けられた。
「別れちゃうのやだ」
ふにゃと口元が歪む。
「は、なんだ……? それ」
「カップルで来ると別れるってみんな言ってた」
「――は?…………え?」
理解が追いつかないのに感情だけが先走って急に高揚していくから余計纏まらない。
「それで必死になってそれ見てたのか?」
「うん、がんばった」
「……そうか」
みんなというのは上鳴達だろうか。そうか余計なことを吹き込んでくれたらしい。帰ったらヤキを入れなければ。
で、……だ。
吹き込まれたジンクスに抗おうと必死になっていたらしいと分かってそろそろ限界が訪れそうだ。
「そのガイドブックに二人きりになれる場所は載ってねえのかよ」
「……え?」
「早く。あと数秒くらいで、多分俺爆発する」
ただの脅しではないと分かるように手のひらの中で何度か爆破してみせると、西岐は慌てて爆豪の腕にしがみついた。一瞬で切り替わる風景。周囲に満ちていた雑然とした音が消えて静けさが広がる。
二人きりとは言い難いが、辺りは暗く誰も他の客を気に留めないような場所。
遠くにテーマパークの煌びやかな明かりが見える。
「……っん、ん」
僅かな抵抗を受けるが押さえ込んだ。
西岐の手から食べかけのスイーツが落ちるがそれもどうでもいい。
口を口で塞いで舌をねじ込む。逃げる舌を追いかけてぬるぬるとこすり合わせれば、抵抗していた腕から力が抜けていく。少し粘る水音と微かな吐息が陽気な園内音楽に混ざる。チョコとベリー系の甘ったるい味。こういう甘味なら悪くない
西岐の身体がぐったりと寄りかかってくるまで味わい尽くす。
こんなものでは溢れた感情がおさまりはしないが、これ以上は本当に抑えが効かなくなってしまいそうで、濡れた唇を舌で拭いながら放す。
「なあ、ちゃんと恋人って認識あったんだな、お前」
山のようにあった言いたいこといろいろがそこに収束されていく。そういうことがちゃんと伝わっているのかいないのかよく分からない奴だから。はっきりと口に出されて衝撃が走った。
「別れたくないって、思ったんだよな」
強く押されたから付き合っているわけではない。望んで一緒にいる。と、そう思っていいわけだ。
「……うん、大好き」
腕の中で頷き笑う姿は本当に愛しくてもう一度唇を啄む。
西岐の睫毛が頬を撫でる感触さえ胸を打つ。
「けど、手は繋げない、俺も見ない、ってのは本末転倒じゃねえの」
この際だと本音を吐露すれば、きょとんとした目が髪の隙間から見上げてくる。口がゆっくりと『あ』の形に開いていく。
「……俺、見てなかった?」
爆豪が頷くと開いた口を手のひらで覆った。
自覚がなかったのか。まあそうだろう。そういうことを計算できるような奴ならこんな苛立ちはそもそもなかっただろう。
一日かけて鬱積したフラストレーションだがその表情だけでもうどうでもよくなる。
そう思っていたのだが。
甘い香りと共に西岐の顔が近づいて、今味わったばかりの唇が爆豪に触れる。柔らかな感触が唇に押し当てられてすぐ離れていく。
「ごめんなさい」
謝罪を口にするその顔は赤い。
折り合いをつけて捻り出した許容の心が吸い込まれていった。
「足んねえよ」
「え」
「それじゃ足りねえ、ちゃんと舌、出せ」
息がかかるほどの距離で低くそう文句をつけると、西岐の頬の赤みが増す。躊躇いの声を小さく漏らしてキュッと爆豪の服を掴む。
慣れない動作で唇を合わせ、ゆっくり舌を差し入れてくる。舌同士が触れただけでビクッと跳ね、少し引きかけるが、意を決したように再び触れさせる。拙い動きで口の中を撫でる舌は段々と熱を帯びていき、西岐が高揚していることを伝えてくる。
「ふ、……んん、ん、――ッ」
堪えられなかった。
仰け反る体に覆いかぶさってむさぼり返す。
絡まりあう柔らかで甘美な感触。乱れた呼吸ごと吸い上げると鼻から甘ったるい声が漏れる。
耳に入ってくる音楽がかろうじて爆豪の理性を繋ぎとめている。
「も、ほてるに……」
「そうだな」
もちろん宿泊先の手配はできている。日帰りは厳しいだろうと用意したものだが、そのおかげで中途半端な状態で長々と帰路を辿る羽目にならずに済む。
こんな熱っぽい目で見られてまだ冷静でいるのは無理だ。
形だけの相槌を返すと、再び蜜を纏う唇に吸い付く。
どこかで花火の上がる音がしていた。
1日1アンケの結果により『爆豪と一緒にTDLに行く』お話を書きました。
本編の設定を使用していますが切り離してお読みください。
ネズミの国にカップルで行くと別れるなんてジンクスがあるらしいが、きっとこういうことではないと思う。
後ろを歩いていたはずの西岐がいない。
振り返った先にはとても戻る気にはなれそうにもないほどの人混み。
ひょこひょことオレンジ色の髪が見えてどうにかかき分けて追いかけてきた。
「は……ひと、すごい……」
混雑した一角を抜け出してきた西岐に爆豪はあからさまな不機嫌を顔に貼りつける。
もう何度はぐれそうになったか分からない。
「だからな、それをしまえって言ってんだろうが」
原因は分かっている。
爆豪が示した"それ"を両手で握りしめて西岐の口がへの字に曲がる。
「……せっかく調べたのに」
「今のペースだとそもそもチェックしたところ回れないから意味ねえんだよ」
ただでさえふらふら歩くせいでいつでも人にぶつかりそうになるのに、数日前に買ったガイドブックに夢中になっているから前が見えていない。
ついでにいうと爆豪も見えていない。
だから気が付くと違う人について行っていたり流れに飲み込まれたりしていなくなるわけだ。
「……次は気をつける、から」
何度同じことを言ったか分からないのだが、それでも西岐はガイドブックを手放そうとはしなくて、結局何度も見失っている。今更その言葉は信用できない。
というかはぐれるのも問題だが、そもそもそこにガイドブックがあること自体が問題で、でもそれを言えるほど爆豪は人間が出来ておらず、ひたすらフラストレーションを溜め込む。結果うなぎ上りに不機嫌が増して歩調も早まり、一層はぐれる確率が増していった。
しかも、
「あの、ね、これ行きたい」
「……うそだろ、そこに行くにはここ引き返すんだぞ」
ガイドブックがガイドブックの役割を果たしておらず無駄足も多い。どうして地図があるのに効率よく回れないのか。
イライラする頭を押さえる。
なるほど、確かにカップルが別れる気がした。
数日前の夜。
いつものメンバーでソファースペースのテレビを見ていた時。
この時期特有のイルミネーションに包まれたネズミの国のCMを見て西岐が『行ったことないんだよね』『一度行ってみたいなあ』と何気なく言ったのを聞いて、爆豪はすぐ部屋に戻ってネットでチケットを買った。
あんなことをあんな場で言えば絶対誰かが誘うし、他の男と行かれるなんて絶対に嫌だったからだ。
プリントアウトしたチケットを見せて誘うと西岐は嬉しそうに目を輝かせ、さっそくガイドブックを買ってあれこれ行きたいところなどを考え始めた。普段のんびりまったりのほほんとしている西岐がそこまで喜んでいるのは気分がよかったし、二人きりで遠出するのは爆豪も楽しみだった。
そう、現地に到着するまではよかったのだ。
実際に目の当たりにしたネズミの国。
想像以上の人混み。
想像以上の浮かれた空気。
想像以上のファンシーさ。
訪れたタイミングなのか右を見ても左を見てもネズミの国コーデをしたカップルだらけ。
一歩踏み入れただけでここは自分の来るべき場所ではなかったと思った。
そんないたたまれない気持ちに耐えているというのにだ、西岐は開園前からずっとガイドブックに夢中で爆豪を見ることはなく、話を聞いていないのか会話はかみ合わず、振り返ったら大体いない。
そろそろ本気で怒っていいやつかなとも思うが、嬉しそうに限定スイーツというものを頬張っているのを見るとそれも出来なくなる。
今日は我ながらよく耐えているほうだ。
「あとどれくらい?」
「……二時間」
スマホで時間を確かめると並び始めてまだ三分の一しか経っていない。
「じゃあねぇ、次は俺ね。……えっと」
気が遠くなりそうな待ち時間だが西岐は待ち疲れた様子もなく、アトラクションに並んでからは数時間移動もないからかガイドブックをバッグにしまい、列に並ぶ前に買ったスイーツを頬張っていて、暇つぶしに始めたヒーロー情報学や歴史学の出題と回答に勤しんでいる。
現金なもので自分に西岐の意識が戻ると幾らか気分もよくなる。
それにしても、栄養という点では食事に興味を示さないくせに、ジャンクフードやスイーツの類は本当に美味しそうに食べる。
「……ひとくち食べる?」
じっと顔を見ていたのを勘違いしたらしく食べかけのスイーツを差し出してくる。
「いらねーよ。つーか食いたいもんがちげえ」
「からいやつ?」
「……からくはない」
どちらかといえば甘そう。とは言えず、まさかこんな大人数のひしめき合う場所で美味しく頂くわけにもいかないので誤魔化すと、西岐はカバンの中に手を突っ込む。
「どの辺のお店?」
「いい、やめろ、出すな、しまえ」
折角しまったガイドブックを取り出そうとする仕草に爆豪は慌てた。またガイドブックに夢中になられては困る。
西岐の手首を掴んで引っ張り出す。
「そんなもん要らねえだろッ、いい加減鬱陶しいんだよ!」
つるっと。
思わず出た本音。苛立ち。
「でも……」
西岐が何か言い淀む。
「なんだよ」
一日分の不満だ。声も顔もいつになく不機嫌になっているのだろう。
西岐から怯えた空気が伝わってくる。
片手に食べかけのスイーツ、もう片手は爆豪に掴まれ、前後はアトラクションに並ぶ人で埋まっている、逃げ場はない。
長い前髪の隙間からチラッと伺うような目が向けられた。
「別れちゃうのやだ」
ふにゃと口元が歪む。
「は、なんだ……? それ」
「カップルで来ると別れるってみんな言ってた」
「――は?…………え?」
理解が追いつかないのに感情だけが先走って急に高揚していくから余計纏まらない。
「それで必死になってそれ見てたのか?」
「うん、がんばった」
「……そうか」
みんなというのは上鳴達だろうか。そうか余計なことを吹き込んでくれたらしい。帰ったらヤキを入れなければ。
で、……だ。
吹き込まれたジンクスに抗おうと必死になっていたらしいと分かってそろそろ限界が訪れそうだ。
「そのガイドブックに二人きりになれる場所は載ってねえのかよ」
「……え?」
「早く。あと数秒くらいで、多分俺爆発する」
ただの脅しではないと分かるように手のひらの中で何度か爆破してみせると、西岐は慌てて爆豪の腕にしがみついた。一瞬で切り替わる風景。周囲に満ちていた雑然とした音が消えて静けさが広がる。
二人きりとは言い難いが、辺りは暗く誰も他の客を気に留めないような場所。
遠くにテーマパークの煌びやかな明かりが見える。
「……っん、ん」
僅かな抵抗を受けるが押さえ込んだ。
西岐の手から食べかけのスイーツが落ちるがそれもどうでもいい。
口を口で塞いで舌をねじ込む。逃げる舌を追いかけてぬるぬるとこすり合わせれば、抵抗していた腕から力が抜けていく。少し粘る水音と微かな吐息が陽気な園内音楽に混ざる。チョコとベリー系の甘ったるい味。こういう甘味なら悪くない
西岐の身体がぐったりと寄りかかってくるまで味わい尽くす。
こんなものでは溢れた感情がおさまりはしないが、これ以上は本当に抑えが効かなくなってしまいそうで、濡れた唇を舌で拭いながら放す。
「なあ、ちゃんと恋人って認識あったんだな、お前」
山のようにあった言いたいこといろいろがそこに収束されていく。そういうことがちゃんと伝わっているのかいないのかよく分からない奴だから。はっきりと口に出されて衝撃が走った。
「別れたくないって、思ったんだよな」
強く押されたから付き合っているわけではない。望んで一緒にいる。と、そう思っていいわけだ。
「……うん、大好き」
腕の中で頷き笑う姿は本当に愛しくてもう一度唇を啄む。
西岐の睫毛が頬を撫でる感触さえ胸を打つ。
「けど、手は繋げない、俺も見ない、ってのは本末転倒じゃねえの」
この際だと本音を吐露すれば、きょとんとした目が髪の隙間から見上げてくる。口がゆっくりと『あ』の形に開いていく。
「……俺、見てなかった?」
爆豪が頷くと開いた口を手のひらで覆った。
自覚がなかったのか。まあそうだろう。そういうことを計算できるような奴ならこんな苛立ちはそもそもなかっただろう。
一日かけて鬱積したフラストレーションだがその表情だけでもうどうでもよくなる。
そう思っていたのだが。
甘い香りと共に西岐の顔が近づいて、今味わったばかりの唇が爆豪に触れる。柔らかな感触が唇に押し当てられてすぐ離れていく。
「ごめんなさい」
謝罪を口にするその顔は赤い。
折り合いをつけて捻り出した許容の心が吸い込まれていった。
「足んねえよ」
「え」
「それじゃ足りねえ、ちゃんと舌、出せ」
息がかかるほどの距離で低くそう文句をつけると、西岐の頬の赤みが増す。躊躇いの声を小さく漏らしてキュッと爆豪の服を掴む。
慣れない動作で唇を合わせ、ゆっくり舌を差し入れてくる。舌同士が触れただけでビクッと跳ね、少し引きかけるが、意を決したように再び触れさせる。拙い動きで口の中を撫でる舌は段々と熱を帯びていき、西岐が高揚していることを伝えてくる。
「ふ、……んん、ん、――ッ」
堪えられなかった。
仰け反る体に覆いかぶさってむさぼり返す。
絡まりあう柔らかで甘美な感触。乱れた呼吸ごと吸い上げると鼻から甘ったるい声が漏れる。
耳に入ってくる音楽がかろうじて爆豪の理性を繋ぎとめている。
「も、ほてるに……」
「そうだな」
もちろん宿泊先の手配はできている。日帰りは厳しいだろうと用意したものだが、そのおかげで中途半端な状態で長々と帰路を辿る羽目にならずに済む。
こんな熱っぽい目で見られてまだ冷静でいるのは無理だ。
形だけの相槌を返すと、再び蜜を纏う唇に吸い付く。
どこかで花火の上がる音がしていた。
create 2017/12/24
update 2017/12/24
update 2017/12/24