一部に非道徳的な表現があります。
突然だが、私は異能力者である。
異能名は特にないものの──寧ろある人って如何やって決めてるのか気になる──明らかに非異能力者とは云えない能力を持っているわけだ。
それはまあ、所謂"年齢操作"と云うやつで。
私は、私自身の年齢を好き放題"設定"することが出来るのである。
そんでもって、私は此の異能をそりゃもう有効活用しまくって生きていた。
例えば映画を観る時や博物館なんかに往く時は、自分の年齢を"12歳"くらいに設定して、堂々と子供料金で入場したり。
逆におひとり様で遊園地を決め込みたい時なんかは、年齢を"65歳"くらいに設定して、シルバー料金で悠々と過ごしたり。
場合によっては無料になったりもするし、シルバー専用窓口とかもあったりするからシルバー設定はかなり便利である。
子供の姿じゃ最悪迷子と勘違いされるしね。
そんでもって、此の日も私は自分の能力をフル活用していた。
場所はヨコハマの前々から目を付けていた一寸お高いホテルのスイーツブッフェ。
なんでもキッズ系の企画店とコラボしたらしく、大人料金7000円の処、お子様料金が真逆の2000円!
こりゃもう往くっきゃないと、うきうきし乍ら着替えを大人が持っても子供が持ってもまあギリセーフだろ、と云ったデザインのリュックに詰めこんで私は現地へと赴いたわけである。
現地のホテルは、やっぱりと云うか大変繁盛していて。
ちらほらと見える子連れ親子に紛れる様に、"12歳の少女"になった私はるんるん気分で列へと並んだ。
云い訳は"お姉ちゃんと一緒に往く約束で、遅れるから先に往っててっていわれてる"で基本OKだ。
二人席なら一人になった処であまり店側にも損失は与えないし、席に案内される時か座った時に"お姉ちゃんが来れなくなっちゃった。でもひとりで楽しみなさいって云われてる"とか云えば、憐れんで貰えておひとり様料金になる上に、たまにサービスまでしてもらえる。
中々に犯罪数が多いヨコハマではあるが、矢張りと云うか、子供には甘いもんである。
なので私は着替えの詰まったリュックをよっこいしょと背負いなおして。
そうしてお店のお姉さんには"二人です"と云って、いつもの如く並んでいたのだけれど。
問題は、入店する時に起こったのである。
「──おや、では私たちと一緒に食べるかい? 一人じゃ寂しいだろう」
「えっ」
後ろに、なんかちぐはぐな親子が並んでるなあとは思ってた。
ちらりと見ただけでも、父親は純日本人なのに、娘の方は確実に外国人っぽく金髪碧眼。
年齢も親子と云うには割と歳離れてるなーとは思いつつ、あんまりじろじろ見ても失礼かなと視線を反らしていたのだけれど。
いつも通り店に入る時に、「一人になってしまったと」伝えたら。
なんとこの年の離れた親子に、真逆のご相伴に誘われてしまったという。
というか、あれだ。現在進行形だ。どうしよう。
「えっと、あの、一人で食べられるから大丈夫です」
「でも、此処のカウンターは背が高いよ? 君じゃあ取れないものもあるだろう」
「そうよ! アタシたちも二人じゃ寂しいなと思ってたの。アナタが一緒に食べて呉れたら嬉しいわ!」
「なんなら、お金もおじさんが出してあげよう」
「えっと……」
──えっと?
なんだろう此の断り難さ。
と云うかなんだろう、此の押しの強さ。
なんだか受付のお姉さんも段々と"此れ大丈夫かな?"って感じの微妙な表情になってきている。
でもわかる。私も同じ気持ち。
と云うか大丈夫じゃないから扶けて欲しい。
「まあまあまあ! では入ろうじゃないか」
「えっあ、う」
ぐいぐいと押されるが儘に店内に入ってしまって、やや胡乱気な様子のお姉さんに席に案内されてしまう。
如何やら、残念なことに4人掛けの準備が出来てしまったようだ。
と云うか
でももう此処まで来てしまったら逃げようもなく。
座って、と云われるが儘、ソファー席に金髪少女と並んで腰かける。
ふかふかの椅子は、流石ヨコハマでも名を馳せる有名ホテルなだけあって大変座り心地が佳い。
私が一寸居心地悪げに座っていれば、目の前の無駄に顔の整ったおじさんは何が嬉しいのかにっこにっこと満面の笑みを浮かべている。
いやほんと、何がそんなに嬉しいんだろう。
顔が綺麗じゃなきゃ念のために通報されるレベルで私──たち?を見て笑ってる。
「いやぁいいねぇ、いいねぇ! 金髪少女のエリスちゃんの横に、黒髪少女の女の子! 此の対比がうん、絵になるねぇ」
「気にしないでね。リンタロウ頭おかしいの」
「えっ、う、うん……?」
──えっうん?
突然の、なんというかこう、だいぶアレな発言に唖然としていれば。
そんな私がを見て更に「うわぁ其の異物を見る目! やっぱりいいねぇ……」と更にしみじみ呟かれ、そっと視線を外した。
ヤバい此の人、思った以上にやべえタイプの人種だ。
もしかしたらもしかしなくともロで始まってンで終わるタイプの人かもしれない。
ええ、もしかしてとんでもない人と相席になってしまったのでは、と青ざめる私に。
然しロリコン疑惑が浮上中のおっさんをまるで気にする素振りもなく、横に座った金髪少女は机に置かれたメニュー表を指差しながらこう問い掛けてくる。
「アナタはどれにする? アタシは此のアップルティーにするわ!」
「あ、えっと……じゃあ私はピーチティーにする。アイスのやつで」
「わかったわ。はいじゃあリンタロウさっさと頼んで」
「うん。任せてよエリスちゃん」
「えっ」
そういうやいなや、さっきまで明らかに変質者な雰囲気を醸し出していた目の前の男は、すっといきなり上級階級に居そうな落ち着いたダンディズムな雰囲気を醸し出して、其の儘軽く手を上げただけで店員を呼びつけてさらりと注文をしてしまう。
流れるような其の対応に、完全に店員が居なくなった後に、私はメニューの"飲み物はオーダー制"と云う文言を確認した。
いやもう、さっきまでのギャップで風邪引きそう。
「ねぇ! アタシはエリス。アナタはなんて云うの?」
「あっ、えと……咲」
「そう、咲ね! じゃあ咲って呼ぶわ。アナタもエリスって呼んで」
「う、うん。エリス……ちゃん」
残念なことに記憶の中の小学生だった私は友達を呼び捨てにするタイプではなく。
更に正しい年齢では社会人やってる身の上では、幼女に対して一律で"ちゃん"を付ける癖がついてしまっていて。
せっかく呼び捨てでいいよと云って呉れたと云うのに、慣れない呼び捨てに私の舌は結局"ちゃん"と云う付属品を付け足してしまった。
それにやっちゃったかな〜〜と思いきや、意外にも少女──エリスは、気にした様子もなくにこりと笑って私の手を取って歩きだす。
「ほら、ケーキ取りに往きましょ。リンタロウも早く来て!」
「えぁっ」
「こらこらエリスちゃん、そんなに引っ張っちゃうと咲ちゃんが転んじゃうだろう?」
──なんだこれ。なんぞこれ。
なんか突然アットホームな感じのやつに巻き後れてしまった勘が凄く否めない。
小さくてふくふくの手のひらがしっかりと自分の手のひらに絡むのを感じながら、私はやや圧倒されるが儘流されてしまうのだった。
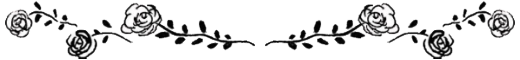
そうして、
──ここは、
高い天井に、硝子張りから見える高層の景色。
壁も床もいちいち華美で、硝子の壁の装飾すら確実に手が込んでいて美しい。
階層が高いのだろう。
少し見上げれば直ぐに美しい青が広がっていて、たまに根性のあるカラスが登ってくるも、直ぐに降下して飛んでいってしまう。
ここは、どこ。
そして何より──
私の躯は、此れ亦凝った造りの椅子に、
手足に巻き付き縛り上げる此れは、革だろうか。
分厚い其れは、如何動いても弛む気配はなくて、今もしも異能を解いた処で、逆に躯をもっと締め付けられるだけだということをありありと伝えてくる。
それでも理解の及ばない状況に陥ると、無駄とわかっていても動いてしまうのが人間というもので。
頭の中では、此の金具を外して貰わない限り此の椅子から立ち上がることなんで出来ないと判っているのに、それでも必死に躯を動かしては、ギシギシと軋む音を上げてしまう。
「やだやだやだっやだよぅ……!」
ぽろりと口からこぼれる言葉は、私の実年齢のそれよりも幼くて。
年齢操作は意外と身体年齢に精神年齢が引っ張られることが多いから、仕方ないと云えば仕方ないんだけど、今其の精神的な弱さは更に自分を追い詰めるだけで、あまり好ましくない。
が然し恐いものは大人だろうが子供だろうが恐いわけで。
私はぼろぼろと大粒の涙を溢しながら、一秒でも早く此処から逃げたい、脱出したいと躯を動かしてはガチガチと歯を鳴らして震えていた。
恐いと、
「──やぁ、起きたのかい」
そんな折りに、突然の声。
それに、思わず息を呑んでびく付いてしまったのは、仕方ないと思う。
だって混乱の極みにいる状態で、さも世間話でも始めるかの様な朗らかな口調で話し掛けられても。
当たり前だけれど、普通に考えても、怯えるのが正しい反応というもので。
「ひっ、! だ、だれ! やだっだれ!?」
私が括り付けられている椅子は、恐らく部屋の中央にあって、壁側の方を向いている。
だから私は横の硝子張りの景色を見ることは出来ても、真後ろを見ることは出来ないのだ。
そして恐らく、この声の主は、今私の後ろにいる。
ばくばくと、心臓が恐怖で暴れ回っている。
なのに呼吸は恐ろしくか細く不安定で、水の中でもないのに溺れてしまいそうだ。
そうして、そんな中に聞こえてきた言葉に。
私はただただ、怯え震えるのだ。
「名前は花倉咲。27歳で、株式会社■■■の一般事務職。大分県出身で、19歳の頃に進学の為上京。在学中は間隔を空けることなく卒業までに複数人と恋人関係となるが、卒業時に別れて以来、特定の恋人はおらず現在も独り身の儘」
「──!」
思わずかぱりと口を開いた。
ついで、過剰に叫びかけもしたが、それは変に喉で詰まって結局言葉になることはなかった。
いやでも待って。いや、え、なんて?
いや──いやいやいや、え、なんで?
なんでそんな、なんで、私のこと、知ってるの?
「……っ!」
思わずばっと視線を下げて自分の躯を見るけれど、そこには勿論
如何頑張ったって、本来の年齢の躯には見えない。見えるはずがないのに!
「っ、ひ、!」
すると、突然の椅子が傾いて、其の儘ぐるりと後ろの方への回転させられる。
勿論椅子に縛り付けられている私は、為す術もなく椅子と共に回転するわけで。
がたん、と音を立てて椅子ごと振り替えさせられた先には──
「なっ、なっ……、!?」
「──うふふ、泣き顔も可愛いねぇ。お顔が真っ赤だ」
──なにこれ、どういうこと?
頭の中は真っ白で、思考が上手く働かない。
でも、なに、え?なんで?なんでここにいるの?
このひとが──私を、こんな風にしたの?
「け、け、ケーキ、の」
「うん。一緒にケーキを食べたねぇ」
「なっなん、なんで、わた、えっ」
「……君は、何処まで覚えてるのかな?」
──どこまで?
何処までって、なんの話だ。
けれど、その言葉を皮切りに、頭の中では勝手に記憶を遡っていってしまってる。
勝手に思考がぐるぐると動いて、目まぐるしく頭の中がかき混ぜられていく。
はふりと、唇から息がこぼれた。
どこまで──ケーキを、食べていて。
甘いピーチティーを飲んで、エリスちゃんとお喋りをして、ケーキをまた食べて。
どくどくと、唸る心音とは別に、耳の奥ではさぁ、と血の気の引く音がする。
──そうだ。次のケーキを取ってきてくれて、それを食べたら、なんだか眠くなってきたのだ。
それで──それで?
わたしは、私、私は、なんて、どうしたんたっけ。
確か、"お腹いっぱいになったから、帰る"って、云って。
頭が、なんだか異常にふわふわしてて。
眠くて、でもなんだか楽しくて、酔っ払った時みたいに、躯が重いのに軽くって。
それで──そうだ。
この人に、"駅まで送っていってあげる"と云われたのだ。
いつもだったら絶対に頷かないのに、何故かその時私は、疑問も持たずにそれを了承した。
そうして一緒にホテルを出て、今まで乗るだなんて考えたこともない高そうな黒い車に、
「……おじさん、わたしに、なに食べさせたの?」
唇が、ふるりと戦慄いた。
それと同時に、信じられないような、茫然とした気持ちに包まれる。
だって──うそでしょ?
食べ物に、なにか混入させて堂々と子供を拐うとか──手慣れすぎでしょ。
明らかに堅気じゃない。
思えば、あの車には運転手が居た気がする。
じゃなかったら、普通後部座席に一緒に乗り込んだりしない筈だ。
日中に、高級ホテルで、高級車の送迎つきで、お忍びで子供と優雅にティータイム?
いや、普通そういう人って、人がごった返す一般解放されたキャンペーンブッフェなんて、使用しないんじゃないのか。
まって、待って。
ひとつ疑問に思えば、次々と訝しげな思考が頭をもたげていく。
おかしい。だっておかしい。
入る時が
あの時お店側は、家族連れでないことも、ましてや知り合いでもないことをきっと知っていた。
なのに、明らかに様子の可笑しい子供が家族でもなければ知り合いでもない男に連れていかれるのを、如何して黙って見逃したの?
いや、抑々──なんで、一緒に入店できたの?
そうだ、おかしい。
普通は、確認とかされない?
家族でない大人が、知り合いでもない様子の子供に声を掛けて、一緒に食べる?
なんでそれを許すの?なんでお店側は注意しなかったの?
受付のお姉さんにそんな権限がなくても、ホテル側のもっと偉いひとが来るなりして対応するのが"普通"だ。
なのに、それがなかった。
それは──なんで?
「……おじさん、わたしがあの店にいくの、知ってたの?」
信じられない気持ちで、けれど何故か確信すら抱いて、そう問いかける。
けれど目の前の男性は、それに微笑ましいものを見るような視線の儘、笑うだけ。
それが、とても怖い。
なんで子供を縛り上げて、拘束して、そんな目で私を見れるの。
「
私の質問には答えず。
けれど、其処から吐き出される言葉の羅列は、
「と或る特定の場所で、時々
──どくりと、心臓が跳ね上がる。
そうして強張った顔の儘、私を見下ろすこの男の人を見上げた。
それは、それは間違いなく──わたしだ。
身に覚えが、ある。
と云うか身に覚えしかない。
やっぱり大人と子供じゃ歩数が違うから、異能を使う時は手短なトイレなんかで行うことが多かったのだ。
だって、どうせバレないだろうとか思っていたし。
真逆こんな風に、たった一人の子供に警戒するとは思っても居なかったから。
だって、別に、食い逃げとかじゃあないのだ。
そりゃあ、正規の金額で飲み食いはしてないけど、でも別に無銭というわけでもない。
確かに一寸
「そうして其の"成人女性"を追っていれば、亦不思議な事が起こった。彼女は行く先々で、どんなに監視をしていてもふらりと姿を消してしまうんだ。──否、違うね。
ぼろりと堪え切れなくなった大粒の涙が、瞳からこぼれて頬を伝って唇へと吸い込まれていく。
すると大きな手が伸ばされて、私の頬に触れたと思えば其の儘涙袋をなぞる様に溢れる涙を掬っていった。
私は、其れが怖くて、更に涙がこぼれてしまうのに。
なのに、
私にとって、死刑宣告にも近い言葉を。
でも、もう、いやだ。
もう、お願いだからやめてほしい。
「面白い異能だね。云うなれば──"年齢操作"と云う奴なのかな。こうして触れても私には何の変化も見られないと云う事は、
「……っごめ、なさ…」
震える唇から自然とこぼれたのは、そんな情けない言葉だった。
だけどもう、其れに尽きる。
だって、
自分の能力を、折角持ってるんだから有効活用したい。
ただ、其れだけだったのだから。
「うん?」
「お、おか、お金、返します。いまっ今まで、騙して安くしてたお金、ぜん、全部、はらいますから……っ、だ、だか、だからっ、ゆ、ゆるしてください……!」
そんなつもりじゃなかった。
こんなことになるなんて思わなかった。
其れは
けれど其れは、一体どうしたら伝わるんだろうか。
一体どうやったら、許して貰えるんだろうか。
此の人は明らかに堅気ではない。
そうして、此のビルの
ヨコハマでもこんなに高い建築となると、数はかなり限られている。
そして其処に悠々と居を構える堅気ではない組織なんて──そんなの、ひとつしかない。
ポート・マフィア。
ヨコハマの裏で暗躍する、実質的な支配者。
私は、そんな犯罪組織に喧嘩を売ってしまったのだ。
──わたし、どうなっちゃうんだろう。
内臓売られるのかな、それとも海外に売り飛ばされるのかな。
イメージが付かないのが逆に恐い。
拷問とかされたらどうしよう。
痛いのなんて嫌だ。怖い。助けて欲しい。
だけど悪いことをしていたのも事実なのだ。
抑々の話でいけば、私が悪い。
だけど、こんなことに、なるなんて思わないじゃないか。
「うっうぅっう゛ぅぅ〜〜っ!」
「……うん? 何故泣くんだい?」
耐え切れずに、涙腺を決壊させていれば。
そんな、心底"不思議"と云った様子の男は、私を見下ろして困ったように笑っている。
何故って、この状況で聞くとか、私に云わせるとか、サイコパスってんのかこの男。
なんて、絶望と混乱の縁に居る私の目の前で。
しかし其の儘、彼は自分の後ろにあった高そうな造りの椅子に腰かけて。
今の今まで気づかなかった、サイドテーブルに置かれていた"紙"を持ち上げ、見せつける様に私の目の前に翳したのだ。
そうして、其処に書かれている
私は、大粒の涙は其の儘に、けれど確かに凍り付いたのである。
「…………、」
それは請求書──ではなく。
いや、むしろ、え?
え?なんなそれ。
「何か勘違いしているようだけれど。私は、
其処には──"愛人契約書"と、書かれていた。
もう一度云う。
其処には、
あいじん──愛人。
それは、あれか。あれだ。
主に囲われて性交をメインとする奉仕的な事をするいかがわしい関係の相手の事だ。
それをなんで、私の前に翳す……?
肉体年齢12歳の私の前に、翳している……?
「……あ、あいじん………?」
「そう、愛人」
もしかしたら見間違いかと思いながらも、そう呆然と私が言葉を読み上げれば。
然し、にこにこと嬉しそうな声が私の言葉を了承的な意味で肯定する。
いやでも然し──え?あいじん???
「………」
私は呆然とした儘、自分の躯を見下ろした。
12歳の幼い躯。
間違っても、
──あたまが、うまく回らない。
だけれど混乱しつつも、自分の舌が絞り出したのはこんな言葉だった。
「………おとなにもどったほうがいいですか?」
「あ、佳い。其の儘で佳いから。と云うよりも
なにか、すごいことばがきこえたきがした。
──いや待て、そんな莫迦なと視線を上げれば。
私の視線に気づいた男は、
でれっと、微笑んで……?
──え、マジで?
「私、性的対象が
待って、とんでもない言葉を云い出し始めた。
嘘嘘、やだ嘘怖い、逃げたいと思っても、当たり前だが縛り上げられた躯は捩ることすら出来やしない。
え、でも待って。ほんと待って。
ええ?性的対象がなんだって??
「だけれど、それは如何しても
恐らく、さっき迄とは違う意味で青ざめている私の頬に、再度指が触れて。
然しさっき迄とは違う恐怖に苛まれている私は、びくんと、そりゃもう激しく躯を跳ねさせてしまう。
いや、縛られているから本当に肩が跳ねるくらいだけど。
「なんたって、君は本来なら27歳──詰まりは、
「…………」
頬を撫でていた手の平が、ゆるゆると滑り落ち、首に触れ、柔らかい肉に埋もれた鎖骨に触れる。
其のあまりに
こいつ、──
「意識を失ったら異能が解けるタイプだったら
今度は私の顎の輪郭を楽しむように触れ始めた男に、くらりとする。
否決して感じてるとかそう云うのじゃなくて。
もっとこう、生存本能的な意味で。
と云うかほんと、え、マジで?
「ね、だからおじさんの愛人にならない? 美味しいものいっぱい食べれるし綺麗なお洋服も着れるしお金も沢山あげるよ」
にこやかに告げられた、其の言葉。
そんな言葉に、私が絞り出せたのは情けないまでの本心だった。
「はっはんざいしゃっ性犯罪者だ……っ!」
「まぁマフィアだから犯罪者だね」
──にべも無い。
否と云うか、間違ってないんだけど凄く間違ってる。
え、なに?待って、え?
なんか其の言葉を聞くと、
「わ、わたしに目を付けたのは……? 年齢詐欺したからじゃ、なくて……?」
「変な子供が居るって報告受けて写真を見たら、可愛かったから」
「もしかして、あのホテルのブッフェは……?」
「君の今までの行動から予測すると、
「つ、つまりあのホテルは……」
「うちの傘下だねぇ。あ、今更だけど、おじさん一寸アングラな組織の一番偉い人やってるんだよね」
「…………え、それ云ってもいいやつなの……?」
恐る恐る問いかけた言葉に返されたとんでもねぇ返答に、思わず愕然とする。
いや、え、待って待って、突然の情報量に追いつけない。
と云うか、え?待って??なんか今凄い言葉聞こえなかった?
「……おじさん、一番偉いおじさんなの……?」
「そうだよぉ。因みに此れ
「…………」
──否、勝手に云ったのそっちじゃん。
なんてのは、云っても意味ないんだろうか。
でも勝手に云ったのそっちで私悪くなくね??
え、まって、待って。
なに、なんなの?私はロリコン的な意味で目を付けられてたの?
金額的な意味じゃなくて?ロリコン的な?躯目当てで??
──えっ、むり、なに其れこわい。
「あなたは、こんな子供に、おさなごに、せいてきこうふんを覚えるへんたい……?」
「いやいや。性的対象が子供だった
「変態……」
「あ、確り喋ることも出来るんだね」
混乱する頭で、其れでも必死に考える。
此の人は、恐らくポート・マフィアの一番偉い人──つまりボス遣ってるヤバい人で、子供にしか性欲を抱けないヤバい変態で?
だけど何らかの理由で、本物の子供を買うことは難しくて──いや普通に犯罪だし、マフィアだから関係ないのかもしれないけど立派な性犯罪。
──此の性犯罪者は、私の事を、性的な目で見ている?
そして、性的とは詰まり──其の股間にぶら下がっている大人の
──え、普通に入んなくね?
そう、理解すれば。
ざぁっと、血の気も元気よく、そりゃもう勢いよく失せていくというもので。
「……無理だよ! 成人男性のおちんちんは12歳の躯にはおっきすぎるよぉ……!」
「! いまのっ今のいいねっ!録音するからもう一回いってくれないかい?」
「うっそやだほんとに興奮するの!? してるの!?」
只のやべー奴じゃん!このおっさん只のやべー奴だよ!
マフィアのボスとかもうそう云う肩書置いといても普通にやべぇよ此の人!
だって、何度も繰り返すけど、私12歳!未発達な、胸だってやっと膨らんできたかな〜〜?今後の為にブラはするけどスポブラで十分かな〜〜??ってくらいの胸なのに!
私発育遅い方だったから!本当にマジでツルペタなのに!
其れが佳いの!?なんで??え??意味わかんない!
「ふええ、こわい……! お願いわたしで興奮しないで……!」
「否もうそう云う言葉がドンピシャって云うかドストライクなんだよねぇ。もしかして狙ってやってる?」
「やってないよぉ! 怖いんだよ! 無理なんだって!」
もう、敬語とかそんなん吹き飛んでる。
いやでもだって、だってこんなん、敬う気も媚びへつらう気も失せるわ!
こちとら躯狙われてんだぞ!?12歳なのに!まだ子供なのに!
「お金もいっぱいあげるからもう働かなくて済むよ?高級品に囲まれて豪遊出来るんだよ?」
「やだよぉ……真っ当な方法で稼いだお金で暮らしたい……肉欲に爛れたお金はやだ……」
「え〜〜? 我儘だな〜〜もう〜〜」
我儘の定義がなんかおかしい。
と云うかなんなんだ、なんでこっちが我儘云って困らせてるみたいな対応されてるんだ。
そんでもって何その"仕方ないなぁ〜"みたいなでれっでれの顔。
マジで切実にお家に帰りたい。
「でもこっちとしてはねぇ。
「ひぃ!」
「でも君の顔も躯も年齢もとても好みだから、折角の逸材をそうみすみす殺すのも厭だし……」
「なんでそんな普通に生殺与奪の話をしちゃうの……」
もうやだわかんない、マフィアわかんない。こわい。
だけどなんか、此の儘云う事を聞かないとヤバいのも、なんとなく判ってきてしまってる。
いやもう、何となく見ない振りしてたんだけど、机の端になんかヤバそうな注射器と薬っぽい瓶が見えるのだ。
それが何なのかは判らないけど、でも、明らかに普通じゃないことは、判ってしまう。
そしてそんな私にトドメを刺すように。
さも"残念"とでも云う素振りで、この男はとんでもないことをポロリと云うのである。
「
「………!」
にこやかな微笑み。
だけれど、その眼は、笑ってなんかいない。
口振りだけは軽妙な儘、然し微塵も未練を感じさせない仕草で私からさらりと視線を外してしまう。
そうして其の指先は、あの机の上の
其の儘注射器を手に取ったと思ったら、まるで、感触を確かめる様に、その中に入っている液体をほんの少し押し出して──。
ぴゅくりと、先端の針から漏れ出した液体に。
ぞっと、躯が芯から震えた。
「──やる! やりますっ!」
気付いたら。
そう、気付いたら、私は叫んでしまっていた。
だけどもう視線はその注射器に釘付けで。
あれが躯の中に入ったら、
だから自分でもとんでもない事を口走ってしまっているって、判ってるのに。
なのに其れを撤回することも叶わず、恐らく血の気の失せた顔色の儘、捲し立てる様にこう言葉を吐き出してしまうのだ。
「や、やるからぁっ、それっお注射しないで……!」
──あぁ、心が、躯に引っ張られてる。
だけれどきっと今は其れが
その証拠に、でれでれの顔に戻ったこの男は、嬉しそうに朱肉を取り出している。
そうして、とても幸せそうに、私にとっては不幸せな言葉を話すのだ。
「そうかい? 君が受け入れて呉れて、嬉しいよ」
ぱちんと、右腕を拘束していたベルトが外される。
かなりキツく縛り上げられていた腕は、拘束が外れると共にじんわりと狭められていた血管を通って血が巡っていく。
其のじわじわとした痺れを感じながら、最早呆然通り越して悄然としている私の手を取って。
此のマフィアのボスだと云う変態ロリコン野郎は、この小さな親指に朱肉をぐり、と押し付けた。
「嗚呼、今更だけどね。私は森鴎外と云うんだ」
よくよく見れば金やらで細かく装飾されているお高そうな
確りと満遍なく押しつぶされる力は、まるで私の事を逃がさないとでも云う様にしつこくて。
くっきりと紙に残る私の拇印に、なんかもう、泣き出したいような気持でいっぱいだ。
「これからよろしくね──咲ちゃん」
お前は、悪魔か。
否ボスって云うくらいだから、寧ろ魔王か、なんて。
軽口すら云えない私は、涙の滲む瞳で、それでも下手くそに笑う事もできないのだ。
さよならわたしのシンデレラ