私は医療に携わる仕事をしている女である。
所謂商社に分類される私の仕事は、取引先に医療器具を売り付けること。
つまりは、営業だ。
そしてそんな私の手には──我が社で作った妊娠検査薬。
安さと精密度の高さが売りの、人気商品のひとつである。
其れを会社のトイレで使用して、私の目は死んでいく。
なんでって、そんなの。
「──うそ……」
判定は──妊娠確定。
口窓の中にくっきりと浮かび上がる赤い線は、どう見ても見間違いではない。
「嘘ぉ……」
心当たりはある──というよりも、一人しかいない。
否しかし、だからこそ、その絶望感が半端な囲のである。
──相手は、懇意にしている森コーポレーションの社長なのだ。
森鴎外。
一代にして会社を設立し、事業を伸ばした優秀な男。
私の一番のお得意様であり、私の売り上げ成績を支える一人。
記憶の中では一分一秒全ての時間を割り振っている、仕事に忙殺されている男。
そして何より──あの人、娘がいるのである。
確か、エリスという名の西洋の血を色濃く映した少女。
何故か森社長の事を"リンタロウ"と呼んでいたが、それは忙しい父親に構ってもらいたい娘のちょっかいとか、揶揄いなのだろう。
娘がいるという事は妻がいるという事で、この時点で認知どころか養育費の確保だって難しい。
なによりこの国は未だに強い男尊女卑の価値観が蔓延っているのだ。
そんな中で、権力のある男の"違う"という言葉ひとつで、認知どころか私の立場すらも危うくなりかねない。
男と女、どちらに"信用"が置かれるのかと云われれば、それは間違いなく男の方。
下手したら、業界内での私の信用は地の底へと落ちてしまう。
──やっと、此処まで登り詰めたのに。
女の癖に、とか色々云われてきたもの全部耐えて、嫌がらせにも耐えて耐えて耐え続けて、やっと掴んだ立場なのだ。
それが産休だなんて取得しようものなら、間違いなく蹴落とされる。居場所がなくなる。
商社と云うのはそういう場所なのだ。
誰も彼もが、誰かの足を引っ張り引き摺り落とす隙を狙ってる。
特にこの会社は、子供なんて身籠った事が発覚したらその時点で相手がいなくても"寿退社"確定。
だから、だからこそ──。
「…………堕ろそう」
それっきゃない。
まだ早期妊娠だし、堕胎してもダメージは受けるけど其処までの重症にはならない筈だ。
──否、それでも躯への損傷でもう妊娠出来なくなる可能性もある。
だけど、それでも、私は今の仕事を失いたくはない。
やっと手に入れた社会的地位を手放したくないのだ。
──だけど、私だけがこの"子供殺し"の罪悪感を背負うのも、なんだかなぁ。
凄く胸の内がもやもやする。
だって向こうは気持ちよくなって、こっちは妊娠って、かなり不平等だ。
あの時確かにゴムはしていたけど、ゴムの避妊率は100%じゃない。
外した時とか先走りとか、膣の入り口に着いた精液で妊娠してしまった事例もある。
といっても、その確率は低いのだけれど。
そう、通常は、ゴムさえしていれば妊娠は防げるのてある。
だから向こうもきっとその気がないどころか、私と同じで妊娠なんざしているわけがないと思ってることだろう。
だけど私は妊娠してしまって、堕ろしても堕ろさなくても、様々なリスクを既に背負わされている。
「……次の面会って、いつだっけ」
私は森社長の担当として、定期的に森コーポレーションにてお時間を頂いているのだ。
その時間を越えたら説明途中でも返される中々シビアなものだけど、時間内に終えさえすれば雑談にも付き合ってくれる。
トイレを出てデスクに戻り、スケジュール帳を開く。
そして其処に書いてある日付を見て、頭の中で日程を換算していく。
──大丈夫だ。まだ、全然間に合う。
堕胎は早ければ早い方がいいのだけれど──これはもう仕方ない。
森社長に打ち明ける。
そして、堕胎を本人に了承して貰い、この罪悪感を一緒に背負ってもらう。
なんたって、孕ませたのは向こうの方だ。
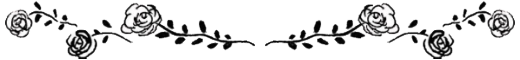
私が森社長と躯の関係を持ったのは、たったの一回だけだ。
その日は製薬会社とか医療器具会社とか医者の方々とかを集めたパーティーで。
私は製薬会社の人間として、そして森社長はお医者様として参加していたのだ。
そうしてその際に色々話が盛り上がって、確か──酔っぱらっていた所為か、森社長があまり性欲がないとかそういう話になって。
じゃあ試してみましょうよと、同じく酔っぱらっていた私は森社長をホテルに引っ張り混んで一発か二発くらいしけ込んだというわけである。
ちなみに森社長は普通に性欲があった。
というよりむしろ仕方ないな〜〜みたいなスタンスを貫いてたけど旺盛な方だった。
あの見た目だし、若い頃はさぞ遊びまくってたことだろう。
──で、まあそんなこんやで私は今森コーポレーションの社長室にいる。
地道にコツコツ信頼を勝ち得ていって、最初は会っても呉れなかったのに今じゃこうして対面してお話しして呉れるようにまでなったのである。
そして森社長は中々に最先端技術への食いつきがいい。
今日だって既に、新しい機材の予約をしてくれたし、多分此の儘いけばいつもと同じように購入してくれることだろう。
まあ、二人きりという事はなくて、いつも絶対に黒服なボディーガードがいるけど。
凄いよね、ボディーガード。
ここまでボディーガードに守られてる日本人も中々いないと、彼らを見ていつも思う。
ヨコハマ確かに物騒だけど、こんなにもボディーガードに守られてる人もいないってか私マジでよくこの人ホテルに連れ込めたな……。
──予定は上々で、設けられた時間を10分残して私は全ての商談を終えていた。
よくやった自分。やればできる自分。
なので此処からは、軽い世間話タイムになるんだけど。
ちらりと、黒服の方々を見詰めてみても、矢張りと云うか出ていく素振りは当たり前だかない。
まあね、それがお仕事だからね。
ああもうどうすっかな〜〜。
「森社長、個人的な我儘で、叶わなくともいいお願いがあるのですが聞くだけ聞いて頂く事は出来ませんか」
「ん? そうだねぇ。まあ、内容によるね。云ってみなさい」
サインしてもらった資料を凡て片した後にそう問いかけてみるけど。
返ってくる返答は、矢っ張りこう、想像通りで。
なのでどうせ駄目だろなぁと思いつつも、万が一の可能性にかけて取り敢えずお願いしてみる。
「少し二人で話したいことがあります」
「あはは、それは無理だね」
「ですよね」
──う〜〜ん知ってた。
まあね、うん。わかってたわかってた。
なので私は一人でうんうん頷きながら、もう仕方ないと顔を上げる。
森社長にも立場があるし、ていうか不倫──のつもりは毛頭ないけどそれに近い女との不義の子とか、かなりのゴシップになっちゃうと思うけど。
まあ黒服ボディーガードって口が固くなきゃ出来ないと思うし、此処から情報が洩れる可能性は多分ないだろう。
だから、もういいかと口を開く。
「子供が、」
「ん?」
「子供ができました」
「……………………は?」
──あ、珍しい顔。
あんまり表情を崩すことのない森社長の驚いた顔を惘乎と眺めながら、この人もこういう顔になるんだなと一人思う。
だって基本、いつも含み笑顔の腹の底が見えない人だから。
「あなたと、わたしの子が、出来てしまいました」
「…………」
静寂が、部屋を包む。
それに、まあそうだよな、と私は再度一人で頷いた。
森社長もそうだけど、周りの黒服の皆さんも揃って綺麗にぽかんとした顔を浮かべている。
まぁね。普通に考えて、会社のトップと取引先の女の間に子供が出来たとか、枕営業かとか疑うよね。違うけど。
森社長だって、今絶対避妊したよなとか自分以外の男の子供じゃないかとか疑ってることだろう。
だって、私が逆の立場だったら絶対に疑うから。
なので、私は先手を打つのである。
「子供はちゃんと堕ろすので安心して下さい」
「は?」
真っ直ぐに森社長の目を見てそう云う。
お涙&同情頂戴みたいに、お腹を擦るだなんて無駄なモーションは取らない。
此処には何も居ないし、居なくなる。
それが私にとっての未来で、現実だ。
「ご存じの通り私は仕事が忙しいです。そして其の仕事を子供の為に手放す気も全くない上に、産休なんて取れないのでスケジュール的にも産めないです。仮に無理して産んでも、その後ワンオペで育てるのなんて無理です。時間も余裕も私にはない。貴方もお忙しくて子供なんて育てられないでしょう? だから宿ってはいますが責任持って堕ろします。此処からは何も産まれません。ご安心下さい」
一息に云いきって、ふうと息を吐く。
よかった。云えた。自分的には何でもない筈なのに、何でもないと云い聞かせているのに。
矢張りと云うか気持ち、お腹がずしりと重くなる。
考えないようにしてても、子供を堕ろすという事実は私に重くのし掛かってくるらしい。
ああやだな。
早く解放されたい。
なので、ではと腰を上げようとしたら。
額に手を当てた森社長が、"理解出来ない"とでも云いたげに私にこう言葉を投げ掛けた。
「──待ってくれ。では何故……君は、私に身籠った事を伝えてきたんだ。今の流れは完全に認知の方向だっただろう」
訝し気な視線。
其の視線を真正面から受け止めて、私は上げかけた腰を椅子に戻して再度口を開いて往く。
ただ、頭の中では此処から一番近い産婦人科の場所を選出してるけど。
ああそうだ。
なるべく、弊社での取引が行われていない病院がいい。
下手に関与があって、万が一でも社に漏れればと思うとぞっとする。
そんな事になったら、私は一巻の終わりだろう。
「……一人で妊娠して一人で堕ろしたら、子供を"殺した"責任も罪悪感も私一人で背負わなきゃいけなくなります。そんなの嫌です。だって不公平でしょう? 貴方だけ気持ちいい思いだけでなんの責任も咎もなく終わるだなんて。私だけ人を殺した事になるだなんて。だから、同じ罪悪感を森社長にも背負って頂こうと思いまして」
「……だから、私に打ち明けたと?」
「はい。──ああ、時間ですね。ではまた、次にお会いする時までには堕ろしていますので」
「────待ちなさい」
面会終了時間だと、再度席を立とうとしてもまた着席を求められる。
なんだろうか。意外と、人情とか持ち合わせてるタイプの人だったんだろうか。
もっと冷静な人だと思ってたのになあ。子供もいる癖に、と素直に待っていれば。
森社長は手を軽く上げて、其の儘ひらりと小さく振った。
すると控えていた黒服の人たちが一礼した後、此の広い部屋を出ていってしまう。
パタン、と締まる扉の音を最後に、静寂が部屋に蔓延していく。
──静かすぎて逆に五月蠅い。
今更人払いなんてして、如何したというのだろうか。
森社長は両手を組んで、其の儘項垂れる様に額を預けていた。
部屋は明るい筈なのに、手の陰に隠れる表情が、見えない筈なのに何故だかとても薄ら怖い様な気がしてしまう。
「私はね。子供が大好きなんだけど、諦めていたんだ」
呆然とした声だった。
否、呆然とだけじゃ云い表せない。
焦りと、動揺と──後はなんだろうか。
短い言葉のひとつひとつに、只の音の並びに。
私じゃ捉え切れない感情の揺らぎを、確かに感じ取ってしまう。
「森社ちょ、」
「なんたってこの年だし、様々な障害もある」
「……」
云い掛けた私の言葉を、まるで遮るように訥々とした口調は続いていく。
否──遮るというか、聞く気がないみたいだ。
なんとなく、ぐっと言葉を詰まらせてしまって、其の儘唇をぴたりと閉ざした。
なんというか、非常に居心地が悪い。
「そんな時、転がり出てきた君を如何して手放す?」
項垂れる様に下を向いていた顔が、緩やかに上げられていく。
そうして見えた瞳に──何故だか、頭の奥で警戒音が鳴った気がした。
思わず、腰が浮く。
そうして無意識の内に
私は急速に競り上がってくる焦燥感の儘に、顔を強張らせて足を動かす。
此処に、居てはいけない。
「君の安全性はよく知っている。なら──君は、私の為に子供を産むべきだ」
──なにを云ってるのとか、意味が判らないとか、云いたい事は沢山ある。
だけれど其のどれもが、どれだけ此の人に伝えたって叫んだって"意味がない"と、何故だか確信を抱いてしまったのだ。
上がる呼吸で、縺れる足で、必死に椅子から離れていく。
だけど如何にも、扉が遠い。
こんなに遠かったっけ。
こんなに、広かったっけ。
厭に部屋が広く感じる。
だけど其れは気の所為だ。
だって、部屋の広さは変わらないから。
変わってるのは、私の感情だけだから。
すると、不意に──
華奢な、腕。
ちらりと見える赤いドレスと金糸の髪の毛。
其れはいつぞや見た、あの、少女のもの。
「──ダメよ。
小さな手が、お腹に触れて、愛おし気に撫でている。
其れが何故だかとても恐ろしくて、なのに、振り払う事が出来なくて。
扉を目前に、声すら出せない私はずるずるとへたり込んでしまう。
「うふふっ! ママよ、ママだわ、ママなのね。私にママが出来るのね!
囀る小鳥の様な華やかな声が耳に触れる。
細く華奢な少女の腕は、腹を、胸をと私の躯に這う様に触れていて。
其の腕が最後に首に触れたと思ったら──首が仰け反る感覚と共に、成す術もなく視界が一気に輪郭を無くしてしまう。
「こらこら、駄目だろうエリスちゃん。追いかけっこは
「ええ〜〜? だぁって、
躯が石の様に重い。
ぐったりと床に転がる躯に、幼い腕が巻き付いている。
悍ましさしか感じない会話が聴こえているような気がして。
だけれど、もう如何にも、意識は沈んでいって止まらない。
「まあ、それはそうなんだけれども。ああうん。楽しみだ。女の子がいいなぁ。ねぇねぇエリスちゃん。やっぱりお家はお人形遊びで定番の、赤い屋根の白いお家とか素敵じゃないかい?」
「あら。男の子だったらどうするの?」
「そうしたら、次こそ女の子を産んで貰えばいい」
輪郭が、崩れていく。
意識が保てなくて、躯が闇に溶けていく。
「嗚呼早く、出てきておくれ」
沈みいく世界の中で。
誰かの手が、腹を撫でた気がした。
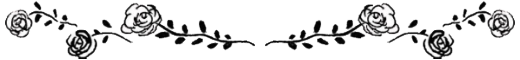
朝の音がする。
ちゅんちゅん、と囀るのは鳥の声だろうか。
──珍しい。いつもは間抜けな鳩の声なのに。
そう思って、
するする肌触りの善いシーツも、躯をしっかりと受け止め包み込むマットも、全部が全部、心地好くて。
「っ、!!?」
ばっと躯を弾き起こす。
否──
私の躯は、起き上がる事はなかった。
ちがう──起き上がる事が出来なかったのだ。
「は、な、なに、なに、っ、な、なに……!?」
躯のバランスが、可笑しい。
いつも通りに動こうとしても、
「っ、な、ど、どこ……っ」
ぐるぐると視界が回る。
知らない天井、知らない壁、知らないベッド、知らない部屋!
何一つとして身に覚えのない場所に、物に、どくどくと心臓が喚き始める。
なんだ。ここはなんだ。どこ。なんで。なんでここにいるの。
疑問が駆け巡って、なのに、答えが出ない。
怖い。此処は何処。なんで私は此処に居るの。
そして──そして。
引き攣る呼吸に、競り上がる
ぼろりと、涙を一粒溢した、時だった。
「あら。起きたのね!」
はしゃぐ様な華やかな声が聴こえて、ひ、と喉を震わせながら恐る恐るそちらを見遣る。
其処には、豪奢な扉を開いて此方を見て笑う、一人の少女が、いて。
赤いドレスの、金糸の髪の少女。
西洋人形を彷彿とさせる、アクアマリンの瞳。
──森社長の、美しいご息女。
なんで此処に、と、声もなく呟く私に。
美しい
そうして、尚も動けない私に対して。彼女はベッドにのし上がり、私の髪を掻き分け、額へ、目蓋へ、頬へ、鼻へと軽いリップ音と共に唇を落としていくのだ。
だけれど私は動けない。
否──
「おはよう
「り、りんた……?」
ごちゃごちゃ絡まる思考回路で。
それでもそれは誰、と問いかけて──ふと、と或る事を思い出す。
そうだ、この少女は、確か父親の事を──森社長の事を、何故だか"リンタロウ"と呼んでいた。
じゃあ、つまり、リンタロウとは?
ベッドに寝転び乍ら楽しそうに私を覗き込む少女を視界いっぱいに映すしかない私の耳に。
更なる混乱を呼び込む声が、近づいてきたのだ。
「こらこらエリスちゃん。
「───は、」
「ええ、つまんないつまんないっ! だって、
──────は?
思考が、止まる。
だって、今、此の子は、なんていった?
9ヶ月。
それはいつから?
私が森社長を訪れたのは妊娠7週の終わり頃だった。
もしもその日を基準に9ヶ月と云っているのなら、今は、いま、そんな、うそ。
「君もね。大事な時期なのだから、無理は禁物だよ」
大きな手のひらが私の頬を撫でて。
其の儘強く強くシーツを掴んでいた私の指先をゆっくりと解いていく。
そうして、私は気付いた。
私の左手の薬指に、光る
そして森社長の左手の薬指にも、私と同じリングが、収まっていることを。
「ぁ、あ、あ」
声が震える。
指が、手が、腕が、躯が、カタカタと震えている。
それに対して森社長は「寒いのかい?」と呟いて、私の手を引き見せつける様に
「も、もりしゃ、な、なん、なんで」
「こらこら。私たちは
「ふ、ふ、ふうふ……?」
──このひとはなにをいっているの。
頭が痛い。混乱する。云っている意味が判らない。怖い。逃げたい。此の人から離れたい。
そう思う私の傍で、ぱっと
だけどそんなの気にならなくて。
ゆっくりと私に被さっている羽毛布団をのけて、私の躯を起こしてくる森社長に。
しかし恐ろしくて、抗う事も叶わない。
「私たちは夫婦だよ。寝ぼけているのかな。あんなに盛大に"式"も上げたのに」
「え、は……しき……?」
「ほらママみて!
そう云って再度ベッドに乗り込んできたエリスは、私の眼前に何かをぐいと突き出した。
だけど近すぎて焦点が合わないと、動かない頭で
薄く笑った森社長がその何かをエリスから受け取り、私殻少し離した処で見えやすいように掲げてくる。そこに、は。
教会の前で、花嫁衣裳を着た私が、幸せそうに──微笑んでいたのだ。
「──────は?」
白いドレス。白いベール。
手には白とピンクのブーケ。指には光る指輪。
笑う私。祝福する様に舞う花吹雪。
そんな私が腕を絡めるのは──花婿の姿をした、森、社長。
「…………、……」
「華やかな式だったよねぇ。君の上司や同僚も沢山駆けつけて呉れて。疎遠だったご両親も涙を流して祝福していたじゃないか」
「指輪は私が運んだのよ!」
「そうだったねぇ〜〜! 白いドレスのエリスちゃんは天使みたいに可愛かったなぁ〜〜。きっと妹とお揃いのお洋服を着たらもっと可愛くなるだろうね〜〜。まあ、産まれるのは男の子だから、
大きな手が、強張る私の頬を撫でる。
産まれる。男の子。次は女。
一方的に語られる言葉を、耳は只々聞き取るだけ。
「だけど自分の子供だからね。男でも女でも、ちゃんと愛すさ。勿論、君の事だって」
云い乍ら頬を優しく引き寄せられて、其の儘軽く唇に口付けられる。
少女と、エリスと酷く似た仕草。
其れを呆然と受け止め乍ら、私はまるで人形の様に座り込むことしか出来ない。
「子供が無事産まれたら、きちんとアレルギーの検査をして、問題なかったら犬を飼おう。賢く強い犬がいい。大型犬がいいな。きっと私たちの子を守る、いい魔除けになる」
森社長は私の肩を抱き、其の儘愛おしそうに大きく膨らんだ私のお腹に手を当てた。
エリスも、そんな森社長に続いて私のお腹を撫でた後、嬉しそうにぴたりと耳を当てている。
私はもう如何すればいいのかわらなくて、何が正解なのか、わかんなくて。
ただそうしなければいけない気がするだけで、二人の真似をする様に、恐る恐る、自分のお腹に手を当ててみる。
間違いなく、私のお腹。
ぱんぱんに膨らんで、針でも刺せば、其の儘弾けてしまいそうな、私のお腹。
薬指を飾る指輪。
覚えていない結婚式。
飛んで往った9ヶ月。
もう直ぐ生まれてしまう──おなかのこ。
「あ、今蹴った」
どちらともつかない、嬉しそうな声。
夢ならどうか醒めてくれと願い乍ら、私は永遠に醒める事のない悪夢の中に囚われたのだ。
間違ったおまじないで孕んでしまった