──私ほど、この世に出来の悪い人間も居ないのだろう。
そう
何の面白みもない黒い瞳に、同じくなんの変哲もない黒い黒髪。
不健康な白い肌に、薄っぺらく小さな唇。
肉付きの悪い貧相な躯に、小さく丸い手。
標準よりもこじんまりとした、低い身長。
何処をとっても、私は如何しようもなく"出来損ない"だ。
私は、そこそこ裕福な家の娘で。
父親は一応社長職を遣っていて、母親は元モデル。
其れらの文字だけ並べれば
理由は──私に、三つ違いの出来の佳い姉が居る為だ。
私とは違い、モデルだった母の優れた容姿を余す処なく受け継いだ姉は、いつどんな時も華やかで、美しい。
鮮やかな亜麻色の髪はいつどんな時もくるりと風に踊っては品よく揺れるし。
健康的な肌は艶やかで、薄く笑うだけで頬がぱっと血色佳く色づくのだ。
意志の強い瞳も、厚く色っぽい唇も、何もかもが私と違う。
そう、何もかもが、私には足りてない。
小さい時から何度も何度も"羨ましい"と思っては、自分の出来の悪さに泣いていた。
鈍くさい私は、如何やっても如何努力しても、姉の様に上手く振舞う処か、可愛らしく笑う事すら満足に出来ないのだ。
今でこそ"社長"の父も、昔は社長にまで至らない只の役員で。
然し其の頃から伸し上がる強い意志を持っていた父は、有権者を家に招き繰り返し
来客の方を向かい入れたり、挨拶したり、案内などの手引きをするもの、そして親交を深めるのも円滑に"人脈"を広げる為の大事な歯車なのである。
特に上役の方々への対応は、父の
そう、
けれど、如何しても、私は華やかな場が苦手で。
どんなににこやかに話しかけられても、近い年頃の子に遊びに誘われても、上手な返しをすることが出来なかったのだ。
そうして困りに困って、社交性の高い姉の陰に隠れて縮こまっている私に。
父も母も、そして姉すらも呆れたように溜息を吐いて居いてはうんざりとした顔を見せて。
その失望の眼差しに、より一層私は怯え、委縮してしまうという悪循環。
詰まる処、私は家族のお荷物なのだ。
──そうして今日も、
父が社長職に就いた時に、てっきりもうこういうのはは卒業かと思ったのに。
然し社長は社長で、更に密な会話とやらをしなくてはならないようで、今も昔も変わらず此の家は
──ああ早く、着替えなければ。
少しでも確り見えるようにと、ビスチェを着こんで、背中のフックを締めていく。
最初こそ慣れずに時間の掛かったこれも、今じゃ指先の感触だけで迷うことなく着ることが出来る様になっていた。
私はあんまり背中が空いたドレスは好きではないから、使用するビスチェはいつもブライダルタイプのものばかり。
そうだ、今日はこの前用意したドレスにしようと、躯にそうレースを撫でた、時だった。
「邪魔するわよ──あら、アナタまだ
ノックもなしに開かれた扉に、びくりと躯を跳ねさせ振り返れば。
其処に居たのは、既にドレスを着こんだ姉だった。
姉らしい、惜しげもなく躯のラインを誇張した、紅いマーメイドドレス。
その鮮明な色は、きっとあの大広間ではさぞ目を引くことだろう。
視線は勝手に、するすると上へと流れていって。
これまた美しく結い上げられた、姉の髪へと移っていく。
姉はいつもの如く、たっぷりとした亜麻色の髪をほんの少し崩しながら纏めていて。
そのきらきらと光りに反射する、撒き散らされたスワロフスキーの輝きに、妹ながら見惚れてしまう。
けれど其処に、よくよく見るとメインとなる髪飾りは無くて。
其れに少し、あれ、と思わず瞳を瞬かせつつ、私はそっと伺う様に唇を開くのだ。
姉と話すのは──いつも、少しだけ、緊張してしまうから。
「わ、私はその、姉さんみたいに、綺麗な躯じゃないから……」
「まぁ、そうよね。いっつも思うけど、貧相な子。痩せこけた鳥みたい。と云うかホント、其れいい加減着るの止めたらァ? 変わんないでしょ。無駄にブライダルなんて着ちゃって。なによ、見せる相手も居ない癖に」
揶揄いと共に投げかけられる言葉の数々に。
少し、ほんの少しだけ、ぐっと息を詰めた。
──けれど、仕方ない。
だって、今言われた言葉は、全て
「母さんが、みっともないから、着なさいって」
「ふーん。ま、どうでもいいけど。ね、アナタあれ買ってたでしょ。紅いコサージュ! あれ貸して欲しいのよ、佳い飾りが見つかんなくって」
「あぁ、うん」
──確かに、今日の姉のドレスに、あの紅い花は似合うだろう。
そう思って、ケース棚に仕舞っている花を取りに下着姿の儘動けば、そんな私の事をじっと見詰めていたらしい姉が、こう言葉を投げかけてきた。
「ねェ、アナタ今日なんのドレス着るの? 此の前と同じのは着ないでしょうね」
「……此の前いらした仕立て屋さんが誂えてくださった、ドレスを、その」
「ふぅん。何色?」
続け様に問いかけられて、思わず言葉を詰まらせる。
けれど、私が吐き出す言葉は
其れを姉も知っているからこそ、こうやって畳みかける様に言葉を投げかけられるのだろう。
「……白」
だって、ほら。
迷い迷いに言葉を絞り出せば。
途端にその顔は、くっと唇を吊り上げるのだから。
「あっは! まぁた、白!? アナタってほんっと好きねェ! なんなの? 純情でも気取ってんの? 毎回毎回飽き足らず白白白! なぁにぃ? "私は可憐な女の子ですぅ"ってェ? やめなさいよ、似合わないから。と云うかもしかして地味と間違えてる? あははっ! ほんっと莫迦な子!」
「………」
何て云えばいいのか判らなくて、思わず俯けば。
其れに更に気をよくしたのか、刃物の様な姉の言葉は次から次へと飛び出して、私の事を切り裂いていくのだ。
「と云うかね、アナタ、いい加減邪魔なのよ。ろくに役目も果たさない癖に。突っ立ってりゃ佳いってもんじゃないのよ。なのにねぇ、なんなの? 昏い顔して壁の華気取り? 折角の
「………、…」
姉の言葉を背中に受けながら、ケースから、紅いコサージュを取り出していく。
スワロフスキーが縫い付けられた紅い花は、照明の光を浴びては、きらきらと輝いている。
──なんで、私はこんななんだろう。
そう思ったら、指先に、ほんの少しだけ力が籠ってしまって。
ああ、いけないと其れを慌てて弛めていく。
幸いなことに、弛めた手の中で、花は変わらずにふんわりと花弁を広げては煌めいていた。
綺麗な綺麗な、紅い花。
貴方も、きっと私なんかより、姉に付けて貰えた方が幸せでしょう。
「ねぇ、一寸聞いて、」
「──姉さん、此れ、あげる」
姉の言葉を遮るように、両手に納めた紅いコサージュを、姉の前へと差し出した。
するも、キッと力強く吊り上がっていた姉の瞳は、この花を見て、途端にゆるりと弛んでいって。
ああ、この対応で
「あら、佳いの? まぁ、アナタには似合いそうもないものね。いいわ、貰ってあげる。感謝しなさいよ」
「うん。ありがとう、姉さん」
私の手の中からぱっとコサージュを取り上げて、姉は其の儘ヒールを高く鳴らして部屋を出入りの扉の方へと歩いて往く。
その後ろ姿を
だって、対応を間違えたら、もっと時間がかかってしまってたんだもの。
然し、そう安堵する私の前で。
惜しげもなく背中を開けたドレスを見事に着こなす姉は、部屋を出る最後に私を振り返って。
そうして、にやりと唇を吊り上げたかと思ったら、その艶やかな微笑みの儘こう囁いたのだ。
「──今日のお客様は、父さん御贔屓の"上客"よ。父さんのお怒りを買いたくないんだったら、お得意の壁の華を気取っとくべきね。だってアナタ、其れしかできないんだし?」
そう、高らかな笑い声と共に。
今度こそ姉は、此の部屋を出ていった。
バタンと音を立てて閉まる扉の音は、なんでかとても冷たくて。
すっかり肌寒くなった躯で、私はもう居ない姉へと、最後にこう言葉を漏らすのだ。
「……うん。全部、判ってるよ」
──ああ、どうして。
ゆっくりと、姿見を振り返る。
そうして其処に映る、ビスチェを着こんだ貧相な躯の女をじぃっと眺めて。
否応なしに潤んでしまう瞳を伏せながら、物心ついた時からずっと、ずぅっと思ってきた言葉を、繰り返すように呟くのだ。
「私は、出来損ないなんだろう」
──せめて、姉の美しさを分けて貰えたら。
そんな、叶いようもない虚しい願いを胸に隠して。
私はひとり、クローゼットを開くのだ。
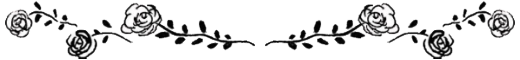
大広間は、すっかり賑やかに華やいでいた。
声を掛けられれれば挨拶をし、一人で居る方が居れば下手なりにも話し相手を買って出ていれば、段々と"今日の上客"が誰なのか判ってくるもので。
恐らくは──森コーポレーション。
此のヨコハマでも随一の規模を誇る、医療を初めとした様々な分野を網羅する大企業だ。
そうして、森コーポレーションと云えば、父の会社の所謂"親"会社で。
あぁ、だから姉はあんなにも気合を入れていたのかと、私は静かに納得する。
だって、確か前に、"森コーポレーションに素敵な人が居る"と話していた筈だから。
こういう企業が入り混じる
詰まる処、彼方も此方も、皆様方はただお喋りに来ているわけではなく、"企業の顔"として取引を持ち寄っていらっしゃるのである。
そうして、そんな中で"娘"の存在理由と云うのは、有体に云えば"華役"だ。
美しく着飾って、企業としての"資金"の潤沢さをアピールすると共に、其の
妻が美しいのは、男としての誇りで。
そうして娘が煌びやかなのは、余すところなく子に"金を掛けている"という父としての矜持の様なもの。
特に姉は20代の後半に差し掛かってきた年頃だから、そろそろ次の段階の"政略結婚"の方まで着手し始めるのだろう。
華やかな一族には、華やかな道具が必要なのだ。
だからこそ、そろそろ、私が此処に
「──……」
黒髪のお客様──確か、森社長と談笑する父と母、そして姉を視界の端にちらりと入れて。
私はほそりと息を細めて、其の儘最小限の跫音で此の大広間から抜け出した。
廊下にもまだまだ人は居て。
目が合う度に控えめに微笑み乍らも、私は足を止めない。
此処で下手に止まってしまえば、途端に喋り相手を望まれてしまうことは今までの経験上判り切っているのである。
するすると人の合間を縫って、一番端の、使われていない空き部屋へと滑り込む。
物置ですらない此の部屋には何もなくて、只小さなバルコニーに続く硝子張りの仕切り扉から青白い月光が差し込むばかり。
「……」
私は小さく息を吐いて、薄いレースカーテンを捲り、仕切り扉の鍵へと手を掛けた。
ほんの少し錆び付き始めた鍵は、少々重たい音を立てながらも外れていく。
そうしてバルコニーの取っ手に手を掛ければ、ギィ、と蝶番の擦れる音と共に扉はゆっくりと開かれていくのだ。
コツン、と靴音を小さく立てながら、白いバルコニーへと足を踏み出した。
まだまだ満ち足りそうにない月は、それでも周りの星をぼかしては吸い込まれそうな夜空を照らしてる。
其の眩い月光を浴びながら、私はまたひとつ息を吐いて髪飾りを外して梳いていく。
ずっと、髪の毛を引っ張られて、少しだけ痛かったのだ。
真珠のバレッタが私の髪から金具を放すと共に、しゅるりと結い上げていた髪はこぼれて、一束は鎖骨に、そして残りは全て背中へと流れていった。
少し火照った肌に、冷たい髪の感触は気持ちよくて。
肌を撫でる夜風に遊ばせながら、私は煌びやかな街の夜景を
此のお屋敷は父が社長職に就いた時に購入した西洋館で、中々に、こうしたバルコニーの数が多い。
そうしてそういう中には、上手い具合に正面口や真下からは判らない処もあって、人混みが苦手な私にとっては大事な呼吸場所なのだ。
街の喧騒から外れた──所謂、"一等地"と呼ばれる場所に構える此の館。
近くには同じようなお屋敷しかなく、似たように華やいでいたり、亦は暗く沈んでいたり。
昔憧れたお伽噺に出てくる様な此の屋敷も、住んでしまえばなんてことない、只の家だった。
──否、きっと、私がそう感じているだけで、姉からすれば此のお屋敷は素晴らしいお屋敷の儘なのだろう。
只、私が相応しくないから。
だから、此の素敵な場所すらも、息苦しい牢獄のように感じてしまうのかもしれない。
「……はぁ」
早く、今日の
そう思って、溜め息を吐いた──そんな、時。
「──ご気分でも優れないのですか?」
そっと掛けられた、其の声に。
真逆誰か居るだなんて思っても見なかった私は、反射的に躯を跳ねさせてしまった。
「……っぁ」
そして其の儘、情けなくも靴のヒールの所為でバランスを崩してしまって。
ぐらり、と重力にそって、躯を傾けてしまう。
──あ、転ぶ。
そう思うのと、躯に
「嗚呼──此れは失礼、驚かせてしまいましたね」
そうして、
自分の状態をやっと理解して、慌てて躯に力を込める。
──わたし、なんてこと。
男の人に、凭れ掛かってしまっている!
そうと気づいてしまえば、もう如何しもうもなく心臓が騒いでしまって。
もたつく仕草の儘、ぱっと其の人の──彼の、胸元に手を置いて、凭れ掛かる躯を自立させていく。
そうして、ふわりと、鼻に触れる香りに。
なんだか酷く、躯が熱くなった気がした。
「……、………ぁ、の、っ、ごめ、なさっ、ッ!」
「おっと」
はくはくと、声にならない声が掠れる。
驚きすぎて、処々つっかえつっかえに言葉を絞り出していれば。
其の動揺が躯にも伝わってしまったのか、再度亦、足元がぐらついてしまう。
すると今度は両腕に支えるように手を添えられて。
其の肌に触れる手袋の感触に、ひくりと肩が震えてしまったのが判った。
──ああ、だめだ。
もう、わたし。なにしても、空回ってしまう。
「ぁ、」
情けなくって、支えられるが儘に俯けば。
片手を残して、もう片方の手が、腕を滑って手へと流れ着く。
其の一連の仕草に、もう如何すればいいのか判らずにおろおろと慌てていれば、目の前から吹き出すような声が聴こえて。
其れにちらりと視線を持ち上げれば──細められた蒼い瞳が、私の事を見詰めていた。
このひと、は。
「──失礼。こうも驚かせてしまうとは思わず」
「い、いえっ、私も、その、驚いてしまってすみません……」
「、ふ、否、貴方が謝る事はひとつもないですよ」
質の善い手袋の感触が、指先をじんわりと温める。
絹が混じっているのだろうか。黒い其の手袋は、月の光を受けてほんの少しだけ光を跳ね返していた。
黒い手袋に、黒地に赤いストライプのスリーピーススタイル。
上のジャケットから覗くベストは、躯にぴったりと合った、恐らく
頭に被った黒に赤の飾りをあしらった帽子まで、見事に癖なく揃えたトータルコードに。
此の人、お洒落さんだわ、となんだか怖じ気づいてしまう。
躯も細く引き締まってて、何よりも見目が麗しい。
こう云う方は、姉みたいに華やかな方が多いから、ほんの一寸だけ、その、苦手なのだ。
そんな私の様子を見てか、彼──否、確か中原さんと云うお名前の方は、私を見てにこりと微笑んだ。
中原──中原、中也さん。
以前にも森社長をお招きした際に、一緒にいらしたお客様。
確か相当な若さでお仕事の重鎮を任されているとか、そうご紹介に当たった覚えがある。
詰まる処は、私なんかよりも、私とこうして話すだなんて畏れ多いほど、優秀な方。
──なんで、此処に居るのだろうか。
此の部屋は先ものべた通り、あの長い廊下の一番奥の部屋。
迷子になるにしても、些か奥に入りすぎている気がする。
「不躾かとは思ったのですが、偶然あの会場を離れた時に、此方に入る貴方の後ろ姿を見つけてしまいまして。気になり、後を追って仕舞ったんです」
そう続け様に再度謝られて、慌てて触れる指先を軽く握り返して首を振る。
ただ、きっと好奇心が勝たれただけなのだ。
そんな風に、私なんかに謝ることはない。
だけど頭の片隅で、如何して私は此の人と手を触れ合っているのだろうかと、ひっそりと疑問には思う。
だって、確かに転びかけてしまったけれど。
今はもう大丈夫で、手を取られる必要はないのに。
そう、不思議に思うのに。
何故か此の心は、"まだ此の手に触れていたい"と、離すことを忘れてしまっている。
如何してかは、判らないけれど。
「……私、少し、華やかな場所が苦手で。特に今日みたいに沢山の方がいらっしゃる時は、時々、あの部屋を離れたくなってしまうんです。……ご招待する側なのに、駄目だって、いけないって、判っているのですが」
蒼い瞳が、浅ましい私を見つめてる。
何を云っても言い訳じみてしまって、こんな私を如何思っているのだろうと、不安な感情がじわじわと胸の底側から沸き上がる。
情けなくって、恥ずかしくて。
ああ、穴があったら、入ってしまいたいくらい。
「──駄目な事はないですよ。実も云うと、俺も其の
「……え、」
掛けられた言葉に、思わずぱっと視線をあげる。
其処には、悪戯っぽく瞳を細めた中原さんが居て。
彼は口角をくっと引き上げながら、小首を軽く傾げてこう言葉を続けていく。
「如何にも、上品な方々の話とやらが肌に合わなくて、時々妙にむず痒くなってしまう。──ので、会場から離れていく貴方を見た時に、如何しても追いかけたくなってしまったンです」
彼が瞳を伏せると、長い睫毛が肌の上に影を作った。
そして少しだけ色味を深くする瞳の虹彩に、
其の色彩は彼の国の青空にとても似合うのだろう。
「其れは……何故?」
「貴方と、話がしたいと思ったから」
悩みに悩んでそう言葉を紡げば、途端に柔らかな声が返されて。
私の唇は、意味もなく空気だけを食んでしまう。
でも──だって。
そんな言葉を云われたのは、生まれてはじめてで。
こんな時、如何返せば佳いのか、私には判らない。
そうして、そうだ。
抑々、年上の方から、こんなにも丁寧に言葉を投げ掛けられること事態が、私にとっては初体験なのだ。
「か、からかって、いらっしゃるの?」
震える唇が絞り出せたのは、そんな素っ気ない言葉で。
他にもっと言い回しはなかったのかと、段々と頬に熱が灯っていってしまう。
ああでも如何してか、気恥ずかしさと共に、僅かな歓びが、胸の内に芽吹いた気がした。
「いいや。其の理由を伺っても?」
「……だって、お客様は、皆様、姉とお話ししたがるもの」
駄目だ駄目だと判っているのに、言葉遣いがどんどん辿々しくなっていってしまう。
こんなの、失礼に値してしまうのに。
父さん──いいえ、父様に怒られてしまうと、思わずきゅっと目蓋を閉じる。
これでは、姉に釘を刺された通り。
やっぱり、私は邪魔物でしかないのかもしれない。
「──俺は、姉君よりも、貴方と話がしたいンです」
其の言葉と共に、握られた指先が、くんと引っ張られた。
決して強くはない、抵抗を忘れるくらいには、優しい力。
そして引き寄せられる儘連れて往かれた先で触れる、柔らかな
思わず閉ざした目蓋を持ち上げれば、私の手の甲に口付ける彼の姿。
それに小さく指先を跳ねさせれば、ゆっくりと唇を離した彼が、亦静かに言葉を重ねていく。
「もうご存じかも知れませんが、俺は中原中也と云います」
伏せられていた蒼い瞳が、ゆるゆると私を見詰めていく。
其のとろりと熱を蕩かした様な色彩に、まるで逆上せた時のような心地を覚えてしまう。
「貴方の口から、名前を伺いたい。教えていただけますか?」
問われた言葉に、頭では其の意味が判っているのに。
なのに唇は上手く動かなくて、はくりと、空気だけを噛んでしまう。
けれど彼──中原、さん、は、そんな私を急かすことなく、ただじっと待ってくれるのだ。
細く震える唇が、とても恥ずかしい。
「……花倉咲と、申します」
「咲さん。貴方の言葉だと、より一層美しく聴こえる」
──
そう思うのに、思っているはずなのに。
如何してか私は彼を、中原さんを突き飛ばすことも出来ずに、ただされるが儘に流されてしまってる。
揶揄われてるって、ちゃんと、思ってるのに。
なのに──如何して、此の手を振り払うことが出来ないのだろう。
「……そんなこと、初めて云われました」
「それはそれは。如何やら幸運な事に、貴方の周りは節穴の男だらけらしい」
涼しい目元でそう云われて、思わず頬が弛んでしまった。
中原さんは、思っていたよりも茶目っ気に溢れているのかも、なんて。
そう思い乍ら自然と微笑みがこぼれれば、同じように口許を弛めた中原さんは、着ているジャケットをするりと脱いで、私の肩へと掛けてくれた。
ふわりと、ぬくもりの残るジャケットが私の肌を隠していく。
「あ、あの、」
「夜風は冷えるので。中に入ると云う手もありますが、其れだと
「………、…えっと」
迷うように声を漏らせば、途端に柔らかく見詰められて。
其の蒼い眼差しに、
だって、私に優しくしたって、意味ないのに。
私は、姉さんでは、ないのに。
──けれど。
「……その、ありがとうございます」
「如何いたしまして」
じわじわと、頬が火照る。
こんなに近くじゃ、きっと、此の熱だって覚られてしまってる。
だけれど、それでも、如何しても。
私も、"二人きり"で居たいと思ってしまうくらいには、まだ言葉を交わしたいと、願ってしまったのだ。
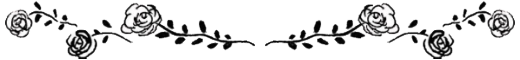
あの後、私は中原さんと色んな事をお喋りした。
最初は聞く側に回っていた筈なのに、中原さんは如何やら聞き上手でもあるらしく。
いつの間にか私は中原さんに、家族にも云ったことがないような事まで打ち明けてしまっていた。
毛布にくるまり乍ら、
此の家に越してきた時は、幼い頃から大好きなお話に出てくるお家みたいで、とてもわくわくしたこと。
けれど
美しい姉が誇らしくて、同時に姉のようになれない自分が酷く情けないこと。
そうして辛くなった時に、こっそり屋根裏部屋に逃げ込んでは、大きな窓から空を覗いていること。
他にも沢山、思い返せば恥ずかしいことばかり打ち明けてしまった気がする。
「……ふふっ」
だけど、心が、とても軽いのだ。
私は年齢的に云えば、今頃は"高等学校2年生"で。
けれど父に、"外は危ない"からと、勉強は全て家庭教師に教わり学校には往かせて貰えていないのだ。
だからこそ、友達と云うものも居らず、思えばこうして誰かに心の内を打ち明けたのは初めてだったのかもしれない。
──中原さん。
中原、中也さん。
唇だけで言葉をなぞれば、途端に胸の内側がくすぐったくなっていく。
そんな感覚は初めてで。まるで角砂糖を舌の上で遊ばせる時みたいにじわじわと蕩ける感情が、何故だかとても愛おしい。
中原さんは、近い内に亦いらっしゃると仰っていた。
近い内って、いつかしら、なんて。
手の甲をするりと撫でた──時だった。
「厭に、ご機嫌、ねェ?」
少し上擦った、猫撫で声。
然し其の声を聞いた瞬間に、私の躯はぞっと芯から震え上がってしまうのだ。
其処には、姉が、姉さんが居て。
美しくつり上げた口端とは裏腹に、少しも笑ってなどいない瞳に、私は知らず知らずの内に肩を縮こませてしまう。
姉さんが、怒ってる。
でも、それは──何故?
「やぁねェ。そんな風に脅えないで? 別にアナタなんて取って食いたくもないから。あ、此れそんな価値もないって意味。ちゃんと伝わった?」
「……えっと、」
「あぁ莫迦だものね、伝わってなかったの。ふぅん。へェ。じゃあ此方は判る? 5秒で考えて。"なぁんで私は怒っているのでしょう"」
「えっ、え、……」
「はぁい、終了。此処が"学校"なら、アナタは落第決定。あっ往かせて貰えてないから判んないわねェ。アナタが世間知らずのこと忘れてたわぁ? ごめんなさいね。でもアナタがいけないんだものね? だってアナタに、学校なんて往く価値ないし」
「…………」
私と違って、姉は外に、大学に通っている。
姉は頭が善くて、父も姉が勉学に励むことを望んだし、姉自身も教養を身につけることを選んだのだ。
けれど、姉ほど頭が善くない私は、"下手に外に出て傷でも付いたら面倒だ"と、外に往く権利は貰えなかった。
──其の意味は、莫迦な私だって、判ってる。
"お前に学ばせる価値はない"と、私は父に、そう断言されたのだ。
でも、別に、其れは佳い。
だって私も、自分にそんな価値があるとは思っていないから。
「──なんで、あの人と話してたの?」
ふ、と。
強い言葉に、意識が引き戻されていく。
迷いつつも姉を見上げれば、其処には苛立たしそうに私を
中原さんとは、大違い。
なんて、こんな状況で思うだなんて。
もしかしたら私は
「
「……!」
気色ばむ姉の剣幕に、思わず肩を竦ませる。
ぜんぶ、全部。今云われて言葉を頭の中で反芻させて、少しでも時間を開けない内に口を開く。
だって姉は、間を開ければ開けるほど、烈火の様に怒りを破裂させるから。
「しゃ、しゃべって、一緒に居たのは、ほんとに、たまたま。偶然お会いして、其の儘私に構ってくださったの」
「二人きりで、髪を解くような
「え、えっと……? 髪は、髪留めが痛くて、中原さんとお会いする前に自分で外したの。
そう云えば。
何故だか、より一層姉の表情は苛烈を極めていってしまう。
それがとても恐ろしくて、肩を竦めて姉を見上げた。
「そンな訳ないでしょ!? 何よカマトトぶってんの!? 私を出し抜いた心算な訳ね。今の今まで、私をせせら笑っていたってことよね! なんて子よ! よくも私を莫迦にしたわね……!」
──なにを、そんなに怒っているの?
姉の怒りがひとつも理解できなくて、思わず一歩躯を引いてしまう。
けれど姉は、そんな仕草すらも許せなかったのだろう。
爛々と瞳を吊り上げた儘、まるで呪いをかける魔女のように低く怒気に満ちた声で、こう言葉を吐き出すのだ。
「覚えてなさい! アタシを
「ね、ねぇさ……っ、あ、!」
思わず伸ばした手は、然し無惨にも叩き落とされ。
じんじんと痛む手の甲を庇えば、鼻で笑う音と共に姉は歩き去って往ってしまう。
──追いかけた方が、佳いのだろうか。
そうは思うけれど、でも、姉の怒りを理解していない状態で何を云っても、恐らく火に油を注ぐだけで。
とんでもないことを引き起こしてしまったと怯えながらも、結局なにも出来ずに、私は立ち竦むことしか出来なかった。
打たれた手の甲が、ただただ、熱い。
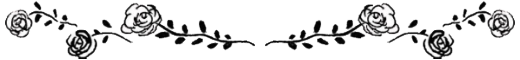
あれからも、私の日常は変わることなく
寧ろ其の頻度は徐々に回数を増している様にも思えて、今までは明確化された"主賓"すらも、如何にも判断をつけにくくなっていた。
きっと、私なんかじゃ理解できない処で物事は動いているんだろうけれど。
だけど、こんなにも多種多様なお客様がいらっしゃるのは珍しくて、段々と、息苦しさが勝ってきてしまう。
月も、すっかり満ち満ちて丸くなってしまった。
夜空を飾る大きな月の回りには、雲ひとつなくて。
恥じらうように輝きを薄くする星たちを従えながら、余すとこなく月光を振り撒いていた。
──そう云えば、中原さんとは、またお会いできるのだろうか。
家の中で足手纏いの私は、両親からも姉からも、来賓を教えてもらえない。
私が知った処で何も変わらないと思っているらしく──実際にそうであるし──私は其の時々によって、其の場で対応を迫られることが常なのだ。
だから、中原さんの勤められる森コーポレーションの皆様がいついらっしゃられるかは、私には判らなくて。
其れを残念に思う反面、いつか来る"近い内"を、こっそり心待にしている自分に気付いてしまう。
誰かを待つのなんて初めてで。
そんな初めてが、こそばゆくて、心地いい。
姉とはあれ以来、きちんと話せておらず。
そのことが不安ではあるものの、けれど、目に見えての"報復"は現時点で与えられて居ない事に、安堵しているのもまた事実だ。
今日も今日とて、白いドレスに身を包んで。
髪飾りは──少し迷って、青い花のコサージュを手に取った。
下ろしていたいのたけれど、それはマナー的に宜しくないから、軽く纏め上げて青い花飾りを髪に咲かせた。
ついつい目に留まって、買ってしまった髪飾り。
鏡に写る自分に、にこりと微笑んでみれば。
花開く花弁も揺れて、それになんだか少しだけ、気恥ずかしく感じてしまう。
お気に入りのフレンチヒールに足を通して。
ああ今日も頑張らなければと、ひとつ呼吸をこぼしていれば。
「──はい」
コンコン、と控えめに扉をノックされて、くるりと振り向き声を出す。
すると「失礼致します」と云う言葉と共に、
確か、一昨年ほど前に入ってきた子だ。
未だ、
然し彼女は、瞳を伏せた儘「旦那様がお呼びです」と声を沈めてそう言葉を続けた。
──父に呼ばれたのならば、往かなければならない。
もう一度姿見を振り返えって、不足部分がないかを確認する。
そうして、前後左右問題ないと再確認してから、扉で私のことを待ち構える
「待たせました。父の元へ連れていってください」
「……はい」
──あれ。
少しの違和感を、感じる。
思わず
だけれど、そう──なにか、変だ。
だって此の子は、もっと愛想が善かった筈だ。
其れでも、其れなりに好意的に接したし、此の子も同じように反応してくれていたのに。
沢山の使用人たちが行き交う廊下を、此の子の背を追いかけて早足で抜けていく。
その中で、年配の
──私が呼ばれていると云う情報、共有されていないのだろうか。
珍しいとは思うけれど、此の子は止まっては呉れないから、仕方なく其の儘進んでいくしかない。
開始時刻が刻一刻と迫る今は、使用人たちにとっては戦場そのもので。
彼らの邪魔にならないよう、ぶつかったりしないよう全方向に注意を向けながら私は進んでいた。
だから、ふいに彼女がこぼした言葉に。
私は、咄嗟に反応することが出来なかったのだ。
「──お嬢様は、
──お綺麗な、方?
其れは一体如何云うこと?と、此の唇が疑問を呟くその前に。
如何やら、目的の場所へと辿り着いてしまったらしく、彼女はぴたりと其の足を止めた。
其所はあの日中原さんと過ごした部屋とは逆にある、亦違う空き部屋で。
こんな処でなんの話があるのだろう、と私は
そうして、
私は自分の目を疑ってしまうのである。
「──嗚呼、来たのか……」
其処には、父が居た。
この前までは確かになにもない部屋だったのに、
「……父、さん? これは、その……誰か越してくるの……?」
窓辺に配置された二人用の卓上の上には、何故だかチェスなんてものまで置いてある。
だけれどなにか違和感があるのは、気のせいなのか。
そう疑問を抱いて、部屋をぐるりと見渡して──その理由に気がついた。
ベッドサイドの小箪笥以外に、此の部屋には物入れが存在しないのだ。
まるで、
だって、なんで。
私は此処に、呼ばれたの?
「姉さんから、
「え、」
──お前のこと?
其れは一体、と次の言葉を待っていれば、然し父は深く深く息を吐き出したから、思わずびくりと肩が跳ねた。
だって、これは。
不機嫌な時の、父だ。
「お──
我が家でのルールで、
今は未だ開始前だけれど、もしかして其れが原因かと、一縷の望みをかけてそう呟くも、父の様子は変わらない。
でもそれじゃあ、困ってしまう、如何しよう。
だって、なんで父が機嫌を損ねているのか、判らない。
「お前は、もう少し歳を重ねたら、嫁がせる心算だったんだ。
──白。
その言葉に、私はそっと自分の服をみる。
白い純白のドレス。父が昔、
だって、父が誉めてくれたのは、其れが初めてだったから。
私にとって、大切な色。
其れを、今、父は、なんて?
ぶつぶつと可笑しな文脈で言葉を続ける父に、思わず信じられない気持ちで、一歩近づく。
だって──だって。
嘘だって、云って欲しい。
「お、おとうさま……」
「──お前には、心底失望した」
縋る様に動いた指先が、ぴくりと止まる。
父は、私のことを、酷く冷たい目で見下していた。
「
「っ、ひ、!」
突然、ぐっと腕を捕まれ、其の儘力任せに寝台へと叩きつけられる。
痛みと恐怖で為す術もなくシーツに埋もれる私に、父はまるで呪詛を吐くような声音で、淡々とこう続けるのだ。
「お前にもう、
「ぇ、……しょ、処女……!? まって、待って! 父さん、何を云ってるの!?」
「──お前には、
「話を聞いて……!」
此の儘ではいけないと、慌てて躯を起こして父に縋り付こうと身を起こせば。
途端に──頬に強い、衝撃。
「──っ、」
まるで、風船が割れる時みたいに、強い音。
其の数秒後に熱くじんじんと痛み出す頬に、手を当てることも忘れて呆然と父を見上げてしまう。
わたし、いま。
父に、叩かれた。
「……既に、
「………、…」
「お前はもう娘じゃない。只の
「………………」
「おい、聞いているのか。返事は如何した」
頭が、上手く動かない。
それでもやっと出来た動作は、頬に手を当てる、只それだけだった。
なにか云いたい。
なにか、云わなければならない。
そう思うのに、でも、何を云えばいいのか判らなくて。
気づけば、ひりつくように熱くなっていく目の奥を湛えた儘。
私は無意識に、こう呟いていたのだ。
「わたし、ほんとうに、しらない……」
──お願い、聞いて、伝わって。
そう、神に祈るような真摯な気持ちで言葉を紡ぐけれど。
だけれども、父はもう、疾っくに私なんかに興味をなくしていた。
「──話は以上だ。此の部屋には鍵を掛ける。客人が入られる迄開くことはない。……嗚呼、間違っても飛び降りるなよ。此れ以上の醜態を晒さないでくれ」
「……おとうさん、わたし、」
「何を云ってももう遅い!」
激しい怒号に、躯が怯える。
父はそんな縮こまる私には、もう目も呉れずに、其の儘苛立たしく靴を鳴らしながら扉へと歩いていってしまう。
「──ぁ、」
──待って、とも、云えずに。
私は、ただ扉が締まっていくのを見ているだけだった。
心臓が、底の方から冷えていく。
私、私は──。
愛されてなど、いなかったのだ。
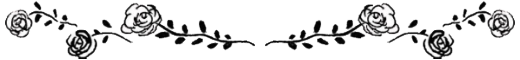
──涙を溢している時間なんてない。
嘆いたって仕方ない、悲しんだって、もう凡て後の祭りなのだ。
だから私は、ずきずきと熱く痛む鼻を啜って、
其れは何故か。
其れは──此の部屋の上に、
私しか使わない、もしかしたら、私しか場所も知らない秘密の部屋。
私だって、寝付けない夜にうろうろさ迷って偶然見つけた場所なのだ。
二階の、此処から少し離れた大時計の
其処を通っていくと続くあの部屋は、確かに此処よりも少し高い眺めだった。
つまりは、如何にか壁を伝って登れば、あの部屋の窓に辿り着く。
幸か不孝か、あの屋根裏の窓は鍵が壊れてるのだ。
だから、外からでも上手く引けば、中へ逃げ込めるかもしれない。
「──……」
ごくりと喉を鳴らして、窓枠の、上の縁へと手を掛ける。
一歩間違えれば其れこそ
だけれどもう立ち止まれないと、私は足を踏み出した。
──あれから、考えに考え抜いたのだ。
なんで、如何してから始まった思考は、私の事を散々責め立てた。
だけど姉が何故あんな"嘘"をついたことすら判らない私なんかじゃ、結局、この
でも、其れでも。
云われたことの意味は判った。
叩きつけられたことの意味は、判ってしまったから。
──嫌だと、思ったのだ。
私はずっと、ずっとずっと、両親の、姉の云いなりで生きてきた。
比べられて、扱き下ろされて、其れでもいつか私のことを認めてくれるかもしれないと、どんなに胸が張り裂けそうでも耐えて生きてきた。
黙って善い子にしていれば、いつか報われると信じていたから。
だけど、違った。
私はきっと、此の先もずっと、何処まで往ったって"私"の儘なのだ。
父は私を認めないし、母は私を比較するし、姉は私を利用する。
其れが判ってしまったから今、裏切られてしまった今。
もう、云われるが儘で居る必要なんてないことに、やっと気が付いた。
反抗──と云うには、少しお粗末で。
だけれども、此れは私にとっては、一世一代の大舞台なのだ。
「……、……!」
──音楽が、聴こえる。
と云うことは、私の躯を望む人たちが、もう直此の部屋に来てしまうと云うことで。
私は横並びの木製の壁に足の指を引っ掻けて、何度もずり落ちながらも壁をなんとか伝っていく。
足も手も、何度と何度も擦れて、じんじんと痛い。
もしかしたら爪が剥がれかけてしまっているのかもしれないが、色んな感情でいっぱいの躯は、幸運にも其れを"痛み"だとは知覚していない。
だから今が、今しかないのだと、私は震える呼吸をなんとか奮い立たせ乍らも、やっとの思いで窓の上まで辿り着くことが出来た。
「──……」
ふぅ、と息を吐いて、落ちないように壁にへばりつく。
そうして足先を伸ばして、開きっぱなしだった窓を締めていった。
ほんの少しのつっかえる音と共に。
部屋の中から、扉の開く音がするのはほぼ同時の事だった。
「っ、!」
ふ、と息を静めて、はためくスカートをたくし上げて巻き上げる。
白いドレスは処々煤けてしまって、ガーターベルト迄みっともなく曝している姿は、父に見られれば其れこそ
もしくは、其の時点で死んでくれと引きずり下ろされて、突き落とされるかもしれない。
そうしている内に、慌ただしく窓が開いて。
私は今度こそ、呼吸を止めた。
「い、居ない! 何処に往ったんだ……!?」
「花倉さん、此れは一体如何云うことで? あんな大金を支払わせた癖に、娘を売る気はないと?」
「ちが、違います! 確かに、確かに此処に
「こんな薄暗い部屋で? 冗談じゃあない。私は会場に戻らせてもらいますよ。お嬢さんの
「も──勿論ですとも!」
其の声と共に、窓はまた力強く締められる。
強い振動に少しだけ躯がぐらつくも、なんとか堪えきって私は息を吐いた。
びゅうびゅうと風は肌を強く撫でて、耳の後ろで青い花が、かさりと擦れて音を立てる。
亦少しの話し声と共に、再度扉の締まる音が聞こえて。
父と其の
──だとしたら、早く登りきらなければ。
父の言葉通りなら、きっとこの後直ぐにでも捜索隊が組まれてしまうことだろう。
窓からは私が"上"に居ることは判らなくても、"外"から見たら一発で私の姿は見付かってしまう。
「……ふぅ」
心を落ち着かせるように息を吐いて、まだまだ遠い"窓枠"を見上げる。
何としてでも、あの場所まで辿り着かなければ。
少なくとも今日の
幸運にも、壁にはいくつかの飾りがあって、上手い具合に手と足を引っ掛けられれば登れないこともないだろう。
──どうか、誰にも見付かりませんように。
月明かりは、私の手元を照らしてくれるけれど。
それと同時に、私自身のことも此の夜にさらけ出してしまう。
ああでも如何か、如何か今だけは。
雲ひとつない夜空の月に、如何か少し光を弱めてと。
私は強く強く願い乍ら、指先に力を込めるのだ。
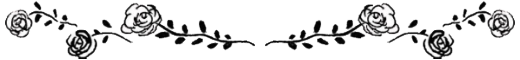
──なんとか、登りきれた。
今私は、やや開いた儘の屋根裏部屋の窓の前で、力なく寝転がっていた。
躯はもう、ぼろぼろで。
純白だった筈のドレスは、あちこち薄く煤けて、処々生地がつれてしまってる。
足も手も、爪は剥がれては居ないものの、場所によっては軽くグラついていて。
じんじんと染みる痛みに追加して、少し力を込めたら赤色に滲むことは、もう見なくたって判ってしまう。
「……はぁ、」
ごろりと転がって、少し開いた窓枠に手を伸ばした。
爪周り以外も真っ赤に染まった指先は、白い窓枠には寧ろ映えるようで。
此れならもう、"不健康"だなんて云われないかしら、なんて。
思って、いれば。
「──、ぅ、」
ぼろり、と。
堪えていた筈の涙が、目の奥から溢れ始めてしまった。
「っ、ひ、ッぅ、う、っ、うぅ〜〜ッ……!」
次から次へとひっきりなしに溢れる涙は、目を焼いて、鼻の先までつんと燃やしてしまう。
段々と息すら出来なくなってしまって、私は躯を起こして、窓のすぐ横の壁へと躯を預けた。
少し埃っぽいレースカーテンが肌を撫でて。
其の柔らかさに、強張っていた心が、じわじわと解けていってしまう。
だって──恐かった。
父も、姉も、売られる恐怖も、私の心をめちゃくちゃにした。
何一つ覚えがないのに、淡々と進められる会話に。
何一つ判らないのに、勝手に落ちていく評価が、私のことをどんどんと削り取っていくようだった。
悲しい、苦しい。
愛されないことが、道具と思われていたことが、こんなにも胸を抉る。
判っていた。
頭のどこかでは、判っていた。
なのに、だけど。
どんなに頭の中で理解していても、実際に言葉として突きつけられるのでは、想像していた苦しみは何倍も強く、次元の違うものだったのだ。
「ふ、ぇ、っ、ぅ、」
──死にたい。
いっそのこと、死んでしまいたい。
そう、棘が巻き付いた心が、泣き叫ぶ。
今此の世界で最も憐れなのは自分なのだと、身の程も知らずに心がそう信じ込んでしまってる。
情けないと思うのは、いったい何に対してなのか。
それすらも熱い涙に沈んでいって、もう、自分の心が判らない。
「、ふ、ぅ……っ」
窓の外には、幾つもの光。
今頃、あの部屋から
靴を捨てて逃げたと思っているのか、其れとも何処か違う場所で力尽きていると思っているのか。
遠く聴こえる弦楽器の音色と共に、ちらちらと庭を照らす細い光のアンバランスさに、涙を溢しながらも薄く笑ってしまった。
──今ここで、飛び降りたら。
彼らはいったい、どんな顔をするのだろうか。
昏い感情が、霧のように胸の内を占めていく。
呼吸もなく溢れる涙は、幾つも頬を伝っては、私の膝にぽろりと落ちていった。
私は何故、あんなにも急いて逃げたのだろう。
此処から出たとしても、もう、往く場所など何処にもないと云うのに。
此れが絶望だなんて、生ぬるいことは云わない。
ただもう、自分の人生に、失望してしまったのだ。
此の先如何すれば善いのかすら判らない。
ただ利用され消費される命なら──自らの意思で散らした方が、きっと何よりも尊く、素晴らしい筈のように、感じてしまったのだ。
頭を緩く動かせば、崩れた髪から櫛がこぼれ落ちる。
そうするともう髪を支えていたものは凡てなくなり、虚しく引っ掛かる花飾りを残して憐れにも毛先は下へと流れていってしまう。
俯けば、さらりと溢れる髪の束に。
ひとつ息をして、閉めた窓に手を掛けた──時だった。
「──やぁっと、見付けた」
ひくりと、躯が強張って。
けれど其れに恐怖を抱くことがなかったのは──きっと、ずっと何処かで、"会いたい"と願った声だったから。
「……なかはら、さん」
其処に居たのは、中原さんだった。
月明かりしかない此の部屋で、暗闇に紛れて此方を見詰める姿は、何故だか死神のよう。
其れは如何してかしらと
以前にお会いした時は、
けれど今は、鮮やかに色を散りばめた前の装いよりも、随分と
袖を通さず肩に掛けている外套なんて、まるで
私がただ惚けるように思っていれば、革の音を立てながら中原さんはゆっくりと此方に近付いてきた。
「今宵の貴方は人気者のようだ。庭先まで、彼方此方を使用人達が探していましたよ」
「……中原さんは、如何して此方にいらっしゃるの?」
私は、屋根裏のことは云ったけれど、其の"通路"迄は話していなかった筈だ。
あの大時計は、一見ただのモニュメントの様で、余り人は寄り付かない。
其れこそ此の屋敷に訪れたばかりの人が偶然でも見つけられる場所のようには思えなくて、素直にそう疑問に思う。
するとそんな私の前に膝をつき。
前の時と同じように私の手を取って、中原さんはこう言葉を紡いでいく。
布に遮られた指先が、私の赤く染まった指をゆるりと撫でた。
「貴方を探して
「……」
私をあの部屋に連れていった、歳の近い、あの女の子。
「そうして其の
次いで、指に触れている方とは反対の指先が、私の目尻に優しく触れた。
睫毛に溜まったままの涙が、手袋に吸われていく。
「そうしたら、其の
「……あの子が」
涙を溢しすぎたのか、それとも、中原さんに会えて──もう、
何故だか酷く心は凪いでいて、今なら幸せな気持ちで飛べると、揺れる瞳でそう思えた。
だって、また、会えた。
其れだけで、たった、其れだけなのに。
こんなにも──嬉しいのだから。
「こんな処まで、いらしてくださって、ありがとうございます。最後にお会いできて、
「──最後?」
祈るようにそう呟けば、其れを拾い上げるように、中原さんは言葉を続ける。
私はそんな中原さんに小さく笑って、触れる手のひらに、ほんの少しだけ力を込めた。
大丈夫。
これで、最後だから。
「……もう、大丈夫です。直ぐに、自分で
唇が、小さく震える。
だけど、平気。大丈夫。
だってあと少しで、私は凡てから解放される。
「こんな私を、見付けて下さって、ありがとうございます。貴方に出会えて、
中原さんが此処から出ていったら、飛ぼう。
あの窓から、此の身を投げ出そう。
此の館は、背が高いから。
だからきっと、一度で逝ける筈。
「……まるで、今生の別れの様な言葉だ」
囁かれた言葉に、薄く笑った。
だって、其の心算で云っているんだもの──なんて。
口が裂けても、打ち明けることはできないけれど。
瞳をそっと伏せて、視線をそらす。
今なら判る。なぜ、姉はあんなにも、あの時私に怒りを向けたのか。
きっと、姉は此の人の事が好きだったのだ。
──今の私と、同じように。
私は子供で、世間知らずで、何一つ物事を理解していなかった。
だから周りの目も、自分が如何思われているのかも、気付く処か気にすることもしていなかった。
けれど其れは間違いだったのだ。
だって、自分を愛せない人間が、誰かから愛されるわけないのだから。
ああ、ひとつ気付けば、凡てが見える。
姉は、自分を愛せる人間だ。
だから父も母も、私よりも姉を愛した。
其れが凡てで、其れが真実だ。
姉は選ばれるべき人間で、私は選ばれない人間。
だからきっと此の人の愛も、私なんかよりも、姉の方が相応しいに決まってる。
そう、だから、此れは最後の幸せ。
愛されなかった私に神様が呉れた、ひとつの夢の眼差し。
此の人の、青空のような瞳が好きだった。
此の人の、夕陽を溶かしたような髪が好きだった。
優しい声も、指の触れ方も、笑うと見える白い歯も、全部が全部、足りない私に"愛"を感じさせてくれた。
だからもう、充分だ。
そう私が手を離そうとした、その時だった。
「──なんで、俺は此処に来たと思う?」
今までとは違う、強い口調。
其れに思わず、伏せていた瞳を持ち上げた。
其処にいるのは、"同じ"中原さん。
だけれど、何処か──知らない人のように、見えたような気がしてしまう。
蒼い瞳が、私を見詰めて細まった。
「……め、
「いいや? 俺は、頼まれてなんか居ない」
触れた指が、複雑に絡んでいく。
それとは別に頬に触れた手のひらが滑って、其の儘顎を掬われる。
其れに動揺する暇もなく、私の瞳と中原さんの瞳が、至近距離で交わり合う。
ともすれば鼻先まで触れてしまいそうな近さに、ほんの少しだけ、頭の中がくらりと揺れた。
「──俺は、
瞳が、ゆるりと見開いていく。
囁かれた言葉を、理解しているのに理解できなくて。
揺らぐ視界で、それでも私を真摯に見詰める中原さんの事を惚けたように見詰めてしまう。
「さ、さらう……?」
「嗚呼、拐う、だ」
「っ、ひゃ、!」
突然強い力で抱き寄せられて、導かれる儘に中原さんの躯へと凭れ掛かってしまう。
まるで、いつぞやと同じときのように。
ただ違うのは、場所が屋根裏であることと──私の鼓動が、以前よりも早くなったと云うこと。
「な、なかはら、さ」
「──一目見た時から、お前が気になって仕方がなかった」
「、!」
突然の言葉に、思わず息を呑んで躯が強張った。
中原さんはそんな私を慰めるように髪を撫でて、其の儘背中へと指を滑らせていく。
「華奢な躯で、立場に関係なく上にも下にも振る舞って。成金だらけのあの場所で、別け隔てなく微笑みかける姿は其れだけで目を引いた。──知らないかもしれないが、実はお前、随分と有名人なんだぜ? "花倉家には白百合が咲いている"ってな」
掠れた笑い声が耳に触れて、とても気恥ずかしい。
前よりも長く触れる中原さんの躯は、服の上からでも其の引き締まった肉体の感触が伝わってきて、何故だか更に心臓が逸ってしまう。
如何してか、息までか細くなってきてしまって。
だからと深く呼吸をすれば、途端に肺いっぱいに知らない香水の薫りが満ちてしまって、更に頭が真っ白になる。
逸る心音が、鼓動が、苦しくて。
触れる躯に、火がついたよう。
「初めて話した時、俺は"偶然"だと云っただろう。あれは嘘。
「──……どうして?」
震える声でそう問い掛ければ、瞬きの間もなく喉の奥で笑う声が聞こえて。
其の心地いい響きに、いつの間にか弛んでいた躯を更に委ねれば、軽く抱き上げられて膝の上に乗せられる。
あぁまた少し、距離が近くなった。
「云ったろ。"二人きりで、話がしたかった"」
そう云って、額に掛かる髪の毛を優しく払う中原さんに。
わたしは、なんだかもうむず痒いような心地でいっぱいになってしまうのだ。
いつの間にか、頭の中からはあの窓から飛び降りる事を忘れていて。
──束の間でもいい。未だあと少しだけ、此の人とこうしていたいと、はしたなくも願い始めてしまう。
「近い内に直ぐ会えると云ったのに、遅くなって悪かった。状況が変わって、其れの対応をしていたら遅くなっちまった」
「……喋り方、そっちが、
少し揶揄うように問い掛ければ、中原さんは不意を突かれた様な瞬きをするから、亦少しだけ唇を弛めてしまう。
最初に合った時とは、大違い。
でも何故だろう。
そっちの方が、とても好ましい。
「あー、厭か?」
「いいえ。男らしくて、素敵です」
「そうかい。其れは何より」
掠れる笑い声に、胸の内を擽る良い匂い。
暖かい体温、優しい指先。
其のどれもが、まるで染めるように私の中に熔けていく。
──此の人と、生きていけたら。
そうしたら、どれだけ幸せなんだろう、なんて。
淡い夢を胸に抱きかけて、私はそっと、瞳を細めた。
まだ、迷ってる。
まだ、心は彷徨っているけど。
「──拐って、くれるの?」
囁いた声は、気付けばとてもか細く揺らいでいた。
そうして、勝手に瞳が潤んでいく。
信じても、佳いのだろうか。
揺れる感情の儘手を伸ばせば。
其れが彼の頬に触れた瞬間に──私の躯は、
「ひゃっ! な、なにっ……!?」
「ご希望とあれば、もう"同意"も同然」
く、と喉の奥で笑う声と共に、確かに背中と太股に、
でも、待って、なにか可笑しい。
わたし──浮いてる?
「な、なかはらさっ……!」
「──
「えっ」
慌てて中原さんの肩に手を当てれば、何処か愉しげな声が聴こえて。
其れに思わず彼の顔を見て──そうして私は、やっと気がつく。
彼を、中原さんを取り巻く膜のように、赤く薄い光が、発光している。
此れはもしかして──"異能力"?
都市伝説のように、真しやかに囁かれる神秘の力。
まさかそんな、と言葉を失う私に、もう一度中原さんは、説き伏せるようにこう囁くのだ。
「どうか中也と、呼んでくれ」
真っ直ぐな瞳に、射抜かれて。
最早色んなことの積み重なりで頭が真っ白になった私は、乞われる儘に、気付けばこう呟いていたのだ。
「ち──ちゅうや、さん」
そう、言葉を差し出せば。
視界いっぱいに、嬉しそうな顔。
──此の人。
夢見心地の儘、それでもじわじわとした
ほんとの、ほんとに──。
わたしのこと、好きなんだ。
「──っ、ひぁ、」
「じゃあ月夜の散歩と往きますかね」
コッコッ、という革靴の音と共に、なかはら──中也さん、は、迷うことなくあの大窓へと歩いて往く。
けれど、彼処は何処にも繋がっていない、
思わず落ちちゃう、と躯を竦める私に、亦も届くのは──愉しそうな、声。
「落ちねェし──見せ付けてやりゃあ善い」
え、と。
云う間もなく、力強い脚力によって意図も簡単に窓枠は蹴り開かれていく。
そうして躊躇いもなく踏み出された足に。
私は、ぎゅう、と中也さんへと縋り付いた。
「──……っ! わぁ!」
風が頬に触れる感触。
それと共に──
わたし──いや、
いま空を、飛んでる!
「すごいっちゅ、中也さんっ! 飛んでる! 飛んでます!」
「──ははっ、云ったろ"月夜の散歩"さ」
「お散歩! すごいっ凄いわ! 本物の魔法使いみたいっ!」
チカチカとした光が、下から幾つも向けられる。
けれどそんなものは空から降り注ぐ月の光の前では霞むばかり。
直ぐ前を見詰めれば、満月を背に素敵な人の横顔。
羽織る外套を靡かせて、堂々とした姿は、とても格好好くて。
じわじわと、胸が、頬が熱くなっていく。
潤む視界の儘微笑めば、同じように微笑みが返ってくる。
昔憧れた物語。
其れが今目の前にあって。
私は、幸せの儘、こう囁くのだ。
「──私を見つけてくれて、ありがとう」
そうして溢れる涙の粒に。
彼は薄く笑って、其の儘ゆっくりと顔を近づけてきた。
でも大丈夫。
世間知らずだって、其くらいは知っている。
だから私は、瞳をそっと瞑って、其の唇を受け入れるのだ。
私の初めての口付けは、蒼い満月の中で満たされて。
此の幸せは、此処から始まるの。
こんなに眩しい夜だから