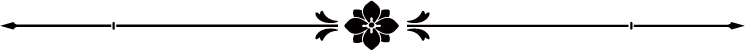生きろ
きっと最初からこうなる運命だったのだと言ったら、二人は怒るだろうか。身動きが取れない状態でも必死に手を伸ばそうとする二人の叫び声が遠くに聞こえる。何を言っているのか正確に聞き取ることは出来なくて、まるで自分が水中に身を沈めているようだった。それなのに天に輝く光は一切見えない。
術を封じられた状態で動けないよう手足を縛られて、それでもなんとかこちらに来ようと身を捩っている。
(喉潰れんぞぉ)
声に出すのは、なんとなくやめておいた。
体に馴染んだ隊服は既に灰に変わってしまった。燃え上がる炎に包まれるそれを見た時、自分の中に生まれた感情を言葉にする暇もないまま、今ここにいる。
初めて着た白装束は、面白いぐらいに似合わなかった。普段まとめている髪は野放しにされている。最後から落ちてくる髪に、よくもまあここまで伸ばしたもんだと感心する。マジで、よく伸ばしたよなぁ。鬱陶しく感じることもあったけれどなんだかんだこの長さが落ち着くようになってしまった。
――死に対しての恐怖は、一切ない。
生まれた時から覚悟をしていたのだ、あるわけがなかった。
ただ、流石に彼らの目の前で死ぬことになるとは思わなかったが。
晴。
「長尾! やめろって……!! ながお!!」
藤士郎。
「景くん止めよう? 他の方法だってきっとあるよ? ね?」
……ごめんな。
持ち上げた口角はちゃんと笑っているように見えただろうか。出来れば、そうであればいい。悲惨な死に顔だけは見せられなかった。否、自分が、見て欲しくなかった。覚えて欲しくなかった。
二人が息を呑む音が静かに聞こえる。次いで、また叫び声が響いた。
名前を、呼ばれている。叫ばれている。引き留めるために、ずっと。
普段握っている得物では使いにくいとわざわざ渡された小刀の刃を自分に向ける。俯いた時に流れた髪は、二人から顔を隠してくれる。この為に伸ばした訳では無いのに、長くてよかった、と。
やめろ、と、さけんだのは、どちらだったか。
力いっぱい刃を自身の心臓に突き立てて。皮膚の破ける感覚が手に伝わって、一瞬ひんやりと冷たさが伝わったかと思えば、じわじわと熱が広がっていく。破れた皮膚の間から血が流れて床を汚す景色は、場所と状況さえ違えば見知った光景に、口角の上がった唇の隙間から息が溢れた。
こうして人は死んでいくのだと、よく知っていた。
部下の犯した罪は上司の責任。監督不行届だと。受けた批難の数は両手じゃ収まりきらないぐらいだが、処分の話を聞いて真っ先に浮かべたのは歳下二人のことだった。
全身の力が抜けて倒れていくのが、やけにスローモーションで見えた。冷たいはずの地面は、熱を奪われていく体とほぼ同じ温度をしていた。
顔だけは見せないように、長いベールで包み込んで。ゆっくりと瞼を下ろせばその先は暗闇。
人が死んでいく景色なんてそう慣れるものでもない。かつての自分がそうであったように、彼らにもまた、同じ悲しみを与えてしまった。
それだけが心残りで、薄れゆく意識の中、悲痛な叫びだけが届いた。
(わりぃ、さきいくわ)
▽
倒れる大切な友人の呼吸が止まったのが、しっかりと見えた。見えてしまった。喉が痛くなるほど叫んでいた言葉は届かず、勢いも失った。
同じく静かになった隣を見て、甲斐田はなんて声をかければいいのか分からない。自分でさえ感情の制御が出来ていないと言うのに、何を言えるというのだろうか。
呆然と動かなくなった友人を見つめる弦月は、静かに涙を零していた。
面積を増やしていた赤はその勢いを止めている。あれだけの血が流れていればもう助からないだろう。そもそも、ひとおもいに突き立てられた刃はしっかりと心臓に届いただろうし、誰よりも人の死を間近で見てきた長尾が場所を間違えるはずもなかった。
だからこそ甲斐田は、己の非力さを恨んでいる。もっと他にもやりようはあった、こんな結末を迎えなくたってよかった。監督不行届だと上の者には口を揃えて言うが、だからと言って長尾が死ななくたってよかっただろう。
自分に向けられていた恨みつらみは、ぐるぐると全身を巡って最終的に別の所へと場所を変える。
いつの間にやって来ていたのか、面布をつけた人間が二人、そばにやって来て拘束を解く。今更解かれたって長尾を助けることは出来ないのに。
だらしなく地面に垂れた腕を動かす気力はどこにも無い。隣では変わらずに呆然と長尾を見つめている弦月がいて、その名前を呼ぶが反応は無い。
「弦月、いこう」
なんとか腕を持ち上げて、弦月の服を軽く引っ張る。弦月はずっと長尾を見つめたまま、甲斐田の言葉に微かに頷いた。
緩やかな動きで近づいて行く。血溜まりを踏んで、ぴちゃ、と水音が無言の空間に響いた。一歩、二歩と水音を響かせて、服が汚れることも厭わずに膝を着く。髪で隠れた顔を見ようとはしなかった。
だって、それは、長尾がさいごに自分たちに願ったことだから。
「けいくん」
返事は無い。
「景くん、」
いつもの豪快な笑い声と共に名前を呼んでくれる声は、何一つ聞こえない。
「…………起きて、」
長尾は、ぴくりとも動かない。
当たり前だった。さきほど、目の前で自ら命を絶ったのだから。見間違えるはずがない。この男が、間違えるはずがない。
虚ろな目をした弦月が長尾に手を伸ばすのをそっと制した。ダメだ。それは、ダメ。言葉にはしなかったものの、意思は正しく伝わったのか動きを止める。
止まる気配のない涙を流し続ける弦月とは別に、甲斐田は泣かなかった。意地だった。泣いてやるもんかと思った。そして、今泣いてはいけないとも思った。だから緩みそうになる涙腺を必死に抑えて、長尾の傍にいる。
いつまで経っても動けない僕達は、正しく理解した。
今まさに、友人の手によってここに縛られたのだと。