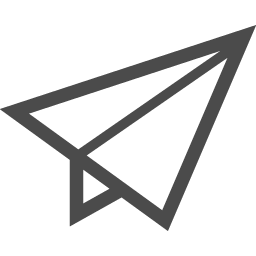
キッズコーチしてる種ヶ島(tns)
尻切れトンボ+SSにしては長い
***
歳の離れた小学生の妹が、少し前からテニススクールに通い始めたらしい。なんでも、「お姉ちゃんがテニスをする姿がカッコ良かったから」だそうだ。大学生になって二回目の夏休みで帰省した私に、母がそう教えてくれた。
大した成績を高校の部活で残した覚えはないが、可愛い末っ子から憧れられるのは満更でもない。機嫌を良くした私は、休みの間彼女の習い事の送迎を引き受けることにした。
レッスンの終了時刻より早めにスクールを訪れると、妹の頑張る姿があった。ビギナーコースと聞いていたがラリーが良く続いている。途中、チャンスボールをスマッシュしようとしてネットに引っ掛けたりもしていたが、本人は笑顔を浮かべ楽しそうだ。
頑張れ頑張れと隠れて様子を窺っていると、ミスをした彼女の元にアドバイスのためか若い男性コーチが近付いて行くのが見えた。その後ろ姿にギョッとする。
……まさか。
しかし何度目を擦ってみても、色の抜け切った髪と軽やかな歩き方にはやはり覚えがあった。
何もこんな偶然が起きなくても。いるかも分からない神様を恨んでみたが当然意味はないだろう。
「お姉ちゃん!」
弾けるような声にハッと顔を上げると、スクールを終えこちらへ走り寄る妹越しに件のコーチの姿があった。すぐに目を逸らし、「おかえり、頑張ってたね」と抱きついてきた彼女へ声をかけたのだが、やはり結局向こうに気付かれてしまったようだった。
「ちゃい☆苗字が同じやからもしかして……とは思ってたけど、まさかホンマに姉妹とはなぁ」
「あー……妹がお世話になってます」
「いえいえ。てか、俺らの仲なのにえらい他人行儀やん!」
「俺らの仲って言ったって……」
「修二コーチ、お姉ちゃんのこと知ってるの?」
ここでも下の名前で呼ばれてるんだ。相変わらず、人好きのするやつだなと、そう思う。そんなの私にはもう関係ないというのに。
修二コーチ、もとい種ヶ島と付き合っていたのは高校卒業前の数ヶ月で、今にして思えば、破局の原因はひとえに私の心の狭さにあったと言えるだろう。
特技を聞かれた時には合コンなどと答える、ノリも顔も良い男を周りの女の子が放っておかないのは当然のこと。種ヶ島に非はないのだけれど、例え彼女が居よう居まいがとにかくモテまくる彼と過ごしているうちに、なんだかどんどん惨めな気持ちになったり不安になったりして、それが全部一人相撲なのが虚しくて、「浮気してんじゃないの」なんてありもしない濡れ衣をきせて突然別れ話を持ちかけたのは私の方だった。
そんなことしていないと言う至極当然な彼の主張を突っぱねて一方的に破局へ持ち込んだものだから結局、私たちはお互いにまともな話し合いをすることなく高校を卒業し、今に至る。
引く手数多な種ヶ島のことだから、別にこちらのことはなんとも思っていないだろうが、かつてを振り返りただひたすら自分が悪かったと自覚している私は、彼を前にして和かな顔を保つのすら難しい。元々、それなりに仲の良い友人関係にあったのにそれすらぶち壊したのだ。今更どんな顔をして会話すれば良いというのか。
つまり今現在私は、非常に、気まずい。
「知っとるも何も、お姉ちゃんと俺同級生でなぁ、結構仲良かってん。なあ?」
「え?あ、そう……かも?」
「ハハ!歯切れ悪!」
私の気まずさなどつゆ知らず、まるで昨日からの続きのように接してくるのだから調子が狂う。終始困り顔の私を見上げて、妹は首を傾げた。
「さっきからお姉ちゃんずっと困ってる。どうして?修二コーチのこと嫌い?」
「え!?ううん、違うよ!嫌いじゃない嫌いじゃない!会うのが久しぶりだから、緊張してるんだよ」
悪気のないストレートな質問に大慌てで首を横に振った。緊張しているのは本当。別れたけれど、本気で嫌いになったわけではないのも、本当。
「そっか!修二コーチかっこいいもんね!」
「あー、……あはは」
「そこは肯定せんのかい!」
濁して笑えば、すかさず種ヶ島がツッコミをして、妹がきゃらきゃらと笑い声を上げた。
綺麗にオチも付いたことだし、いい加減この落ち着かない空間から撤退しよう。そう決めて末っ子の小さな手を握ったところで、「あ!一瞬待って」と声を上げた種ヶ島は小走りでバックヤードへ向かい、言った通り一瞬で戻ってきた。
手には一枚のチラシ。それを無理やり私に握らせる。
「なに?」
「今度、体験スクールの日があんねん。姉妹でテニスしてみーひん?楽しいと思うで」
「いや、私は、」
「やりたい!!」
「うーん、お姉ちゃん、ラケット持って帰ってきてないし……」
目を輝かせたのはもちろん妹。できるだけ種ヶ島と顔を合わせたくない私は、懸命に言い訳を探して説得を試みる。
それを知ってか知らずか、営業上手のコーチはご丁寧に私の意見を正論で潰してみせた。
「貸しラケットくらいあるし心配いらんよ。シューズの貸し出しもやっとるし、運動できる服と元気があれば誰でも参加OKやで」
「……お母さんに聞いてからね」
「今聞くから電話貸して!」
大はしゃぎの彼女にスマホを奪われ、私はすっかり手持ち無沙汰となった。他のスクール生たちの元気な挨拶に笑顔を返す種ヶ島の横で、再度居心地悪くするしかない。
せめて車に戻ってから電話させるべきだった。心の中で何度も何度もため息をついていると、彼が子どもみたいに私の腕を控えめにつつく。
「なあ。さっきの“嫌いじゃない”ってやつ、ホンマの話?」
「え?まあ別に、嫌いとかではないけど……。なんでそんなこと聞くの?」
「俺にもまだ挽回の余地あるんかな思て」
「ばんかい」
「そ、挽回。嫌われてないなら、もっとグイグイ行っても構へんよな?」
「え」
挽回?グイグイって、何?
面食らっているうちに、満面の笑みを浮かべた妹がスキップで舞い戻ってくる。母親からのOKが出たらしい。
横で修二が小さく「よっしゃ!」と拳を作った。
「ほんなら来週、お待ちしてます。番号変わってへんから、分からんことあったら連絡してや」
二年越しに、何だかとんでもないことになってきた気がする。顔を引き攣らせ頷く私とは裏腹、彼はいつもの人好きする笑顔で手を振った。