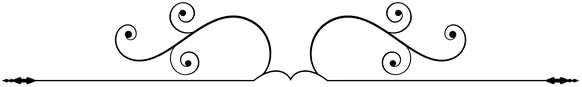
05
事情を知った上司が「今日は早めに仕事を切り上げて良いぞ」とニコニコ顔で言い、矢継ぎ早に「ついでにお前の有給を5日間取っておいたぞ」と畳みかけてきたものだから、月島は3時過ぎに会社を出て、こうしてコンビニで買い物をしていた。
「ただいまー。」
家の扉を開けて挨拶しても、いつもの妻の出迎えはない。
靴を揃えることなく急いで上がり、台所にある冷蔵庫の冷凍スペースにコンビニで買って来たバニラのアイスクリームを入れ、スポーツドリンクをコップに注いで寝室に向かう。
「お帰りなさい……。」
額に熱冷ましのシートを貼った妻が、夫を出迎えるために体を起こそうとするので、慌てて支える。
「まだ熱があるんだから無理するな。…飲み物買って来たんだが、飲むか?」
尋ねるとすぐにコクッと頷く祐季。嬉しそうにコップを受け取り、余程喉が渇いていたのかゴクゴクと飲み干した。
祐季が熱を出したのは昨日の朝だ。隣でしんどそうにしていたので熱を測れば39度。慌てて会社に連絡して自分の出勤が遅くなると伝え、妻を病院に連れて診せれば風邪とわかり。
心配していたインフルエンザではないと安堵したものの、それでも月島は妻が心配で落ち着けず。
今日は最初から休むつもりでいたのだが、妻の祐季が大丈夫だからと言うので渋々出勤するも、ここのところ仕事が忙しかったこともあって小さなミスが続き、直属の上司である鶴見社長から事情を聞かれて現在に至るわけである。
「腹は空いてるか?」
「少し……。」
「よし。うどん買って来たから、今日は俺が作る。」
「え、基さんが?」
不安げな表情を向けられたので、うどんぐらいは作れると返してムキになる。自分が作るからと言う祐季を強引に受け流し、張り切って台所へ向かった。
たかが冷凍うどんと舐めてかかったことで悪戦苦闘した月島は、妻のありがたさを痛感する。
茹で時間は袋に表示があるものの、小鍋でお湯を沸かして麺を投入してふと気づいたのは、時間の感覚がわからないということ。キッチンタイマーとして使おうと慌てて寝室に置いてきたスマホを取ろうとするも、鍋を火にかけたまま台所を離れるのはいかがなものかと思い直し、出来上がったのはふやふやのコシがないやわらかうどんであった。
作り直そうかとは考えたが、これ以上待たせるわけにはいかない。腹をくくって、やわらかうどんをつゆが注がれている丼に入れた。
「出来たぞ。」
「火傷とか大丈夫ですか?」
「ああ、怪我はない。」
妻がまるで子を気遣う母親のようで複雑な気持ちになった月島だが、それよりも気になるのはうどんの評価である。
恐る恐る反応をうかがう夫をよそに、祐季はさして気にする様子はなく、寧ろ嬉しそうにうどんをすする。
「あー、その……少し麺を茹ですぎてな。食べにくくないか?」
「いえ、懐かしくて私は好きです。」
「懐かしい?」
自分が生まれ育った九州でのうどんは舌で切れるほどやわらかく、つゆも関東の真っ黒いものとは全然違うのだ、と昔を懐かしむように話す祐季。
今迄何回か鯉登専務をうどん屋に誘ったものの頑なに断られ続ける謎が解けた月島常務であった。
