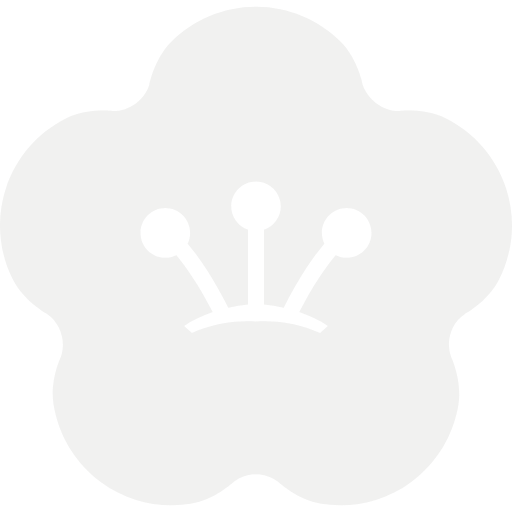靴を履いていないから地面を踏み抜くたびに小石が足に突き刺さる。そんな痛みなんて気にしてられなかった。
いつの間にか周囲から民家はなくなっていて、田んぼが並ぶあで道を駆け抜けていく。
そこは余計に大きな石ころが転がっている道だけれど、足を止めることなんて許されない。
げらげらと下卑た笑い声をあげながら「稀血、稀血」と楽しそうに追いかけてくる”それ”に捕まれば、殺されてしまうことなんて火を見るより明らかだったから。
今日は月が綺麗な夜だった。
あたりに散りばめられた星たちがまるで光を奪われてしまっているかのように、月だけが強く光り輝いている。
黒く塗りつぶされたような空に一つだけぽかんと浮かぶ月は、どこか寂しげな雰囲気を放っているようにも思った。
だけれども窓枠から見えるちっぽけな風景にその月は収まりきらず、部屋の中にいる私はその月の全貌を想像することしか出来ない。
いつもいつも与えられた本を読みながら、切り取られた小さな風景を見るだけの日々は退屈で窮屈でつまらなかった。
だからと言って素直に「外に出たい」と言ったところで、兄はいつも困ったように微笑むだけ。
外は危険がいっぱいだからなんて子供に言い聞かせるようなことしか言わないで、たいした理由は教えてくれずに私が読み終わった本を新しい本に交換していく。
そんな日々を一体いつまで続ければいいんだろう。少なくとももう二年は経つと記憶している。
今日の月はなんだか惹き付けられるような、そんな気がして見ているだけでは抑えられなかった。
もっと近くでその大きな月が見たくて、さらに窓から身を乗り出して掴めそうなそれに手を伸ばす。
カーペットから足を浮かせて、夢中になっていれば不意にぐらりと視界が傾いた。
しまった、なんて思うも遅く重力に従って私の体は窓の外に放り出される。
しかし目を閉じて身構えた割にその後に来たのはほんの少しの衝撃だけで、大して高さがなかったからだろう。
こてん、と放り出された体はどうやら地面に生える綺麗に切りそろえられた芝生が受け止めてくれたらしかった。
父と母が死んでから兄は私を外に出さなくなった。
怖い顔をした兄に外に出てはいけないよ、と何度も何度も言われていたから私はそれを守ってきた。
着ていたワンピースの汚れを払うことも忘れて、空を見上げる。
切り取られたちっぽけだった風景が、辺り一面に広がっていて思わず息を飲んだ。
窓越しでしか見ることの出来なかった月がそこにあったから。
裏庭の出口の場所は幼い頃ここで遊んだ記憶が、ここから近いことを思い出させた。
抑えられない好奇心が、私を急かす。
どの道、この汚れてしまったワンピースでは外に出たことを隠すことは出来ないのだから、どうせ怒られるのならばどこまで出ても同じだろうなんて。
そう、甘かった。そんな考えを持って私は外に出てきてしまったのだ。
兄の言っていた危険がなにかなんて考えもせず、ただただ好奇心の赴くままに。
このまま家に戻っても、みんな殺されてしまうだけだろう。
第一、かなり離れたところまで来てしまっている、引き返す前に追いつかれてしまうだろうから逃げ切ることは出来なさそうだ。
助けを呼ぼうにもそもそもあれは人に倒せるものなのだろうか?
そんな疑問を感じるぐらいにはそれは異形だった。
はあはあと上がる息が限界だと悲鳴をあげるものの、足を止めるわけにはいかなかった。日頃の運動不足が恨めしくて仕方がない。
振り向くわけにもいかなかった。
走れど走れど笑い声は引き離されるどころか、だんだんと近付いてくる。焦らすようにじりじりと、少しずつ。
「つぅかまえた」
さっきまで後ろで聞こえていた声が不意に耳元から聞こえた。
どくり、と心臓が嫌な音を立てる。
なんで、なんて考える暇もなく、手とは呼びがたいごつごつとしたそれが私の腕を掴んだ。
「鬼ごっこなんて久しぶりだったなぁ、ひひひ、実にいいなぁ。えぇ?月が綺麗だなあ。お前もそう思うだろ?俺はついてるぜ、稀血に出会えるなんてなあ」
人間のなりそこないのようないびつな形をした”それ”はそう言って大きな口を歪ませる。
そこにある死の形がはっきりと見えた気がした。
死にたくない、堰を切ったようにぽろぽろとこぼれる涙が止まらなかった。なんで家の外になんて出たんだろうか、兄の言う通り家の中だけで過ごしていれば良かったのだ。
なんて今更後悔してももう遅い。
ぐいっとものすごい力で宙ぶらりんに持ち上げられて、声をあげようにもはくはくと空気が出るだけ。酸欠でカラカラになった喉は焼け付いているかのような錯覚を起こした。
にやにやと笑うそれのあんぐりと開けれた口がゆっくりと近付いてきて、それで、それで。
私、は。
目を閉じておけ、そんな知らない誰かの声と共に藤の匂いが鼻をかすめた気がした。
言われた通りぎゅっと目を閉じれば「ぎゃあ」なんて短い悲鳴のあとに足から手が離される感覚。
襲って来る浮遊間、今度は受け止めてくれる芝生なんてなくて思いっきり硬い地面に投げ出される。
痛い、痛い、打ち付けた体がズキズキと痛みを主張する。
状況が理解出来なくてぐるぐると頭が回るような感覚に陥った。
もう目を開けていいのだろうか、今どうなっているんだろうか、私は助かったのだろうか。よくわからない。
「無事か?」
そんな、凛とした声が聞こえてゆっくりと顔を上げればさっきまでいたものは居なくなっていて、代わりにと言ったように月を背に立つその人の手には刀が握られていた。
何も言わない私にしびれを切らしたのか、その人は未だ地面にうずくまる私を強引に起き上がらせ座らせるとぐるぐると足に布を巻き付ける。
「立てるか」
「あ…ありがとうございます、あの」
「説明は後でする。とりあえずここを移動したい」
す、と差し出された手に掴まれば強い力で引っ張られる。
気が抜けたのだろうか、それとも走りすぎたからだろうか、しかし足が踏ん張れずにへたん、とその場に座り込んでしまった。
があがあとその人の肩に止まっていたカラスが急げ、急げと喚き出す。
ぎょっとした私とは裏腹に五月蝿そうに眉をひそめたその人は私のことをひょいと片手で抱き上げると、無表情な顔で「家はどこだ」と呟いた。
私の事を助けてくれたその人はあまり口数が多い方ではないようだ。
彼とはこちらが聞くことに言葉を返す程度の会話しかなく、彼から話しかけてくることはなかったように思う。
ぽつりぽつり、気になることを問いかければ言い淀むことなくそれに応える彼の話は俄に信じ難いものばかり。鬼とそれを狩る鬼狩り、なんて。
部屋に籠るようになってからは読み終わった本は兄が入れ替えてしまうので昔読んだ本をもう一度読むことは無くなったけれど、確かお伽噺の中にそんな話があったように思う。
まだ父と母が生きていた頃に、悪いことをすれば鬼が来るよという言葉と共に読み聞かせられた。内容はよくある昔話だった筈だ。
それが怖くて怖くて本当に小さかった頃の私は話の途中でぴいぴい泣いてしまって、その夜は両親のベッドで嫌がる兄も巻き込んで一緒に寝た覚えがあった。
結局そんな私を見て両親は鬼の話をしなくなったし、結局私がその結末を読めるようになったのは少し大きくなってから。
その頃には鬼への恐怖なんて忘れて本の中に登場する鬼狩りの青年のことを目を輝かせながら「かっこいい」と何度も読んだものである。
とどのつまり私にとって鬼や鬼狩りなんてものは紙の中の登場人物でしか無くて、あんな思いをしたあとだというのに、朝が来ればいつものように目を覚ましてベッドの上にいるのではないかなんて考えている。
それほどに彼が語った話は夢物語のようで考えられないことばかりだったから。
私のその考えを見透かしているのか、はたまたま別の理由からか彼が感情の読み取れない目で静かに私を見下ろしている。
「信じられないか」
「…それはもう」
「だろうな」
それだけ言って、彼は視線を前に戻した。
まだまだ聞きたいことはあるのだけれど、どこから聞いていいのかわからなかった。
そう言えば、あの鬼は私のことをなんて言っていたっけな。そう。
「私のこと稀血って、言ってました」
「珍しい性質の血液を持つもののことをそう呼ぶ。鬼は人間を食えば食うほど強くなる。しかし稀血の人間を食えば、普通の人間を食らうのとは桁違いの力を手に入れられる。だから狙われやすい」
「…人間を、食べる」
ああやって私がしつこく追いかけ回されたのは殺すためじゃなくて、食べるため。
もしもあのまま助けに来てくれなかったら、そう考えると胃からなにかこみ上げてきそうだった。
「良いものではない。が、それで何か変わる訳でもない」
彼は視線すら向けずにそう言って、それからはお互い何も話さなかった。
ただぼうっと惚けていればいつの間に着いていたのか家の前でその腕から降ろされる。
少し落ち着いたからか、足は痛かったけれど今度はへたり込むことはなく立つことが出来た。
いよいよドロドロになってしまったワンピースは汚れていないところを探す方が難しそうだ。
気休め程度に土を払ってみても取れそうにはなかった。
彼の隣を飛んでいたカラスが手を出せと喋って、その口から小さなお守りが吐き出される。
さっきから思っていたけれど、喋ったりお守りを出したりこのカラスは何なのだろうか。不思議なことばかりだ。
受け取ったお守りからは藤の柔らかな香りがした。
どうやらそれは匂い袋のようで曰く藤の匂いは鬼避けになるらしかった。
「ありがとうございました。本当に、いろいろ」
「気にするな」
もらったお守りをぎゅっと握りしめてお辞儀をすればそんな短な言葉と共に彼は背を向けて歩き出す。
何かお礼をと言ったもののどうやら先を急ぐらしく、それ以上引き止めることが出来なかった。
彼の真っ黒な髪と服は夜に溶け込むような色をしていて、かと思えば派手な色の羽織を着たその人はこの夜の中ではよく目立つ。
その人の姿が遠くなったところで、名前を聞くのもこちらが名乗るのも忘れていたことに気がついた。
いつかまたお礼と一緒に聞くことができるだろうか。
「なまえ様!」
悲鳴のような、女中の甲高い声が屋敷の中から聞こえてきた。
よく世話を焼いてくれているタキのものだと言うことはすぐに分かった。
その声は随分と怒っているようで、忘れていたけれど何も言わずに抜け出してきたんだったっけ。
しかし少し青白く血の気が引いたような顔をしているから、ひどく心配を掛けてしまったんだろう。
「一体どこに行っておられたのですか!」
「…ごめんなさい」
「ああ、私たちがどれほど心配したと…!」
怪我をしていることに気がついたタキはすごい剣幕で「早く手当をしないと!」と私の手を引いて、屋敷の中へと向かっていく。
ふ、と振り向いた先にもう彼の姿は見当たらなかった。
*
彼、冨岡義勇は考える。
なまえ様、と先程の少女がそう呼ばれているのは義勇の耳にも入っていた。
彼女の着ていた服は寝間着にしては仕立てのいいもので、傷一つない手から裕福な家の者であると言うことは想像に難くなかった。
実際に彼女が家だと指し示したのは街からは少し外れにあるものの、ひどく大きな洋風の家でこの地に立ち寄っただけの義勇にもその家がこの辺りでいちばん大きいものなのだと理解するのに時間など必要なかった。
それにしては、と。先ほど彼女を送っていった家のことを思い返す。
あの屋敷はどうにも人の気配が乏しかった。
ぽつぽつと感じる気配は二つ、三つ程度のもの。いくら真夜中だと言えどあの家の広さならば使用人など、住み込みのものがもっといてもおかしくないはずだろうに。
そして先程倒したあの鬼。
人型にこそなりきれていなかったものの、かなりの人数を食らっている鬼であったのは間違いないだろう。
人が住む街も近く、だからこそ迅速にそして内密に処理するために柱である義勇が派遣された訳であったのだが、一匹ならまだしもそれほどの鬼が近くに”沢山”いたというのに今の今まで稀血の少女が襲われずに済む、なんてことはあるのだろうか。
まぁ、俺には関係のないことか。
はた、とそこまで考えて彼は思考をやめた。一刀のうちに目の前にいた鬼を切り伏せる。
叫ぶ鬼の醜い悲鳴が静かな空に吸い込まれて消えていく。
報告より数が多かったもののたった今切ったそれでこの街にいた鬼の気配はくなった。
そしてかの少女にも藤の香のお守りを渡したのだから、またこの街に鬼が現れたとしてもこれ以上彼女が襲われることもないだろう。
何を考えたところで、彼がこの街に居座る理由なんてものはもう無いのだから。
刀に付いた血を振り払ってからそれを鞘に収めると合わせたかのように「お館様が呼んでいる」とぎゃあぎゃあカラスが鳴き出した。
丁度いい。鬼の数が想定より多かったこと、そして稀血の少女。
今回のことはお館様に報告しておく必要があるだろう。
いつの間にかその大きな月は姿を消し、白んで来た空が朝の訪れを告げる。
闇に生きる鬼たちは活動をやめ陽の当たらない日陰の方に身を隠す時間だ。
あんな月の後だからきっと今日は晴天だろう。義勇は差し込む日差しを遮るように薄く目を細めた。