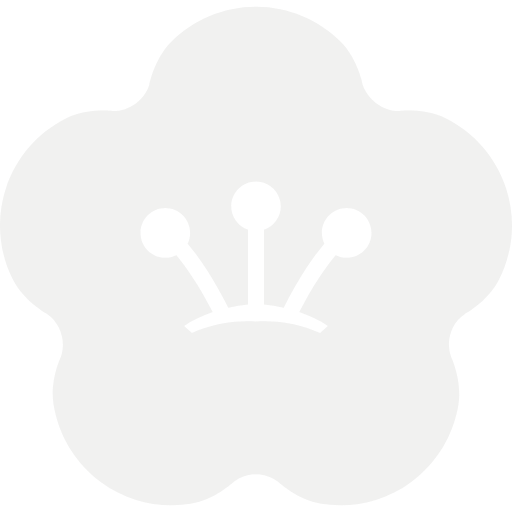「なぜ、お前はそうも私の言うことを聞き入れてくれないんだ」
兄が帰ってきたのはその日の次の晩のことだ。
普段はもっと街中にある別宅で仕事をしている兄がこっちの家に帰ってくることは珍しい。
帰ってきて早々大きな音を立てて部屋の扉を開けた兄は、私の足に巻かれている包帯を見て大きくため息を吐くと呆れたようにそう言った。
タキには言わないで、とお願いしてたけれどどうにも無意味だったらしい。
タキは今夕ご飯の後片付けをしている頃だから、きっと彼女以外の女中から聞いたんだろう。
そしてずかずかと部屋に入ってきた兄はふと足を止めた。
すんすんと匂いを嗅いだかと思うと不機嫌そうに眉を顰める。
ある程度の距離から近付いてこなくなった兄はじ、と私の手元にあるお守りのことを睨めつけていた。
あっ、とぽつりこぼした言葉に兄は
「お兄ちゃんは、あまり好きじゃなかったっけ」
「藤の花、か。…どこで貰って来たんだい?」
口調こそいつもの兄と変わらず柔らかいものの、そう聞く兄の顔は見たことが無いほど怖いもので、なんて言っても兄の逆鱗に触れてしまいそうで思わず口をつぐんでしまう。
兄は花全般の匂いをあまり好ましく思わない人だと言うのは知っていたはずなのに、なんで忘れてたんだろう。
片付けるね、と蚊の鳴くような声で呟いてそれを机の引き出しに仕舞った。
その時にタオルに包んでおいたから、匂いは漏れてこないだろう。
おそるおそる兄の顔を覗いてみれば、また彼は大きなため息を吐いて「こっちへ来なさい」と私のことを呼び寄せた。
兄の後をついて部屋を出れば、その廊下はひどく騒がしく何人もの人が私たちの隣をすれ違っていく。
私の世話をするものなどほんのひとにぎりで、普段は人気が少ない屋敷も兄が帰ってくればその騒がしさを取り戻す。
普段はこちらの屋敷に出入りしないような兄の部下にあたる人たちや、父の仕事を継いだ兄の世話をしに別宅に出向いているする人たちが一気にこっちへ戻ってきて慌ただしく廊下をかけていく様子はすこし新鮮だった。
とはいえ両親と住んでた頃に比べれば随分と人は減ったけれども、いまは二人しか住んでいないのだから当然といえば当然なのかもしれない。
何も言わずに先を行く兄についていけば、たどり着いたの兄の部屋。
本人は不在なことが多いというのに、綺麗に片付けられた部屋には私の部屋とは違って向かい合わせで座れる机があった。
「紅茶の用意を、それと今日の仕事はもう終わりだ。何かあれば明日聞く、と皆に伝えておいてくれ」
「かしこまりました。夕食のご用意は?」
「いい、外で食べてきた」
ぽすり、着ていたジャケットを乱雑にソファーに投げ捨てて座った兄を尻目に私も腰を落とす。
昔はよくこうして兄の部屋に遊びに来ていたものだったけれど、ここに来るのは随分と久々だった。
沈むソファーの感覚はやっぱり昔と変わらない。
「どうして外に出たりなんてした?」
お互いに何も言わない居心地の悪い空間で、先に口火を切ったのは兄の方だった。
「……出たかったから」
それ以外に、言えることなんて何も無い。
目の間に出された紅茶に口をつけて、おそるおそる兄の方を見る。
兄は何も言わなかった、難しげな顔で紅茶にも口をつけずに黙り込んでいた。
「知ってたの、お兄ちゃんは鬼のこと」
その空間が耐えられなくて、今度は私が尋ねる。
すっ、と冷たく細められた目が私のことを捉えた。
それはどう答えるか考えあぐねているような、かと思えば私を品定めするかのような、そんな表情だったように思える。
昔私がここに来ていた時は一体どんな話をしていたんだっけ。
こんなふうに兄と話すことに、緊張感を覚えることなど無かったはずだ。
兄はこんな目をする人だっただろうか。
「…知っていた。父さんと母さんの遺体を最初に見つけたのが私だったからな。酷い有様だったよ。どうしたらそんな死に方をするのか調べていたら、鬼という存在にたどり着いた」
長い長い沈黙のあと、ふう。と諦めたように小さく息を吐いた兄は苦虫を噛み潰したような顔でそう言った。
鬼に襲われたなんて突拍子もないことを言っても、タキは疑うこともせずにそれを信じた。
神妙な顔をして「そうですか」と言葉を紡いだ。
それはタキが鬼という存在を知っていた、ということにほかならず引いては兄も昔から鬼のことを知ってたんだろう。
今日は兄のため息をよく聞く日だと思う。
酷い有様だったと兄は言った。
実際にどうだったかなんてそれを知っているのは兄だけなのだから、私はただただ想像することしか出来ないけれど、きっとぐちゃぐちゃに食い散らかされていた。という事だろう。
それを想像してまた胃の中ぐっと掴まれたような間隔が私の体を通り抜けていく。
想像していた通りのことだったとしていたとしても、昨日実際に出会っているとしても、鬼という存在のことをそう簡単に受け止めることなんて出来そうになかった。
「言いたくなかったんだ、お前を不安にさせてしまうだろう」
昨日の鬼のことを思い出して体が震える。
手に持った紅茶を波立たせながら、青い顔をした私を見て兄は切なげに笑った。
「ごめん、なさい」
ふ、と反射的にそう言っていた。
家から出してくれない兄の心配を煩わしいとさえ思っていた。
自分の両親が鬼に殺されたことなんて露ほども知らずに、兄の心配を無駄にして。
「すまない、そんな顔をさせたかったわけじゃないんだ」
ひどい顔をしていたんだろう。
足が張り付いたように動がなくて、もっと兄に何か言いたかったはずなのに言うことがあったはずなのに。
「送ってやれ、猗窩座」という兄の声で入ってきたその人に体を支えられて部屋を出る。
先程まであんなにうるさく聞こえていた廊下は、人がいるはずなのにひどく静かに聞こえた。
猗窩座さんは兄の部下にあたる人で、兄が父の仕事を継いだあの日から何かと面倒を見てくれる、もう1人の兄のような存在であった。
ぽすり、少し低い体温の手が私の頭をゆるゆると撫でる。
「人間の肉体というものは脆いからな」
そう言って猗窩座さんは本当に切なそうな顔で微笑んだ。
「匂いが移ってしまっているな」
「藤の匂いは、俺も嫌いだ」
「また顔を出す」