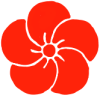
初めての
恋い焦がれた想いが念願叶って成就し、縁は結ばれ恋仲となってから初めて口付けを交わした時の事である。
嬉しさよりも恥ずかしさが勝って顔を真っ赤に発火させた彼女は、小さく感想をごちた。
「“顔から火が出る”とは、まさにこの事やぁ〜ん……………ッ」
其処へ、一人口付けた感覚の余韻を確めていた彼がぽつり、問いかける。
「…なぁ、悪ぃんだけど……もう一回してみても良いか?」
「え…ッ!?」
「あ、いや…アンタさえ良ければ、で良いんだが………嫌じゃなきゃ、もう一回、口吸いしても良いか?」
「ッ〜〜〜…!?」
無言のリアクション…からの視線を逸らしつつ、顔を真っ赤にさせながらもコクリ、と頷きを返してみせた柧眞。
了承を得た彼は、離れていた距離を埋めるようにそ…っと彼女へと近寄り、彼女の頬へその手を伸ばした。
彼の掌が頬に触れたのを合図に、彼女は緊張した面持ちで再び瞳を閉じる。
其れを皮切りに彼は優しく彼女の唇へと己の唇を落とした。
壊れ物を扱うように触れ、彼女の反応を窺いながら徐々に口付けを深くしていく。
初めはそっと触れ合う程度に、そうして少しずつ柔く食むように口付けていき、やがて本能に従うように深く深く口付けていく。
視線は一切逸らさない。
彼女の一つ一つの挙動を逃さないように、瞳は伏せないまま、彼女を見つめたままに口付ける。
そうして口付けに溶けていく彼女の様子を目蓋の裏に焼き付けるのだ。
己の好いた女が、己の口付けだけでこんなにも恍惚とした蕩けた表情になるのを…。
互いの口内を行き来して溢れた唾液が、口端から顎へと伝い落ちる。
飲み下し切れなかった分が零れてしまったのだ。
互いの唇から銀糸が伝い、今しがた繋がっていた事を示すように艶かしく光った。
慣れぬ事に息継ぎすらも儘ならぬようである彼女は、一生懸命に呼吸を整えようと必死であった。
だがしかし、そんな様すら愛おしいと感情を溢れさせて止まぬ気持ちが急いて、性急にも次の口付けをせがんだ。
息を整え切れぬままの彼女へ覆い被さるように口付け、その身を押し倒す。
今、この時に、この部屋にはただ二人だけ。
時刻も夜更けの皆が寝静まった後の刻である。
そんな刻に、一人の男と女が揃えば、忽ち盛り上がるものであった。
最早、其れは自然の摂理とさえ言えよう。
晴れて恋仲と結ばれたばかりの浮かれた気持ちは、先へ先へと逸るばかりである。
だけども、男は大層痛く女を大事にしていた為か、この時ばかりは其れ以上先へ進む事はしなかった。
互いに口付け合うだけで精一杯だったのもあったかもしれないが、その口付け合うという行為だけでも十二分に満たされていたからである。
「――ッは……はぁ、…たぬ、さ………っ、」
「ン……?」
「…んぅっ、……名前、呼んで…?」
「……柧眞、」
「うんっ……たぬさん、好きだよ」
「――柧眞…っ、」
「ぁ、ンふ…っ、好き、大好きっ……たぬさんと、恋人…んっ、なれて、嬉しい……っ、」
「…俺もだよ、んなの……もっと早く、こうなれてりゃ良かったのにって、思わずには居られねぇよ」
「ふっ、ァ……」
拙いながらも必死に想いを口にしようとする彼女に
そして、口付けのついでのつもりで、組み敷いた彼女の無防備に曝されていた首筋へと吸い付いた。
後で確認をすればきっと痕が残っている事だろうが、今この時ばかりは頭が馬鹿になったみたく湯立っていて思考が働かなかった。
彼に施されるまま受け入れ、彼女は貪欲に色に落ちていく。
覆い被さってくる愛しき男の身を受け入れ、嬉しそうに微笑む。
蕩けた笑みに引かれて、彼もまた愛しき女の身を抱き寄せて、己の腕の中へと閉じ込める。
どんな形であれ、彼女と彼はこうして出逢い、惹かれ合った
その糸を解こうものなら、容易にはいかぬ事だろう。
其れ程までに、二人の縁は既に強く絡み合い結ばっていたのである。
要は、結ばれるべくして結ばれた二人という事なり。
―周囲も其れを静かに温かく見守りつつ祝福しているのは、彼等の知らぬところなのである。
執筆日:2021.09.22
表紙 - 戻る