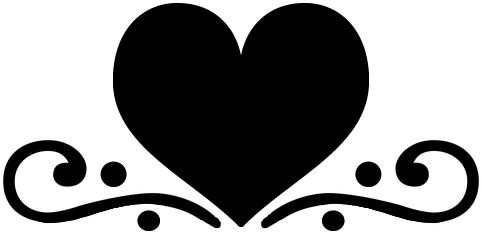
December
君の計算式に欠けているもの//茜アイドル業と学業を両立するのは難しい。レッスン、取材、撮影、学校、ライブ、レコーディング、テスト、みたいな日々が続いていると、いつの間にか学業は疎かになってしまうのだ。次の定期考査の課題を早めに終わらすのは得策だということに気づいたのは、二学期の終わりの今だった。だから事務所で勉強中。
「なまえちゃん、何書いてるの?」
「数字」
そんな私に声をかけてきたのは茜ちゃんだった。茜ちゃんは私と同じく高校に通っているんだけど、まったくもって勉強をしている姿をこの事務所内で見ない。あんなに勉強をしていなさそうな未来や翼だって何度かは目にしたことがあるというのに。
「そりゃあ茜ちゃんだって文字が読めないわけじゃないんだからそれぐらいわかるよ〜! どうしてそんなことしてるのかが気になるって、そう言ってるんだよ!」
「私、馬鹿だからきちんと言いたいこと、伝えたいことを文字にしてくれないとわからないわ。それで、どうしてかって聞かれたら、まあ好きだから、としか言えないかな」
「な〜にそれ〜。ぜんっぜん面白くないよ〜。なまえちゃんっていわゆる理系女子、つまりリケジョとかいうやつなの!? 茜ちゃんはもっとバラエティーに富んだ面白い回答を期待していたのだ!!」
……茜ちゃんは、私にとっては少し回りくどい話し方をするように思える。面白いことを瞬時に考えて発言するなんて、どれだけつかれることなのだろうか。茜ちゃんはバラエティーアイドルがとても向いていると常々私は考えているのだ。
「そう。それは申し訳ないとしか言い様がないよね。私は面白みが無いって、よく言われるから。この事務所には私よりも面白い人はたくさんいるんだから、その人のところにいけばいいじゃない」
「へっ? なまえちゃん、そんな……茜ちゃんのこと見捨てるっていうの……!?」
それと、茜ちゃんは私が思ってもみないことをなんてことなく口に出すから、いつも私は驚いてしまう。やっぱり茜ちゃんはバラエティーに向いている。
「な、なんでそうなるかな……面白いことを求めているなら、私じゃない人でいいと思うんだけど」
「も〜、茜ちゃんはホントのホントのバカじゃないんだぞ! なまえちゃんに面白さが欠片もないって思ってたら期待なんてしないし、こうしてそばにいたりもしないよ。茜ちゃんは知ってるもんね! 天然な子が時折出すクリティカルヒットのダメージはとても大きいということを……! つまり、茜ちゃんはなまえちゃんと話すことに希望を持っている、ということなのであった」
「な、何を言っているのかよくわからないよ……」
脆くて甘いお菓子//育
「わたし、大人になったらなまえさんのこと絶対幸せにしてあげるからね!」
育ちゃんは、まだまだ幼い。10歳とかいう私とはかけ離れている年齢だ。隣に並ぶと姉妹に間違われるってくらいなのに、私達の関係は、恋人と呼ばれるものだった。
「ほんとに? 嬉しいなあ……」
育ちゃんは私と出会ったときに、一目惚れだと言いながら告白してきたのだが、いかんせん私よりもとても幼い。私は可愛く見られるように努力はしているつもりだが、自分で可愛いとは思ったことは一度もなかった。こんなにも幼い少女に惚れられるようなかっこよさも可愛さも美しさも兼ね合わせていないのだが、たまたま近所に引っ越してきた彼女とは、随分と距離を詰められてしまったのだ。この場合絆された、といったほうがいいのだろうか。
「なまえさん、もっと笑って! 今みたいな顔もっとして!」
「ええ、どんな顔してた? あんまりわかんないや」
「えっとね、すっごい幸せそうな顔してた! ふにゃ〜ってほっぺたがゆるゆるになってたの!」
「ほんと〜? ちょっと恥ずかしいなあ」
「あ〜! なまえさん照れてる〜! ほっぺた真っ赤だ〜!」
「そ、そんなことないよ〜! 育ちゃん、触っちゃダメだって〜!」
「ほっぺたあったかい! 私とおんなじだね!」
溜息が君を撫でるだろう//雪歩
息を吐くと、視界が薄い白に染まる。それくらい寒い季節にやっとなったのだ。冬というのは、身体的には冷える季節だが、私の心としてはとても暖かく感じられるように思える。それはやっぱり、隣に彼女が居るからなのだろうか。
「雪歩〜寒いね〜!」
「そうだね、なまえちゃん。今年も雪、降るみたい」
ふわりと、雪が舞うように笑う。毎日見ているはずなのに、冬が近づくにつれて、どんどん儚く、とけていくもののように感じてしまうのだ。
「……まあ、去年みたいにクリスマスじゃないけどね。でも、なんとなく嬉しい」
「その気持ち、分かる気がするなあ……なまえちゃん、今年もその時、一緒にいてくれますか?」
なんだか愛の告白みたいに、真剣な顔をした雪歩。その台詞は本当は私が言いたかったのに。
「一人じゃ寂しいって? 仕方ないなあ。私もきっと一人で虚しくいるとおもうから、雪歩の美味しいお茶を飲ませてもらおうかな」
「うん。事務所で淹れて待ってるから」
「事務所はちょっと寒くない? まあ雪歩と一緒なら気にならないか」
するすると、お互いの指が絡み合っていく。手袋越しにでも、雪歩の熱は伝わった。
たかが銀河に距てられ//紗代子
「あ、オリオン座見えるよ、紗代子」
劇場の屋上は冬はとても寒い。風が吹くと、凍えそうになるくらいだ。さっき買ったばかりの温かい缶コーヒーをほっぺたに当てながら、私と紗代子は今日のライブの熱気が冷めやらないまま空を眺めていた。
「本当? 今日は雲が殆ど無いし、もしかしたら天の川も見れるかもね」
「え、天の川って夏だけじゃないの?」
夜空に星が入ったミルクを流したような景色は、暑い季節限定のものだと思っていたが、どうやら違うらしい。
「ううん。冬でも一応見れるよ。夏と比べたら、そこまで綺麗に見えるわけじゃないけど……」
「へ〜、紗代子って詳しいんだ、星に」
「ミルキーウェイとして活動する時、ちょっと気になって調べただけだから、他のことはあんまりだけどね」
プラチナスターライブが終わってから、ユニットの仕事は随分と減ったが、身につけた知識と経験は確かに役立っている。それは多分、私や紗代子だけじゃなくて、みんなも同じだ。
「……紗代子ってさ、仕事熱心だよね。こんだけ仕事人だと恋人とかできても仕事優先しそう」
「そ、そんなことないわよ! 私だってちょっとは気を抜きたいときだって……あるけど……」
「あるけど、仕事に手は抜けない、と。まあ、紗代子らしくて真面目でいいんじゃないのかな。別に悪いことでもないし。でも休憩はきちんと挟みなよ。織姫と彦星だって一年に一日は休暇が与えられるんだから」
冬の天の川は不思議なくらいにきれいに見えた。ぬるくなった缶コーヒーに口をつけながら、隣にいる紗代子の涙には気づかないふりをする。
「それにしたって、働きすぎには変わりないけど」
触れちゃいけないところだと、私もわかっていたから、あ能天気に踏み外す。本当は、もっと柔らかい言い方ができたはずなのに。
「そうね。倒れちゃ元も子もないもの。ありがと、なまえ」
くすりと笑う笑顔はいつもと同じに思えた。紗代子は優しいんだね、悲しいくらい。