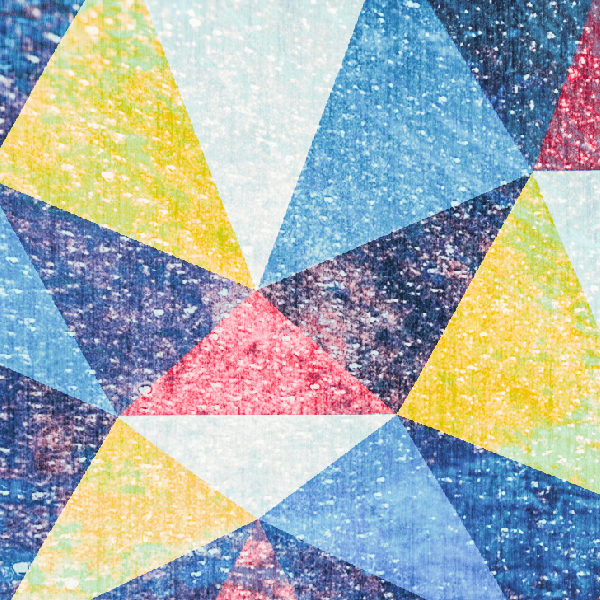
惑星の隅まで2人で行こう
綺麗なものほど、キラキラしているものほど簡単に汚されてしまいそうだし、壊れてしまいそうだし、無くしてしまいそうだ。
そう思うとずっと一緒にいないといけない、大切にしたい、そう思う。
◇◆
苗字名前という女は誰にでも軽率に「かっこいい」「イケメン」「かわいい」「ステキだ」という。
顔が性格が行動が、どんな相手であっても簡単に、そして思うままにそう口にして、キラキラと瞳を輝かせ、彼女は笑うのだ。
「いやあ、あの人イケメンだったなあ」
「…名前、もうそろそろ揚がるぞ」
「はーい」
ポツリと呟いた彼女の言葉に反応する者は、"ほぼ"この玉狛支部にはいない。流石に一々反応していてはこちらも疲れるし、正直聞き飽きた。
「へー、どんな人だったの?」
そうちゃんと聞いてくれるのは小南くらいだろう。名前は揚がっていく天ぷらたちをキッチンペーパーを敷いたバットに移しながら口を開いた。
「他の学年の人だと思うんですけど」
「うんうん」
「学校で、階段の1番上から落ちかけた時に」
「うん、…ってちょっとストップ」
「サッて支えてくれて…」
「こら、あたしの話を聞きなさいよ!」
律儀に小南は相槌を打っていたが、彼女の言葉に待ったをかける。しかし、名前は聞いているのか聞いていないのかそのまま続けてしまう。
小南の方が名前よりも1つ下ではあるが、仲の良さや名前が敬語を使われるのが苦手なせいでお互いタメで話す。烏丸はそれでも敬語だが、彼は年上の人に対してはほとんどそうなので言うのは諦めた。
「また階段から落ちそうになったの?」
「いやあ、何か自分の足に引っかかっちゃって」
「...この前は上履きが脱げかけて、その前は滑ったと言ってたな」
「我ながらドジですよねえ」
あはは、と笑っているが、正直他から見れば笑い事ではない。戦闘に関してはピカイチだし、頭も運動神経もそれなりに良いくせに彼女は運がないというか、ドジというか。鈴鳴の別役みたいに周りを巻き込んで何かを起こすわけではないが、聞く度にそろそろ大怪我するのでは?というような場面に遭遇している。
「とりまる、1日名前のこと監視してなさいよ」
「いや学年違いますし、まずそれだとただのストーカーです」
「玉狛が許すぞ!な、雷神丸!」
「えー、そこまで酷くないよ」
「酷いよ」
「酷いねえ」
えー、陽太郎に栞に迅さんまでそんなこと言う。そう言って、名前は口を尖らせる。
「名前はすぐ確率の低い未来に行くし、すぐ変わることもあるから助言が難しいんだよね」
「迅さんの予知すら惑わす不運さは、我ながらある意味凄いですよね」
苦笑する迅に常々思ってるそれを言う。迅が予知する未来の中で、名前という存在はちょっとだけ特異らしい。予知した未来の中で確率の低いものに簡単に突っ込む、らしいのだ。それだけなら良いけれど、悪い未来も良い未来も瞬く間にコロコロ変わってしまうのが彼女の未来だ。他が迅さんの云う"最善"に行ったとしても、何故か名前だけはそれを辿っていないこともあるらしい。
「開き直らない」
「はーい」
「伸ばさないの」
「はーい」
「こら」
懲りずに返事を伸ばせば、小南がジトっと名前を見やる。
「今の桐絵の顔かわいいー!ねー、もう1回!」
「話を変えない!」
いつものようにそんな会話をしていれば時間はあっという間に過ぎていく。そろそろ時間がやばいな、と考えながら丼物用の器にご飯と天ぷら、そして名前特製秘伝のタレをかける。よし、出来上がりだ。気の利く烏丸が完成したものから運んでいてくれる。
「さすがイケメン、できる男、かっこいい」
「...それほどでも」
「おれはー?」
「陽太郎は可愛いだね」
えー、と不満そうな声が聞こえてくるが、かわいいのなんて今のうちだけだ。この支部で育っていくなら迅タイプか木崎&烏丸タイプになりそうだし。
海老の天ぷら1つおまけね、と陽太郎に言えば「おおー」と喜んだ。ほら、そういう単純なところもかわいいって言っちゃう理由になるんだからね。
心の中でそんなことを考えながら、海老の天ぷらを1つ追加してあげる。早く食べたそうにソワソワする姿にクスクス笑いながら配膳を終え、そして席に着いた。
「いただきます」
いつものようにそう言って、いつものようにみんなで談笑しながらご飯を食べる。ああ、こんな日常本当にいい。大切にしないと。そんな思いも一緒に咀嚼しながらこの時間を堪能した。
◇◆
「じゃ、私はそろそろ」
「またあしたー」
「はーい」
待ち合わせの時間が近づいてきたから、とみんなに声をかけて入り口に向かう。唯一迅さんだけが着いてきた。めずらしいな、そんなことを思った。
「生駒っちによろしくね」
「はーい。迅さんが今日もかっこよかったって言っときますね」
「それ今度おれが殺されるヤツだからやめようか」
「?はーい」
顔を強ばらせた迅を見て名前は首を傾げる。そんな様子にやれやれと思いながらも迅は続ける。
「本当は送って行きたかったんだけどな」
「...大丈夫ですよ!全く心配症ですね」
「...」
「迅さん?」
迅は何だかんだ忙しい人だからわざわざこんなこと頼めない。烏丸も木崎も小南も宇佐美も陽太郎もみんなみんな優しいからこれ以上"巻き込んじゃダメ"なんだ。本当だったらイコさんも、...ああいや、これは言わない約束だったね。
「あ、ごめんな」
「いえ」
「まじ生駒っちから毎回今日は大丈夫なのかってメッセージが来てることだし、気をつけるんだぞ」
「えー、イコさんも心配性だね」
思わず苦笑した。そんなことしてたのか。あの人は本当に.......。
「.....」
「大丈夫だよ、迅さん。.....あ、そろそろ行かなきゃだから。また明日」
「うん。また明日ね」
見送ってくれるあの人に軽く手を振る。もしかしたら私に"明日"なんて、そんなことを思いながらゆっくりと玉狛支部を出た。
見上げた昼の空にくっきりと確かに"月"が浮かんでいた。
◇◆
「イコさーん」
「お、来た来た」
待ち合わせしていた公園にたどり着けば既にそこには生駒がいた。ラフな格好、片手にサッカーボール。ボーダーじゃあまり見えない格好に思わず笑う。
「イコさん、ちょー似合ってる」
「ホンマかいな」
「ホンマです」
きゃー、イケてる!とはしゃぎながらリフティングを始めた生駒の写真を撮る。すると相も変わらずカメラ目線の生駒が撮れた。なんでいつもそんなにカメラ目線なのかは結局分からないままだ。
「私にも蹴って」
「ほーい」
軽く蹴られたサッカーボールを足で受け取る。運動は苦手じゃない。サッカーも小学生の時は男子に混じってしてたし、中学でも体育の時間に「リフティングできた回数でちょっと成績加点する」という謎ルールでそれなりに加点を貰えたくらいにはできる。
彼はサッカーが好きらしい。昨日電話した時に久しぶりにサッカーしたいと言ったから、今こんな風に2人でボールを蹴っている。
「イコさん、今日のお昼は何食べたの?」
「今日はな、食堂に新メニュー出てたからそれ食べたで」
「え、新メニュー?」
「ハンバーグカレーや」
ハンバーグカレー、名前は思わず繰り返した。
「ハンバーグにカレーって最強じゃん」
「せやろ!しかもな、上に目玉焼き乗っててな」
「おー」
「ハンバーグの中にはチーズ入っててん」
「なにそれ、最強オブ最強すぎる」
無表情でサッカーをしている男女の会話とテンションとは思えないが、2人にとっての日常はこんな感じだった。
「玉狛の昼飯は?」
「今日はねー、私が当番だったからもちろん天丼だよ」
「何やて!」
「あ、ボール」
蹴り返したボールを生駒が受け止めなかったので、ボールは生駒を通り過ぎて行ってしまった。しかし、生駒はボールのことなど気にしていないらしい。
「名前の天丼やと!?」
「そ、そうだけど」
「美味いやつやん」
「あ、あ...ありがとう」
でも、それよりボール追いかけなくていいのか?と思っていればちゃんと追いかけ始めた。
「イコさんには今度作ってあげるから」
「約束やで」
「うん」.
生駒は名前の作る天丼が好きらしい。たまに作るとすごく喜ぶから見ていて楽しいものだ。
小さい頃から天丼の魅惑にハマり、自分で研究して自分なりの黄金比でタレを作っていた。やっと納得するに至るまで主に自分と家族が犠牲になったのだが、その分満足できる美味しいものができた。玉狛でも小南のカレーと並んで、名前が当番だと天丼が多い。自分の中での納得できるものが、他人にも評価をもらえるとそれはもう嬉しいものだ。
「何か天ぷらにして欲しいものあったら言ってね」
「おん」
今日はもうサッカーはやめにして帰路に着く。手を繋いで歩くのにも慣れた。なんたって付き合ってもう数ヶ月は経つのだ。歳は一つだけ違えど、元から何故か波長が合っていたわけだし。
「イコさん、今度ギター聞かせてよ」
「今から聞きに来るか?」
「いいの?」
「ええで」
気がついたら2人は付き合っていた。お互い何食わぬ表情のまま「かわいい」だの「イケメン」だの割と誰にでも言うし、意外と分かりづらい性格をしていたりもする。そんな2人がくっ付いたことを、何故か未だに玉狛と生駒隊とその他数人以外知るものはほとんど居ない。
「あと今度お菓子作り挑戦したいんだけど食べてくれる?」
「おー、ええなあ」
「後で何作るか一緒に考えて」
「おう。俺も料理始めたいから教えてな」
「うん」
ぽつりぽつり、いつものように呟きながらぎゅっと手を握って歩いていく。生駒はふと自分よりも随分と低いところにある彼女を見た。「ん?」と彼女がこちらを見上げる。キラキラ、相変わらずその瞳の中に綺麗な輝きが見えて無意識のうちに握る手の力を強くしてしまった。しかし、すぐにハッとして緩める。小さく謝罪すると「大丈夫」と返ってきた。
何だか流れ星みたいにどこかに流れて行ってそのままいなくなってしまいそうだ。
柄にもないことをつい考える。でも、彼女の"普段"を知っていると有り得ない話でもないかもしれない。もしかしたら彼女は1人だけ逸れてそのまま帰ってこないかもしれない。そんな気がしてならないのだ。
__ああ、胸騒ぎがする。
綺麗なものほど、大切なものほど簡単に手から零れ落ちて、ついぞ掬いあげられなくなってしまうから。それを知っているからこそ、だから、__。
「ね、イコさん」
「ん?なんや?」
名前が口を開いた。生駒は彼女の言葉を静かに待つ。ふと見上げた空は雲ひとつない快晴だった。
見事なまでに"青一色"に染められた空が綺麗だと思った。
(このままどこまでも2人で行こう)
(それで終着点も綺麗なままだといいね)