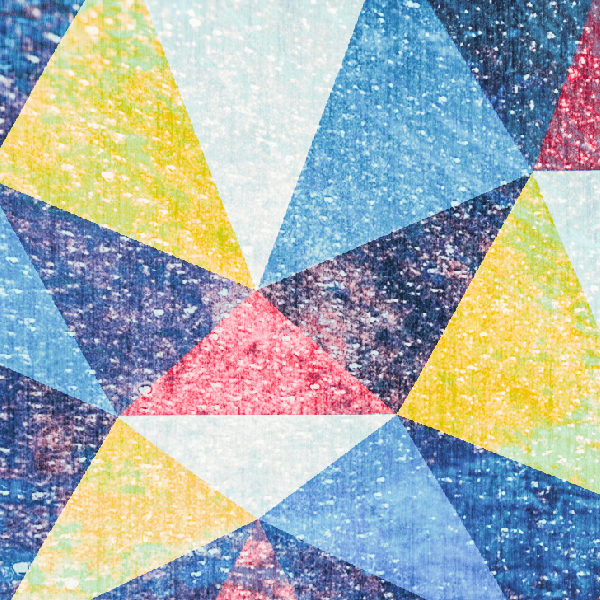
夜明けの狭間に連れてって
*高専時代の五条の話
私は生まれつき色が見えない、らしい。
らしい、というのもその"色"というものを目の当たりにしたことがないから実感がなかった。
まあ実感はなくたって現実で段々と思い知らされるようになるのだが。
私にとっては私の見えている世界が全てなのだから当たり前だろう。色が足りていないらしいこの世界も私的には綺麗だと思う。
色々な見分けがつかなくて困ってしまったり、周りをイライラさせてしまったり、哀れみを吐かれたりするけれどこればかりはどうしようもないと割り切っていた。
ウチの家には何やら"化け物"が取り付いているらしい。"化け物"というか"疫病神"というか何かそういうものらしい。こういうことは意外と他の家にもあるらしかった。家系図を見ながらされる代々伝わってた疫病神の話にはもう聞き飽きた。
何故疫病神が憑いているのか、それは先祖が何やら"力"を持っていたからだ。決して何かよからぬ事をして祟られた訳ではなく、逆にその"力"というものに魅了されたその疫病神が代々引っ付いて離れないのだとか。
今回その疫病神のターゲットは私になった。
祖母が亡くなって2週間後に生まれた私。元々祖母に憑いていた"それ"は一瞬だけ兄にくっついたらしいが、私が産まれると私に憑きなおした。その証拠に色が全くない世界を見る羽目になったわけで。
両親からしてみれば私のことは気の毒には思っているらしいが、跡取りである兄から"それ"が離れたことには安堵しているらしかった。親戚的にも私が死ぬまでは余程のことがない限り憑きなおさないと思われるので心底ほっとしているようだった。
__しかし、事態はある日簡単にそして急速に善い方向に好転しながら動いていく。
私はその日、その空の色に魅入ってしまった。
だって色を取り戻した瞬間に見たのがあの色だ。これ以上にないくらい綺麗だと心から思った。心を奪われるってこんな感覚なんだ。ざわざわ五月蝿すぎる心音は収まることを知らず鳴っている。
他の色なんてその時まで見たことはなかったから仕方ないかもしれない。と言いたいが、他の色をあとからどれだけ見てもやはりそれとは比較なんかできなくって。
「初めて見た色がそれだったなんて哀れね」
私が私に向けてそう零した。
___ああ、本当に。
◇◆
そう、その男は突然現れた。
中学からの帰り道、モノクロの世界をぼんやりと歩いていく。一色覚、いわゆる全色盲の私はその日とても憂鬱だった。
朝から靴下が色違いになっていたことをクラスメイトにからかわれた。
休み時間にわざとらしく「赤のそれとって」と色を指定して話しかけてくる奴がいた。彼はいつもそんな言い方をする。私のことを知っているなら、右のとか左のとかそういうので言ってほしい。というかまず自分で勝手に取れ。
きわめつけは給食の時間だ。今日はふりかけがついていた。今日のそれは個包装で配られなかった。給食室で手作りされたそのふりかけは小さなボールに入っていて、ご飯を持っていく時に給食係が掛けてくれる。私はその時間、委員会の用事があって教室にいなかったのだ。教室に戻ると既に配膳は済んでいた。「いただきます」と日直の言葉に合わせてボソリと呟く。ちらちらと隣の席から視線を感じる。隣の席の彼は毎日給食の献立を暗記しているようなやつだった。
ご飯をひと口食べた私は噎せる。横から笑い声がした。口の中が痛い。辛すぎて痛かった。何をかけられたのかはよく分からない。多分唐辛子とかそういったものを粉末にしたやつをふりかけに混ぜやがった。「ほら、残したらダメだろ?」と言ったそいつのご飯に私のご飯をぶっかけた。教室にみんなの笑い声が響く。
彼らは普段はそれなりに親切なのだが、年頃というか、自分にないものは分からないというかとにかく悪気はないらしい。自分がされたら嫌なことは人にしないなんて結局言葉だけである。その無自覚な悪意が1番腹立たしい。「怒るなよ、からかっただけじゃん」じゃない。あとから白ご飯の残りと少しだけ余ったふりかけをくれたが、されたことには変わりないのだ。
そんなわけで今日は本当に最悪な1日であった。途中まで帰ろうと言ってくれた子の言葉に「今日はごめんね」と言って1人で帰る。見慣れたモノクロの世界にいつもは何とも思わないのに今日に限っては腹立たしくて仕方がない。
「お前、それ何?」
「......?」
突然、知らない人に声をかけられた。振り向く。身長の高い男の人。私は首を傾げる。多分どこかの制服なのだろうが、何となく見慣れない服装をしていた。モノクロの世界に異様に黒く焼き付いた彼は目のあたりも黒い。多分サングラスを掛けている。髪は格好に対して白い。外人さんだろうか?
そんなことを考えながら彼を見上げる。そう云えば、何が「お前、それは何?」なのだろう。傾げていた首を戻して瞬きをする。
___それからたった数分後、私のモノクロの世界は初めて急速に色づき始めた。
そして彼の持つその"空の色"に心を鷲掴みにされるのだった。
◇◆
色のない目をした女がとぼとぼと歩いている。
任務で訪れた都会とは決していえない町に彼女はいた。
その町は紅葉が有名な所だった。任務終わりにたまたま歩いていたこの道の脇には綺麗に植えられた木があって、それは美しく色付いている。
__その世界の中で彼女だけが浮いていた。
思わず足を止めて通り過ぎていくセーラー服を着た女の子を視線で追いかける。
「なんだ、あれ?」
呪霊だ。呪霊がいる。しかもあれは1級?いや、特級か。
半透明の"それ"はニタニタと笑いながら、女の子の目を覆い隠してくっついている。彼女にはそれが見えていない。平然と何事もなく歩いていく。しかし、"視える"こっちからしたらそれは異常な光景だった。決して見過ごすことのできないものだった。アレを放っておくのはマズイ。視えるものなら素人だろうと誰だってそう思うのでは?と言えるくらいそれは異常だった。
「お前、それ何?」
「......?」
思わず声をかけてしまった。こんなのを見過ごして帰るだなんて、何だか後味が悪かったから。変に夢とかに出て来られても困るわけで。
その女の子は突然のことにビクリと肩を震わせる。そして振り返ると同時に首を傾げる。色の無い目が言っている。
なんだコイツ?
と。この五条悟を見てそんなふてぶてしい顔をするなんて。そんなことを思いながらムッとする。そして、幾分か年下だろう女の子をじっと見つめた。
「それ、祓ってやろうか?」
「それ?」
「お前の背中にくっついてるやつ」
「.....背中?...あ、疫病神のこと?」
何言ってるんだ、と言う表情をしていた彼女ははっと思い出したようにその言葉を発した。疫病神、つまり疾病を流行らせる神のことだ。まあ確かにこれくらいのやつが憑いていると災難に沢山遭いそうだし、あながち間違ってはないだろう。それにしても一応何かが憑いているという自覚はあるのか。
「ま、これくらいなら一瞬だな」
「え?」
そう言えば、呪霊がこちらに威嚇してくる。
なんだ。攻撃してくるかと思ったが、そいつは相変わらずこの女の子にひっついたままだ。これだけ近づいているのに珍しい。それにしても粘着質とはなんて薄気味悪い。彼女が酷く哀れである。
不思議そうにこちらを見上げる彼女にもう一歩近づくと、"それ"はやっと動き出した。一瞬で距離を開けると、「え?え?」と女の子は困惑した声を上げた。
突風が吹いて、大量の紅葉した葉が降り注ぐ。風でサングラスが飛ばされた。あー、サイアク。
「.....はあ、面倒だな」
ぽつり呟いた。
__あ、いけね。帳おろさないとまた怒られる。
ついこの間もそのことで説教を食らった。あー、でも面倒だしすぐ終わらせればいっか。
そう自己完結して攻撃を仕掛けた。
◇◆
「おい、終わったぞ」
「.....おわった?」
結局何も着いてこれていない彼女は、尻もちをついたまま固く目を閉じていた。それに憑く呪霊はもう居ない。
「.....ほら、いつまで座ってんだよ」
「.....ごめんなさい。.....__え?」
彼女の腕を引いて立ち上がらせようとする。慌てて足に力を入れた彼女は瞑っていた目を開いた。そして次の瞬間には何かに驚いたように声を上げた。
「.....っ、きれい」
「は?」
さっきまで半透明な呪霊越しだった瞳と目が合った。そして彼女はぽつり零した。
いや、急に何を言い出すんだよ?そう困惑しながらその瞳を見つめる。
「...っ」
キラキラ、ありえないくらい綺麗に光る瞳に思わず息を飲んだ。いつもは息を飲まれる側だというのに。思わず見蕩れてしまっていたのだ。
___あの呪霊が隠したくなるのも分かりたくはないが、分かる気もする。
「お前、名前は?」
「......」
「はあ...。俺、五条悟。で、名前は?」
「...苗字名前です」
まずは自分から名乗れ。彼女の表情がそう言ってる気がして、ため息混じりに名前を言った。すると彼女も名を呟いた。
「そ。...これからよろしく」
「これから?」
その瞳の輝きに囚われたら、もう逃がしてやるなんて無理だと思った。
(悟、中学生に手を出したんだって?)
(はあ!?何言ってんの傑!まだ出してねーし!)
(いや、"まだ"って言ってるけど)