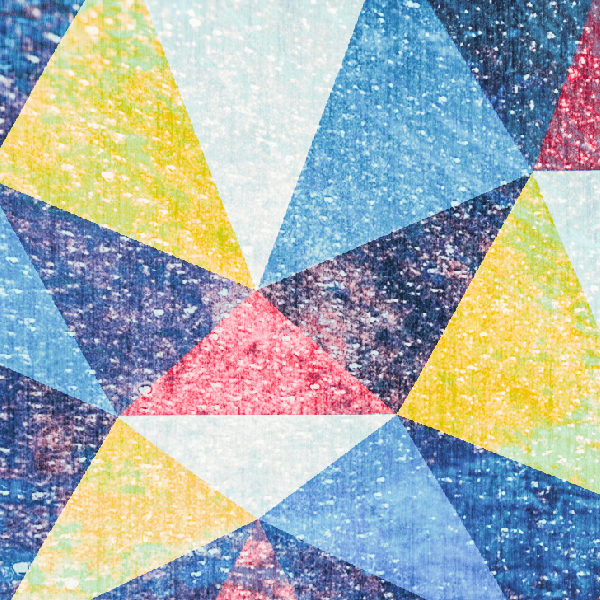
僕たちの愛、きっと三角
「おいしい...」
名前はショートケーキを頬張ると、そう言って頬を緩めた。フォークで一口一口を大事に大事に、丁寧に切り分けて口に運ぶ姿がなんだか面白い。
__買ってきてよかった。
つい食べる手を止めてその姿をじっと見つめてしまう。にこにこと上機嫌の彼女の口の端にはクリームが付いていて、なんだか子供っぽい。
ティッシュでそっと拭いてやると、ぱちぱちと瞬いた彼女はふわりと笑った。
「良かったね」
「うん。蛍くん、ありがとうね」
「いいよ。僕が食べたかっただけだし」
ふと食べたくなって買ってきたいちごのショートケーキ。自分が気に入っている店のそれは相変わらず美味しくて、幸福感と安心をもたらしてくれる。
名前も一緒だと更に至福を感じられて、今日はいつになく気分が良かった。
「"好きなもの"と"好きなもの"の組み合わせって本当に最高...」
しみじみとそう言った彼女の瞳がきらきらと宝石を閉じ込めたように光り輝いていた。それを見つめて思う。
名前は、ケーキが好きだ。あといちご。だからいちごのショートケーキはもっと好き。
僕はショートケーキが好きだ。そして、彼女のことも.....。
「そうだね」
彼女のそれに同意するように頷いた。イチゴをフォークに乗せた彼女がそれをぱくりと食べる。
__きらきら
効果音で言うならそんな感じ。1番幸せそうな表情を浮かべた彼女。それをちらりと見て、そして飲み物を飲む。
好きなものを見る時や食べる時のその表情は飽きない。
__でも、その表情が昔は苦手だった。
◇◆
僕がバレーをしているのを見る時、彼女は決まってその表情を浮かべる。
"たかが部活のバレー"。
そのバレーをしている時の自分をなぜ彼女はそんな風に見てくるのかが分からない。正直鬱陶しいと思ったこともあった。僕にそんなに期待したって、そんな感情をぶつけてきたって意味ないのに。
彼女は決して「がんばれ」とは言わなかった。
でも、「バレーをしている時の僕が好き」と言っていた。よく分からない。一生懸命になれない、ならない、自分のどこが良いのかさっぱり分からない。
「蛍くんはバレー好きだもんね」
彼女が当然のように言う。顔を顰める。何を言っているんだと。
そのきらきらとした瞳は飾りか何かか?
僕の眼鏡を一瞬だけでも掛けてやった方がいいのではないか?
割と本気でそんなことを思った。憎まれ口をたたいても気にしない彼女はただ笑う。
「いつか分かるよ。大丈夫」
そう言ってにっこりと笑う。
◇◆
「たしかに分かったかも」
「え、何が?」
「いや、何でもないよ」
先にショートケーキを食べ終えた僕は、まだまだ時間をかけてショートケーキを頬張る彼女をぼんやりと頬杖をついて見つめる。
あの日から随分時間が経った。バレーにハマったあの瞬間、彼女が多分1番喜んでいた、と思う。
「ね?」
そう言ってしたり顔で笑う彼女にムカついて、頬を引っ張ってみたら、そのあと随分と根に持たれた。
それを治したのは多分ショートケーキだ。
どうして彼女とショートケーキを食べることになったかはよく覚えていない。でも、2人でいま食べているこのショートケーキが売ってある店に行く機会があった。
2人して即決でショートケーキを選んで、イートインで食べて帰ったあの日。
__そして今日。
「またクリーム付いたけど」
「え?」
「はあ...」
彼女との関係は随分と変わった。
ただの同級生。同じ部活の選手とマネージャー。ちょっとムカつく奴。隣のクラス。気になる人。そして恋人。
近いようでちょっと遠かった僕らが、いつの間にか隣を歩くようになって、そして随分と経った今日も2人でショートケーキを食べている。
「あ、そっちか...」
「.....」
見当違いなところを触る彼女の顔についたクリームをまたティッシュでそっと拭いてやる。
ちょっとは大人っぽくなったと思ったのに、やっぱり根は子どもみたいだ。
「えへへ」
「何その顔」
「いやあ、幸せだなって」
「ふうん」
ようやくショートケーキを食べ終えた彼女が、フォークを置いた。にこにことこちらを見上げてくるから、そっと前髪を掻き分けて、そこにキスを落としてやる。
するとイチゴみたいに真っ赤になる彼女がいて、笑ってしまった。
「急にひどい」
「いまさら?」
心の準備というものがあってね!とか何とか言っている彼女。パニックになっているのかその言葉には脈絡がない。面白くなって、ついトドメを打ってやりたくなった。
「.....っ」
その口にキスを落とす。数秒ぽかんとした彼女はついにショートしたのか、「な、ななな」とよく分からない言葉を口から吐き出していた。
僕からは無意識に離れようとするその身体を追いかける。腕を伸ばせば簡単に捕まる距離にいた彼女を引き寄せてやると、彼女は顔を両手で押さえている。隙間から見える色はやっぱり真っ赤だ。
あーあ。これじゃあ彼女のきらきらとした瞳が見えない。
「.....」
「.....」
そっと彼女の耳に口元を近づけた。近づいてきたのが分かったのか彼女がビクッと震えた。
その反応が面白くて、つい意地悪したくなる。
「名前」
「な、なんでしょうか」
相変わらず顔を両手で覆ったままの彼女がモゴモゴと返事をした。そっと耳元で囁かれたせいで擽ったそうだ。
__"好きなもの"と"好きなもの"組み合わせって本当に最高。
そう言っていた先ほどの彼女の言葉を思い出す。何気ない休日に食べるショートケーキが好きだ。名前のことも好きだ。
それを組みあわせて感じられる今日のこの幸せは確かに最高だと思う。
「ねえ」
「.....うん」
「ショートケーキのお返し、ちゃんと頂戴」
(この幸せに形があるなら)
(きっとショートケーキの形だよ)