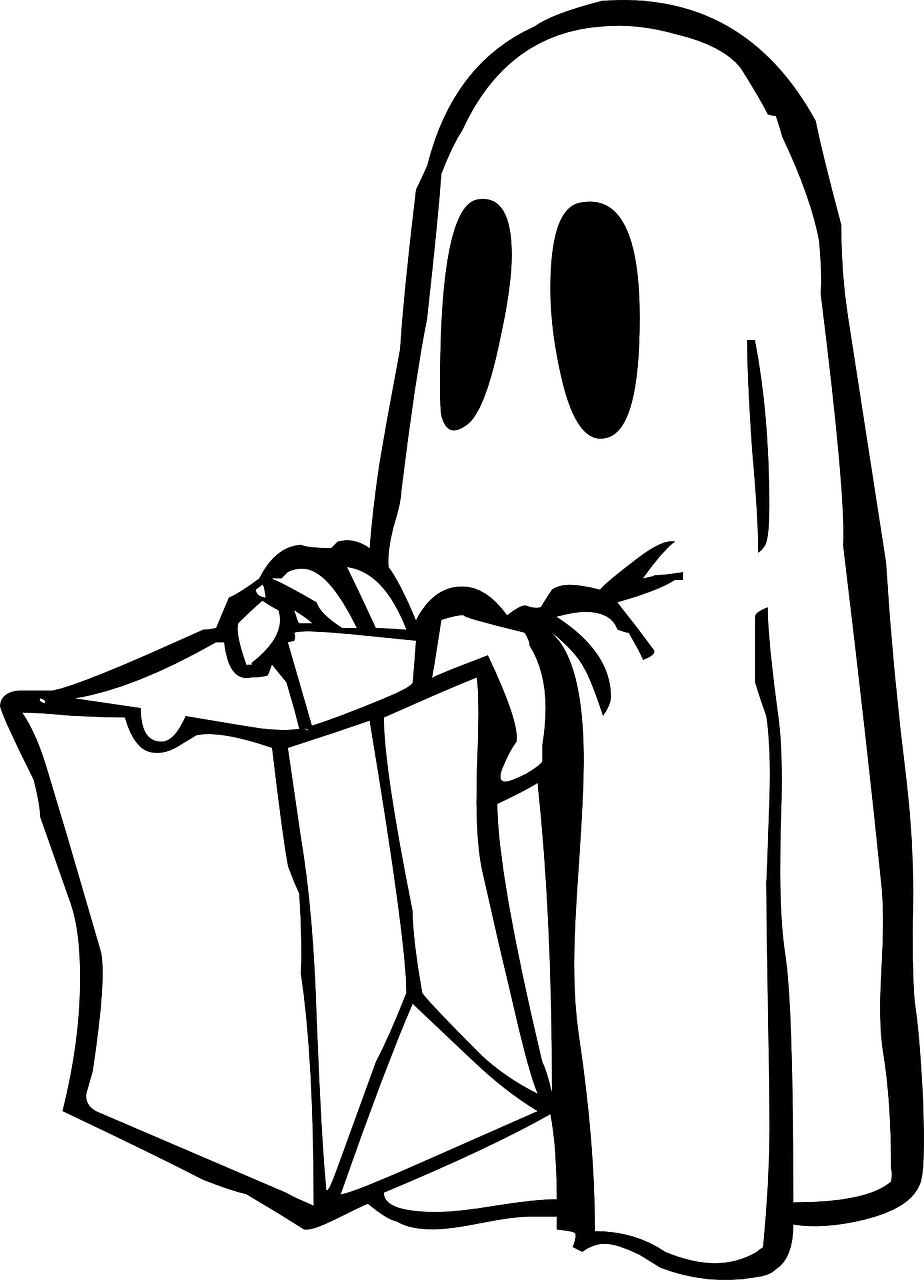
クザン
家具の少ない質素な部屋の中、クザンは間接照明の淡い光に照らされながら頬杖をついて酒を注いでいた。
「今日はまた随分呑んでるね」
「・・・・・・あらら、また見えちゃったよ」
知らぬ間に対面の椅子に人がいた。
と言っても、透けて向こうが見える彼の身体では影が出来ず、部屋には変わらずクザンの長い影だけが伸びる。
もうそんなに呑んだのか、とクザンは己の額に手を置いた。そう思えば、心なしか頭が重いような、違和感がないわけではない。
「まだ私のことお酒の幻覚だと思ってるんだ」
「そうじゃなけりゃなんだっていうのさ・・・・・・アパル、お前はもう死んだんだから」
ぽつりと小さく――そして苦々しく吐き出されたその言葉を、どうにか頭から引き剥がしたくてクザンはグラスを呷った。
「毎年毎年そう・・・・・・お酒飲んで、そうやって逃げる」
私が嘘ついたことあった? とアパルは首を傾げた。
生前と同じ長い黒髪が揺れて、照明を受けて艶を宿す。
肌は生気がなく真っ白で、身体だって透けているくせにそういうところは何故か人間のようだ。
たちが悪い、とまたグビッとクザンは喉を鳴らす。
「嘘なんてそりゃ山ほどついてたでしょうが。俺が遠征に出発する朝、体調悪いのに平気な振りして見送って、帰ってきたら入院してる、なんて何回あったことか」
「だって、本当に平気だと思ったんだもん。それに忙しい朝にそんなこと言われてもクザン困るでしょう?」
罰が悪そうに視線がそっぽを向いたが、すぐに小さく笑った顔で同意を求めてくる。
はあー、とクザンの口から長い息が漏れる。
「そんなことで困ってたらわざわざお前を家に呼ぶわけないでしょうが。言ってくれなきゃ逆に困る。何度おれの肝が冷えたか」
アパルは生まれつき身体が弱く、外をぶらつくことすら辛いような病弱さだ。
本人が一番、自分の身体の変化に顕著だろう。わかっていてこの男は隠していたのだ。毎回毎回。
家族や頼れる者を早くに亡くしたアパルを自宅に誘ったのはクザンだ。
迷惑をかけるからと拒むアパルを、あの手この手で説得して同居にこぎ着けた。
しかし、全くクザンに頼ろうともしないのだから頭が痛かった。
遠征から帰ってきて報告をしていれば、クザンがアパルの身元引受人になっていることを知っているセンゴクから、アパルの病状を聞かされる。
その足で病院に向かえば、いつだって真っ白な部屋の真っ白なベッドに横たわる美しい男がいて、クザンは安堵感にずるずると腰を下ろすのだ。
――ごめんなさい。大丈夫だって言ったんだけど・・・・・・。
なのに当人は家で出迎えられなかったことを悔やんでいて、やるせない思いになった。
「言っとくけど、サンちゃんがいなければ危ない場面は山ほどあったんだからね?」
「うん・・・・・・あ、サンちゃん元気にしてる?」
しょぼんとした様子で頷いたアパルは、パッと顔を明るくして少女の今を問う。
サンちゃん――サイラとは当時十五の少女で、クザンが連れてきた家政婦、というよりはアパルの世話役のようなものだ。
母を亡くし、小さな弟を食べさせるために働き口を探していたが子供を雇ってくれるところもなく途方に暮れていたのを、クザンが声をかけた。
愛嬌のある可愛らしい少女で、アパルにもクザンにもよく懐いていた。
とくにアパルには病弱だった母を重ねてか、随分と献身的になってくれたものだ。
「この前二人目が生まれたってハガキがきたよ」
ほら、とテーブルの隅に置かれた一枚のハガキをアパルに差し出す。
すぐ手に取れる位置にわざわざ置いていたことに気づいたが、アパルはそこには触れずにハガキに目を落とす。
赤ん坊を抱えた女性と、その女性の隣で小さな子供を肩車する男性。幸せそうに笑った親子の写真だ。
「・・・・・・大きくなったね」
「あれから約二十年・・・・・・あの子も大人になったんだよ」
「そうだよね」
当時まだ幼さの残っていた少女だって、三十半ばの大人の女性になるほどの期間。サイラはもうアパルの年をとっくに追い越してしまっている。
成長を喜びつつも、寂しさの影がうつるアパルの笑みに、思わずクザンが腕を伸ばした。
スッとアパルの頬を通り抜けた己の指をグッと握りしめて戻し、クザンは再びグラスを呷る。
「そろそろ呑むの止めれば? 明日も仕事でしょう?」
翌日まで酒が残るようなことはないだろうが、心配になる。
一緒に住んでいた頃は、酒を飲んでいるところなどほとんど見たことがないから余計に。
(まあ、私に気を遣って呑まなかったのは分かってるんだけど・・・・・・)
アパルが酒が飲めないからなのか、それともいつ容態が急変しても病院に向かえるようになのかはわからないが、アパルのためだというのはよく理解していた。
「溺れるようなことはしないさ。でも、素面じゃお前と話せる気がしねぇのよ・・・・・・もう二十年経つって言うのに、未だにお前の顔をちゃんと見れないんだからね、こっちは」
今でこそ冷静に喋っているように見えるが、初めての年のハロウィンなんて最悪だった。
あの時はたまたま酒が入っていて、幻覚だと思って触れないアパルを抱きしめて泣いて、寝かしつけられて。
夢に見ることは多々あったが幻覚見るのなんてこの日だけ。
本当は分かってるが、幻覚だと言わないと当初の自分の醜態が恥ずかしすぎる。
せっかく料理を筆頭に家事をこなしてテキパキ世話をして培った頼れる男の称号が、無残に消えてしまった。
「・・・・・・そんなにショックだった? 私が死んだの。言っちゃうとあれだけど私は自分が長生きできるとは思ってなかったよ?」
「そりゃヨボヨボのじいちゃんになるまでとは俺だって思ってなかったよ。でもね〜・・・・・・」
人というのは慣れる生き物だ。
はっきり言えば油断していたのだ。いつだって病室に駆けつけ、それでも弱ったアパルが笑みで出迎えてくれて。
どこかで覚悟はしつつも、どこかで楽観していた。
だからこそ、いつも通りに行かなかったあの日がやけに目の奥に焼き付いてる。
遠征から帰宅して、クザンが報告に行く前にセンゴクの方から出向いた所から嫌な予感がしていた。
走って駆けつければ馴染みの看護師がクザンを見て動揺を示し、普段とは違う方向に誘導する。
向かわされたのは霊安室で、そこにはすでに冷たくなったアパルがいた。
軍にいれば人なんて簡単に死ぬとよく分かってる。
でも、想いを向ける人間が死んで、そう割り切れるほど若いクザンは出来た人間ではなかった。
「・・・・・・なんで外に出たりしたのさ。雪が降ってたのわかってたでしょうに」
そんな寒い中で、アパルが平気でいられる訳がないのだ。
何度かあったことだ。
雪が見たいからと縁側に腰掛けて少しだけ外を眺める。
サイラも渋い顔をしたが、少しだけならといつもと同じように対応した。
しかし、いつものように無事ではいられなかった。
暖かいお茶を取ってくるとサイラが傍を離れたうちに発作を起こし、アパルは雪の中に倒れ込んでしまった。
数分も経たずに戻ってきたサイラは、吐血して赤く染まった雪に沈むアパルを見つけ、すぐに救急に連絡を入れたが間に合わなかった。
真っ赤に腫らした目の少女が、クザンに抱きついて泣きじゃくりながら教えてくれたことだ。
ごめんなさい、と泣く少女の頭を撫でて慰めてやることしかクザンは出来なかった。
自分だって感情が追いついていなかったのだから。
「よく雪が降ってると見たがったでしょう? なんでなのかって聞いたことなかったなって思ってさ」
カラン、と氷が溶けて音を立ててグラスの中で揺れた。
「クザンみたいだったから、かな」
「おれ?」
想像とは違う答えに、ついきょとりと目を合わせてしまった。
やっと目が合ったことを内心で喜びながら、アパルはグラスをもつクザンの手に己のものを重ねる。
ビクリと一瞬だけクザンは驚いたが、引くことはせずにそのまま触れ合わせてくれた。
「クザンて、能力のせいか冷たいでしょう? だからかな・・・・・・なんか空気が冷たいとクザンのこと思い出しちゃって」
それに雪って白いし、と付け加えられ、「俺が白いのは軍服でしょうが」と力なく返した。
クザンは項垂れるように頭を落とし、「なんだそれ」とため息と共に声を零す。
(俺みたいだから見ていたかったってこと? 俺を思い出すから?)
ぐるぐると制御できない感情が身体を巡る。アルコールのせいなのか顔に熱が昇った。
クザンだって男なので、意中の人物にそんなことを言われれば簡単に舞い上がる。
「そういうね、期待させるようなこと言うんじゃないよ。明日の俺が使い物にならなくなるでしょうが。言っとくけど、お前が死んで結構参ってたのよ? おれ」
「うん」
「あのサカズキやガープさんにだって気つかわれるぐらいだったんだからね?」
「うん。見てたから知ってる・・・・・・あ、私ちゃんとクザンにそういう風に好かれてたんだって思って、ちょっと後悔した」
見てたのか・・・・・・と頭を抱えるクザンだが、その後に続いた後悔という言葉にハッとアパルを見やる。
「二十年経っても相変わらずだし、結婚も、ましてや恋人だっ出来ないし、だから・・・・・・もう言っちゃうけど」
アパルはそこで言葉を切ってキョロキョロと視線を彷徨わせた。
両手はテーブルの上で組まれ、細い指が落ち着きなく動いていた。
「後悔したの・・・・・・好きだって、ちゃんと言っておけばよかったって」
「す、き?」
「クザンは優しいからこんな私を放っておけなかったんだろうなって納得させて。私の方が早く死ぬだろうしこんな気持ち押しつけちゃダメだって思って」
「いや、え、え?」
アパルからもたらされた言葉が上手く咀嚼で出来ずにクザンは混乱をきたした。
(やっぱりこれ幻覚か)と半ば諦めまでいったところでどうにか正気に戻る。
「え、まじ・・・・・・?」
「マジです」
キリッと真面目な顔で反復されて、うわ〜とクザンは顔を覆った。じわじわと身体が熱くなって実感が伴う。
「おまっ・・・・・・えッ、なんでそんな簡単に言えるの。俺なんか家に住ませておいてそのまま結局言えなかったのに」
「簡単じゃないよ。二十年、ずっと言いたくて我慢してたんだもん。いつかクザンには恋人とか奥さんとか出来るだろうしって」
「出来るわけないでしょうが・・・・・・俺って結構一途よ?」
「うん。知ってる」
この二十年、しっかり見てきたから。
照れくさそうに、しかし嬉しさを滲ませてはにかむアパルに、クザンは身のうちに湧き上がる感情を隠すように俯いてしまう。
「・・・・・泣いてる?」
身を乗り出してアパルが覗き込むように声をかければ、
「いや、なんでよ?」
と、くぐもったクザンの声が答える。
「ううん。だって・・・・・・」
――だって、あの時と同じだったから。
家で倒れたり、体調を崩して気づけば病院だなんてアパルにとってはよくあることだった。
薄れる意識の中で、ああ、またクザンに迷惑かけちゃうな・・・・・・と思うのは毎回のことで、それでも家を出て行くと言えなかったのは単にアパルがクザンの傍にいたかったからに他ならない。
病室の薄暗い天井を見て、ゆっくりと首を傾けると、いつもベッド脇にクザンが大きな身体を丸めて座っていた。
電気も付けず、アパルの手を己の大きな両手で包んで、祈るような姿勢で俯く。
その瞬間に湧き上がる感情を純粋に愛と称してよいのか、自分でも戸惑うほどだった。
だって迷惑をかけて喜ぶだなんて、アパルにとっては信じられないことだから。
(あの時の同じような気がしたんだよね・・・・・・)
必死に何かを押し殺しているような。そんな雰囲気。
「だって・・・・・・? どうしたのさ?」
「ううん。なんでもない・・・・・・ねぇ顔を見せてよ」
「いや〜今は無理じゃない? おれ相当かっこ悪い顔してるから」
「でも見たい」
「ダメだって」
組んだ指で隠すように俯くクザンは一向に顔を見せてくれない。ムッとしたアパルは一度乗り出していた身を引く。
「ん、ゴホッ、ゲホッ」
「ッ、アパル!」
コンコンと咳き込むような音を出せば、クザンは拍子抜けするほど簡単に身体を椅子から立ちあがらせた。
それを待っていたアパルは、クザンが顔を上げた瞬間を狙ってその頬を両手で包み、そっと顔を寄せる。
クザンの気怠げな瞳が見開くさまを見送り、静かに目を閉じた。
数秒、そんな短い時間の触れあい。
互いに視覚以外に触れたという認識を感じることも出来ない、そんな寂しいキス。
それでも、二人にとって初めての触れあいだった。
「・・・・・・好きだって言ってたら、キスぐらい出来たかな。クザンは唇も冷たそうだね」
呆けたクザンは答えない。
天下の海軍大将が隙だらけで、アパルはつい「ふふ」と笑みを零す。
病弱故か、それとも本人の気質故か、アパルは控えめに笑うことが多かった。
――おかえりなさい、クザン。
出迎えるために、クザンの退勤時間になればベッドからおきて廊下で待っていたことをクザンは知っていた。
玄関の音が聞こえてからだと、アパルの足では間に合わないから。
それに対して「ただいま」と返しつつも、寒いんだから寝てなさいよと苦言を呈し、その細い身体を抱えてベッドに連れて行く。
けれど、内心ではクザンはその瞬間が嬉しかった。
長く細い黒髪がサラサラと白い頬を滑っていき、クザンを見つけると柔らかく笑む瞳が、僅かに熱をのせる頬が。
アパルがいなくなって真っ暗な玄関口に立ったとき、自分がどれだけ心を救われていたのかを知った。
「あ、もう時間みたい」
もうすぐ日付の変わる時計に気づき、アパルが声を上げた。
それに慌てたのはクザンだ。
つい腕を掴もうとしてその手は空を切った。
内心で舌打ちをしつつ、透けるアパルの身体に詰め寄るようにクザンは身を乗り出す。
「アパルっ! 俺が行くまで、もうちょっと待っててくんない」
「・・・・・・うん。ずっと待ってる。だから長生きしてね」
「あーまあこの仕事してりゃいつ死ぬかわかんないけど、努力はするか」
「うん。そうして」
アパルの身体に光が立ち上る。もうすぐ時間が来る。
そこでクザンは、己がはっきりとした言葉を口にしていないことに気づいた。
「あー、アパル」
「うん?」
「ちゃんと言ってなかったけどよ、俺はお前に惚れてちゃってんのよ。自分でも引くぐらいに」
なんせ出会って数年で同居を申し出るぐらいなので。
「ふふ、自分で言うの?」
「やばい奴だって自覚がないよりあった方が良くない?」
「確かにね」
クザン自身、客観的に見ても海軍所属という肩書きがなければめちゃくちゃ怪しかったことぐらいは理解している。
なんせたまたま訪れた病院で一目惚れして健気に通ってしまうぐらいなのだから。
「もう三十年ぐらい惚れてんのよ。おれ結構重いからさ、俺が死ぬまでに覚悟だけ決めといてよ」
「二十年化けて出る私にそういうこと言う?」
どっちもどっちだと思うよ。
と、ふわりと笑うアパルに、クザンは己の身を屈めてその小さな口を覆う。
それでも、どうしたって感じることの出来ない熱に、不満げに顔をしかめた。
「ふふ、ひどい顔」
「そりゃ、こういう顔にもなるでしょ」
「幽霊同士ならもしかしたら出来るかもね」
「あと何年お預けなのよ、それ」
げっそりした顔で言えば、これまたクスクスとアパルが笑う。
それで長生きしろ、なんて言うんだからひどい男だ。
「クザン」
「ん?」
「浮気しちゃダメだからね」
カチッと時計の針が真上を指す。パッとシャボン玉が弾けるように光の粒となってアパルが消えた。
照明の光に照らされる一人の室内に戻り、クザンは気が抜けたようにドカリと椅子に腰掛けた。
「三十年惚れてんだよ。今更目移り出来るわけないでしょうが」
グラスに入っていた氷は全て溶けて、残されていた少量の酒が随分と色を薄くしている。
それをぐいっと一度で呷ったクザンは、「あ〜〜」と盛大に唸りながら顔を覆った。
「ガキじゃあるまいし、今更キスの一つや二つでなんで俺は・・・・・・」
十代のガキだってキスしたぐらいでこんな真っ赤にはならないだろう。
しかも、はっきりと触れたわけでもないのに。
ほんと叶わねぇよ、とほとほと困った顔でクザンは残った瓶の酒をそのまま呷り、生ぬるさに眉をひそめながら寝室に向かった。
(おやァ? クザン珍しくご機嫌そうだねぇ〜いつもこの日は青白い顔してるのに)
(俺がどんな顔色しててもいいでしょうが)
(なんだいわっしらが心配してやってんのに失礼なやつだねェ〜)
(まあ、なに? ちょっと嬉しいことがあったのよ、昨日ね)
(へぇ良かったじゃないかい。何があったんだい?)
(それがね、・・・・・・って言うわけないでしょうが)
(つれない奴だね。サカズキとの笑い話にしようと思ってたのに)
(なんじゃクザン! 今日は随分元気そうじゃの!)
(あ、ガープさん)
(わはは! 煎餅やろう!)