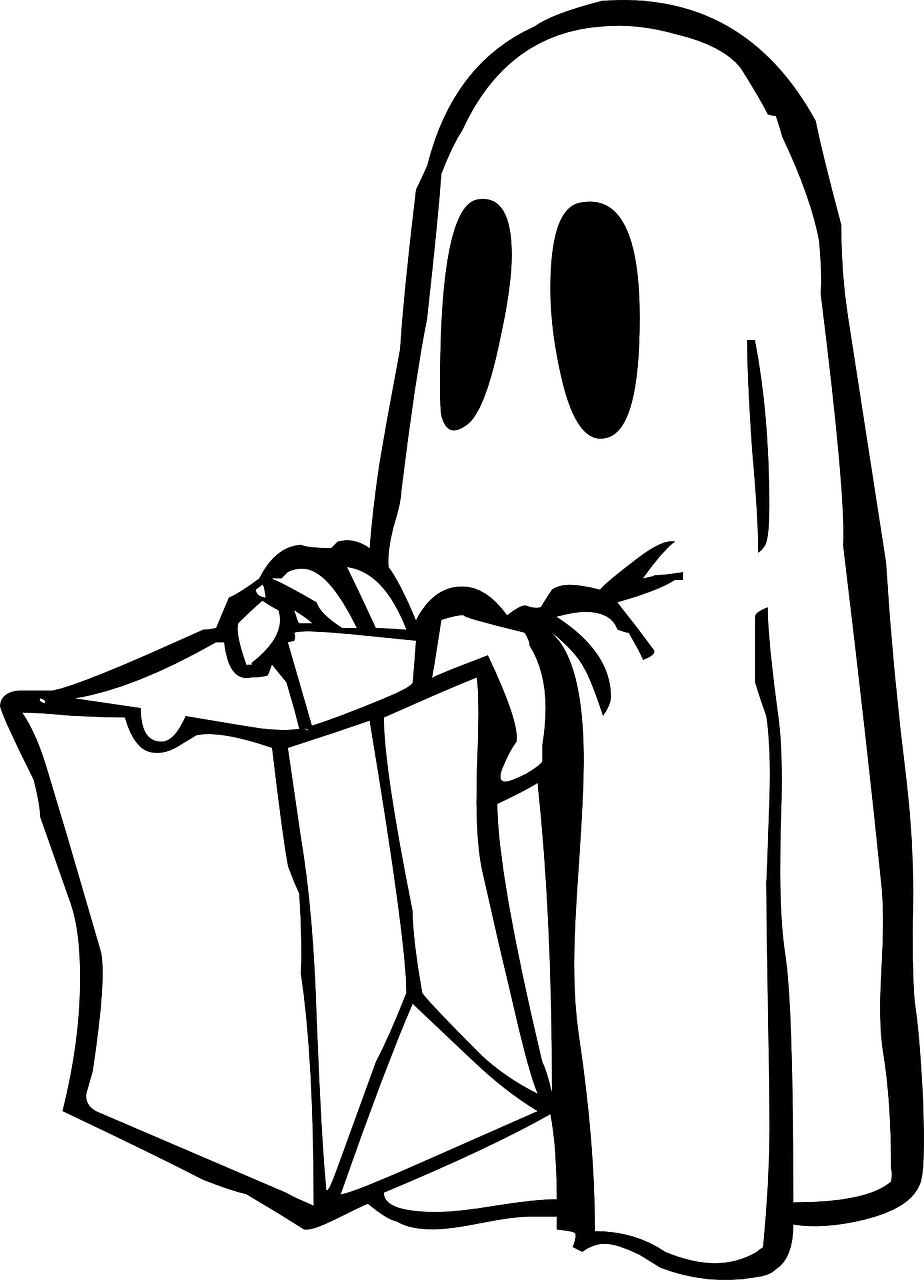
イゾウ
今日のモビー・ディック号は静かなものだ。
島について初日は、船番や留守番の隊以外はほとんど外に出ている。しかも、夜半頃とあっては夜の見張り番以外は寝ているせいか、甲板にいるのはイゾウだけだ。
今、立ち寄っているのは春島だが、やはり十月とあっては夜は冷える。
陽が沈む頃からこの甲板で飲み始めたので結構長い時間外の空気にさらされている。冷えた身体を温めようと、イゾウは手元のお猪口を呷る。
くいっと傾ければ、熱い酒が喉を下っていった。
(こんなんじゃ夜明けまでいそうだな)
日付が変わってしまえば諦められるだろうが、今のイゾウは時計を手元に置いていない。
そうなると、陽が出るまでは(まだ日が変わっていないんじゃないか・・・・・・)とたらたら言い訳を述べて居座りそうだ。
寒い中、しかも外で一晩中酒を呷っていたなんて知られたら怒られそうだ。
脳裏に思い出した男の姿に、ふっと思わず笑みがこぼれてしまった。
(怒るためにでもいい・・・・・・化けて出てきてくれないもんか・・・・・・)
今、目前に広がるような暖かで平和な春島で出会った男だった。
己の暮らす島を表すような、穏やかで柔らかな雰囲気を持つ美しい青年で、人を疑うことを知らぬ者だった。
海賊だと知りながら、店を訪れたイゾウにも怖がる素振りもなく普通に接客をするような。
見るからに荒くれ者とわかる他船の海賊にだって、「落とし物ですよ」と朗らかに親切心を出す姿には、イゾウも頭を抱えたくなった。ある意味恐ろしい人物だ。
(怒った姿、結局一回も見てないな・・・・・・)
あの島には馴染みの蔵人がいて、その人の作る酒をオヤジも船員たちも気に入ってるので、年に二回程度は定期的に訪れていた。
二十年近く付き合いはあったが、よく考えたら会えた回数はさほど多くないのか、と今更ながらにイゾウは思う。
「もう、日付変わっちまったかな・・・・・・」
徳利を傾けてみたが、どうやらもうこの一口で終わりらしい。お猪口の半分程度でポタポタと流れが途切れてしまった。
思ったより飲みきるのが早い。
(ハロウィンの噂なんて、所詮、迷信だったか・・・・・・)
これを飲んだら部屋にでも戻ろうか、と思いつつ一口でお猪口を空にしたくせに、イゾウは立ち上がれそうになかった。
身体の芯を下っていった酒の熱さが落ち着き、肌寒さが蘇った頃、ふいに男の声が届いた。
「月見酒ですか?」
ハッと、小さく息が詰まった。
聞き覚えのあるその声に、ふるりと鳥肌が立つ。そちらに目を向けたいのをぐっと堪えてイゾウは平素のように声を出す。
「酒はもう空になっちまってな。人を待ってるんだ」
「船の甲板で?」
「ああ」
そこで、イゾウを暖かな光が照らす。
ちらりと目を向ければ、その人物の片手に小さなランプが握られていた。
「こんな遅い時間に待ち合わせですか?」
「ああ。夜じゃないと会えないらしい。いつ来るのかはわからないからこんな時間まで待っちまったよ」
「その人は来たんですか?」
「優しい奴なんだ。寒い中じっと待つ姿でも見せりゃ観念して出てきてくれるだろうと思ったがその通りだったな」
ゆるりとイゾウが頭を上げる。
そこには、ランプ片手に黒いマントを揺らす橙色のカボチャ頭がいた。
「確かジャクランタンだったか?」
「残念。ジャック・オー・ランタンです」
「ほとんど正解だろう? 死者の魂が悪魔やら異形の形で出てくるってのは本当だったんだな」
異形の姿をしているのに、あまりに不釣り合いなもの柔らかな声に本当にアパルなのだとイゾウは衝撃を受ける。
まさか本当に再び言葉を交わせるとは思っていなかったのだから。
「せっかくなら顔が見たかったが・・・・・・霊ってのはその姿じゃないといけないのか?」
眼前のジャック・オー・ランタン――もといアパルは、僅かな動揺を見せた。
言葉を詰まらせるようなその仕草に、イゾウはもしや・・・・・・と素直に疑問を口に出す。
「もしかして元の姿になれるんじゃねぇのか?」
「それは・・・・・・」
「せっかくなら顔が見たいんだけどな」
請うような言葉でもまだ戸惑う様子を見せるアパルに、イゾウはある想いを口にする。
「それとも、もう俺に顔も見せたくないか?」
「そんなことは・・・・・・!」
遮るように答えたアパルに驚いてイゾウが見上げると、覚悟を決めたようにアパルが息を詰めた。
マントやカボチャ頭がスルスルと糸が解けるように光となって消え、その下に隠されていた美しいかんばせが露わになる。
「・・・・・・どうして、私のことなんて待ってるの?」
月光の淡い輝きでも分かるほどに長い睫毛が白い頬に影を落とし、泣き出すように震えた。
「こんなに冷たくなって・・・・・・」
「ここより寒い島なんざいくらでも知ってる。一年近く待ったんだ。お前に会えるかもしれない数時間なんて待つ内にも入らないさ」
透けた細い指がイゾウの頬を撫でるので、その手を引き留めて掌に唇を押し当てた。
触れている感覚はあるのに、それはひどく曖昧で頭が混乱する。
確かに目には見えているのに、触覚だけに頼ると簡単に見失ってしまいそうなほどだ。
「私、死んだんだよ? 聞いてないの?」
「いや。島に着いてすぐに知ったさ。冷たくなったお前にも触れた」
「じゃあ、どうして」
今でも指先に蘇るアパルの冷ややかな身体の感触。
死んだことは十分に理解している。葬式にだって出て、滞在中は毎日のように墓にも通った。
それでもなお、その相手を待ち続けた理由なんて簡単だ。
「お前に会いたかったからさ。ただそれだけだ」
「私、会うつもりなかったんだよ」
「だろうな。お前は優しい奴だからゴチャゴチャ余計なこと考えてそうだ」
だから俺はこうして一人月見酒でもしてたのさ、とカラリと笑ったイゾウを、アパルはムッと拗ねたような表情で見る。
事実、アパルはイゾウがこんなあからさまにアパルを待たなければ姿は見せなかった。
見透かされていた恥ずかしさと、そうまでして己に会いたいと願ってくれた嬉しさで、どう反応していいのか困る。
死人である自分が、イゾウのことを縛るようなことはしたくなかったのに。
「なあ、アパル。俺を恨んじゃいないのか?」
「え、どうして?」
「お前が死んだのは、俺のせいみたいなもんだろ」
あまりにも素っ頓狂なことを言うイゾウに、アパルはさっきまでの複雑な思いも彼方に飛ばして目をしばたたかせた。
だって、アパルが死んだこととイゾウは全くの無関係だからだ。
アパルは、ある春島で雑貨屋を営んでいた。
様々な商品を並べていたが、その中でも特にアパルが力を入れていたのは化粧品などの美容関係の品だった。
アパル自身、髪の手入れや化粧を好むため、趣味の延長で商船から色んな化粧品を揃えては島の女性たちと感想を交わしていた。
しかし、際立った容姿のせいで海賊が停泊している時は頻繁に目を付けられ、何度か危ない目にも遭っていたため、女性たちからは化粧をするのは店の中の接客時だけにしな、と忠告されていたのだ。
そんな中で店を訪れたのがイゾウだった。
同じ男性でありながら化粧品に興味を持ち、あれこれ聞いてくれるのは楽しかった。
プライベートでたまたま顔を合わせたとき、不思議そうに化粧はしていないんだなと問われ事情を話せば、自分と一緒にいるときはすりゃいい、とイゾウは笑ってくれた。
そうしてイゾウが島に立ち寄ったときは、イゾウがアパルを誘って街に繰り出すのが恒例になっていた。
普段はイゾウがアパルの店に寄るのだが、あの日はたまたま事前に手紙が届いていたのだ。
ある島特有の花から採取できる珍しい香油をたまたま手に入れられた。近くの海域にいるため、そう経たずに着く、と。
ちょうど店の定休日だったので、たまには出迎えに行こうかなと思いついたのだ。
その日は商船も他の海賊船もなく、港は静かなものだった。
さほど大きな島でもないので、こういった日の方が多い。
遠目に漁の船が浮かぶ海面をぼんやり眺めていたアパル。近くでは子供たちが遊んでいた。
早く来すぎたかな、と思っていればドボンと大きな水音がアパルの耳に届く。
ハッと振り向けばさっきまで遊んでいた子供たちが数名、堤防から身を乗り出して海を覗き込んでいる。それだけで察したアパルが走って子供たちの元へと向かえば、案の定少し離れた所で子供が一人溺れていた。
他の子供たちに大人を呼んでくるように頼み、自分は海に飛び込んだ。
確か腕の中の子供が引き上げられるところまでは覚えいるのだが、そこで意識は途切れている。
そのあと死んだのだと思う。
(あの男の子、気にしてなきゃいいけれど・・・・・・)
それなりに成長した子だったので、アパルが死んだことは大きくなっても記憶に残っているかもしれない。
(私がもっと大きくて力もあったら余裕だったかもしれないけど・・・・・・この通りだからなぁ)
イゾウに比べてひょろすぎる腕を見てアパルは肩を落とす。
そうして、ふわりと浮くような軽さで身を屈めてイゾウの隣に腰を下ろした。
「イゾウのせいってことはないよね? むしろイゾウは関係ないんじゃ・・・・・・?」
「それはそれでなんか気になる言い方だが・・・・・・でも、いつも通り俺が何も言わずに店に行ってたらお前は港には来なかっただろう?」
ふむ、とアパルは抱えた膝に顎を乗せて考える。
(イゾウは、自分が手紙を出したせいで私が港に行ってそのせいで事故にあったと思ってる?)
――それは、なんだか・・・・・・
「それは違うんじゃないかな・・・・・・」
「そうか?」
「うん。だって迎えに行こうって思ったのも私だし、海に飛び込んだのも私だし・・・・・・別にイゾウが迎えに来てくれ、とも海に飛び込めって言ったわけでもないよね?」
心底不思議そうな様子のアパルに、イゾウの方が拍子抜けしてしまうほどだ。
「そんなこと一年近く気にしてた?」
「毎日な・・・・・・お前に手紙を書いてた夜になると、落ち着かなくなる。部屋で一人でいると机を見てぼんやり、あの時手紙なんざ書かなければ今もお前はあの島で生きてたんじゃないのかって暴れ出したいような気持ちになるさ」
「じゃあ、もう気にしないで。誰もイゾウのせいだなんて思ってないもん。イゾウ以外は」
潮風で僅かに乱れていたイゾウの黒い髪を、アパルは繊細な手つきで耳にかけた。
「そう簡単に割り切れないだろ。惚れた相手が自分がきっかけで死んだようなもんだ。いくら自分を責めたって足りねぇさ」
イゾウの頬の輪郭を撫でていた白い指がピタリと動きを止めた。
パチリと大きく音が聞こえてきそうなほどに、アパルの瞳が見開かれて瞬く。
放心したように開いた薄い唇。瞳が一瞬考えるように下を向いて、すぐにまた昇ってきた。
そして、イゾウと視線が交われば幽霊なのに僅かに頬が赤らんだ。
「え、えっ・・・・・・なに言って」
「お前も同じ気持ちだと思ってたんだが・・・・・・違うか?」
「いや、えっ、だって急に・・・・・・言われても」
肩を竦めて逃げようと身を引くアパルを、イゾウが身を乗り出して追いかける。
甲板の上できゅっと丸まっていたアパルの透けた手に、イゾウは己のものを重ねて引き留めれば、想像したように透過することはなく、微かな感触が伝わった。
「あっ」
「おっと」
背中から倒れそうになったアパルを慌てて支える。
そうすれば、二人の身体がピタリと触れ合う。それなのに鼓動が絡まることはなくて、熱が交わることもない。
「ねぇ、イゾウ・・・・・・私、もう死んでるんだよ」
「ああ、知ってる」
「だったら、なんで」
イゾウの肩に触れた両手で距離を取ろうとするが、背中に回った彼の存外たくましい腕がそうはさせてくれない。
「一年だ」
囁かれた声は、低く小さく――しかしどこまでも意志が通っていた。
「イゾウ・・・・・・?」
ゆるりとアパルが顔を上げた先、少し背を伸ばしただけで触れ合うような距離にイゾウはいた。
何か耐えるように力がこもって皺の寄った眉。
刻むように一心に見下ろしてくる瞳。
それに囚われた瞬間、アパルが吐き出そうとしていた言葉は消えた。
「一年、よく考えた。罪悪感とかそういうんじゃなく、ただお前が恋しかった。本当かどうかわからないハロウィンの噂に縋るぐらいにはな」
「でも、これから長いんだもん。その内きっと忘れられるよ」
じっとその瞳を見返すことが出来ず、ついアパルは目をそらしてしまう。
そうしないと、今にも目の前の身体に腕を伸ばしてしまいそうだった。
「ははっ、海賊なんていつ死ぬかわからねぇもんだろ? そんなあるかわからない未来を見て今伝えられる言葉を逃したくない」
アパルの髪をすくい、イゾウがそれを優しく耳にかけた。
生前はさらりと細い絹のような黒髪がイゾウの肌を撫でたものだが、今じゃ川の水を掴むような不確かな感覚しかない。
「言えずに会えなくなっちまった。でも奇跡的にこうして話が出来てる。今度こそ伝えたいんだ」
「今度こそ・・・・・・」
「ああ。あの時、言えなかったからな」
そう言ってイゾウは懐から小瓶を取り出した。コトリと甲板の上に置く。
「渡したかった香油だ。あの島じゃ恋人に送るのが流行で、互いに付け合って同じ香りを纏うんだそうだ」
「同じ、香りを・・・・・・?」
「ああ・・・・・・アパル、俺はお前に同じ香りを身につけて欲しかった。ただの男のくだらない独占欲さ」
器用に片手で蓋を開け、ぽたりと一滴垂らした香油をアパルの手首にゆっくりと塗り込む。
「あっ・・・・・・いい香り・・・・・・」
すっと鼻を通る甘さはくどくなく、すっきりとした爽快感も含まれる。強すぎない香りはアパルの好みのものだ。
ほっと肩を落としリラックスした様子のアパルに、イゾウも嬉しそうに笑む。
「お前の好きな香りだと思ってな・・・・・・それでついでにさっきの話も聞いたんで、いい機会だと思ったんだ」
とっくに香油は肌に馴染んでしまったのに、イゾウは薄いアパルの手首を撫でながら紡ぐ。
「俺に、この香りを纏っておく権利をくれ。俺が死んだら、この香りを辿って迎えに来て欲しい」
ほら、と香油の瓶を手渡された。
両手に収まるその瓶を、アパルは戸惑うよう見下ろした。
――互いに付け合って同じ香りを纏うんだそうだ
(私が、つける・・・・・・)
すでに死んだアパルが、まだ生者であるイゾウを縛るような真似をしていいのだろうか。
ないはずの鼓動が、アパルの胸で聞こえる気がした。
喉が渇くことなんてないのに、緊張で喉が張り付くようだ。
「私、もう死んでて」
「ああ」
「もうイゾウには会えないんだなって思って」
「ああ」
「それが、それが寂しかった」
両親は幼い頃に死んで、残された店だけが居場所だった。
街の人と仲は良かったけれど、みんな家族がいて、帰る場所があって、アパルだけがどこか浮いていた。
イゾウは島の人ではないから、どこか一緒にいて楽だった。家を持たない海賊だったのも安心した要素の一つだったかもしれない。
頼れる人もいなくて、海賊に絡まれたって島の人は家族がいるからそっちを守るので手一杯だし、自分だけでどうにかしないといけなかった。
おかげで変な誘いを断るのだけ上手くなって、外に出なくなって、やっぱりお店だけが居場所で。
――大丈夫だ。俺が一緒にいるときは好きにすればいい。
だから、イゾウが連れ出してくれる時間が、なんの心配もしなくて良くて、ほっと地に足が着いたような心地で誰かに寄りかかれる唯一だった。
「私、ずっとイゾウに甘えてばかりだったよね」
「そんなことはねぇさ。俺だって、お前に甘えてばっかりだっただろう」
誰かの家に上がり込んで楽にして、船の上じゃ絶対に味わえない平穏を知った。
モビーがイゾウにとっての家族で家だったが、アパルの家に上がり込むとどこか違う世界で平和を享受しているような安らぎを感じられた。
海賊稼業に不満はないが、イゾウにとってはアパルの二人での時間も、己には不可欠なものだった。
「・・・・・・会わないつもりだったけど、本当は会いたかったの」
イゾウが待っていたからなんて嘘で、本当は自分が我慢できなかっただけ。
本当にイゾウに忘れて欲しかったのなら、自分に縛られて欲しくなかったのなら意地でも姿を見せないべきだったのに。
それでもアパルはこうしてイゾウの前に現れてしまった。
「会いたくて、でも私死んじゃったし・・・・・・そしたらさ、忘れてもらわなきゃって思うじゃん」
ふるりとアパルの瞳が震え、潤みが増した。
涙で光るその目を、イゾウが愛おしげに見つめて零れた涙の跡を拭う。
「それは俺の意志も聞いてからにして貰いたいな。忘れたいなんざ一ミリも思ってない」
「んぐ」
鼻を摘ままれてきゅうと顔をしかめたアパルに、イゾウは声を上げて笑った。
「はははッ! そんな顔するならさっさと覚悟決めて香り付けてくれ」
大きな手に頬を包まれ、アパルはイゾウの微笑む眼差しを受け止めていた。
一度だけ視線を落とし、観念したように瞬きをすれば垂れた瞳でイゾウの姿を映す。
「ほんとうに、いいかな・・・・・・」
「むしろ、どーんとこい」
「・・・・・・イゾウ・・・・・・手、貸して」
己の頬に触れる手を両手で解き、まず自分の指に一滴香油を垂らしてからその肌に塗り込んだ。
最後に、同じ香りのする互いの手首をすり寄せる。
香りが交じって、主張が強くなる。
一生忘れられないほど強く、イゾウに、アパルに刻み込まれる。
「ちゃんと付けてね」
「お前に付けて貰えないのは残念だが・・・・・・死んだときの楽しみにしておこう」
「そんな楽しみ作らなくていいよ」
香りが漂うその手を取り、アパルは頬を押し当てる。
厚い皮膚の手は、しっとりとアパルの肌に触れ、香りは柔らかくこちらを包んでくれる。
「ありがとう、イゾウ」
ぽろぽろと微笑むアパルの瞳から零れる涙を、イゾウが唇で触れて拭う。
赤く彩られたイゾウの唇が僅かに濡れて光る姿に、アパルもそっと身を寄せた。
唇についた水滴を、アパルは舌先でちろりと拭った。
そうして今度は自然と二人の距離が縮まって、アパルの柔らかな唇を、イゾウの赤が覆う。
瞑った目の端から零れた涙が転がり、甲板に落ちる前に光の粒子となって消えた。
アパルの輪郭が淡く明滅し、少しずつその透明度が上がっていく。
「イゾウ」
「ん?」
「大好き」
「俺は愛してるよ」
きょとん、とアパルが瞬き、すぐにいじらしく思える顔で訴える。
「ず、ずるい! 私だって愛して――」
最後の一音を告げる前にイゾウの眼前から愛おしい人の姿が消えた。
一緒にランプも消えたもので、一瞬で闇に包まれる。
余韻を惜しむようにイゾウは目を閉じ、アパルの姿を思い描いた。
「随分冷えるな……」
星空を眺めて息を吐けば白く濁った空気が広がって夜空に溶ける。
胸にわきあがるもの悲しさは、潮風の冷たさのせいだと決めつけた。