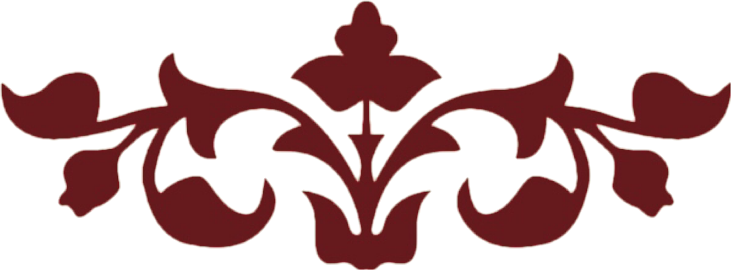
枯葉 の羽
『最後のダリハ地区が墜ちた。イシュヴァール全区が、完全に国軍の管轄に入った』
その知らせを聞いた途端、肩の力がふっと抜けた。目を閉じ、息を吐く。
ああ、やっと終わった。
正直に言えば、実感はまだない。内乱はもう少し続きそうな気がするし、明日も戦場への出番があるようにも思える。けれど、あちこちから喜びの声が聞こえ、万歳する者、へなへなと座り込む者、笑って肩を組む者たちの姿を見ていると、自然と口元に笑みが浮かび、「内乱が終わったこと」を目で見てやっと、実感できる気がした。
これで血のにおいとも、褐色の罪人とも、引鉄を引く痛みともしばらくお別れだ。
もうひとつ、おめでたいことがある。任務の実績が評価され、キンブリー少佐が昇進を果たした。少佐ではなく中佐になったという。上司の仕事の腕が認められるのは、部下としても嬉しいことだ。もちろん、恋人としても。
さっそくこれから、内乱の終結と中佐への昇進を祝い、キンブリー隊の宴の席を用意しよう。中佐が私用で帰ってくる前に、お酒と煙草を調達しなくては。
キンブリー隊で残ったのは、私を含め全員で六名。そのうち補充兵として二名が、最近仲間に入ったばかりだ。中佐の活躍のおかげで、ほかの隊よりも数多く生き延びることができた。皆が皆、中佐を信頼しているかどうかは分からないけれど、少なくとも私はこうして生かしてくれたことに感謝の念が絶えない。
お酒を三本持ってきて、六個分のマグカップをひとまず平らな瓦礫の上に置く。煙草は准尉が持ってきてくれた。
同期の大柄な少尉が私を呼ぶ。
「ラシャード! 良い酒持ってきたか?」
「これしかなかったんだけど……美味しいと思う?」
「なんだって美味いさ。今日はなにを飲んでも最高に美味いに決まってる」
彼の言う通りだ。今日はなにを飲んだって、なにを食べたって最高に美味しいはず。この喜びをみんなで分かち合えるのは本当に幸せなことだ。
ほかの隊員は皆集まっている。残るは中佐だけだ。私たちは彼が来るまでの間、これからの希望について語りあうことにした。
まず、中央に帰って真っ先にしたいのは、自室のふかふかのベッドで寝ること。そして、自分で朝ごはんを作って食べること。久しぶりにベーコン二枚のハムエッグと、バターをぬったトーストが食べたい。新鮮なレタスとトマトのサラダ、そしてミネストローネもあれば完璧だ。きっと目を閉じて噛みしめるほど美味しいに違いない。
忘れないうちに東部の田舎に電話をかけなくては。無事に戻りました、心配かけてごめんね。そう言って両親の安堵した声を聞きたい。なんなら、休暇をとってしばらく実家に帰ってもいいかもしれない。もう三年帰っていないから、そろそろ顔を出さないと両親が拗ねてしまうかも、なんて。
それから、街にでかけてワンピースや香水を買いたい。戦場では毎日ズボン、においは血と腐臭と硝煙なんかしか嗅がなかったから、その反動だろう。思いっきりオシャレをして、中佐に、キンブリー中佐に会いに行くんだ。
たくさんデートがしたい。別にどこかに出かけなくても良い。家のソファで寄り添ってなにか他愛のない話をするだけでも楽しいに決まっている。でも、もし、わがままを聞いてくれるのならば、水族館に行ってみたい。ゆらゆらと泳ぐ色とりどりの魚を眺めたり、美しいクラゲの浮遊感を楽しんだり、巨大なサメの迫力に息を呑んでみたいのだ。そして、引き寄せ合うようにそっと、手を繋げたら。
心躍る想像は次から次へと浮かび上がっていく。思い浮かんだことをすべて実践してみたい。仕事のことも、戦場の消し去りたい記憶も、ぜんぶどこかに捨てて歩きたい。終わったのだから。すべて、終わったのだから。
私が想像の世界に行っている間、皆は談笑していた。誰も彼もが笑っている。そう、イシュヴァールの暑い冬の時期は終わった。これからは穏やかな、暖かな春がやって来る。
「で、ラシャードは?」
急に話を振られて、きょとんとしてしまった。
「帰ったら、なにすんだ?」
「ああ、えっと……」
「もちろんあの人とラブラブデートだよな?」
私と中佐の関係を知っている同期が、ニヤついた視線をこちらに投げてきた。事情を知らない者たちは、誰のことだ、と騒ぎ立てている。
顔が熱くなっていくのが分かる。相変わらず数人の兵は、誰のことだよ、と興味津々で私や周りの兵につっかかる。
もう耐えきれずに立ち上がった。
「キ、キンブリー中佐を探してきます!」
そうしてずんずん歩き出すと、ヒュウ、と誰かが口笛を吹いたのが聞こえた。
一体、中佐はどこにいるんだろう。功労者であり主役の彼なしでは、宴は始めようにも始められない。私は、瓦礫だらけの道をひたすら歩いた。
道の途中で、忘れかけていた悲しいものを見た。折り重なって倒れているイシュヴァール人の親子の遺体だ。服も肌もボロボロになった小柄な母親が、少年をかばうように抱きしめている。遺体はひどく損傷しており、顔は焼けただれていて分からない。おそらく、国家錬金術師の「手柄」だ。
いつもなら見ないふりを決め込んでその場を去っただろう。しかし、なぜだか今日はその親子を放ってはおけなかった。強く、心を引っ張られる感覚を覚えたのだ。
私は陥没した地面に親子を運び、その上から土をかけた。そして、落ちていた棒を拾って、その土の上に立てた。質素だが、墓のつもりだった。
自分に埋葬する資格などないかもしれない。ふと浮かんだその考えを掻き消し、どうか安らかにお眠りください、と手を合わせた。
再び、中佐を探しに行こうと立ち上がったとき、遠くの方の建物が密集している地域で、人だかりができているのが見えた。そこに行けば見つかる気がして、急ぎ足で向かった。
ざわざわと大勢の軍人たちが声をひそめてなにかを話している。その人だかりの先になにがあるのか分からず、私は遠慮がちに人々をかき分けて行った。
「ほら、とっとと歩けキンブリー!」
聞こえてきた大声に、瞠目する。私は急いで人ごみをかき分け、最前列を目指した。胸騒ぎがする。キンブリー中佐の身になにかがあった。なにがあったんだろう。どうか、良くないことではありませんように。お願い。お願い!
最前列に顔を出した。前後ふたり、合わせて四人の軍人たちに挟まれている中佐の姿は、確かに見つけた。しかし、軍人はロープを持っていて、そのロープが繋がる先は――信じがたいことに中佐の手首だった。
「中佐! キンブリー中佐!」
私は混乱した頭で、彼を夢中で呼んだ。視線が合った。
彼は凪いだ湖の水面のように、静かな表情を浮かべていた。
「中佐、どうして、なにがあったんですか!」
彼の後ろについていた軍人が、私を横目で睨んだ。
「キンブリーの部下か?」
「ええはい」
「仲間に伝えてやれ。この爆弾狂は、上官殺しの罪で独房行きだってな」
――なんだって?
「五人だ。こいつぁ上官を五人も殺った、殺人鬼なんだよ!」
思考が追いつかない。頭が真っ白になってしまって、なにも考えられない。なにかの間違いではないのか。
中佐が殺しを? イシュヴァール人ではなく? それも五人も?
「うそ……」
「行くぞキンブリー!」
中佐の前の軍人がロープを引っ張り、彼らは歩き出す。私は慌てて手を伸ばした。
「待ってください! 彼と、彼と、お話しをさせてください!」
彼らは無言で歩いて行く。私の声など聞こえないというように。
「そんな、中佐! キンブリー中佐ぁ!」
「アヤ」
振り返らない背中が、私を呼んだ。
「……愛していますよ」
ああ、どうして。どうして、そんな言葉を?
私は夢中で叫んだ。
「待ってます! 中佐が戻られるのを、ずっと待ってますから!」
涙が後から後からあふれだした。止まらなかった。
背中が遠くなって、もう、見えない。
上着の、締めつけられる胸のあたりを、ぎゅっと握った。
私も愛しています。いつまでも、愛しています。
季節は巡る。春に夏が覆い被さって、夏を秋が侵食する。秋は冬に飲みこまれて、冬は春のまぶしさに負けてしまう。そんなふうにして一年は過ぎていく。
彼との別れから、まだ一年。
この一年間で様々なことが起きた。私は重罪人の元部下。中央には居場所がなく、立つ瀬もなく、ほどなくして北に左遷させられた。それからは、彼のことを考えないようにと、仕事に今まで以上に熱心に取り組んだ。その姿勢が大変真面目だということで、年度末にはささやかな賞をいただいた。
その陰で、夜、悔しさとやるせなさでお酒に溺れる日々が続いた。情けない自分を見せるのがいやで、両親のもとを訪ねることさえできないでいた。ブリッグズの新しい友人とは、まだよそよそしいままで、かつての友人たちに泣きながら電話をかけた日もあった。
キンブリー中佐のことを揶揄し、軽蔑した噂話が耳に入ったことが何度かある。私はそのたびに、違う、彼にはなにか理由があったのだ。理由があり、仕方なく手を下したのだ。そう噛みつきたいのをぐっと堪えて、胸に仕舞い込んだ。自分が陰口を叩かれるのは良かった。けれど、彼を悪く言われることは、ひどく傷ついた。やり場のない哀しみを抱えて、物陰でひっそりと涙を流したことは少なくない。
中佐はきっと、安全地帯で戦況を伺い、人殺しを扇動した腐った根性を持つ上官たちを見るに堪えなかったのだ。だから鉄槌を、正義の鉄槌を下したのではないか。私にはそう思える。
果たして、それは事実なのか。分からない。確認しようにも、重罪人として独房に閉じ込められている彼との面会や文通、差し入れなどは、一切許されないのだから。
この先もう一生会えないのだろうか。描いていた明るい未来はやってこないのだろうか。また心から笑える日は、来るのだろうか。
キンブリーさん。
あなたを、諦めきれない。
見慣れた荒地、砂を含んだ生ぬるい風。気がつけば、私はまたイシュヴァールの地にいた。先頭を歩くのは、キンブリー中佐だ。仲間と弾薬箱を抱え、銃を携えて、彼の広い背中を追いかけた。
気を抜いてはいけない。気を抜いたらこちらが殺られる。必ず生き残って、中佐と一緒に楽しく笑える未来を現実のものにするんだ。
「ラシャード少尉」
中佐が振り返る。私は返事をして彼を見た。
――彼の顔はおぞましい悪魔になっていた。
私は引きつらせた声をあげた。うろたえ、退いた。すると、後ろから何者かに手首を掴まれる。
おそるおそる振り返れば、いつかの焼死体の母親が立っていた。隣には彼女にしがみついている少年もいる。彼らの顔は焼けただれていて、笑っているのか怒っているのか分からない。それでも、声が聞こえる。
「私たちにお墓を作ってくれたのよね。じゃあ、今度は私たちがあなたを埋めてあげる」
ぐっと心臓を掴まれたその瞬間、悲鳴を上げて飛び起きた。心臓がばくばくと早鐘を打っている。呼吸が浅い。ひどい汗だ。でも、よく見れば自分の寝室。ああ、そうか。夢、また夢だったのか。
戦場を後にしてから、こうしてしばしば悪夢を見るようになった。うなされ、金縛りにあう夜もたびたびある。
イシュヴァールで人が死ぬごとに、私の中のなにかも死んでいった。人を殺めたように見えて、実は自分自身も同様に殺していたのだと、気づいた。
結局、眠れないまま朝を迎えた。今日はせっかくの休日だというのに、体はだるく、家から一歩も出たくない気分だ。それでも、晩ご飯の材料と、明日食べるパンを買いに行かなくてはいけないし、キッチンの洗剤もきれている。重い腰を上げ、支度を始めた。
ざわめく雑踏の中を歩く。今から向かうノースシティのマーケットは、いつ訪れても混雑している。にぎやかで、まぶしくて、沈んだ心には少し、つらい。普段ならば近道をして向かうところを、今日はなるべく遠回りを繰り返して歩いた。
途中、どこか寂れた公園に差し掛かった。遠くで赤いブランコが風に揺れている。なにも悲しいことがなく、無邪気に遊んでいた子ども時代に、戻りたくなった。
けれど本当のことを言えば、中佐と一緒に過ごしていたあの日々に戻りたい。仕事をして、デートをして、隣で眠ったあの幸せな日常に。それが叶わないのなら、いっそのこと、少佐に出会う前に戻りたい。あの頃の私だって、それなりに幸せだったと思う。大きな喜びがない代わりに、たいして強い悲しみも感じなかったはずだ。
とはいうものの、その頃の自分をなぜか思い出せない。少佐に出会うまでの私は、本当に「私」だったのだろうか。彼と出会う前は、どうやって息をしていたのだろう。どんなことで悲しみ、どんなことで笑っていたんだろう?
冷たい風が吹く。頬にかかる髪を耳にかけた。
そんなこと、いくら考えたところで、あの頃の自分には戻れないのに。胸に空いてしまった穴を埋めることなど、できやしないのに。
段々と歩みが遅くなり、ついに立ち止まってしまう。私はうつむいた。
足元に枯れ葉が落ちている。と思ったが、よく見るとそれは、蝶々だった。蝶は、羽と羽の間に三十度ほどの角度を生んだまま、静寂に溶けて死んでいた。
いや、わずかに動いている。羽の動きはひどく緩慢だけれど、生きている。
蝶は弱々しく体を震わせた。苦しんでいるのかもしれない。人間に追いかけまわされたのか、車にぶつかってしまったのか、はたまた胸のポンプが動作不良を起こしてしまったのか。いずれにしても、かわいそうだ。
「きみももう、飛べないのね」
自然に口から出た呟きに、違和感を覚えた。きみ「も」って?
ああ、そうか。
癒えない苦しみが身体を蝕んでいる。もう過去と同じようには飛べない。
この蝶は、私だ。
びゅう、と強い風が吹いた。落ち葉の転がる小さな音がし、もう一度髪を耳にかけた。蝶は必死に地面にしがみついている。枯れ葉色の羽は、まだ動いていた。十分苦しいはずなのに、なおも動きを止めようとしない。
羽を動かそうと一生懸命あがいている。苦しみの渦の中で生きようと、もがいている。
その姿を見て、ふと思う。ただ、苦しむだけの毎日ではだめなのかもしれない。
――この蝶のように、ならなくちゃ。
「……いつかまた、空を飛べる日が来るといいね」
きみも、私も。
去年まで住んでいた家の近くと、実家のポストの下に落ちていた二羽の蝶に、インスピレーションを受けて書きました。
(了)20180524
(改)20190109