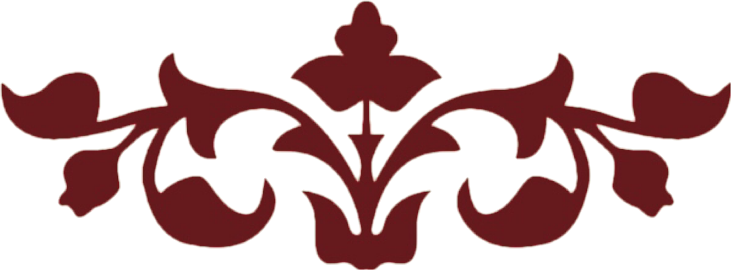
散らざる花は凛として
九時の方角から大規模な爆発が起きた。大気を震わせるその振動は、胸の中に不安の渦を生みだす。遠くを見やると、ほぼ瓦礫の山と化した建物が、煙の柱をもうもうと吐き出す姿が見えた。
食糧やら簡易コンロやらがびっしり詰まった木箱を、もうひとりの同僚と担ぎ込む。軍の拠点から爆発を起こしたであろう張本人・キンブリー少佐の元へと急いだ。
大総統令三〇六六号。閣下がそれに署名し、国家錬金術師がイシュヴァール殲滅戦に参戦してから、半月後。照りつける午後の日差しが、焼け野原を歩く私の無意識層の片隅に陰鬱な影を落とした。
キンブリー隊は拠点から二十分ほど歩いたところにある、荒廃した小高い丘に固まっていた。眼下には、担当区域であるカンダ地区が一望できる。
辺りには死臭に加え、なにやらただごとでない空気が漂っていた。それは、使いで一旦隊を離れる前とは一線を画すほど緊迫したものだった。
私は、はっと息を飲んだ。転がっている死体は褐色のものばかりではない。青い軍服に身を包んだひとりの軍人が、血を流してうつ伏せに倒れている。髪型と背格好から察するに、彼は新入りの軍曹だ。
同僚たちはうつむき、青ざめた顔で沈黙している。私たちは荷物を下ろし、彼の前で黙祷を捧げた。
悲哀の表情を浮かべた私を、上官は淡々とした口調で労ってくれた。彼の軍服は砂埃と血液で汚れていた。勇敢にも少佐に挑んで敗れた、哀れな民の返り血だ。もう幾度となく目にしている。
「では、そろそろ休憩に入りましょう」
少佐は、格子状になった木製のふたの隙間から覗く物資を見ながら、金のボタンに手をかけ、汚れた上着を脱いだ。
お湯を注いだ顆粒のスープに、神妙な自分の顔が浮かんでいる。私は、少しの間だけでもひとりになりたかったので、少佐や同僚たちが見えなくなる場所まで離れ、荒れた地面に座っていた。
先ほどある准尉が、私たちが物資を運んでいる最中に起きた、凄まじく衝撃的な話を聞かせてくれた。その内容が後をひいているのか、胸はじくじくと痛み、鈍い頭痛が続いている。
それは亡くなった軍曹のことだった。彼は、今朝キンブリー隊に急きょ配属が決まった、東部の兵である。私はまだ一言しか言葉を交わしていないが、それでも同志の死は深い哀しみを呼んだ。
だが、そのショックをはるかに上回る衝撃があった。彼の死因だ。なんと彼は、敵からの攻撃を予測した少佐に、突如身代わりのように引っ張りこまれ、そのまま爆死してしまったという。
つまり、仲間を「盾」にしたのだ。准尉ともうひとりの同僚は、その瞬間をしっかりこの目で見たと言っている。
少佐の上着に付着していたあの血は、敵ではなく、味方の軍曹のものだったのだ。
「……うそ、でしょ……」
手が震え、スープのカップが滑り落ちた。足下にこぼれた液体が、革靴の側面を濡らす。今になってやっと、恐怖は足先から電流のように這い上がってきた。
ぎゅっと目をつむる。思わず自分の体を抱きしめた。
そんなはずはない。戦場は人を変えると言うが、少佐が自分の兵にそんな卑劣なことをするはずがない。もし間違いでないのなら、なにか意図があるはずだ。きっと。
私はすがりつくようにスプーンフォークを握りしめ、何度もかぶりを振った。
確かに、キンブリー少佐は、まとう雰囲気と食えない性格から誤解され、敬遠されがちな人物ではある。
しかし実際の彼は、水場で涼み羽を休める白い鳥のように、ロウソクにゆらめく暖かな灯のように、皆が想像するよりずっと、繊細で優しい人なのだ。それは、公私ともに彼のそばにいた私が誰よりも知っている。
それだというのに。いかんせん身体の震えは止まらない。表面的な事実に囚われて、彼の考えを、真意を読めない自分が腹立たしい。
もうすぐ号令がかかる。こんな情けない姿では出て行けない。このまま動揺していては上官を、いや、自分の命すら満足に守れない。
思考を振り切るように立ち上がる。集合場所に戻ろうと歩を進めた、そのとき。背後の茂みが大きくがさりと揺れた。
「ゆるさない、アメストリス人」
まるで、地獄の業火で身を焼かれた人間が発するような、深い憎しみの募った呟きが聞こえた。
考えるより先に手が動いた。腰のホルスターから銃を引き抜き、ふり返ると同時に声の主に銃を向ける。
だが、相手は焼け痕の残る鉄板を手にしていた。下手に撃てば跳弾する。もどかしくも、先手を取ることはできなかった。
頭部を血だらけにしたイシュヴァールの武僧は、持っていた太い棒を素早く振り、構えていた銃を払いとばした。
武僧は、ほんの一瞬狼狽した私の隙をついた。しまった、と思うと同時に、左わき腹に強烈な突きを入れられた。重く沈むような痛みに叫び声すら出ない。私は成す術もないまま、真後ろに突き飛ばされた。
口内にあふれる鉄の味。すべてを飲み込めず、それは唇の端からつうと垂れた。
拳に力をいれ、歯を食いしばる。ここで倒れてはいけない、気を確かに持たなければ。この程度で殺られたら、少佐の副官の名が廃る。たとえ死んでも死にきれないだろう。
凶器を振り上げる彼の動きを読み、よける。落ちた銃は二メートルほど向こうにある。痛む腹部をかばいながら立ち上がったが、視界がぐらりと揺れ、くずおれる。
そのすぐ後に、彼が乱暴に投げ捨てた鉄板が、頭上をかすめた。幸運にも、体勢を崩したおかげで怪我はない。
だが、憤慨した男が野獣のような叫び声をあげ、足下の銃を思い切り蹴ってしまう。銃は、とても届きそうにない距離までとんでしまった。
逃げなくては。そうは思うものの、蛇に睨まれた蛙のようにまったく力が入らない。急激に血の気が引き、身体の芯が硬直する。
なんで、どうして、こんなときに!
身体と地面に大きな影が落ちた。見上げると、復讐の獣と化した男が、目の前で凶器を持った両手を振り上げるところだった。
殺られる。
誰か、たすけて。
――少佐。
首をすくめ、強く目をつむった。すかさず、なにか骨のような硬いものが砕ける音がした。
……けれど、なぜだか痛みひとつない。
恐るおそる瞼を開くと、目の覚めるような青色の背中が映った。そこに垂れる、見慣れた漆黒の尻尾髪。
ああ、嘘みたい。本当に、来てくれた。
「イシュヴァール人。貴方は赦しません。今すぐ私の目の前から、消え失せろ」
凶器の棒が音をたてて足下に落ちる。武僧は、少佐に殴られた衝撃でよろめいた。上官の背中越しに見た男の顔から、とっさに目を逸らす。顎が、どす黒く血塗られたうえに、無残にも砕けている。もはや原形をとどめてはいなかった。
「とっとと滅びなさい、イシュヴァール人!」
まばゆい錬成反応とともに、生臭い紅が弾け飛んだ。破損したシャワーヘッドから勢い良く噴出される汚水のような、派手な血飛沫だった。
すべてが一瞬で紅蓮に染まる。衝撃的な光景に目をみはり、声まで失った。抑えようとも、湧き上がる恐怖心から来る震えは抑えられず、ただ呆然と少佐の背中を見つめるほかなかった。
硝煙のにおいが鼻を刺す。やがて、重みが地面に崩れ落ちる音がした。武僧が息絶えたのだ。
ふっ、と全身の力が抜ける。重力が突然強くなったように、私も自然と地面に吸い寄せられていく。
なにか重いものが、もう一度どさりと落ちる音がした。それは自分が倒れた音だと理解すると同時に、瞼が落ちていく。少佐の声も暑すぎる日差しも、五感で感じるすべてのものが、早足で遠のいていった。
誰かがいる。私を、呼んでいる。
「アヤ! 気がついたのね!」
安堵のため息をつき、胸に手を当てこちらを覗きこんでいる。誰かと思えば、彼女は士官学校時代からの友人だった。
安全なテント内、四肢は欠けていない。なにより命があることに溜飲が下がる。
「危機一髪だったわね……。とにかく無事で良かった。体、痛いでしょ?」
「ううん、平気。心配かけてごめんね」
包帯でぐるぐると巻かれた腹部は、痛くはあるが激痛ではない。少し休めばすぐ戦線復帰できるだろう。
「キンブリー少佐、何度も様子を見に来ていたわよ。二十一時にまた来るって言っていたから、そろそろ見えるはずだけど……」
少佐。ああそうだ、すんでのところで少佐が助けに来てくれたんだっけ。心の中で呼んだだけなのに、少佐はちゃんと来てくれた。私を、守ってくれた……。
上半身を起こすと左わき腹に痛みが走ったが、不思議とさほど気にならなかった。
「キンブリー隊の准尉に話を聞いたわよ。あんた、よほど少佐に気に入られているのね!」
なんのことなのか見当がつかない。小首を傾げると、彼女は無邪気にウインクし、詳細を話してくれた。
それは、私が倒れている間に起きた出来事だった。その准尉をはじめキンブリー隊の同僚たちは、少佐の対応を不可解に、また苦々しく思っていたという。少佐は、屈強な武僧から私を素手で助け出してくれた。それに対し、あの「名誉ある急ごしらえの軍曹殿」の扱い。その待遇の差は、天と地ほどあると。
もちろん、そんな軽口を叩く命知らずの者はいない。けれど、少佐は彼らの心情を読みとって冷静に言い放ったらしい。「盾にも限りがありますから、守れるものは守らなくては」と。
でもコレってたぶん照れ隠しよねえ、と陽気で呑気な彼女はニヤつく口元を隠さずに、こちらに視線を投げた。
「そ、そんなことないでしょ」
「そうかしら? 表向きにはそう言っているけど、ホントはあんただけを是が非でも守りたいんじゃない? いくら少佐でも、愛する花を盾代わりにしようとは思わないだろうしね」
「だけど、本当に言葉通りの意味かもしれないでしょ。たとえ盾にされても、全然、後悔しないよ」
「相変わらず一途というか、愛が重いというか……まったく」
仮に、少佐がどういう言い方をしていたってなにも思わないし、そこに深い意味がなくてもかまわない。彼は命の恩人、それでなくても大切なひとなんだから。
「ラシャード少尉」
天幕の入り口を捲って入って来たのは、噂をしていたキンブリー少佐だった。珍しく、焦りを滲ませた声だ。どこか思いつめたように眉根を寄せ、私と視線を交えた。
少佐は、敬礼したままの友人に断りを入れ、少しの間席を外すように命じた。そして、先ほどまで彼女が座っていた、木製のスツールに腰掛けた。
彼女の足音が去ると、静けさが織りなす、かすかな静寂の音が聞こえた。
「……無事でなによりです。怪我はどうです、痛みませんか」
「はい、異常ありません。少佐、この度は多大なるご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでし……」
厚みのある彼の手が、手の上に重ねられる。その体温に気をとられて、謝罪は途切れてしまった。
「貴女に怪我を負わせるなど、不覚でした」
「そんな、すべて私の過失です。なにも告げず、勝手に陣営を離れたのですから、自業自得です。それにもかかわらず助けに来てくださって……本当に感謝しています」
「あのような凄惨な光景を目にして礼が言えるとは。貴女も少しは戦場慣れしたということでしょうか」
凄惨な、光景? そういえば、少佐はどうやってあの武僧を仕留めたのだろう。助けてもらっておきながら、肝心の場面を忘れるとは大問題だ。だが、私の記憶は少佐の背中が見えたところでぷつりと途絶えている。どんなに記憶をたどっても、薄情なことにまるっきり思い出せない。
「ああ、覚えていませんか。ならば無理に思い出さなくて結構。血生臭い記憶は、忘れた方が優しい貴女のためになりますから」
口元だけで薄く微笑み、少佐は視線を外した。果たしてそれでいいのかと戸惑いつつ、彼の言葉にあいまいに頷く。どうあがいても思い出せないのなら、むだな執着は捨てた方が賢明なのかもしれない。私は彼のように、強くないから。
ふと視線を落とし、重ねられた彼の手を見て驚いた。指の第二関節が赤みを帯びている。それも、四本もの指が。
「少佐っ、手が赤く「柄にもなく、ぞっとしましたよ」
遮るように声を被せられ、口をつぐむ。
「点呼の際、貴女の姿がどこにも見えないと分かったときは。いやな予感と言うのは、往々にして当たるものです。そして予想通り、貴女は絶体絶命の危機に瀕していた。思わず二度も総毛立ちましたよ」
こんなにも心配をかけてしまったのか。ひとりになりたいからと、勝手に陣営を離れた自分の迂闊さを思い出し、猛反省する。
そしてあろうことか、彼に怪我まで負わせてしまった。錬金術が使える少佐は、素手で戦うことはほぼない。だからこの怪我はおそらく、私を助け出した際に負ったものだろう。申し訳なさで胸がぎゅっと締めつけられる。腹部の痛みとは、比べものにならないくらい。
「無我夢中で相手を仕留めました。しかし、あの程度の痛めつけ方ではまだ足りない。貴女を傷つけたあのイシュヴァール人が、それほどまでに憎い」
「少佐……」
淡々とした声の調子に、黒い執念が滲み出ている。眼光は鋭く、残忍な虹彩はぎらぎらと冷徹に燃えていた。その様子を見ていると、彼の思いに手放しで喜び、感謝の言葉を連ねることなどできなかった。
私を守ったって仕方ないのに。むしろ私が彼を守る立場であるのに。
自分の命に代えてでも、この殲滅戦の主戦力となる国家錬金術師を守らなければならない……。これは戦場における軍人の、暗黙のルールでもある。
しかし、それは仕事上の話だ。私はその不文律だけで彼を防護するのではない。少佐は命の恩人で、私の一番大切なひと。理由は、人間としてごく自然な感情、それだけだ。
少佐のためならたとえ、文字通り彼の盾として散ることになっても――。
「私ひとり生きていても仕方ない」
思わず目を見開いた。考えを読まれてしまったのだろうか。
「たとえ私が、数多の兵を身代わりにこの戦場を生き抜いたとしても、そこには寸分の価値もありません。アヤ、貴女がいなければ」
少佐の真剣な瞳が、私を捉えて離さない。実直な声と、嘘を語らぬ青の双眸に吸い込まれる。
頬をそっと触れられる。負傷した方の手だった。
「決して貴女を死なせはしません。その代わり、勝手に私の前から去ることは許しませんよ。貴女はもう、私のものなんですから」
「は、い」
顔を寄せてきた少佐を、涙の薄い膜越しにじっと見つめた。
貴女は私のもの。晴れて想いが実った日、そのときもこうして同じ言葉を告げられた。彼の気持ちはあの頃から変わっていない、私と同じ気持ちを持ち続けてくれているのだと思うと、今度こそ涙があふれだした。
「それに同じ死ぬのであれば、私と爆風に巻き込まれて息絶えていただきたい」
「……つまり私は、安らかな最期を迎えられないのですね」
彼は私の涙を拭いながら、ええそうですよ、と人の良い笑みを浮かべて、傲慢な要望を平然と押しつけた。
「最期に見たものが私であって欲しい。そして、貴女の散り際を抱きとめたい。貴女を、たったひとりで逝かせたくはありませんから」
静かに唇が重ねられる。驚きよりも
彼は、私という土地を優しく蹂躙するように、深く熱情的に求めた。
――キンブリー少佐は、ひどい上官だ。
ある軍曹は盾の代わりにされ、ある少尉は命の終え方を勝手に決められてしまった。
……そのことだけを聞けば、人は彼に対してなんらかの悪感情を持つに違いないだろう。
しかし、それだけが事実ではない。彼は、軍人の責務、また国家錬金術師である自らの仕事を理解し、本来の目的をぶれることなく果たし続けている。
今なら彼の意図が分かる。少佐は、あの軍曹に「軍曹」としての本分をまっとうすることを、強いたにすぎなかった。確かに、到底許される行為ではないだろう。だが、ここは戦場。平和な日常においての倫理や常識などは通じず、人を殺めた分だけ英雄とされる、特殊な場所だ。少佐は、己の信念を彼に適用し、軍人の暗黙の了解に黙従させたのだ。私たちが果たすべき目的のために。
人が側面しか見ずにくだした評価など、信じない。一度悪感情を抱いた人々は、それに囚われ続けるだろう。おそらくそれらの人々は、負傷しつつも部下を助けたというエピソードには興味を示さない。部下の命の終え方を定めた根底には、確かな愛情があると説明しても、間違いなく一笑に付すだろう。
評価がどうであろうと、誰がなんと言おうと、私は彼のそばにいる。たとえ、戸惑うことがあっても、私は彼を信じる。理解しようと努める。少佐より大事なひとはいないから。少佐が誰よりも大切だから。
長いくちづけの後、彼は私に言った。この戦いを終えたらまた以前のように一緒にいたい、と。私は微笑んで頷いた。
これまでよりも長く濃い時間を過ごそう。そのために必ず生きて帰ろう。
私たちは、確かな約束を交わした。
治療のために五日間養生した後、私は懸命に仕事に身を投じた。道なかばで命を落とさないように、生き伸びることに俄然執着した。すべてはその約束を、その未来を叶えるために。
彼の手の怪我は二日で治り、私の左わき腹の痛みは十日目で気にならなくなった。
まだまだ戦える。もう決して散り急いだりはしない。
命を散らすにはまだ、早すぎるから。
(了)20160406
(改)20190109