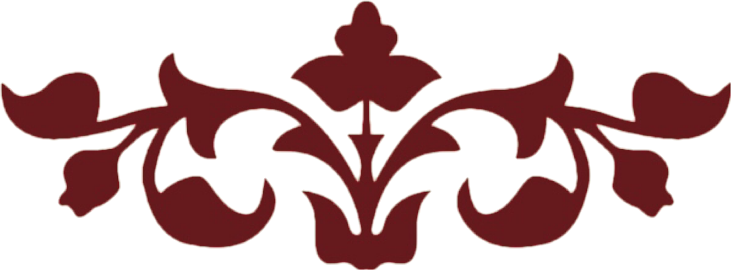
凍 てつく涙は頬の上
白く舞い上がる雪煙に、午後の淡い陽光が透る。その光は、ここブリッグズ砦の高い窓辺まで届いた。
普段なら気にも留めない吹雪になぜか目を奪われたのは、過去に同じようなものを見たことを思い出したからだろうか。イシュヴァールの砂嵐だ。あれもこんなふうに高く大きく舞っていた。と、思いを馳せてすぐ、ここは戦場ではないのだからと、その考えを頭の隅の方へ押しやった。そう、ここは戦場ではないのだ。ひとくちに平和というと語弊が生まれるが、少なくとも今は臨戦態勢ではない。
ほんの数秒前までは、そう思っていた。だから、ドラクマ方面から突如姿を現した何千の軍隊の影と連なる戦車が見えたとき、呆然としてその場に立ち尽くしてしまった。
「北のドラクマより、開戦宣言あり!」
流れている放送の内容がうまく呑み込めない。一拍置いて、そばにあった簡易望遠鏡をしゃくり取り、中を覗きこんだ。遠くに群がる人影の中、黒い毛皮の帽子を被り仁王立ちしている五十代くらいの指揮官が見える。
その男の隣にいる人物を見て、思わず目をみはった。
どうして、キンブリーさんがそこに?
「さすが難攻不落の地ですね。ブリッグズの北壁こと、アームストロング少将の留守を狙っての出撃をもろともしない。指示と報告は風より早く伝えられ、部隊は即座に戦闘態勢に入り、そして瞬殺。いやあ素晴らしい」
「……恐れ入ります」
並んで隣を歩くのは、五日ぶりに見るキンブリーさんだ。彼の横顔には返り血を拭った跡がある。私たちは、ひとまず軍に見つからない人気のない場所へと移動していた。
ドラクマ軍との戦いを終えた後、私は招集命令を無視し、脱走した。あげく、戦いを扇動したというキンブリーさんを逃がそうとしている。
後でどんな罰がくだるだろう。考えると背筋が凍る思いがしたが、それをひとまず振り払う。まず、目の前の問題を片付けなければならない。どこに逃げるかだ。
雪原の中に、廃墟と化した一軒家を運よく見つけた私たちは、一目散にそこに向かった。古びた木製のドアを念のためノックするが、やはり返事はない。鍵が開いていたので、恐るおそる足を踏み入れると、主を失った孤独で老いたリビングルームが私たちを迎えた。暗く乾燥したその廃墟の中で、私たちは一旦身を隠すことにした。
ドラクマ兵との戦闘は、私たちブリッグズ兵の勝利をもって幕を閉じた。ソファに薄く積もっていた埃を払うキンブリーさんに言わせれば、それは計算済みのことであったという。
「ブリッグズ兵が敗れる? ……ありえません」
彼は小豆色のソファにどかりと腰を下ろし、脚を組んで息をつく。少し間をとって腰掛ける私に視線だけくれて、不敵に微笑む。
「私は最初から、ドラクマ兵で紋を刻もうと考えていましたからね」
「紋を刻む? どういうことですか?」
「ああ、失敬。こちらの話です」
彼は微笑みを絶やさずに言った。なんとなく、氷の壁のような、見えない壁に触れた気がした。
「伝えるのが遅くなりました、ただいま戻りましたよ、アヤ」
「……おかえりなさい、キンブリーさん」
私は少し控えめに微笑んだ。
五日前、
正直に言えば、彼が傷の男の捜索をしているときから、どこか寂しさを感じていた。ブリッグズで実に六年ぶりの再会を果たしたというのに、彼は砦にほんの数日しか滞在しなかったからだ。立場上、わがままを言えないことは分かっている。けれど、寂しい、会いたいと思う気持ちは、抑えられない。
捜索から戻るのを今か今かと待っていたというのに、顔も見られないまま、彼がドラクマに出発したと聞いたときの落胆ときたら。あれほど会えるのを楽しみにしていたのに、また延期だ。私は募る寂しさにまた、ふたをしなければならなくなった。
そんな日々が長くは続かなかったのは、まだ良かった。遅くなってしまったけれど、こうして、ただいまとおかえりのやりとりもできた。
「ドラクマはどんな国でした?」
彼は顎に手を添えながら、視線を上げて答えた。
「そうですね、寒さはこちらとほぼ変わりません。街並みも良いですし、物価もそれほど高くない。男尊女卑は、多少目立ちましたがね」
「なるほど……そうなんですか」
「建物のすべての部屋に暖炉がありました。窓はこちらと同じく二重構造でしたね。それから、人々は毛皮の帽子を被っているんです。実用的であり、ファッション性もある。ブリッグズでも流行りそうなものですが」
「ふふ、私もひとつ持ってますよ。ところで、お食事はお口に合いました?」
「ええ。ボルシチという煮込み料理をご存知ですか? そうですねぇ、深紅色のシチュー、と言ったところでしょうか。あれは美味しかった。貴女もきっと気に入ると思いますよ」
「そうなんですか! 噂には聞いたことあります。私も食べてみたいなぁ」
「ええ、ぜひ」
そう言いながら、彼は私の頬を優しく撫で始めた。青と黒が溶け込んだ美しい瞳が、私を甘く見つめる。突然のアプローチに戸惑って、つい視線を膝の上の手に落とす。今になっても、見つめられていると思うと、恥ずかしくて顔が熱くなる。そうしていると、頬を撫でていた彼の手が顔の輪郭をなぞるように下りていき、そのまま顎をすくわれる。どこか冷静な、それでいて妙に熱のこもった双眸だった。
「……やっと会えましたね」
「はい……」
声がかすれた。胸の高鳴りも、目がうるんでいくのも、抑えられない。優しい手で肩を抱き寄せられ、身体を預けた。
満たされている。くすんだ絨毯の上や、蜘蛛の巣が張られたむき出しの梁の隙間に、永遠が見えるような気がした。彼とこうして触れ合っている、それだけで。
「アヤ」
「はい、なんでしょう」
「もっと貴女に触れたい」
突然の言葉で、体温が上がった気がした。彼は、照れることも臆することもなく、じっと見つめてくる。
「貴女が欲しい」
手がこちらに伸び、上着のひとつめのボタンをなんのためらいもなくはずした。
「だ、だめです」
「ドラクマにいる間、貴女のことが頭から離れなかった。いえ、独房にいた頃から、ずっと」
ソファがぎしりと音を立てる。背もたれに手をつかれ、私はだんだん肘掛けの方へと押し倒されていく。気が付けば肘掛けを枕にして、彼に組み敷かれてしまった。
「何度くちづけても、身体を重ねても、足りない」
息のかかる距離で告げられ、胸がきゅう、と締めつけられた。
そして、優しくキスをされる。まるで、温かいさくらんぼを食んだような、じんわりとした熱が唇を甘く痺れさせるキスだった。
夢のような甘い時間を、ずっと続けていたい。
けれど、その前に。
「キンブリー、さん」
心をすっきりさせるために、聞かなくてはいけない。本当のことが知りたい。
「どうして、ブリッグズに来たんですか?」
彼は顔色を変えぬまま、いたって冷静な声で告げた。
「無論、貴女に会うためですよ」
「……傷の男を、追ってきたんでしょう?」
彼は黙って、私に喋らせた。
「ドラクマに向かったのも、軍を焚きつけてブリッグズ兵と戦わせるためだって、言ってましたよね。どうして、なんのために私たちを潰そうとなさったんですか」
「潰すなんてとんでもない。言ったでしょう、ブリッグズ兵が敗れるはずはないと」
「それじゃ、どうして」
「これが、私の今の仕事だからですよ」
分からない。分からない。
「それは、なんのお仕事ですか?」
彼は、答えの代わりに、私の上着のふたつめのボタンに手をかける。その手を制した。
「教えてください。でないと……」
「私が信用できませんか?」
「もちろん、信用しています。でも、本当のことが知りた、ひゃっ」
言い終わらないうちに、ざらりとした感覚が耳を襲う。熱い舌が、耳たぶやその裏側を這い、背すじがぞくぞくと甘く震える。
「やっ……あっ」
はぐらかされてはだめだ。ごまかされてはだめだ。ちゃんと、彼のことが知りたい。真実が知りたいのに。
「キンブリーさんっ」
「どうしました」
「もうやめて……」
「そんな声で止められても逆効果ですが」
本気であると伝えるために、彼の胸板を力いっぱい押した。む、と呟いたキンブリーさんは、不服そうに眉をしかめる。
「ねえ、どうして、んっ」
今度はくちづけられる。塞がれてしまっては、なにも聞けない。これ以上なにも訊くなということだろうか。知らず知らずのうちに、涙が滲んでくる。彼との間にまた、絶対零度の氷の壁を感じたからだ。
――このひとを、信じていいの?
初めて自分の心が、ぐらりと揺らぎだした。なにもかもが、分からなかった。
視線を交わすことなく、唇は離れていく。私も彼も、これ以上の行為を続ける気はないというように、身体を離し、視線を逸らして、黙っていた。
しばしの沈黙が、ふたりの間に浮遊する。それを先に破ろうとしたのは、私だった。
「最後に、ひとつだけ、聞かせてください」
声が震える。目のふちに溜まった涙が、あふれそうだ。
「……私のこと、好きですか?」
「アヤ」
ぎゅっと、手を握られる。そうされて、声だけでなく手まで震えていたことに気づいた。
「愛しています、心から愛していますよ」
彼の声は、いつにも増して真剣だった。けれど、その顔を見ることすらできず、私は横顔のまま、涙の粒を落とした。
「貴女に、寂しく不安な思いをさせているのは、重々承知しています。不誠実な私を疑うのも無理はない。申し訳なく思っています」
頬の涙を、彼は優しく拭ってくれた。
「もう少しだけ時間をください。なにもかもが終われば、貴女のもとに戻り、すべてを打ち明けます。そして許されるのなら、もう二度と貴女から離れない。……それまで待っていただけますか」
なにも言えず、ただ頷いた。彼は、私を壊れもののように抱き寄せ、額にキスを落とした。
今はなにも教えてくれない。そしてまた、どこかに行ってしまう。それなら、こんなに優しくしないで欲しい。哀しみが深まっていくだけなのに。
触れ合っているのに、こんなにも寒い。ひどく、寒かった。
任務中に脱走したことで、案の定、上司から厳しいお咎めを受けた。罰として、今はひたすら雪かきをさせられている。
かじかんだ手に力を込め、ひたすら無心にスコップを動かす。除雪しても除雪しても、きりがない。一息入れようと手を止めて、スコップを雪の中に立てた。真白い雪を眺めて、あの人の色だ、とぼんやりと思う。ソフト帽、スーツ、コート。すべて雪の色をまとって、ここに現れた。そして、行ってしまった。
去り際に微笑みを浮かべ、脱いだ帽子を軽く上げたまま歩き出した、あの人。今度はいつ、会えるのだろう。
気づけば、涙がすうっと頬を滑っていた。
早く戻ってきて。頬の涙が凍ってしまわぬうちに、あなたへの想いが凍りついてしまわぬうちに。
果てしなく遠い空までもが、彼の色に染まっていた。
(了)20161201
(改)20190115