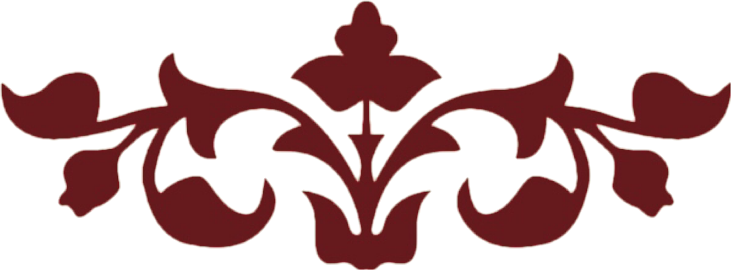
レゾンデートルと黄昏と
六年半ぶりに中央司令部の門前に立った。北門は壊れ、司令部の建物は半壊している。それだけでも衝撃的だが、さらに信じられないのは、エントランスに続く道いっぱいに巨大な穴が空いていることだ。
現在は修繕工事中ということだが、変わり果てた元職場は、イシュヴァール戦の終結を想起させる要素であふれているように思えてならない。
「ほんと、派手にやってくれたよな」
その声に振り返れば、金髪金眼の強気な雰囲気をまとう少年が立っていた。エドワード・エルリック。キンブリー元中佐と一時行動をともにしていた、国家錬金術師だ。
立ち並ぶ街路樹の梢がざわざわと揺れている。冬枯れのその中を私たちは歩く。
三つ編みではなくただ髪を束ねたエド君は、キンブリーさんのようにコートのポケットに手を入れたまま、私の話に耳を傾けていた。
イシュヴァール戦後、私は中央から北方へと左遷された。心ない軍人たちには、元上官の愚行の連帯責任だな、とわざと聞こえるように言われたりもした。実際、その通りなんだろうけれど。
私は必死に働いた。がむしゃらに走り続けて六年後、終身刑を言い渡されたはずの元上官がまさかの釈放になり、念願叶っての再会をすることができた。
しかし、喜んだのも束の間、キンブリーさんは北での用を終えるとすぐに中央に戻ってしまった。後を追いたくてもブリッグズから離れることはできない。
悔しさを滲ませながらも仕事に励んでいたある日――皆既日食の日のことだ。書類の仕分けをしていたとき、突然息ができなくなった。それに加え、まるで世界中の人々の強い苦しみをひとつにしたような、激しい苦痛が流れこんできた。どういうわけか、床からは無数の黒い手まで生えてくる。
ただごとではない。この現象はなに、と考える間もなく、苦しさに耐えきれずにとうとう椅子から滑り落ちた。意識が遠のいていくことに抗ったが、むだだった。大切な恋人の名前を呼ぼうとしたが、それも叶わず、私の記憶は途絶えた。
意識は無事に戻った。時計を見ると、しばらくの間気を失っていたようだった。恐怖のあまり動けなくなっていた私を、ある中尉が見つけてくれた。後から聞いた話では、どうやら、気を失ったのは私ひとりではなく、皆同じ体験をしていたらしい。
その翌日、キンブリーさんが中央病院に搬送されたと知った。私が彼を気にかけていることを知るアームストロング少将が、こっそりと教えてくれたのだ。いても立ってもいられず、すぐさま休暇届を出し、特急列車に揺られ、ここ中央に戻って来たのだった。
「ふーん、じゃボロボロのキンブリーを見に、わざわざ北方司令部からやって来たっつーことか」
「ボロボロ!?」
「死んでいてもおかしくないな」
そんな、そんなにひどい状態なんて。ぐらりと、眩暈がした。
歩みが止まる。エド君は私の一歩手前で止まってこちらを見た。勝気な金の瞳に、さらに鋭さが増す。
だが、声音は穏やかになった。
「まあ、ついてこいよ」
病院特有のどこか金属くさいにおいがする。私はこのにおいがいくつになっても苦手だ。
中央病院内では、点滴バッグを繋いだ患者たちがのろのろと院内を徘徊しているのとは対に、ナースシューズの靴音をせわしく鳴らす看護師たちがいた。
「おい、ちょっと待てよ中尉」
「エド君はゆっくりでいいよ」
私たちはその看護師たちより大股で歩を進め、受付で案内された病室へ向かおうと急いだ。移動中の執刀医と見舞いに来た家族が、ぎょっとした形相でこちらを振り返ったが、気にしない。
「一三〇七……一三〇七……ここね」
一三〇七号室の部屋前のプレートには、確かにあの人の名前が書いてある。
「俺はここで待ってるから。後で話したいことがあるんだ」
少年は向かいのラウンジの丸椅子に腰かけ、そばのブックスタンドから適当な雑誌を手に取った。その手は機械鎧ではなく、普通の手。
気になるけれどその話は後で聞こう。今はあの人の安否しか頭になかった。
カラカラと、個室の引き戸が鳴った。薄緑色のカーテンが、窓辺でふんわりと控えめに揺れている。耳を澄ますと、ラジオ・キャピタルのパーソナリティがひとり静かに喋っていた。
「……失礼します」
声をかけたが返事はない。私はなるべく足音を立てないよう、そろりと歩いた。
白いカーテンの奥でベッドの脚が見える。掛布団が見える。薄鼠色の服が、包帯とギプスで矯正された白い首が、そして確かにあの上官の若干やつれた顔が見えた。
キンブリーさんは、こちらを呆然と見ていた。
「しょうさ……っ!」
夢中でそばまで駆けて行った。ボロボロだと聞いていた、死んでいてもおかしくないとさえ。それなのに、あなたはまだ私を待っていてくれた。私を置いて行きはしなかった。
彼はなにも言わない。その代わり、口元に笑みを湛えて私をじっと見ている。固定された首は動かせないらしい。彼は視線をこちらにやり、涙に濡れた私の頬に手を小さく伸ばした。
優しい手つきで頬をひと撫でされ、私はもう一度少佐、と呼んだ。人間、夢中になると、慣れ親しんだ呼び名の方が自然に出るらしかった。
「しょ、さ、しょさ。無事、で本当に良かっ……」
嗚咽がもれる。大の大人がかっこ悪い。だがそんなことはもう、どうでも良かった。
シーツに伏して嬉し泣きを堪えられずにいると、少佐は赤子をあやすように頭を撫でてくれる。その行為にただただ、甘えていた。
「少佐、私、不安で仕方なかったんです。少佐にもしものことがあったらと思うと、もう……。でも、またこうしてお会いできて、本当に、本当に嬉しくて……」
またもや返事がない。
「あ……私ばかり喋ってごめんなさい。あの、お体の具合はどうですか。首にギプスって、つらいですよね……。お医者さまはなんと?」
やはり返答はなかった。全身から血の気が引いていくのを、まざまざと感じた。
彼は枕元に置いてあるメモ帳とペンを掴み、なにかを書きだした。私はぞっとする思いで彼を見つめる。鼓動が速くなる。
もしや、彼は。
『頸椎と声帯を損傷しました。残念ですが肘は満足に伸ばせず、声も出ないのです』
残酷な文章が、そこにはあった。
声が、出ないなんて。
私まで言葉を失った。かけるべき言葉がひとつも見つからない。少佐の声がもう聞けないなんて。それに加え、腕も満足に動かせないなんて。
あの皆既日食の日の得も言われぬ苦しみを、また思い出した。あのときよりも、つらい。
励まさなくては。きっといつかは良くなると。大丈夫ですよと、言ってあげなければ。
けれど、そんな無責任に気休めの希望は語れない。
ペンの走る音がする。少佐は再度メモ帳に書いた文を見せた。弱々しくも、整った流麗な字だった。
『世界は私を選んだのでしょうか』
私はその文を二度読んだ。そこには嘆きでもなく、怒りでもない言葉があった。彼は虚空をじっと見つめている。
なんて声をかけるべきなのだろう。逡巡するばかりで、なにも気の利いた言葉が思い浮かばない。そして、深く考えられないままこの口が軽率に、賛同の言葉を発した。
「選ばれたのだと思います、きっと……」
少佐は眉をひそめる。紙を捲り、白紙に反論文を書き連ね始めた。
『この身体で生きてゆけと?』
『こんな醜態を晒さねばならなくなったというのに』
『今のこの状態の私を世界は認め、この身体で生きてゆけと言うのでしょうか?』
「……少佐」
点滴チューブを繋いだ腕が、だらりと落ちる。もう、なにも言えなくなった。
書き殴られた字は、反論文でもあり、自分自身や、私でない誰かにやり場のない怒りをぶつけて問うているようで、それが一層私の心に影を落として締めつける。
いっそ、罵ってくれればよかったのに。それで楽になるなら、よかったのに。
彼はゆっくりと目を閉じる。
耳を、心を閉ざしてしまう前に、今の私の気持ちを告げたい。たとえそれが、なんの意味もなさなかったとしても。
絞り出すような声で、彼を呼んだ。
「先ほどの質問、やっぱり私には……分かりかねます」
ですが、と私は続けた。
「たとえ世界が少佐を選ばなくても、私は少佐を……あなたを選びました。それだけでは、だめでしょうか」
窓から吹きこんできた風が、カーテンをやわらかく揺らしている。春の訪れる匂いを連れて。
毒突かれても良い。なにを言い出すかと呆れられ、一蹴されてもかまわない。今、伝えたいことはちゃんと告げられたのだから。
少佐は依然として表情を動かさないまま、深呼吸をする。布団が少しふくらみ、またへこんだ。
そのとき、彼の目尻に光るものが見えた。それはすうっとこめかみを伝い、やがて髪の生え際に隠れてしまった。
彼の涙を、初めて見た。
内心でおろおろする私を知ってか知らずか、彼は閉じていた瞳を開き、再度ペンを走らせる。
『アヤ』
そこに私の名があった。
「は、はい」
『ありがとうございます』
それだけを書くと、彼はかすかな笑みをこちらに向けた。
私の中のなにかがあふれだす。視界がまた滲み、少佐の顔がまたぼやける。本当に、今日は泣いてばかりだ。
けれど、これでいい。これで良かったんだ。
浅く息を吸い込んで、彼に微笑みかける。
「……少佐、あの日の約束を覚えておいでですか? イシュヴァール戦で私が負傷したときにお約束したことを」
『もちろん』
『以前よりも長く濃い時間を過ごすこと、そのために必ず生きて帰ること』
『でしたね?』
私は笑った。
「良かった、覚えていてくださっていて……。長く濃い時間、一緒に過ごしましょうね」
『ええ、必ず』
必ず。
その字を見て、泣きながら笑った。彼も静かな微笑を返してくれた。
もう絶対にこの人から離れたりしない。
彼とともに、生きたい。
また来ます、と言って名残惜しくも病室を出た後、ラウンジにいるエド君のもとに行った。
彼とは小一時間ほど話をした。なにも知らなさそうな私を見かねてか、エド君は重い口を開いた。それはとても衝撃的な話だったが、なによりも大事な話だった。
キンブリーさんが、
エド君は、あいつに関わって大丈夫なのかよ、と心配してくれた。私は、小さく頷いた。
戸惑いがないわけではない。これから時間をかけて、消化していかなくてはいけないと思っている。
けれど。
「大丈夫。信じているから」
エド君は、そうか、と呟いたきり、黙ってしまった。
「しょ……中佐の怪我を、治す方法はあるのかな?」
「ないこたぁねえけど……」
エド君は、中佐も使ったことがあるという伝説の代物、賢者の石の存在を教えてくれた。戦いで視力を失ったマスタング大佐も、その石の力を使って視力を取り戻す予定だという。
一縷の希望が見えた。これがあれば、キンブリーさんも、きっと。
私は、彼の身体を元に戻してもらうよう、必死に頼んだ。
エド君は渋りながらも、条件付きでこれを承諾してくれた。そこで出された条件は、むやみに爆破しない、イシュヴァール人をはじめ、これ以上人を殺めないことだった。
「悔しいけど、あいつには借りがある。一度、危ないところを助けてもらったんだ」
「そう、なんだ」
足を組みかえた彼は、私が買ってあげたコーラをぐぐっと飲んだ。彼らになにがあったのかは分からないけれど、キンブリーさんにとって敵であるはずのエド君を助けたこと、それが分かって少し安心した。
窓外に広がる中央の風景を見下ろした。建物が密集しているにもかかわらず、どこか閑散とした印象を覚えた。
「……私ね、中佐からなんにも大切なことを聞かされてなかった。賢者の石を持っていたってことも、北方になにしに来たかも、人造人間側についていたことも。内乱後、北方司令部で再会したときも、なにひとつ教えてもらえなかった」
暗くならないよう、微笑むことを心掛けた。
「それが少し寂しいの。仮にもその、彼のこいび……副官だったのに」
眼下には半壊の中央司令部が見える。私と中佐の、かつての仕事場だ。
「私、信頼してもらえなかったのかな」
この建物のように、いつの間にか私たちの間にも、ヒビが入っていたのかもしれないと考えると――。
「心配かけたくなかった」
はっとして彼の顔を見る。エド君は、いくらか早口で言葉を続ける。
「ほ、ほらっ、大切なひとほど心配させたくないんだよ、男ってやつは。……キンブリーも同じだったんだろ」
「そう、かな」
「ああ」
「……ありがとう。エド君」
お、おう、と返事して、照れくさそうに視線を逸らしたエド君は、頬をぽりぽり掻いている。優しく頼もしい彼の姿を、感謝のまなざしで見つめていた。
心配をかけたくないからなにも言わない。そういえば、私自身もそんなところがある。エド君の読み通りかもしれない。
そうでなければ、あのイシュヴァール戦での約束だって、覚えていないはずだ。エド君の言葉に納得すると、自然と頬が緩んだ。
いつの間にか、ラウンジにはオレンジ色の温かな光が差し込んでいた。夕日に照らされた彼の金色の髪が、なんだかまぶしく見える。
「エド君の髪、綺麗だね」
「ラシャード中尉も良い色に染まってんじゃん」
そろそろアルを迎えに行かないとな。少年はそう言って、立ち上がった。
ふと、自分の毛先をつまんでみた。私のそれも、夕日をほのかに反射させてきらきらと輝いている。たったそれだけで、少しだけ嬉しくなった。
(了)20160426
(改)20190115