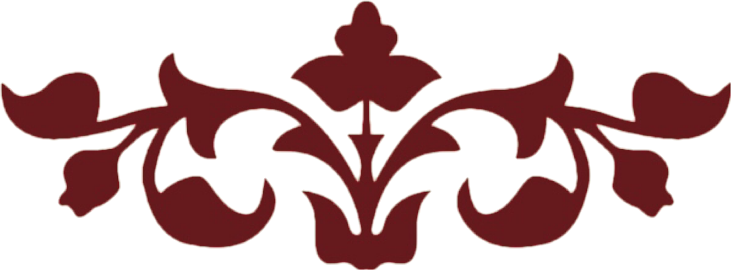
両掌 のふたり
いつものようにポストを覗き、朝刊を取り出す。新聞のほかに、今日は水道屋のチラシと一枚の絵ハガキが入っていた。送り主は、なんとエド君。驚いた。どうやって私たちのことや、新居の住所を知ったのだろう。
ハガキの中のエド君は、屈託なく笑っていた。隣にいる青年は初めて見るけれど、アル君だろうか。見るからに優しそうな人だから、きっとそうなのだろう。
ふたりの笑顔を見て、私の口元も自然に綻ぶ。元気そうでなによりだ。特にエド君は、初めて知り合ったときよりもなんだか大人びていて、身長も伸びている気がする。男の子は突然急成長して周囲を驚かせるけれど、まさしく彼もその例に倣っていた。
ハガキをくるりと裏返して表を見ると、なにやらメッセージが書いてある。
『風の便りで聞いた。中尉、結婚おめでとう。お幸せに』
まさか、彼から祝福されるとは思ってもみなかった。ありがとう、と呟き、写真の彼に微笑んだ。
新聞を小脇に抱えて自宅に戻り、ダイニングで食後のコーヒーを飲んでいるゾルフに新聞と絵ハガキを見せた。ゾルフは頷き、しばらくそのハガキを眺めていた。
「表に、あなたへのメッセージが書いてありましたよ」
彼は表面のメッセージを目で追う。
『キンブリー。約束の日に手助けしてくれて、どうも。でも、中尉泣かしたら、タダじゃおかないからな。覚えとけよ』
約束の日とはいつのことだろう。内容は分からなかったが、最後の文章にエド君らしさが滲み出ていて、ついくすくす笑ってしまう。
「エド君のこと、助けてあげたんですか?」
ゾルフに聞けば、彼は手帳に一言こう書いて、薄く微笑む。
『さあ、なんのことか分かりませんね』
――その健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか。
この神父さまの言葉を聞いたのは、一ヶ月前のことだ。私たちは神のもとで、とこしえの愛を誓い、キスを交わした。夢のような結婚式の様子や、まぶしさを覚えるほど似合っていた白のタキシード姿を、目を閉じて繰り返し思い出す。
家族や友人やかつての同僚に祝ってもらった後、ふたりで披露宴をこっそり抜け出したりもした。少しの間だけで良いからふたりきりになりたい、と私が言ったからだ。本当は主役が抜けるなんてだめかもしれない。けれど、どうしても晴れ姿の彼に触れたかったのだ。
人目を気にする心配のない建物の裏で、ゾルフと手を繋いだ。額にキスもしてもらった。そして、いつもの手帳を見せてもらうと、そこには私へのメッセージが書かれてあった。
『今日の日を貴女と迎えられて、とても嬉しく思います』
『私の右手に刻まれている太陽を見ると、いつも明るく頑張る貴女を思い出します。アヤ、いつまでも私の太陽でいてください』
思わず口元を覆った。そんな、嬉しいことを言ってもらえるなんて。感激のあまり彼に抱きついた。ポマードの匂いがふんわりと香った。
彼がそう言うのなら、私は太陽になろう。悲しいことやつらいことがあっても、やるせなさに苛まれても、いつでも明るく笑って彼を照らそう。そう、温かい腕の中で誓ったのだった。
それから、一月が経つ。結婚生活はすこぶる順調だ。ケンカは今のところまだしていないし、気まずくなったこともない。料理の腕は期待しないで欲しい、とあらかじめ断っていたせいか、手料理への文句もまだない。ずっと一緒にいられることがただ幸せで、相手に対する注文もなかった。ただ、夜の営みが思った以上に多くなり、睡眠不足と腰痛ぎみになってきたことだけが悩みだ。
結婚を機に軍を退役した私は、近くの養鶏所で働いている。ゾルフは、国家錬金術師時代の莫大な研究費を貯蓄してあるから私まで働く必要はない、と言ってくれたが、それには首を横に振った。気持ちはありがたいけれど、私は家にずっといるよりは外に出て働く方が性に合っているし、なにより、彼に甘えてばかりいられない。だから、昔から大好きなひよこや鶏たちに囲まれながら、忙しくも楽しい毎日を送っている。
ゾルフは、自分の錬金術を活用できる職業を選んだ。主に、橋や煙突、高層ビルなどを爆破して解体する仕事や、油田がある地域に火災が起きたとき、爆風で炎を吹き飛ばす爆風消火の仕事をしている。爆破好きの彼にとっては、まさに天職だ。いわゆるフリーランスだけれど、ダイナマイトの購入やその費用は必要なく、爆破の規模を思いのままに調整でき、なにより爆破技術専門の元国家錬金術師が手掛けるという点から、方々から声がかかっている。国家錬金術師が嫌厭される風潮は、確かにある。それでも、依頼が来ることについて、ゾルフは「大方、『軍の狗が飼い主の手を噛んで、民衆のためにやっと働く気になった』と思い込んで仕事を頼んでくるのでしょう」と推測している。
ちなみに三日前は、道路を塞いでいた巨大な落石を破壊しに行き、今日はイーストシティ郊外にぽつんと建っている、廃墟と化した倉庫を爆破して欲しい、との依頼を受けに行くのだとか。依頼者からの電話を取るのは私で、内容と報酬を聞いて仕事を請け負うか彼に確認してから返事をする。倉庫の依頼を受けたとき、彼は意味ありげに手帳にこう書いた。
『好きですよ。倉庫を爆破させるのは』
彼がこの職業を選んだ背景には、彼自身の興味に加え、私とエド君とドクターマルコーの願いも込められている。以前、ゾルフのお見舞いに初めて行った後、エド君と話をしたときに「むやみに爆破しない」「イシュヴァール人をはじめ、これ以上人を殺めない」ことを守るのなら、賢者の石を使っても良いと言ってくれた。結局は、彼が紹介してくれたルートから賢者の石を手に入れたわけではなかったのだけれど、エド君の思いを引き継ぎ、ゾルフには「人を傷つけることはしないで」とお願いした。ドクターから聞いた、彼が人殺しをさせられていたことは、まだ知らない設定なのだ。ゾルフがいつか、自分の口から本当のことを話してくれたら良いのだけれど。
彼を真っ当な人間に更生させて欲しい。過ちを認め、贖わせて欲しい。殺しとは無縁で、人々のために残りの命を使えるような人に変えて欲しい……。ドクターマルコーと約束したことも、ちゃんと心にとどめている。今の仕事は、ちゃんと人のためになる。仕事で彼の錬金術を使っているのだから、あまりストレスも溜まらないはずだ。欲望のままにむやみになにかを爆破することもないだろう。
ドクターに誓った通り、彼の心を変えるために、まずは自分が変わろうと決意している。けれど、情けない話、本当に彼を善い方向に導くことができるのか、彼の悪魔をどうしたら沈められるのか、思い悩んで弱気になる日もある。それに、まずは自分が変わるんだと言っても、どのように変われば良いのか、分からない。ただ物分かりの良い、完璧な良妻になれば良いのか。結婚式の日に決めた、太陽のようにいつでも明るく笑っている妻であれば良いのだろうか。
結婚から一月、まだ結論は出ていなかった。
玄関の姿見をチェックした後、靴を履く姿を見守る。準備のできた彼に、微笑んでかばんを差し出す。
「行ってらっしゃい。お仕事、頑張ってくださいね」
普段ならそのままかばんを受け取り、行ってきますのキスをしてくれる。けれど、今日は私の顔をじっと見つめている。心配になって声をかけると、彼は靴箱の上のメモ帳にペンを走らせた。
『顔色が優れないようですね。つらくありませんか』
確かに彼の言う通り、鏡に映る私の血色は良くない。さっきまでは普通だったのに、どうしてだろう。仕事やら睡眠不足やらで疲れが溜まっているのかもしれない。ちょうど、今日は休日だ。せっかくだから、のんびりゆったり過ごそう。
『今日は羽を伸ばして、ゆっくりお休みなさい』
「はい、そうします。あなたもお気をつけて」
彼は私の髪を触り、毛先にキスを落とした。そして、かばんを受け取り、出かけて行った。
家事を一通り終わらせた後、紅茶を淹れて一息つく。さっきから大あくびが止まらない。紅茶を飲み終わったらお昼寝しようと決め、テーブルの隅に置いてあるメモ帳に手を伸ばした。
これは、ゾルフの使い終わった筆談用のメモ帳だ。勝手に読んでも良いと許可はもらっているし、彼と婚約してからわがままを言って、これらのメモ帳の山は譲ってもらった。今では、ひとりの時間にこれを読むのがひそかな楽しみになっている。このメモ帳はちょうど、十冊目のようだ。
これには、看護師さん、医師、そして私との会話の記録が書かれてある。といっても、彼の言葉しか書かれていないのだけれど、私にとってはそれだけで十分だ。内容は、他愛ないやりとりから、ちょっとした冗談、真剣な話などなど。読んでいると、病院での会話が様々思い起こされた。ときおり、会話ではなく彼の呟きのような言葉を目にする。「彼女の声が聞きたい」「少し髪を切ったようだ。似合っている」「もうすぐ彼女が来る時間」と書かれてあるのを見たときは、思わずどきっとしてしまった。
彼の退院日で、このメモ帳は使われなくなったんだろう。看護師と医師へのお礼の言葉を述べた文章の後はなにも書かれていない。そういえば、それ以降は手帳に言葉を書くようにしていたのを思い出す。一応、メモ帳の終わりの方までぱらぱらとページを捲ってみる。楽しみが終わってしまったなあ、などと思いながら。
最後の方に差し掛かったときだ。彼の字がぎっしり詰まったページを発見した。一番上には『愛するアヤへ』と書かれてある。また、胸がどきりと音を立てる。つまり、私への手紙だ。一体なにが書かれてあるんだろう。逸る気持ちを抑えながら、達筆の文字を追った。
愛するアヤへ
見つかってしまいましたね。
貴女にこのメモ帳の山が欲しいとリクエストされていたことを思い出し、本の後書きを執筆するように、夜ふけにこっそりとペンを執っています。しかし、いくら会話の記録といってもここには私の言葉しかないというのに、そんなものを欲しがる貴女は、物好きですね。
せっかくですから、いくつか言っておきたかったことをこの場を借りてお伝えします。まず、謝罪を。これまで貴女に、大切なことをなにひとつ伝えていなかった。特に、出所後の仕事の話は、一から十まで内密にしていましたね。様々な疑念を抱いたことでしょう。不安な思いをさせてしまい、本当に申し訳なかった。
正直にお話ししましょう。私は、人造人間と呼ばれる、人ならざる人たちと手を組んでいました。なんのためか。それは、我欲を満たすため、ただそれだけでした。これまで、傷の男の捜索や、貴女がたブリッグズ兵とドラクマ兵の戦いを扇動し「血の紋」を刻む行為、そして、私たちの行動を阻止しようとする輩を排除しようとしてきました。約束の日が終わるとともに、これらの仕事も終わりましたよ。
約束の日とはなにか。貴女も経験したでしょう、皆既日食の日のことです。人造人間たちにとって非常に大切な、そして、世界が大きく変貌するかもしれない、可能性に満ちた日でした。まあ結局は、鋼の錬金術師とその仲間たちが奴らの野望を食い止め、平和な日常が戻り、めでたしめでたし……となりましたがね。
その約束の日に、私は攻撃を受けて首を負傷しました。例の怪我です。致命傷を負いましたが、さらにその状態で、ある人造人間の体内に取り込まれてしまった。つまり、私は一度死んでいます。鋼の錬金術師がその人造人間を倒さなければ、私は一生その身体から脱出できなかったでしょう。
気がつけば、中央の地下で倒れていました。幸いにも、救助隊に発見され、そのまま病院に搬送されました。肘は満足に動かず、声もでない状態でしたが、貴女に励まされ、今日まで生きてこられた。ドクターマルコーは私を治療することを拒んだはずです。渋る彼を貴女はどのように説得したのでしょう。本当に、頭が下がるばかりです。
実は、約束の日を迎えるにあたって、人造人間側にあることを要望していました。きたるべき日が来て人造人間側が無事、ことを成し遂げて人間側が滅んでも、貴女だけは救うようにと。それが不可能であれば、私の爆風でともに心中しようと考えていました。……改めて考えると滑稽ですね。貴女と生きたかったというのに、なぜ自ら破滅の道を選んでいたのでしょう。私たちの幸福が
私はずっと、自身を異端な存在だと認めて生きてきました。世間一般の人々とは異なる考えを持ち続けていた私が、人並みの幸せを手に入れられるなどとは到底思えなかった。ですから、自分が幸せになることに一種の恐怖を覚えていたのです。イシュヴァール戦終結時に収監されたのも同じこと。貴女との幸福な日々をもっと過ごしていたい、その気持ちは真実でしたが、本当はその幸せの大きさに怯えて、罪を犯した。私は自ら鳥かごに入る、諦念に満ちた臆病な鳥だったのです。
ですが、貴女はいつもどんなときも私を待ってくれていた。六年の間、いや、その後も仕事で忽然と姿を消す私を、辛抱強く。病院に搬送されて動けなかった私を、迎えにまで来てくれた。『たとえ世界が少佐を選ばなくても、私は少佐を、あなたを選びました。』貴女のこの言葉に、どれほど救われたことでしょう。そのとき、なにが起きても貴女を守ると、もうふたりの幸福から逃げはしないと、固く心に決めました。
過去の私がこの手紙を読めば、笑うでしょうね。愛などくだらないと一蹴してきたというのに。私には必要ないものだと、諦め、怯え、目を背けてきたというのに。貴女に出逢って、その価値観すら変えられてしまいましたよ。
先ほど述べた通り、私は一度死んだ人間です。ですから、二度目の人生は、貴女を幸せにするためだけに生きたい。
私は今、確かに幸福を実感しています。もう二度と、それから距離を置いたりはしません。
明日はいよいよ、私たちの結婚式です。貴女の綺麗な晴れ姿を、ずっと心待ちにしていました。今夜はちゃんと眠れるでしょうか、それほど楽しみです。忘れられない、最高の一日にしましょう。
愛する太陽が私の胸の中を、日々を、未来を、温かく照らしています。貴女という、まぶしい太陽が。
いつかこのページを開く貴女へ 心からの愛をこめて
――ゾルフ。
気づけば涙をこぼしながら、メモ帳を抱きしめていた。狂おしいほどの愛しさや感謝が胸を突き上げている。ありがとう、とか、愛している、といった言葉では、伝えきれないほどの強い気持ちが湧き上がってきて、もう一度名前を呼んだ。
湧き上がってくるのは、プラスの感情だけではない。彼の苦悩に気づいてあげられなかった自分への腹立たしさや、葛藤しながらも隣にいてくれた彼への罪悪感もある。ありあまる幸せを感じ、自分だけがのんきにはしゃいでいた、という事実に恥かしくもなった。一緒に過ごしてきたというのに、大切な彼のことを全然理解していなかった。様々な気持ちがないまぜになり、少し混乱している。
けれど、やるべきことは決まった。涙を拭い、頷く。
彼にお返事を書こう。今の私の気持ちを正直に書こう。この胸の内のように、ぐちゃぐちゃで支離滅裂な文章になってしまうかもしれない。けれど、伝えたい言葉があるから。あなたに知ってもらいたいから。怯えないで、って。幸せになっても良いんですよ、って。
ふたりで心から幸せになりましょう、って。
ペンと便箋を取りに行こうと立ち上がったそのとき、床がぐるりと一回転し、目の前が白くなった。
「アヤっ!」
頭がぐらぐらする。お尻や掌が痛い。ぶつけたのではく、どうやら尻もちをついたようだ。
――いや、そんなことより、声がした?
「アヤ、大丈夫ですか」
どうしてここにいるのだろう、ゾルフがすぐさま走り寄ってきてくれた。しゃがみこみ、視線を合わせてくれる。大げさなほど、血相を変えて。
「あなた、声が戻ったんですね。良かった……」
「ええ、しかしそんなことより、怪我はありませんか」
「はい平気です。でも、どうしてこんなに早く?」
「今朝の様子がどうも気になって、急いで帰ってきたんですよ」
「ありがとうございます。大丈夫ですよ、慣れてます。最近、こんなのばっかりですから」
微笑んでみせると、彼は目を丸くした。そして、私の両肩を掴んだ。
「……なぜ言わなかったんです」
「なぜって、あなたもそういうふうにして私を気遣ってくれていたでしょ?」
だから、と続けようとすると、強い力で抱きしめられた。
「今すぐ病院に行きましょう。今すぐに」
私たちは、東部一と名高い総合病院に向かった。予約もなしに診てもらうことになったので、そこで数時間待ち、それから診察してもらった。
男性の医師は言った。
「脳貧血ですね。疲れが溜まっていたのかもしれません。意識して鉄分を多く摂ってください」
貧血、か。通りで血色が悪かったのか。納得しつつ、重い病気ではないと分かり、胸を撫で下ろす。
「それから、新婚さん、でしたね。でしたら妊娠している可能性もありますよ」
えっ、と声が出た。思わず目をしばたたく。
そういえば、月経が来ていなかった。元々不順気味だから、それほど気にしていなかったけれど。思い当たる夜は何度かあるし、もしかして本当に……?
「産婦人科で診てみますか」
「はい」
今度は三階の産婦人科に行き、妊娠検査を受ける。診察室に入る頃には、廊下の大きな窓から西日が差し込んでいた。
待合室で、ゾルフは神妙な面持ちで指を組み、じっと座っていた。私が診察室から出てくると、彼は即座に立ち上がり、どうでした、と尋ねた。
「あなた」
背伸びをして、耳元でささやく。
――赤ちゃんができました。
そのときの彼の、悦びの矢に射貫かれたような横顔!
「そうですか……そうですか!」
眉根を寄せて目を閉じ、微笑んでいる。まるで、湧き上がる喜びと涙を抑えるように。
人目もはばからず、彼は抱きしめてくれた。笑みがこぼれた。
「ふふ、八週目だそうですよ」
「ええ、ええ……ありがとう」
目頭を押さえながら、彼は深く頷く。私たちは、しばらくそうして喜びを分かち合っていた。
自分の身体にもうひとつの生命が宿っている。実感はまだ少ししか湧かないけれど、嬉しい気持ちと同時に芽生えたのは、母になることへの漠然とした責任感だった。少女が大人になるように、妻から母へと変わっていく。その準備をしておかなければ、と思った。
列車に揺られながら、優しくお腹を撫でる。あなたは男の子だろうか、女の子だろうか。ゾルフに似ている? それとも私に? いつ、会えるかな。
楽しみですね、とゾルフは微笑んだ。
そう、今日は二度も奇跡が起こった。まさか、あのタイミングで彼の声が戻るなんて。待ち望んでいた声を、また聞くことができるなんて。その喜びで改めて胸がいっぱいになる。
「ねえ、あなた、もっともっと声を聞かせてください」
「ええ。なにについてお話ししましょうか?」
ぱっ、と言葉が返ってくることすら嬉しい。その声を聞いているだけでも十分、満たされる。
「なんでも良いんです。なんでも……」
腕を絡ませて、重い瞼をゆっくりと閉じた。
「――アヤ、アヤ。着きましたよ」
彼に名前を呼ばれて、目が覚めた。ほっとしたのか、いつの間にかうとうとしてしまったようだ。
夢じゃない。ぜんぶ、現実だ。
名前を呼ばれる、その幸せを心から噛みしめながら瞼を擦った。
列車から降りると、真っ赤な夕焼けが広がっていた。まばゆい夕日に照らされながら、私たちは帰途につく。
新たな生命が息づいている、と診察された帰り道に、夕日の中を歩く私たち。まるで映画の主人公のようだ。そのまま町を一望できる高台に上がって、愛をささやき、見つめ合い、キスをする……。
そこまで想像して、つい口元が緩んでしまう。なんてロマンチックなんだろう。
そのうっとりとした気分を、腹の虫が台なしにする。その鳴き声の大きさを、私は笑ってごまかすしかなかった。
「そういえば、ふたりとも昼食を食べていませんでしたね」
ゾルフが思い出したように言った。
「少し早いですが、夕食にしましょうか。駅前に、あなた好みの美味しいレストランがありましたね。今日はお祝いしましょう」
「はい。声が戻ったことも併せて、お祝いしましょうね!」
改札を通り抜けると、あの赤い夕焼けが私たちを待っていた。太陽は、遠くの山並みに半分身を沈めている。湯船に鼻先まで沈めてぶくぶくと泡を出す、小さな子どものように。駅前には、偉人の銅像を囲むようにしてベンチが並んでいる。レストランに向かう前に、少しだけお話ししたいことがあるんです、と言って、ふたりで腰を下ろした。
夜が近づくにつれ、日中の暑さを忘れた空気がひんやりと漂いだす。涼しい風が、半そでから覗く腕をかすかに撫でて消えていった。
彼の背後の空に、三日月がうっすらと浮かんでいる。私のイメージした通りだ。
「メモ帳の最後のお手紙、読みました」
「そうでした、か」
彼は一度微笑み、自分の手元に視線を落とした。私はその、月の錬成陣が描かれた左手に触れた。
「私のこと、太陽って言ってくださいましたよね。それなら、あなたはお月さまです。私をいつも温かく見守ってくれる、優しいお月さまです」
軽く握られていた、彼の右手をゆっくりと開く。太陽が顔を出した。
「そうすると、この両手には私たちふたりが刻まれているということですね」
彼は微笑む。私も、はい、と返事して笑った。
そして、右手で太陽の手を、左手で月の手を、指を絡ませて握った。彼は私と、繋がれた手を交互に見る。
「私、お月さまを照らせる太陽になります」
そう言って、微笑む。
「あなたが苦しいとき、涙を流したいときに、そばに寄り添いたいんです。そのとき、大丈夫ですよって、心配なさらないでって、大きな幸福や不幸に怯えなくても良いんですよって、伝えたいんです。ふたりでいれば、きっと心から笑える未来がやってきます。それに、三人になれば、もっともっと心が満たされる日々がやってきますよ」
彼は、まばたきさえせずにこちらを見ていた。ぎゅっと、繋いだ手に力を込める。
「あなた、幸せになっても良いんですよ。……一緒に幸せになりましょう?」
変わりたい。あなたの苦痛を半分にし、喜びを二倍に変えられるように。あなたと、生まれてくる生命を、誰よりも幸せにできるように。
変わりたい。いや、私は変わる。
覆い被さる雨雲に屈しない太陽になる。暗い夜を乗り越え、何度でも何度でも空を昇る太陽になるんだ。
ふっ、と彼は空を仰いだ。そのまま目を閉じている。まるで、心を沈めるように、涙を閉じ込めるように。
やわらかな風が吹いた。木々が葉を揺らしてざわめいている。ゾルフの結った髪もさらさらと、揺れている。
「……まったく、貴女には敵いませんね」
私と視線を交えた彼の口元には、いつもよりも穏やかな笑みがあった。
「しかし、ひとつだけ勘違いしていることが」
「えっ、な、なんでしょう」
彼は、私の両手を優しく握り返した。
「夜に浮かぶ月が光っているように見えるのは、太陽の光を反射しているからです。月はずっと、太陽に照らされているのですよ」
そうだったんだ。的確に想いを伝えようとしたのに、無知がばれて、なんだか恥ずかしい。
「すなわち、私はすでに、貴女に照らされているのです」
月は、私を映しだすその目を細めて、優しく笑った。
「もうずっと前から、貴女に照らしてもらっているのですよ」
「ゾルフ……!」
どうしてあなたの言葉は、こんなにも私を嬉しくさせるんだろう? たまらなくなって、彼に抱きついた。
本当に今日の私たちは、人目をはばからずに抱き合っている。けれど、今はそれで良い。だって、湧き上がる無上の喜びや愛しさを表現しないではいられないのだから。
彼の両手に頬を包まれる。太陽と月に、両掌に描かれた私たちに、包まれている。
「愛しています、アヤ。心から」
「私も、誰よりもあなたを……ゾルフを愛しています」
どちらからともなく、キスをした。幸福の温度が胸いっぱいに広がった。
夕焼けがやきもちを妬いて赤く染まっている。間違いなく今の私たちは、世界で一番、幸せなふたりだ。
幸福しかない人生というのは、ありえないのかもしれない。
世の中は暗く悲しいニュースであふれかえっている。なにもかも上手くいかない日常に嘆き、傷ついた心を癒す術さえ分からず涙に濡れながら、私たちは戦っている。
けれど、希望が見えないときも、明日はきっと、未来はきっと良くなると信じていれば、なにかが必ず変わっていく。
それは、自分の心かもしれないし、あるいは世界、あるいは未来かもしれない。
絵ハガキの中で笑うふたりの兄弟は、なにがあっても諦めずにいた。念願だった身体を無事に取り戻して、明るく元気に生きていることだろう。
その絵ハガキを、結婚式の写真の隣に飾った。ウエディングドレスを着た私と、白いタキシード姿の夫に笑いかける。カメラの方を向いて微笑むこの頃の夫は、まだ声が戻っていなかった。
けれど、今はどうだろう?
「アヤ、ただいま帰りました」
今では念願叶って、大好きなあの声がまた聞けるようになった。私の名前も、たくさんたくさん呼んでくれている。
叶わない願いはあるかもしれない。けれどそれは、いつか叶う可能性を秘めていることを決して忘れてはいけない。
「おかえりなさい、あなた」
白馬に乗った王子さまがいなくたって、映画の主人公でなくたって。
信じてさえいれば、ハッピーエンドは誰にでも起こりうる。
(了)20181122
(改)20190115