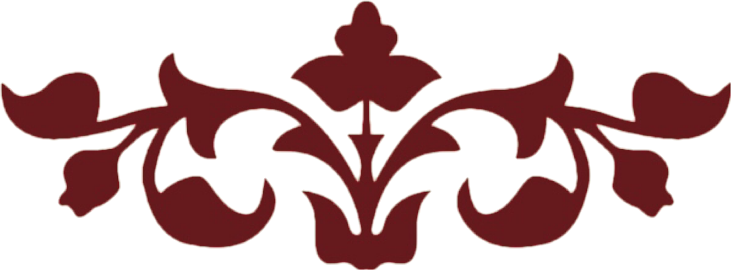
I'm yours
『私はあなたのものです』
甘やかに響くこの台詞に、憧れていた。私もいつか、心からそう言える王子さまに出会いたい、結ばれたいと、ひそかに願っていた。
幸運にも、願いは聞き届けられたみたいだ。その言葉を伝えたいと思える人が、ついに現れたから。
『あなたは私のものです』
もしもその人が同じ台詞を口にするなら、たぶんこう言い換えるだろう。言葉の順番を逆にして、有無を言わせない圧力と静かな独占欲を、やんわりと見せつけて。
これは例えばの話だけれど、もし、もし、彼にこう言われながら、じっと見つめられたらどうなるだろう。そのまま抱き寄せられて、強く抱きしめられたら。優しい声で「好きです」なんて、ささやかれたとしたら……?
「夢見がちな乙女、ですか」
「な、なんでそのことを」
ぼうっとしていた頭が一気に覚醒した。どうしてばれてしまったんだろう。無意識にニヤけていたのだろうか?
さっきまで妄想に登場していた上司・キンブリー少佐は、こちらを見ずにペンを走らせている。
「誰も貴女のことだとは言っていませんよ」
いや、私に向けて言ったに違いないのに。まあ、仕事中に妄想していた自分が一番悪いのだけれど。
「反応したということは、貴女もそうですか。大抵の女性は夢見がちなようですね」
ふむ、と彼は顎に手をやる。どうやら、本当に私に向けた言葉じゃなかったらしい。
「そうですね。女の子はよく、白馬に乗った王子さまを待ち焦がれているって言いますからね」
自分に当てはまることを、さも一般論から引っ張り出したように話してみる。
仕分け終わった書類を抱え、少佐のデスクの前に向かう。
はっきり言って珍しい。あの仕事人間・恋愛興味なしに見える少佐が、女性に関心を示すとは。
「さすがにある程度の年齢になったら、目が覚めるんじゃないでしょうか。少佐、この報告書にサインお願いします」
ブーメランだなんて思わない。自分のことは一旦棚に上げておく。それが、ザ・アヤ流。
「ええ。ですが、貴女は違いましたね? その類の憧れは消えていないようだ」
「だっ、だからどうしてそのことを!?」
しまった、またやってしまった。慌てて咳ばらいを繰り返すも、全然ごまかせていないようだ。なぜって、少佐、笑っているから。
切れ長の瞳が細められている。その笑みと羞恥とで、あっという間に顔が熱くなる。
「本当に違いますってば、そんなのとっくの昔に消えちゃいましたよっ!」
たまらずくるりと背を向けると、彼が声を出さずに笑っている息の音が聞こえた。否定しているのにまったく信じてもらえないなんて。思っている以上に嘘が下手なのかもしれない。
自分の席に戻ろうとした矢先、サインしましたよ、とすぐにお声がかかる。ばつが悪く、視線を合わせずに舞い戻った。
「憧れがあっても良いじゃないですか。可愛らしい」
「かっ、かわっ!?」
ああ、いちいち反応してはダメよ、アヤ!
「しかし、錬金術師としては理解に苦しみますね。それでは頭の中で理論を構築して、実践には至らないのと同じ。考えた理論を試してみたい、つまり、憧れを実現させたいとは思わないのでしょうか」
少佐は腕組みをして、椅子の背もたれにぐっともたれた。彼に聞こえないよう、軽く息を吐く。こうしてすぐ錬金術師の顔になるんだから。
報告書の下部には、少佐の滑らかで美しいサインが書かれてある。さっきまでの色んな動揺を隠しつつ、その書類をクリアファイルに挟み込んだ。
「錬金術師だって最初は、こんな物が作りたい、あんな錬成は可能だろうかと、想像をふくらましますよね? それと同じではないでしょうか……」
憧れを実現したくても、王子さまの登場は運に限るような気はするけれど。
「なるほど、合点がいきました。それなら貴女がいくら王子に焦がれようとも、異論はありませんよ」
「ですから、いつか王子が迎えに来るなんて、これっぽっちも考えてませんと……」
少佐が椅子を揺らして立ち上がったので、なんとなく語尾を弱めた。
「では王子の代わりに」
彼はゆったりとした歩き方でこちらの方に来た。
「私が迎えにいくのはどうです?」
伸びてきた片手に顎を固定され、漆黒と深い青の混じった綺麗な瞳と視線を合わせた。夜の色に塗られた男の双眸には、からかいと余裕がたっぷりと感じられる。冗談だと分かっているのに、見つめられているうちに頬や額が熱くなり、鼓膜にはどくどくと胸の音が聞こえ始めた。
なにも言えず視線を逸らすと、普段の呼び名である「ラシャード少尉」、ではなくファーストネームで優しく呼ばれる。
「アヤ、いかがです」
「か、からかわないでくださいっ」
「おや。そんなつもりは毛頭ありませんが」
一瞬肩を上げ、少佐は困ったように笑う。
「まあ迎えに行くというよりは……貴女を奪いに行く。こちらの方がしっくりきますね」
下唇のすぐ下の辺りを親指でおもむろになぞられながら、彼のいささか強引な台詞を聞いた。キンブリー少佐は微笑を浮かべたまま、私を楽しげに見つめている。まばたきもできずに固まっていたら、彼の爪の先が唇のふちにかすかに埋もれる感覚まで分かった。
「うば、う?」
「そうです」
突然、さっきの妄想が蘇る。
『あなたは私のものです』
もし今、その台詞を言われたら。腕を引っ張られて、ぎゅっと抱きしめられることが現実に起きたら。「好きです」なんてささやかれたら。
興奮で思わず上ずった声が出そうな喉で、うわ言のように呟く。
「奪うもなにも、私は誰のものでもありません……」
「それは良いことを聞きました」
唇のふちを行き来していた指が、下唇に触れる。指は右端に移動し、ぷくりとふくらんだそれを軽く押さえながら左へと移動する。身をよじって抵抗すると、彼のもう片方の手が逃げるなと言わんばかりに、私の腰にまわされた。
「キンブリー少佐、ん」
「私が貰って差し上げましょう」
唇の隙間を親指でこじ開けられ、舌の先に触れられる。遠慮を知らないそれは、まるで一種の戯れのように、ちろちろとそこを刺激した。
「……っ!?」
「誰かに盗られてしまう前に」
「っ、ふぁ……」
「それではご不満ですか?」
どういうわけか私は、奇妙で甘美なこの感覚を、与えられるがままになっていた。想いを寄せる人からのアプローチを、もう、拒むことなどできなかったのだ。
触れられたところは、じんわりと温かい余韻が残る。それが消える寸前に、またいじられた。私を慈しむように、少し目を細めている少佐の視線に、身体の奥がぞくりと甘く痺れた。
夢見た王子さまはこんなにも近くにいた。けれど、彼はまるで、婚約の決まった令嬢をさらう悪役みたい。それでも良いなんて思えるのは、この人に魅力がありすぎるからだろうか。きっと、心から好きになってしまったからだろう。
彼の「気まぐれ」はしばらく続いた。その間、自分の心臓の音に押し潰されてしまいそうだった。ようやく解放されたとき、視界はうっすら涙の膜に包まれていて、少佐の表情がぼやけて見えた。
彼は、唾液で濡れた指先を、当然のようにぺろりとひと舐めした。それだけで、ぞくりと甘い痺れが身体の奥に走る。
彼は、私の顔を見て満足そうに口角を上げた。
「不満ではない、と見なしますよ」
「少、佐」
かと思うと、その笑みはすぐに消える。
「弱りましたね」
少佐は、私の後退を阻む背後のデスクに両手をつき、吐息を感じるほどの至近距離で私を射抜く。思わず息を呑んだ。
「職場だというのに歯止めがきかない」
心臓が一際大きく跳ねた。もう頭も舌も、うまく回らない。私はこれからどうなるのだろう。
吐息が唇に触れる。彼は、胸の内に湧き上がるなにかを抑えるように、眉間に皺を寄せて私の名前を呼んだ。
「アヤ」
「っ、はい」
「貴女は私のものですよ」
「しょ、さ……んんっ」
そんなことを言わなくても、私はもう……。
その気恥ずかしい返事は、塞がれた唇の内側に仕舞い込んだ。
――私はもう、あなたのものです。
(了)20151205
(改)20181124