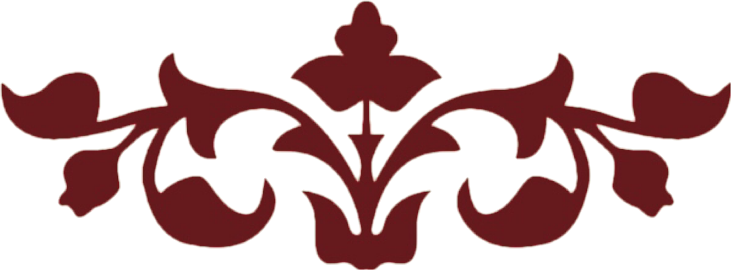
Memory of Encounter
季節は巡る。春に夏が覆い被さって、夏を秋が侵食する。秋は冬に飲みこまれて、冬は春のまぶしさに負けてしまう。そんなふうにして一年は過ぎていく。
彼と出会ってからもう一年。いや、まだ一年か。
晴れた休日に洗濯ものを干していると、なぜだか彼と初めて出会ったときを思い出す。私にとって深く印象的で、一生涯忘れることのないだろう、あの日のことを。
穏やかな、ある春の日のこと。絶好の洗濯日和だというのに、私は緊張のあまり洗濯するのを忘れたまま登庁した。
なじみのない廊下を通り、隅っこの執務室の前に立つ。頭の中では、数日前に飲みの席で、異動先がキンブリー少佐の配下になったと話したときの友人たちの反応が、よみがえっていた。
『うそ〜、キンブリー少佐って顔は良いけど、すごく変わった人らしいじゃん?』
『爆破の錬金術の専門らしいし、アタシはかかわりたくないな』
『ドンマイ、アヤ』
噂と言えば、噂だ。しかし、そんな危険人物だとささやかれている少佐の元でこれから働くなんて。ここに来て、尻込みする気持ちがどんよりと芽生える。
とはいえ、いつまでもここでため息なんかついていられない。約束の時間が過ぎてしまう。会ってみたら案外良い人かもしれないし、悲観する必要はない。そうだ、そうに決まっている。
ネガティブなイメージを隅へ追いやるように、なかばヤケな気持ちでドアを三度ノックした。どうぞ、と声がする。必要以上の力でドアノブを握り、中に入った。
「失礼します」
ああ、どうか変な人ではありませんように。
奥のデスクに視線を移すと、黒い髪の男性の姿が目に入った。前髪を上げていて――あぶれた髪がふたすじたれていて――、色白で、凛とした眉の形をしている。一口に言えば気品あふれる方で、とても軍人とは思えない。
この人が、キンブリー少佐。
「ああ、貴女が……」
「本日からお世話になります。アヤ・ラシャード少尉です。何卒よろしくお願い申し上げます」
私は、はきはきと挨拶をして、ピシッと音がなりそうな敬礼をする。昨日の晩、姿見を相手に何度も練習したので完璧なはず。
「ゾルフ・J・キンブリーと申します。紅蓮の錬金術師です」
少佐は口角を上げ、こちらを見た。青い瞳をしていた。
「よろしく、ラシャード少尉。私の副官」
私も同じく微笑みを返した。
良かった、第一印象は話に聞いていたよりまともそうだ。以前補佐していた、人使いも言葉遣いも荒い中佐よりも良い人に見える。
「良い仕事をすると、スウィフト中佐から聞いています。よく気が利き、誰が相手でも円滑なコミュニケーションを図っている。おまけに、場を和ませる不思議な魅力があるようで。中佐が退役されたこと、感謝せねばなりませんね」
「恐れ入ります」
少し褒めすぎだと思うけれど、そんな評価がついているなんて、素直に嬉しいと思う。
彼はデスクに両肘をつき、組んだ指の上に顎を乗せてにんまり笑った。
「それに射撃もお手のものとか」
「せ、精いっぱい努力いたします……」
遠回しに痛いところを突かれて、私のライフはいきなり半分に減ってしまった。そんな言い方するなんていじわるだ……。
彼は、椅子の背もたれにもたれて、脚を組んだ。
「この国に、いえ、まずは私に忠誠を誓う気はありますか」
「もちろんです、少佐」
「皆、そう言ったのにやめていくんですよ」
思わず、まばたきを繰り返した。
彼の眉間に皺が寄る。その顔は、歪められても絵になっていた。
「貴女の前に来た少尉も、その前の軍曹も、またその前の准尉も。皆、口をそろえてそう言ったはずですが、ある日辞表を提出する。あるいは、忽然といなくなってしまう」
どういうことだろう。皆、彼のもとで働くのがいやになってしまった? それとも……。
『爆破の錬金術の専門らしいし、アタシはかかわりたくないな』
使えないから消された、とか。
「さて、ラシャード少尉」
彼の青い瞳が私を捉える。ぞくり、と二の腕が粟立った。
「貴女は何日もつでしょうね?」
深い笑みと、鋭い視線。まるで大蛇に睨まれたように、背中に冷たい汗が伝うのを感じた。返事の代わりに微笑んで見せたけれど、きちんと笑えていたかどうかは、分からない。
そのときだった。
ボン、と大きな衝撃が窓ガラスの向こうで聞こえた。一体なんだろう、今の音は。
「爆発ですね」
こともなげに彼はそう言った。唇には笑みさえ浮かべている。
「ああ、実に良い音だ。体の芯によく響く」
爆発音が良い音? 変わっている。変わり者すぎる。そんな人、聞いたことがないし、私にはまったく理解できない。
さて、と呟いて、少佐が席を立つ。
「せっかくですから、見物しに行きましょうか」
少佐のひと声で、私たちは爆破現場の見物に向かうことになった。はっきり言うと、そんなもの見たくはない。危険だし、野次馬根性を出すのも気が引けたのだけれど、少佐が行きましょうと言うのだからついて行くしかなかった。
音の方向からして、現場は倉庫の方ではないかと彼は予想した。司令部を出て、火の手が上がっている方向を見ると、確かに倉庫が燃え上がっていた。
焼けたのは第三倉庫だった。火はぼうぼうと燃え上がり、遠巻きにそれを眺める野次馬たちがすでに群がっていた。少佐は彼らをかき分け、ひたすら前を目指す。その背中を一生懸命追った。
彼は長い髪を後ろで結んでいた。男性には珍しいヘアスタイルだけれど、変わり者の彼が選んだ髪型だと思えば頷ける。
「勢いよく燃えていますね」
誰に言うでもなく、少佐が呟く。とうとう私たちは最前列に来た。消防隊はまだ到着していないらしい。こんなに激しく燃えているのだから、隣の倉庫に延焼する可能性は大きいだろう。早く、消防隊が来ないだろうか。
「おいっ、キンブリー!」
荒々しい声に振り返ると、中年のよく肥えた軍人が眉を吊り上げ、仁王立ちしていた。肩章の星の数を盗み見る。少将だった。
「倉庫を爆破させたのはおまえじゃないだろうな!」
少佐は平然としていた。後方からは、そこかしこでひそひそ話が聞こえてくる。
「なんとか言ったらどうなんだ! おい、紅蓮の錬金術師め!」
「ま、待ってください!」
私は慌ててふたりの間に割り入った。少将の目がぎらり、こちらを睨む。
「爆破直後、キンブリー少佐は執務室で私と会話していました! ですから、少佐は爆破と関係ありません」
太い腕を組み、少将はふんと鼻を鳴らす。
「へっ、あらかじめ小細工をしていたかもしれんだろう? ガソリンや油を撒いて、後は自然に発火するように仕掛けておいたに違いねえ」
それ、錬金術と関係ないような……。
苦笑する私の隣で、少佐がくすりと笑う。
「せっかく爆破するなら、迷わず私は錬金術を使いますよ。しかし、惜しいことに私は未熟な術師。遠隔錬成など不可能です。したがって、司令部にいながらにして倉庫を爆破するという奇術は使えません」
少将が眉根を寄せ、口をへの字に曲げる。今だとばかりに私も応戦した。
「倉庫を爆破したからといって、少佐にはなんのメリットもないはずです。理由もなしにそんなことをするでしょうか?」
ばつの悪そうな顔をして、少将は少佐を睨み、私を睨んだ。そして頭をがしがしと掻いて、「覚えてろよ」と捨て台詞を吐き、野次馬たちの中に姿を消した。
しばらくして到着した消防隊の指示もあり、私たちは執務室に戻ることにした。
廊下を歩きながら、袖の匂いを嗅いでみた。若干、煙のにおいがする。この軍服はおろしたてだというのに仕方ない、明日洗濯しよう。生地が傷むけれど、煙のにおいをまとって仕事するよりはましだろう。
そう思いながら執務室のドアを開け、少佐を通す。私も続いて中に入り、ドアを閉めた。
そのとき、扉にトン、と手がつかれる。同時に影が私を覆う。何事かと思い振り返ると、少佐の美しい顔が、拳五個分ほどの距離に迫っていた。
「先ほどは、かばってくださりありがとうございました」
優しい笑みを見せられ、思わずどきんと胸が跳ねる。この距離で彼の笑顔を見るなんて、どんな女性でも間違いなくクラッときてしまうはず。軍人とはいえ私も乙女だから、自然とそうなってしまう。
いえ、となんとか返事し、微笑みを返しながら彼から離れようとした。すると、もう片方の手が伸び、私の行く手を阻むように扉を押さえた。つまり私は、彼の両腕に閉じ込められていることになる。
美しい顔が、近い。
「しょ、少佐?」
「なんの疑いも持たないとは、人の良い方だ」
その一言に胸がざわついた。なんの話だろう。
「私が嘘をついている。そのようには考えなかったのでしょう?」
「あの、おっしゃる意味が……」
思い当たるのは、先ほどの少将とのやりとりだ。あのとき彼は、なんと言っただろう。そうだ、遠隔錬成は不可能だと言っていた。それは嘘ということだろうか。
「遠隔錬成の方法をすでに習得しているとすれば? 執務室にいながらにして錬成は可能ですよ」
彼は私の耳元で、いたずらの計画を話すかのように楽しげにささやく。
「貴女は言いましたね、倉庫を爆破するメリットがないと。私が爆発音を好むことは知っていたでしょう? ただ爆破音が聞きたいがために、倉庫をひとつ犠牲にした……。ありえない話ではないですよ」
心臓がせわしなく鼓動する。最初に覚えたときめきは、湧き上がる黒い恐怖に塗りつぶされてしまった。
ということは、彼が、少佐が、倉庫を爆破した張本人かもしれない……?
彼の視線から逃れるように、横を向いて言った。
「そ、それじゃまるで、ご自分が犯人だとおっしゃっているみたいですよ」
「ええ、そうかもしれませんね」
怖い。なにを考えているのか分からない。今なら、彼のもとを去っていった過去の部下たちの気持ちが、分かるような気がする。
「本当のことを、教えてください」
「人にものを頼むときは目を見て頼むものですよ、少尉」
今この人の目を見たら、指先や声が震えてしまうかもしれない。情けない、弱い私を初日からさらけ出すことになりかねない。
そんな予感を覚えながらも観念し、私は青い瞳と視線を交わらせた。
「おや、少々やりすぎましたかね」
少佐の表情がかすかに滲んでいる。涙目になっているのだろう。情けない私を見られてしまったけれど、なにがあっても涙はこぼさないでいよう。
私は、引き結んでいた口元を緩めた。負けるものかと、精いっぱいの見栄を張り、微笑んで見せる。
「いいえ。平気です」
彼はふっと笑い、伸ばしていた両手を下ろして私を解放した。
「そうですか。では、おしゃべりはここまでにして、そろそろ仕事に取り掛かりましょう。手始めにその書類の山をチェックしていただけますか」
「……イエス・サー」
心臓はまだとくとくと音を立てている。
倉庫を爆破したのは彼かもしれない。彼は危険人物かもしれない。なにも、知らない。分からない。
あなたがやったんですか、ともう一度訊いてみる度胸と余裕は、なかった。
――懐かしい思い出だ。
あの事件の真相は今でも藪の中で、私も彼もその話題を今さら持ち出すことはしない。
仮に、あのときの犯人が少佐だとしても、今の私の気持ちが揺らぐことはないだろう。彼への気持ちは、倉庫を燃やした炎のように熱く燃え上がっているのだから。
最初はあんなに警戒していたのに、それがいつしか恋に変わるだなんて、思ってもみなかった。この世界にありえないことなんて、きっとないのだろう。特に恋愛においては。
洗濯物がぱたぱたとはためいている。干した軍服の青が、空の青が、鮮やかだ。この鮮やかな青を、来週の今頃は果たして見られるのだろうか。
イシュヴァール殲滅戦。ついに戦場に駆り出されることになった。生きて帰れるのだろうか。心が萎びることなく戻って来られるだろうか。
今までのように、楽しい日々が待っているわけではないのは明らかだった。覚悟を決めなくてはいけない。決意をしなければならない。
軍服に袖を通したときから、こんな日が来ることは分かっていたはずだ。今こそ、あのときの覚悟を思い起こして、自分を奮い立たせなければ。
そう、思えたら良かったのだけれど。私はまだ、怯えている。どうか、七日後の自分が、国のために、軍のために、あの人のために戦えますように。額を袖にひっつけるようにして、そう祈った。
いつかのように、袖の匂いをすんと嗅いでみた。もちろんあの煙のにおいはしない。けれど、東の戦地に赴けばこれもまた煙たくなるのだろう。どうせ煙たいのであれば、あの人が起こした爆発の、硝煙のにおいに包まれたい。
「……でもやっぱり、煙たいのはいやだなぁ」
ふっと、乾いた笑みがこぼれた。
キンブリーさんにはどこかミステリアスな部分があって欲しい。
(了)20180515
(改)20181223