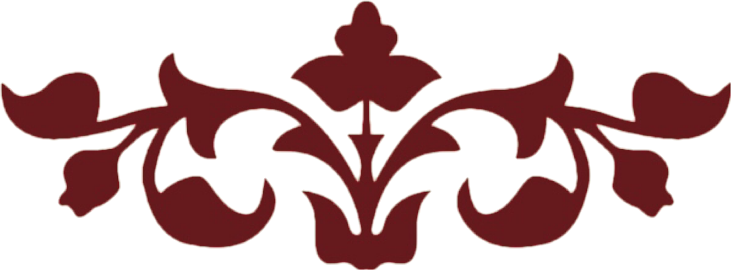
White Day Kiss
その棺は真夜中になると動いた。
二十四時の鐘の音で中のミイラが目を覚ますのか、棺はガタガタと音を立てて震え出す。しばらくしてその動きが止まれば、ふたの隙間から白い霧がふわりと出てくる。墓場に立ち込めるその霧は、やがて四足歩行の獣の形で荒地を駆け出し、走り出すうちに本物の狼へと変身した。
狼は崖の近くまで来ると、今度はこうもりへと姿を変え、月に向かって飛び立った。降り立った先は、街はずれの青いレンガの家だ。こうもりは、白いコートを着た青い瞳の美しい男性へと変化を遂げ、迷わずドアをノックした。しばらくして、ブロンドの髪の女性が中から出てくる。ふたりは抱擁し、ともに中に入った。
扉が閉まるや否や、男性は今までの柔和な表情を一変させ、冷酷な本性を見せる。そして、あろうことか女性の首すじに噛みついた。驚いた女性は抵抗するが、男性の力には敵わない。鋭利な牙が肌に突き刺さり、滴る血を吸い上げられ、女性は苦悶の声を上げた。男性を遠ざけようと胸板を押さえる手が、小刻みに震え、止まり、やがて力なくだらりとたれる。抵抗の果てに、女性は気を失い、ぐったりと床に倒れた。
血を吸った男性――すなわちヴァンパイアは、残忍な表情を浮かべて女性を見下ろし、地を這うような低い声で短く笑うのだった。
からになったポップコーンの容器と、氷が溶けて水っぽくなったアイスティーをごみ箱に捨てる。暗く沈んだ余韻がまだ胸に残る中、どうでした、と隣の彼に尋ねてみる。キンブリー少佐は顎に手をやり、ふうむと唸る。
「よく見るB級ものですね。ホラーにしてはあまり臨場感がありませんし、少々退屈に思いましたが――アヤ、貴女はそうは思わなかったようですね」
まるで読心術でも心得ているかのように、ぴたりと言い当てられて目をしばたたく。やっぱり、顔に出ていたんだろうか。
「だって、愛した人がヴァンパイアだったんですよ。人間ではなくて、怪物なんですよ? それだけで十分怖いじゃないですか……!」
「ええ、現実であれば恐ろしい話です」
少佐は、余裕そうな顔で平然と話す。錬金術師は皆、オカルトや非科学的な話を好まないのかもしれない。
「ですが、現に
「やだ、そういうこと言わないでください!」
彼の口元は弧を描いている。本気でそうは思っていないのか、その恐ろしさを楽しんでいるのか。ただ単に、私の怖がる姿を楽しんでいるだけかもしれないけれど。
映画館の外に出た瞬間、びゅうと吹いた寒風に身をすくめた。もう春だというのに、
レイトショーの終了時刻は二十三時。普段はこの時間にうろつくことはしないが、少佐と一緒にいること、ふたりとも明日は非番だということでそれも許される。彼と会話しながら、街灯にぼんやりと照らされた真夜中の石畳を踏む。今日は、新品のヒールをはいてきた。だからなのか、少佐はいつもよりもゆっくりと歩き、私の歩みに合わせてくれている。その気遣いが嬉しかった。
帰り道も映画の感想を伝えあった。ほとんど私が喋っている気がするけれど。
「ヴァンパイアはあの女性だけで飽き足らず、その後も大勢の女性の血を飲んでましたよね。ええと、全員で何人でしたっけ」
「二十三人ですよ。バリー・ザ・チョッパーと同じです」
バリー・ザ・チョッパーというのは、昔、中央に現れた殺人鬼のことだ。元々は肉屋の主人だったが、その正体は肉切り包丁で人間を斬り刻むことに快感を覚える狂人だった。少佐によれば、二十三人もの人間の命を奪い、裁判で極刑に処されたという。
久しぶりにその名前を聞いて鳥肌が立った。本当に恐ろしい怪物は世の中にいるんだ。
「どうです、やはりフィクションより生身の人間の方が怖いでしょう?」
「……どちらも怖いです」
「はは。貴女は軍服を脱ぐと、あどけない少女になりますね」
彼は私の背中に手をまわす。そして、肩をそっと掴んで自分の方へ引き寄せた。ちょうど、すれ違う人々から少女である私を守るように。紳士の所作をそれとなくこなす彼に、内心でどきどきしながら弱腰で聞いてみる。
「軍人なのに、情けないって思いました?」
「いいえ。可愛らしいと思っただけですよ」
「もう、本当に?」
その言葉に、実は照れてしまったことを知られたくなくて、少し顔を背けて夜の街を歩いた。
今日、三月十四日はホワイトデーというらしい。バレンタインデーと同じく、東の国ではポピュラーなイベントで、その流行の波が今年アメストリスにもやってきたのだとか。流行りに敏感な友人いわく、バレンタインデーでチョコを貰った男性が、お返しとしてお菓子やアクセサリーを女性にプレゼントするのだという。
一か月前の二月十四日に、大勢の女子たちが少佐にチョコレートを渡しに来たのがきっかけで、バレンタインデーなるものの存在を知った。なんでも、東の国では女性が好きな男性にチョコレートを、そして別の国では男性が好意を持つ女性にお花をプレゼントする日だそうだ。
それで、なんと私も男性からお花を貰ったのだけれど、それを不満に思った少佐がお花を爆破してしまうという小さな事件が起こった。その後、仕事帰りに無事、花屋に寄って少佐から白いバラをプレゼントされ、彼と一緒にチョコレートを買いに行った。彼は渡したトリュフチョコを大層気に入ってくれて、それから「貴女からの贈りものはなんでも嬉しい」という嬉しいお言葉ももれなくいただいた。
そして、今日はホワイトデーだ。私としては、バレンタインのお礼なんていらなかった。そもそも、もうバレンタインデーに少佐からお花を貰っているのだから。それで、代わりに映画でも見に行きましょう、と彼を誘った。ものを貰うのも嬉しいけれど、なによりもふたりで一緒にいることの方が、何倍も嬉しいのだ。映画の内容はともかく、忙しい日々の合間を縫ってデートに出かけ、ふたりで同じものを見て、感想を言い合えるのは本当に素敵だと思う。
ホワイトデーはキンブリー少佐の日だと、私は勝手に思っている。ホワイトデー、つまり白い日。ネクタイを除いて、全身白の装いをした、彼の記念日だ。
そう伝えると彼は、なるほど、と言って短く笑った。
「それなら、今日だけは少しばかり羽目をはずしても、許されるかもしれませんね」
私を見る少佐の目はいつだって優しい。私が映画の感想を長々と喋っても、今のようにホワイトデーが少佐の日だとかヘンなことを言っても、その瞳は変わらない。時折、その青の瞳をすいと細めて、頷きながら微笑んでくれる。そんな微笑み方をされると、私の胸は切なく疼く。もちろん嬉しいのに、好きという気持ちが押し寄せてきて、苦しくなることがある。
今も、そうだ。
見慣れた街路樹の道と小さな公園を過ぎると、私の住むアパートはもう目の前だ。デートのとき、少佐はいつも家まで送り届けてくれるのだけれど、毎回この別れの瞬間が寂しくてたまらない。だから時々、寂しさに負けたときはこんな提案をする。
「あの、良かったら上がって行ってください」
「良いんですか?」
少佐は目を丸くする。私は頷いて彼の袖を小さく引っ張った。
「できればもうちょっとお話したいんです」
やってしまってから駄々っ子みたいだと気づき、内心苦笑しながら彼の反応を窺う。少佐は、貴女が良いならお言葉に甘えます、と言って困ったように笑った。
心の中でバンザイし、うきうき気分で鍵を開ける。今朝、なんとなくだけど掃除機をかけておいて良かった。そうだ、友人に貰った美味しいアールグレイの紅茶を飲んでもらおう。それから、デパートで買ったティーカップも少佐に見てもらいたい。
色んなことを考えながら、彼を中に招きドアを閉めた。鍵をかけ終わったそのとき、すっと手が伸びてきて、ドアを押さえた。なにかと思って振り返ると、彼は私を閉じ込めるかのようにドアに両手をつき、こちらを見下ろしていた。
「……少佐?」
「美味しそうな匂いがしますね」
彼は先ほどまでの紳士的な笑みではなく、いつも私を翻弄するときの嗜虐的な笑みを浮かべている。顎をすくわれた。
「やはりそうだ。美味しそうな血の匂いがします」
「や、やめてください。そんな、映画のヴァンパイアみたいな台詞……」
笑ってかぶりを振る私に、少佐が大真面目な声で告げる。
「貴女、私がヴァンパイアだとは思わなかったのですか?」
その言葉に全身が硬直する。少佐が、ヴァンパイア?
「ああ、そうは思わなかったからこうして招いてくださったのですね。信頼されているのはありがたいことです。しかし、女性なら少しは警戒しても良いでしょうに」
「冗談はよしてください、そんなわけ……」
混乱する私の頭に映画の映像が浮かぶ。そういえばあのヴァンパイアは、少佐と同じ白いコートを着ていたような。いやいや、ただの偶然だ。
「信じられませんか? 私の正体が」
少佐の青の双眸は、獲物を狙うようにぎらぎらと妖しく輝いている。
あのヴァンパイアと、同じ色だ。
『現に合成獣や殺人鬼などの類がこの世に存在している以上、ヴァンパイアが街をうろついていたとしても、なんらおかしな話ではないでしょう』
帰り道での彼の言葉が脳裏によぎる。
まさか、本当に?
「うそ……」
「ずっと待っていました。愛する貴女の血をいただくこの日を」
映画のワンシーンが頭の中で流れ出す。ヴァンパイアを家に招いた女性は、玄関先で吸血されていた。もしかして、これから私も……?
逃げようと視線をさまよわせた。しかし、考えを読まれたのか両手首を掴まれてしまった。抵抗して逃げようとするが、男の人の力には敵わない。
あの美しい顔はすぐそこに迫っている。弱点であるにんにくは、当然持っていない。こんなときに限ってキッチンにもない。
「やだ、お願い少佐、やめて!」
いやだ、と何度も首を振る。元は人間でも、一度吸血されたらヴァンパイアになってしまう。そんなのいやだ。夜に血を求めてさまようあんな怪物にはなりたくない。
首すじを、ぺろりとひと舐めされた。とてつもない恐怖と後悔が押し寄せ、涙が滲む。
どうして今まで気づかなかったんだろう。少佐はずっと私を狙っていたというのに。
牙が当たる。私の拒絶と懇願もむなしく、そのまま吸われた。
「やぁ……」
ああ、なんてことだろう。これで私もヴァンパイアになってしまった。怪物の、仲間入りだ。
それでもどういうわけか、彼をきらいにはなれなかった。憎むことなど、できなかった。
好きだ。胸の苦しさを覚えるほどに。
テーブルの上に置かれた苺のティーカップ。それに注がれた紅茶の表面に、笑みを隠しきれないのか口元を片手で覆う少佐が映っている。
「……少佐」
彼の肩は小刻みに震えている。それを見て、膝の上に置かれた私の拳も震え出す。
「また笑ってますねー!?」
「すみません」
今度はごまかすように咳ばらいをしている。そんな彼を、前のめりになってきつく睨んだ。
「少〜佐〜」
「いたずらが過ぎたと思っています。ですが、あんな簡単に騙されるとは思ってもみませんでした。それにまさか、ヴァンパイアになる覚悟までしていたとは」
「わー! もう! 忘れてくださいってば!」
たまらなくなって、ソファのクッションに顔をうずめた。
結論から言うと、少佐はヴァンパイアなんかじゃなかった。彼の迫真の演技に私が踊らされていただけだったのだ。ネタばらしされたとき、「少佐のばかー!」と、彼の胸板をぽかぽかと叩いた。彼は謝罪しながら今のように笑っていた。
少佐いわく、ただ私の驚く顔が見たかったらしい。本当はヴァンパイアだと告げてから、すぐ嘘だと言うつもりが、いたずら心に火がついてそのまま演技を続けたのだとか。
「今日は私の日なんでしょう? 羽目をはずしても許されるかと思いまして」
「はずしすぎです!」
怖くて涙まで出てきたというのに。最初の方のウキウキ気分を返して欲しい。
「機嫌を直してください、アヤ。お詫びに良いものを差し上げますから」
「……良いもの?」
「ええ。ホワイトデーのお返しです」
彼はポケットに手を入れ、白くて小さい箱を取り出した。それをテーブルの上にことりと置く。
「開けてみても……?」
「どうぞ」
箱に手を伸ばして、ゆっくりと丁寧に開けてみる。銀色にきらりと光るハートがふたつ、並んでいる。中に入っていたのは、可愛らしいハートの形のシルバーピアスだった。
ピアスと彼を交互に見て、嬉しさをどう表現しようか迷いながら口を開けた。
「少佐……!」
「気に入っていただけましたか?」
「はい、とっても!」
「それは良かった」
卓上型の鏡を持ってきて、ひんやりとしたピアスを、耳につける。鏡に右耳を映し、左耳を映して、笑う。耳に飾られたハートはとてもキュートで、洗練されている。ただ身につけるだけで、ぱあっと嬉しくなる。単純な私は、騙されたことなど、もうどうでも良くなってしまった。
「とても良く似合っていますよ」
「ありがとうございます! ……でも」
少佐が小首を傾げ、私はうつむいて視線を逸らす。
「バレンタインデーのときもお花をいただいたのに、私ばっかり貰いすぎですよね」
「……ふむ。では、私もなにかいただきましょうか」
どうしよう。彼へのプレゼントを用意していない。今出せるのはせいぜいバウムクーヘンぐらいで、けれどそんな安価なものが、このアクセサリーに見合うはずがない。
焦る私を見て、彼は手招きをした。そばに行くと、腕を掴まれ、引き寄せられる。至近距離で見つめあうと彼は笑みを深くする。
「今日は貴女からしてください。それで、十分です」
人差し指が唇に当てられる。
私が、少佐にキスをする?
「えっ、え……!」
少し想像するだけで、顔が火照り出す。冷えていた指先も一瞬で熱くなった。
「いけませんか?」
恥ずかしい。けれど、ほかにプレゼントできるものはない。それに、これくらいのことで彼が喜んでくれるのなら。大丈夫、少しの間だけ、恥ずかしさを我慢すれば。
「じゃ、あの、目、閉じててください……」
「分かりました」
微笑みながら、彼は瞼を閉じた。少佐の口角の上がった薄い唇をじっと見て、唾を飲む。心臓がうるさいくらいに跳ねて、その鼓動が頭に響く。髪を耳にかけながら、彼にゆっくり近づき、目を閉じる。胸の鼓動に押しつぶされそうになりながら、そっと唇を寄せた。
やわらかなそれに触れた瞬間、部屋の壁時計がボーンと鳴った。二十四時を知らせる音だ。それに驚いて肩が跳ねたとき、ぐっと腰を引き寄せられた。これだけでは終わらせないと告げるようにキスは続く。主導権はいつの間にか彼が握っていた。
角度を変え、何度もついばむように重ねられ、それは段々深くなっていく。二十四時の鐘の音とともに動き出すなんて、まるであのヴァンパイアみたいだ。
今日の彼のいたずらで、ひとつ分かったことがある。彼がどんな人であっても、いや、仮に人でなかったとしても、私は愛し続けるのだろう。たとえ、ヴァンパイアでも、殺人鬼でも、怪物であったとしても。
そんなことを頭の片隅で思いながら、押し寄せる熱に身を任せた。
熱くなったシーツの上で、少佐が私の首すじをつう、となぞった。こそばゆさに首をすくめると、彼が呟く。
「……痕になってしまいましたね」
玄関先で吸われたそこには、紅い華が咲いているのだろう。しばらくはタートルネックを着て過ごさなくてはいけない。私はわざと浅いため息を吐いた。
「もう、少佐がヴァンパイアになりきるからですよ」
「すみません。ですがこれで、虫はつかなくなりますね。少なくとも、一か月前の彼のような虫は」
彼はすまなさそうにする素振りなど見せず、いつもの余裕たっぷりの笑みを浮かべる。どうやら、バレンタインデーにお花を贈ってくれた男性を、まだ気にしているらしい。そんなに気になるのかと、彼の根深い執着心に思わず笑ってしまった。
「どうかしましたか?」
「いいえ、なにも。ピアス、似合ってましたか?」
「ええ。とても良く似合っていましたよ」
彼に抱きしめられる。嬉しくなって、同じようにぎゅっと抱きしめ返した。
耳を銀色に彩るハートのピアスはお気に入り。ヴァンパイアのようでそうでないあなたが、ただ愛おしい。
色々なことがあった三月十四日は、私にとって忘れられない日となった。
(了)20170314
(改)20181223