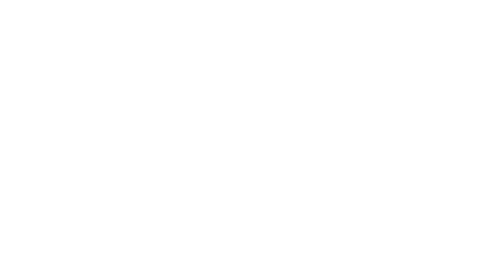
はじめまして。
初めて彼と会ったのは、都心の駅近くにある小さなバーの片隅だった。
仕事終わり、いつもどおり「彼氏」との待ち合わせのために時間より少しだけ早くきて、カウンターの隅でカクテルをあおっていた。セックス・オン・ザ・ビーチと名付けられたそのカクテルは名前の通りビーチを思わせる鮮やかなピンク色をして、ストローに口を付けると、アルコールが入っていることを忘れてしまいそうなくらいに甘いシロップの味が舌先から広がる。週に数回このバーに来てはいつも同じものを頼むのでマスターももう、店に入った時点でいつも同じ席に通して、いつもと同じカクテルを作ってくれる。そしてそれから、それを半分くらい飲んだところで扉が開く。扉の上に取り付けられたドアベルがリン、と鳴って来客を知らせるのに振り返って、ぱあっと笑みを浮かべた。
「ヨシフくん!」
名前を呼ぶと彼はすぐに気づいてこちらへと歩いてきた。誰も座っていないわたしの右隣は彼の定位置だ。彼は優しく笑って、立ち上がったわたしを抱きしめると触れるだけの口づけをくれる。今日も甘いな、と囁く声はきっと唇に残ったカクテルのことを言ってるんだと、わかっていたって恥ずかしい。そっと頭を撫でる彼に甘えるようにくっつくと、そういうのは家に帰ってからな、なんて困ったような声。仕方がなくカウンターに再び腰掛けるとマスターはやっぱり何も言わずに氷の入った琥珀色の液体を彼の前に置いた。ここに来るたびにいつも飲んでいるラガヴーリンを口に含んではあ、と一度ため息をつく。
「今日もお仕事忙しかったの?」
「ああ、そうだな。また出張が入るかもしれないんだ。今度はそう長期ではないと思うが…」
「えっまた?大変だね…」
わたしは彼が何をしているのか、詳しいことは「何も知らない」。なるべく聞かないようにしているし、彼も聞いてほしくなさそうにしているから。どこに行くの、って聞いてもいいのかな?出張はいつからだろう?問いかけようと口を開いてはみるけれど、やっぱり聞いちゃいけないのかもな、と思って口を閉じて。ヨシフくんはそんなわたしには気づかずにぼんやり、カウンターの向こうに並ぶたくさんのウイスキーを眺めていた。なにか悩んでいるのかもしれない。仕事じゃない話でもいいからした方がいいのかな、なんて、もう一度口を開いたその時だった。
「お楽しみのところ失礼します」
突然、後ろから低い男性の声。
不思議に思って振り返ると、柔和な顔つきの目の細い男性が立っていた。
「島崎」
「こんにちは、少しだけ大丈夫でしょうか」
物腰穏やかな話し方の男性を不思議そうに眺めていると、彼は少しだけ顔をわたしの方へ向けて小さく会釈をするので、わたしも慌てて頭を下げた。ヨシフくんはどこか硬い表情でそれを見ている――仕事の話なら、もしかしたらわたしには、聞かれたくないのかもしれない。
「ヨシフくん行っておいで。仕事の人でしょう?」
「あ、ああ…」
少しだけ動揺したふうの彼を見送ると、彼らはバーの反対側の隅へと歩いてゆくのを見送って底に僅かに残ったピンク色の液体を吸い込んで飲み干すと、マスターにおかわりを頼んだ。隅で囁くように話し合う二人の声をかき消すように、シャカシャカとシェイカーの向こうで氷が音をたてる。その音を聞きながらそっと振り返ると、何を言っているのかはわからないけれどヨシフくんはいつもよりも緊張したような表情を浮かべていて、同僚らしい物腰穏やかな男とは対照的。隣の男性は敬語だったしまだまだ若そうだけれど、もしかしたらヨシフくんより立場は上なのかもしれない。まあ、どんな仕事をしてるのかさえ、知らないんだけど。
「どうぞ」
「あ、ありがとうございます」
ぼうっと眺めているとマスターに後ろから声をかけられて慌てて振り向いた。置かれたのは新しいカクテル――今度はロングアイランド・アイスティーというらしい。人生で飲んだどんなアイスティーよりも美味しいけれど、かなり強いカクテルらしいから気をつけて飲まないと。スマホを開いてカクテルを味わいながらSNSを眺めてしばらく待っていると、ようやく話が終わったようで二人が歩いてきた。
「彼女さんでしょうか?綺麗な方ですね。デートの邪魔をしてしまって申し訳ありません」
「いえ、島崎さん?ですか?お仕事お疲れ様です。ヨシフくんもいつも忙しそうにしているし…」
「そうですね、社長は特に私の人使いが荒いものですから毎日大変ですよ」
「おい島崎。いい加減もういいだろう。必要以上にプライベートを邪魔しないでくれ」
突然に攻撃的な口調になった彼に、そんなに強く言わなくてもいいのに。と、開きかけた口はそのまま固まった。ヨシフくんがひどく、厳しい表情を浮かべていたから。ピリ、と場に緊張感が漂う。それでも島崎さんの笑顔は崩れなかった。わたしは一体どんな顔をしてればいいんだろう。状況も把握できないし、ただ何も言えずにふたりを交互にみつめるばかり。やがて島崎さんのほうがその笑顔のまま、口を開いた。
「……それは大変、失礼しました」
「用は済んだだろ。さっさと帰ってくれないか」
「ええ、そうですね」
島崎さん、という人は別段気を害した様子もない。ヨシフくんはまだ、強い敵意を発しているのに。だんだんとそれが恐ろしいような気さえしてくるくらいだった。それでもまだ、申し訳なさの方が勝って、歩き出そうとするその背中に声をかける。
「…おしごとがんばってくださいね」
「ありがとうございます。それではまた」
目の前を通った彼から、島崎さんの着けていたらしい香水の匂いが鼻を掠めた。
ヨシフくんは黙ったままで、わたしはなにもいえなくて。まだ緊張感の漂うバーの片隅に、リン、とドアベルの音が響き渡った。