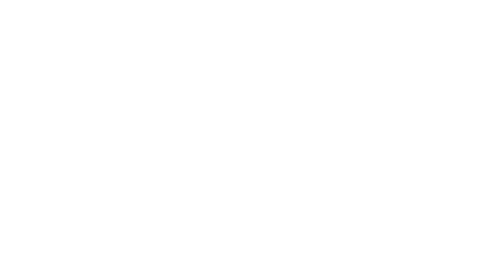
その仮面の向こうがわ
すまない、と囁いた彼に肩を抱かれて、ようやく雰囲気が落ち着いて。カクテルを飲み干した頃にはうっすらと頬が赤く色づいて程よく酔いが回り気分も軽い。まあお仕事のことはよくわからないけれど、ヨシフくんはいつも優しいし、どうでもいいか、なんて楽観的なことを思い直した。
「そろそろ行こう?」
「ああ、そうだな」
隣でラガヴーリンを飲み干した彼に声をかけると、マスターに会計を頼む。2人で3杯しか飲んでいないので大した額でもないそれをわたしがカードで支払ってしまうと、手を繋いでさっきあの人が消えて行ったのと同じ扉を開いた。
秋の夜は思いのほか冷える。外に出た瞬間に感じた寒気に思わず腕をさすると、大丈夫か、と問う彼が腰に腕を回して、肩口に感じる彼の体温にどこか暖かな気持ちでありがとう、と頷いた。路地裏のバーは駅からは少し距離があるけれど、慣れきった道のりは彼と歩けばあっという間。駅から電車にのってどちらかの家へ行くのが仕事終わりのデートの定番だった。今日は私の家。電車を1本乗り継いで、ついた駅から徒歩5分。小さなアパートメントの3階の扉を開いて、中に入ると鍵を閉める。
——そこまできてようやくわたしは、今まで着けていた仮面を取り去った。ヨシフくんの彼氏で、仕事のことは何も知らないOLという仮面を。
「…あれが、5超だっていう島崎ですか?」
「ああ、そうだ。最近会ったばかりで能力はわかっていないが、爪の幹部だ。相当の実力者だろう」
「確かにラスボスって感じの雰囲気してましたね」
「社長の威圧感はあんなものじゃないけどな」
彼の本職は、公務員。公安の特殊部門——主に超能力者が潜入を行うための極秘部門である——に所属する公務員能力者であり、今はとある組織のスパイ活動を継続中。超能力者を集めて世界征服を図るその組織に、危険を犯して潜入しては情報を集めていた。
「明後日登庁するので、まあ顔とか背格好とか、外見の情報くらいはとっておいたほうがいいですね」
「ああ、すまない。頼む」
そしてわたしは、非能力者、ただの公務員。けれど、1つだけ人と違うところがある。能力者のサポートをするために、日本政府によって国民どころかほとんどの公務員にさえ公にされていない数々の超能力に関する見識を持っている——別に持ちたくて持っているわけでは全く、ないけれど。
小さな頃から要領だけはよかったわたし。テストの点数は毎回満点近く、それを見た親も先生もわたしの将来を勝手に期待していた。でも別に逆らう理由なんてなかったし、褒められるのは悪い気がしないから、言われるがままに勉強して、大学に入って。大学で勉強していたときはもう少し別の未来を想像していたような気がする——教育に関係する仕事に就きたいとか、そんなことを思っていた、ような。けれどまた流されるままに公務員試験を受けて流れ着いたのは、公安という教育とは掠りもしない省庁。あれよあれよという間に気づけばこの人の超能力を目の前で見せつけられて、潜入捜査官と公安内部とを繋ぐパイプ役に選ばれていた。全く現実というのはよくわからないなと思うけれど、直接潜入するよりも危険は少なくて、また意思決定する上司よりも責任の少ない、わたしにとってはちょうどいい仕事だと思っている。そんなことバレたらこの人にも上司にも、怒られてしまいそうだけれど。
今の仕事は「彼氏」が爪で得た情報を「デート」で聞き出して、まとめて上司に報告するという作業だった。正直話を聞いている限りは爪の統率なんてめちゃくちゃだし、彼が直接登庁して報告したってばれることなんかないと思うけれど、まあ規則は規則だから仕方がない。長いものには巻かれろ、それがわたしの座右の銘。いちいち上に突っかかったりはしない——だって面倒だし。
しかしまあ、それにしても。
今日初めてあったあの背の高い男のことを思い返した。
「かっこよかったなぁ」
「…相手は犯罪集団の幹部だが」
「やだな、何もないですよ」
堅物のわたしの「恋人」はこんな小さな一言にだって苦い表情で小言を言うので、ひょっとして嫉妬?なんて揶揄ってみたくもなるけれど、一応年上なのでそんなことは口が裂けても言えない。ちょっと面倒だなとも思うけれど能力は確かで、毎度齎される情報は確かに内部にいなければ絶対に手に入らなさそうなものばかりだった——まあ今日は偶然、関係のないわたしも幹部の顔を拝むことができてしまったわけだけど、それだって彼が内部の人間だと信じられていたからだろう。しかもスパイとして情報を集めながら、彼の他に数人いる外国人部隊を班組織の対抗力として味方につけようとしているらしい。この仕事が終わったらきっとすごく昇進するんだろうな、というのがここ1年ほど彼と「交際」をしている私の感想だった。
ふ、とそんなことを考えていると目の前に影が差す。得られたことを全て話し終えた「彼氏」が目の前に立っていた。そっと立ち上がるとさっきみたいに優しいキスが降ってくる。けれどここはわたしの家で、他にはだれもいないから別にもう、それを演じる必要もない。仮面をかぶる、必要も。少しずつ深くなる口付けに、腕を彼の首に回して応えた。慣れた風に横抱きにされて寝室へと運ばれていく。
ーーこの行為になにか意味があるわけじゃあない。
「ぁ……ん……っ」
鼻にかかったような声が自分の口から漏れでた。深い口付けを交わしながら、服の下に挿し込まれた右手に与えらえる小さな快感を受け止める。目の前のネクタイを解いて、シャツのボタンを1つずつ外してゆくと、唇が離れて着ていたシャツや下着を剥がされた。枕元にあったリモコンを操作して、部屋の電気を消す。
夜は静かに深まっていった。