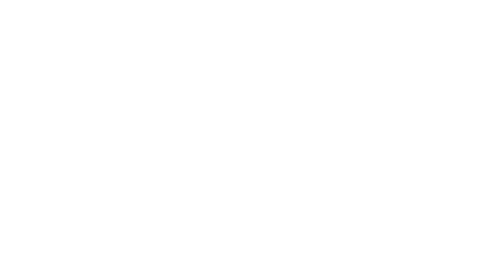隣の部屋から物音を聞き取って目の前にいた島崎が立ち上がった。右手の温もりも離れてゆく。
「……あ、」
「起きたようですね」
いつもと同じ抑揚の少ない声が淡々とそう告げる。彼の視線の先を同じように見つめるとガチャリと音がして、扉が開かれた。
「お前は……」
「目覚めましたか」
「……どういうことだ?」
峯岸はわたしと島崎がいっしょにいることに状況が飲み込めない、という風に眉を寄せた。彼女に住居をお借りしているところでしてね。キミが寝ていたベッドは私が使っているものなのですが。そう嫌味っぽく言う島崎に苛々とした表情を浮かべた峯岸は、お前は何者なんだとわたしを見つめていた。
「……ごめんなさい、まあ確かに、あなたのことは知っていたけど……しがない無能力公務員だよ、あんまり気にしないで」
「……そのしがない無能力公務員がなぜコイツと……」
「……なんで……拾ったから……?」
峯岸はわたしの要領を得ないその返事にわけがわからない、といいたげに顔を顰めたものの、敵でも危ない人間でもないということは理解されたのか、無能力だと聞いた以上最悪なんとかなるだろうとか、そういうことを思われたのかはよく分からないけれど、とにかくため息を吐いて警戒体制を解いた。わたしもなんでここで島崎と共同生活を送っているのかは実のところよく分かっていなかったので、詳しく尋ねられても困ってしまうし、深く尋ねずにいてくれたことは素直にありがたいと思う。峯岸はこちらに歩みよりながら再び口を開く。
「……とにかく、迷惑を掛けたようだな。オレも、コイツも」
「何を言っているんですか、キミを助けたのは私ですよ」
「普段はお前が彼女に助けられてるんだろ」
不満げに峯岸の言葉に抗議する島崎の様子はいつも見ている穏やかな様子と違って気心の知れた相手に対するそれで。「爪」内部のことは、能力だとか、名前だとか、職業だとか、そういう事務的なことは聞いていても、中の人間関係のことはまるで知らなかったし、『5超』とはいえ島崎が誰かと親しげに話しているところなんて想像もしていなかったので、彼のその様子に驚きさえ覚える。
そうか、ちゃんと「爪」の中では人間関係が、あって。あたりまえの、ことだ。ちゃんとこの人も、そこで、生きていたんだから。
「……まあ、ともかく。此処は何処だ?俺はそろそろ帰るが……」
「お送りしますよ、キミを最後に拾った場所までなら」
「ああ、助かる。……お前は、」
「……みょうじなまえ」
「……みょうじ、その……世話になったな。島崎を頼む」
峯岸はあまり多くを語らなかった。そもそも不必要なことをだらだらと話すようなタイプでもなさそうだったし、別に、多分もう一生この人と会うことは、ないだろうけど。ちらりと一瞬彼の視線が、テーブルに置かれたままだった少し萎びた花へ向けられる。一日花束のまま放置されていたそれに手を伸ばすと、花は再び生気を取り戻した。ありがとう、と呟くとふ、と逸らされる視線——どうしたんです?と尋ねる島崎にふたりとも何も言えずに、まあいいですが、と興味を失った彼が峯岸を一瞬で連れ去ったので、すぐに部屋にはわたし一人が残された。
「……お花、飾ろうかな」
花瓶ってどこにあったっけ。確か押入れの引き出しの中にあったはず。起き上がってテーブルへ近づくとふわりと花の香りが鼻腔を擽った。
「たしかに、いい香りだなあ」
これなら見えない彼にもきっと、その美しさが伝わるだろうか。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
峯岸は隣に立つ男のことを人並みに知っているはずだった。彼にいつもと同じ笑顔を浮かべたまま連れてこられた場所は確かに自らが意識を失う——あの神樹の根に力を奪われる直前に立っていた場所と寸分の狂いさえない。相変わらず優秀なテレポーターだと感心してしまいながら、隣で調味タワー、あるいは神樹が「あった」方を確認している島崎を盗み見ながら、峯岸は先ほどまで話していた女のことを思い返していた。
(島崎が好みそうな女には見えなかったが、)
良くも悪くもどこにでもいそうな女だった。何より、彼は感知能力が高いわけではないとはいえ彼女からは全く彼らと同じ物を——『爪』にいた頃なら誰しもが持っていただろう超能力を、感じられない。おそらく無能力の一般人だろう。たとえ公務員だったとして、彼らに、特に島崎にとっては歯牙にも掛けないような存在のはずだった。
「此処でよかったでしょうか」
「あ、ああ……」
「それはよかったです。では、」
「島崎、」
さっさと帰ろうとした島崎を呼び止めたのは半分無意識のようなものだった。なんでしょう、と尋ねる彼に峯岸は少し言葉を迷って、やがて口を開く。
「彼女とはどういう関係だ?」
「……私はただの居候ですよ」
それ以上でも以下でもない、と語る彼に峯岸は今度こそ黙り込んだ。そう答えるまでに珍しく言い淀んだ島崎の内心がどんなものであるか、「爪」でそれなりに交流があったとはいえ彼はどうも何を考えているのか分かりにくい。それでもきっと何かがあるのだと、そう察した。
「オレは店に戻る。店を閉めないといけないからな」
「そうですか。峯岸くんも元気にやっているようで安心しましたよ」
「ああ、お前もな」
またな。峯岸はその言葉を残して島崎に背を向けた。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
島崎は峯岸が背中を向けて去ってゆくのを黙って見つめていた。彼が自販機の向こう、交差点を曲がって消えてゆくのを確認してようやく、小さなため息を吐き出す。
「彼女とはどういう関係だ? ですか……」
彼の頭に渦巻いているのはつい先ほど彼に問われたその言葉。何も間違った答えは返していないはずだった。自分はただの居候で、彼女はその家主で。滞在費を多めに渡してはあるが、障害を持つ彼と共同生活をするのはたとえ彼にそれを補って余りある特別な力があるとしてもそう簡単ではないだろう。それでも文句を言わずに受け入れてもらえることは生きる手段が限られている島崎にとっては非常に都合がよく、またありがたいことでもあった。
しかし別に島崎もあの場所にこだわる必要などない。実際追い出されていたらそれはそれでうまくやるすべはいくらでもあっただろうし、「爪」が健在だった頃の貯金は贅沢をしなければある程度は暮らしていけるくらいの額に達している。それでもあの家に留まりたいと思った。思って、思うままに行動をした。そちらの方が面白そうだと思ったからだった。
——まあ、そりゃ、目の前で倒れてる人がいたら放っておけないでしょ。
峯岸と彼女を助け出した後、目を覚ました彼女との会話を思い出す。面白そう、その直感は間違っていなかった。だが島崎にとって、彼女はそれ以上の何かであるようにも感じられた。
「貴女のような人で世界が埋め尽くされていたなら、きっと超能力などなくとも幸せに生きられるのでしょうね」
誰もいない住宅街の小さな路地で、彼の呟きは誰に聞かれることもなく消えてゆく。そしてその音が消えた頃にはもう、彼の姿は其処にはなかった。