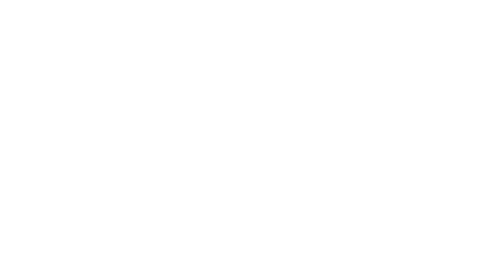
最後のピースはあなたが持っていた
「……ぅ、ん……?」
「目が覚めましたか?」
「……し、まざき……?」
ばたりと、音がつきそうなくらいに勢いよく体を起こすと、途端背中に引きつるような痛みが走って思わず体を抱きしめる。もういちどゆっくりと体を倒してからようやく、自宅のわたしがいつも眠っている布団の上に寝かされていることを認識した。
「……もしかして助けにきてくれました……?」
「そのつもりだったわけではないのですが……まあ、結果的にはそうなりますね」
「あり、がとう……」
「私のベッドには峯岸を寝かせてあります。怪我はないようですが……」
「ああ、彼も……助けてくれたの……」
相変わらず目蓋を閉じたままの彼が、貴女も外傷はなくて安心しました、なんて言葉をわたしにかけるのをどこか、人ごとのような気持ちで聞いていた。何度も何度も、わたしの中に描かれていたはずの島崎という男の像が壊されてゆく。そして。
「あ、ちなみに落ちてたものって……」
「ああ、携帯と、花束ですか?」
「……うん、そうそう……」
携帯も落としていたのか。ダイニングテーブルの方を指差す彼に、テーブルの上はこの高さでは見えないけれどきっとそこに置かれているのだろうと理解して頷いた。
「はい、通話相手が心配していたので自宅へ連れて帰る旨を伝えて切らせていただきました」
「ヨシフさん……あ、ありがとう……」
「花束はとりあえずそこに置いてありますが……どなたかへのプレゼント用でしたか?」
「……いや、そういう、わけでは」
ほんとうに、奇妙な気分だった。なんでわたし、否定してるんだろう。峯岸は隣で起きているだろうか、眠っていてくれたら、せめていまの会話は聞かないでいてくれたらいいと、そんなことを考えてしまう。
「でも、すごい偶然だったよ、峯岸のいる花屋だったなんて」
「やはり彼のことはご存知だったんですね」
「まあそりゃあね、スパイもいたし」
ああ、そういえばさっきの……そうつぶやいた彼に気がついてなかったのかと、少しおかしな気分になった。彼はやはり、興味のないものには少し冷たい。わたしだって衣食住さえ提供していなければ同じような扱いだったのかもしれないなと考えて小さく笑っていると、何を笑っているんですかと少し拗ねたような声が掛けられて再び彼へと視線を戻す。たしかに、何を笑ってるんだろう。何に——何にわたしは今、安心を覚えたの、だったっけ。
「貴女は超能力者ではないんですから、超能力者の争いに入っていってできることなんてあるわけないでしょう」
「まあ、そうなんだけど……神樹がそれ絡みと決まったわけでもなかったし……」
「ただのブロッコリーがああなると思いますか?」
怒って、いるのだろうか。仕事だから仕方ないじゃないと、そう返したわたしに呆れたようにため息をついた島崎に首を傾げてしまう。なぜ怒っているんだろう。——もうしかして、心配、してくれていた?いや、まさかね。
「あー、心配かけました?」
「当たり前です。ここは貴女の家ですよ」
その言葉にまた、安心してしまう自分がいた。そしてその向こうに落胆してしまう、自分も。家主がいなくなると何かと不便だから、だから心配していてくれたんだ。わたしがどうとかじゃあ、なくて。
(ああ、でも、心配してもらえただけで、十分——)
そこまで考えてはっとする。十分、なんだろう。わたしは一体、何を。
「……そもそもどうして峯岸を助けたんです?」
「え?」
わたしの心中の動揺を他所に島崎からも予想外の質問を投げかけられて声が裏返ってしまった。どうして、彼を助けたのか。貴女は面倒ごとが嫌いなのでは?呆れたような声が言葉を重ねる。
「まあ、そりゃ、突然倒れてる人なんか見たら、放っておけないでしょ」
「……見ず知らずの、他人でもですか?」
「他人かどうか、関係ある?」
当たり前のことを言っているつもりだったので、理解できないとでも言いたげな表情の島崎に少し困ってしまう。確かに少し、偽善者っぽかったかもしれない。面倒ごとが嫌いだなんて言いながら毎度巻き込まれているの、もしかしてわたしが自分で巻き込まれに行っているのかもしれない。つまり、わたし、少々頭が、悪いのかも。呆れられてしまっただろうか。たっぷり5秒くらい黙っていた島崎がようやく口を開いた。
「……意外と優しいんですね、知りませんでした」
「そうかな?当たり前のことをしただけだよ」
「……そう、ですか」
何かを納得したのかもしれない。小さく頷いて彼は口角を少しばかり上げた。それがなんだか心臓に悪くて思わず瞳を、逸らしてしまう。
「まあともかく、無事でよかったですよ。あの『神樹』はなかなか厄介もののようですね」
「!島崎も調べて……?」
「いえ、そういうわけではないのですが。貴女に近寄った時に何か強い力を感じましてね」
「そ、れは……」
思い出すと体が小さく震えるのが分かった。脳に直接語りかけるようなたくさんの声。神樹、神樹とくりかえすそれは明確に洗脳させるための、それで。あんなものが人の住む場所に当たり前にあるなんて、ただ触れただけ、だったのに。
突然右手に暖かなものが触れて顔を上げた。
いつかに嗅いだ匂いが鼻から広がって、息を呑む。
彼が、すぐそばでじっとわたしのほうへと、顔を向けて、いて。綺麗な顔だと、現実逃避をするようにそう、おもった。
「『神樹』ですが、先ほどニュースで消滅したと」
「え、消滅……?」
「はい。ですから、」
——もう、大丈夫ですよ。
抑揚のない声だった。いつもと同じ穏やかな表情で、いつもと同じ声。けれど右手から暖かな熱が、広がって。それで。
「——ぁ、」
ぽつりと、水滴が彼の右手に——わたしの右手を包む彼の手に滴り落ちた。それに気がついた彼は驚いたような、表情を浮かべていて。見えないのだから、こんなことをしたって意味なんかないのに。そう思いながらも俯いてしまう。体の震えは今も止まらないけれど、さっきまでわたしを支配していた恐怖はどこかへ消えて、今はそう、安心感さえ、覚えてしまう。
悪い人だと、思っていた。
実際、悪い人なはずだった。彼は敵だったし、戦いもした。一歩間違えばこの国がめちゃくちゃになってしまうくらいに非道いことをする人だった。そんな彼の言葉や温もりに安心する未来なんて、考えたことも、なかった。
彼はそれ以上何を言うでもなく、抱きしめるでもなく。ただ、右手を繋いだままそこにいた。わたしは流れてしまった涙を拭って、何度か小さく深呼吸を繰り返す。涙は簡単に止まった。体の、震えも。
「……島崎、突然ごめんね。ありがとう。峯岸さん?は大丈夫?」
「ええ、おそらくじき目覚めるかと」
それはよかった。
なるべく明るい声を作ってそう言うと、島崎はそうですねと、興味なさげに呟いて立ち上がる。右手を包んでいた温もりが離れてゆくのを名残惜しい気持ちで見送って。
——ああ、名残惜しいだなんて、そんなことを、わたしは、考えてしまうように、なってしまったのか。
日常に散りばめられたピースのどれにも気づかないようにして、それが一つの感情を形作ろうとしていることから目を背けて生きてきた。けれどもう、だめだった。最後のピースは嵌ってしまった。ごまかしきれない感情は彼の香りに、声に、温もりに。全てに胸を甘く鳴らせてしまう。
彼の目が見えなくてよかった。
きっと熱くとろけてしまったわたしの表情を、彼に見られなくて済むから。