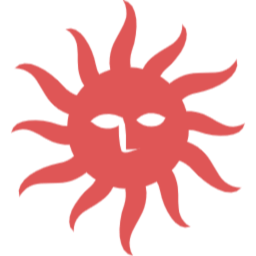
未来の話をしよう
――伝えたいことがあるから会いたい。
言われた言葉がずっと胸の中に棲みついている。翔陽がそんな風に改まって言うなんて滅多にないことだから、約束の日、私は緊張に見舞われていた。
年が明けて早々。年末年始はお互いの実家に帰省していたから、会うのは久しぶりだった。
仕事を早々に切り上げて翔陽の指定した待ち合わせ場所の近くまで向かうと、寒空の下で夜空を見上げている翔陽が目に入った。
「翔陽」
「名前!」
雪を溶かすような笑み。
駆け寄って、名前を呼び終わるよりも先にこちらへ視線を向けた翔陽は「おつかれ」といつもの調子で言う。白い息と緑のマフラー。柔らかいその表情は私の心の中で溶けた。
「仕事大丈夫?」
「うん。翔陽こそ今日は練習終わるの早かったんだね」
「名前と会うから残らないで帰ってきた」
「おお。珍しいね」
つまり、翔陽が練習を切り上げる選択するくらい今日告げられる話は重大な話というわけだ。
翔陽と付き合って約2年。私が社会人になってからは会うペースや時間帯も変わったけれど、特に問題があったようには思えない。悪い話は想定してないけど、改まって言うくらいだから私達にとって大切な話なんだろう。来月いっぱいでVリーグも終わりを迎えるから次の契約のことなのかなとも思うけど。
「翔陽夜ご飯食べた?」
何を言われても翔陽の選択を応援してあげようと心に決めて尋ねる。結局、今日中には翔陽の伝えたいことははっきりするんだし。
そう思っていたのに。
夜ご飯を食べ、カフェで少しだけ話しをして、じゃあそろそろ帰ろうか、という時間まで一緒にいても翔陽が「伝えたい事」を切り出すことはなかった。言うべきタイミングを計っているのか、結局その日、翔陽は珍しく私を家まで送ると言い出した。
素直に頷き、一緒に地下鉄に乗る。最寄り駅からマンションまでの数百メートル。隣に並ぶ翔陽からはいつもより浮足立っている感じがするけど交わされる言葉はなくて、マフラーに顔をうずめる。
何も言わず盗むように翔陽に視線を向けた。赤くなった耳。寒そう。だけど愛おしい。
「翔陽、もうマンションついちゃうよ?」
「う⋯⋯ごめん」
「良いのに、何言っても。私、翔陽の決めたことなら応援するし、悩みなら一緒に解決策考えるし、嬉しいお知らせなら全力で喜ぶから。あんまり緊張しないで話してよ」
私の息も翔陽の息も白く舞う。きっと私の耳も赤い。
促す言葉に観念したのか、翔陽は夜に溶かすような声量で話し始めた。
「あー⋯⋯言いたい事は2つあって」
「うん」
「1つは来シーズン、俺、ブラジルのチームと契約しようと思ってるって話なんだけど」
ああ、そうか。やっぱり。なんとなく翔陽が海外を選択する気はしていた。
影山選手が去年イタリアに渡ったし、バレーの為に単身リオに行くような人だから海外は多分、翔陽にとってそれほど遠い場所の話じゃないのだ。少し肩の荷が下りたと、私は気の抜けた笑みを向ける。こういう話の最悪のパターンってきっと、距離を置きたいとか別れたいとかそういうのだと思うし。
「予想的中した」
「え?」
「時期的にもタイミング的にも? まあ、そういう感じの話かなあって思ってて」
「じゃあ名前、今もしかしてあんまり驚いてない?」
「そんなこともないんだけど、でも言ったでしょ。翔陽が決めたことなら応援するって。ブラジル私も好きだし、思い出たくさんある場所だし、バレーも強いし! 翔陽が選ぶのわかるなぁって。今私に言うってことは内定もらってるってことだよね? すごいね、翔陽。いつも頑張ってるもんね。気軽に会えなくなるのは普通に寂しいけど、翔陽が海外で活躍する姿私も見たいし」
出来るだけ明るく言う。嬉しいも寂しいも、言ったことは全て事実だ。日本とブラジルは遠いけど、日本代表に召集されたら日本には帰国するだろうし、私が仕事でブラジルに行くこともあるかもしれない。未来は案外、なるようにしかならない。だからやっぱりいくら寂しくても応援するという選択肢は私にはない。
「名前」
「うん」
「もう一つの話なんだけど、こっちのが本題っていうか」
マンションまであと数十メートルのところで私の手を引いて翔陽が立ち止まる。私の前に回り込んで向かい合うように立った翔陽は、先ほどよりもずっと緊張した眼差しで私を見つめた。まっすぐ、ブレることもない視線。
「翔陽⋯⋯?」
どうしたのと意味を込めて名前を呼ぶ。
翔陽は深呼吸を繰り返し、その度に白い息は冬の夜に消えていく。
そして翔陽は言った。
「俺と結婚して」
「え?」
真剣な面持ちと、その言葉に冬の凍てつく寒さを忘れた。けっこん。ケッコン。結婚。遠くにあるようなものだと思っていた言葉が急に私の目の前に現れる。それはまさに青天の霹靂だった。
「これから先、どんな風にバレーをやっていきたいのかを考えたとき俺はやっぱり海外に挑戦したいって思って、強い奴と試合したり、もっともっと自分が上手になっていくところ想像してたら、名前の顔がパッて浮かんだ」
「⋯⋯私?」
「俺の日常に名前がいてくれてるのすげえ嬉しくて、応援とか、こうやって一緒に出掛けられるのとか、俺、本当に好きで。ブラジル遠いし、仕事のこともあると思うし、でもめちゃくちゃ考えて、ずっと考えて、俺やっぱり名前にはそばにいてほしい。名前には近くで俺がバレーしてるところ見ててほしい。ずっと応援しててほしい。我儘なこと言ってんのわかってるけど、名前がそばにいる人生がいい」
これまでの人生で感じたことのない感覚が体中を駆け巡る。私たちは血の繋がりもない赤の他人。別々の場所で生まれ、そして育った。見てきた景色も過ごしてきた時間も違うのに、こんなにも好きになることが出来て、好きになってもらえる。尊いと思う以外、あるだろうか。
真っ白な雪のように、不純物はなかった。余計な不安も心配も、これからの気がかりも、なにもなかった。
「する。翔陽と結婚する」
だから、私の本能が答えを出した。
「え!? 俺が言うのも変だけどもっと悩まなくて大丈夫!?」
冷静になれば、考えなくてはいけない問題点はたくさんある。仕事のこと、家族のこと、渡航のこと、友達のこと。でもそれは解決できない問題ではない。ゆっくり、一つ一つクリアしていけば良いだけの話なのだ。
「だって翔陽の言葉聞いてすごく嬉しかったし、一緒にいたいなって思うし、私が頑張れば仕事はどこでも出来るし。悩む余地ないよ」
未来に想いを馳せる。30歳の私。40歳の私。50歳、60歳、70歳の私。そんな風に年を重ねていく私のそばに翔陽がいてくれたら、これ以上に幸せな未来はないと思う。
「だから、うん。結婚しよう。これからもずっと、よろしくお願いします」
翔陽に向かってとびきりの笑みを向ける。泣きそうになったのは翔陽で、人のいない夜の路上で私を強く抱きしめた。緑のマフラーが私の頬に触れる。私の好きな翔陽の香りがした。
(21.06.18)