「はーい、見てらっしゃい来てらっしゃい!新作のイタズラグッズがたぁーくさんあるよ〜。ほらほらほーら。マクゴナル先生のような気難しい頭になってしまう授業の宿題だってこのとーりたちまちみんなが大好きなお菓子に変わってしまうよ〜!そこのお嬢さん、鼻にでっかいニキビがあるお嬢さん。さては夜中にポテトチップスを食べたな?でもだぁーいじょぉーぶ!このピンクのエキスを飲めば、見目麗しい美人に変わること間違いなし!まあ、一時間だけだけどねぇ。他にも摩訶不思議で面白ヘンテコなグッズが目白押し!さあさあさあ!」
ホグワーツの廊下の一角で聞きたくもない声が反響した。移動しようとここに来たのが間違いだった。時間がかかっても遠回りすればよかった。それは柱から現れた人物と、それを取り巻く光景を見て切に強く思った。見つかる前に戻ろう。両手に抱えた本を力強く握り締め、一歩足を後ろへずらす。だが、どんな悪運が己に取り付いているのか、下がった足元には空き瓶があって、それに気づかない僕は蹴ってしまった。小さく音を立ててころころと渦中の中へ吸い込まれるように消えた。それと同時だった。ちらりと足元へ目を遣ったそいつが僕を捉えたのは。背中に這う悪寒なんて露も知らないそいつは、たちまち嬉しそうな笑顔を浮かべて、いろんな生徒が跋扈してる中を押し出すように出てきて僕に駆け寄った。
「やあ!セブルスじゃないか!」
凛とした声が僕の名前を呼ぶ。生まれてこの方幸せなものしか見たことないと言わんばかりの弾んだ声だ。僕はそれも嫌いだ。フレンドなどと言って肩に腕を回してくる行為も嫌いだ。
「名前で呼ぶな。腕を回すな」
ぱしっと払うと次は払われないようにいっそう強く力を込めて腕を回してきた。執拗い。消えろ。そんな感情を込めて睨んだのだが、彼女は傷付くことや怯むことはあるのかと思わず聞いてしまいたくなるくらいものともせず、声を上げて笑った。
「友人なんだからいいじゃないか!」
「貴様と友人になった覚えはない」
「セブルスは記憶力がいいと思っていたが、それはあたしの思い過ごしかい? 君、そんなに衰えたんだね。可哀想に。その若い歳でおじいさんの脳を持つのは苦しかろう。だが、だぁいじょぉーぶ!あたしが開発したこの “若返り脳薬” を一滴飲めばあら不思議!あれほど歳をとった脳も少年少女時代に戻ること間違いなし!」
「僕の脳は年取っていない!」
「む? そうなのか? そうならそうと言ってくれよ、セブルス」
この、話を全く聞かない、全く噛み合わない奴はグリフィンドールに所属しながらスリザリンの僕やレギュラスに何かと理由をつけてはちょっかいを出してくる僕より一個上の先輩である。前に──向こうが勝手にべらべらとお願いしてもいない話を話しただけだが──では、組み分けの際スリザリンに入ろうと思っていたのだが、一人部屋は寂しくて寝られないとの理由でグリフィンドールに入ったらしい。馬鹿の上には馬鹿が居るというのは、こういうことなんだろう。
「そんなことより最近話しかけてきてくれないじゃないか、セブルス。友人のあたしはとても悲しいよ」
陽気に笑ったかと思えば、両手を顔にくっ付け声を上げて泣く真似をし始める。こいつは静かにするということはできないのか。
「誰が友人だ。僕に友人は居ない」
「あらあら? ではリリー・エバンズはなんなんだい?」
「かっ、彼女はっ、友人以上の存在ということだっ」
揶揄されているのは重々承知なはずなのに、思わず顔が赤くなってしまう。
「流石だねセブルス。うんうん。いやあ、あたしは嬉しいよ。いつも聞くが、やっぱり嬉しい。うん、嬉しい」
感心と呟きながら神妙に頷く。一体何が嬉しいんだと聞きたいが、またあのうざったい声の調子でべらべらと喋るのかと思ったら、その気は瞬時に萎えた。だけど聞こうとしようがしまいが、勝手に喋るのが彼女である。
「セブルスったらリリー・エバンズと居る時以外は、いつも一人だからね。心配していたんだよ。いやはや、グリフィンドールを嫌っているから、リリー・エバンズもさして友人とは思っていないのかと思っていたが、そうかそうか、大切か。それは良かった良かった。厨房のクリーチャーに言って今日の夕食は赤飯にしてもらおうか!」
「やめろっ!」
出し抜けに提案されたとんでも作戦を間髪入れずに止めさせる。こいつにはとことん敵わないと改めて痛感する。敵いたくもないが。こいつ、グリフィンドールを嫌っていることは解っているくせに何故自分が僕に嫌われていることには気付かないんだ。
「ん? おや、セブルス。次は魔法薬学かい?」
手にある本を見て言った。
「ああ」
「いいよねぇ、魔法薬学。スラグホーン先生の教えは実に面白い。ユーモアがあるから面白いのかな? いや、魔法薬学が面白いのか。まあいい。あたしもそろそろ行かねばならない時間でね。終わったら迎えに行くよ」
「来なくていい。むしろ来るな」
地下牢の教室を出たらこいつが笑って立っているのだと想像したら、げんなりとなること間違いない。しかも今日はグリフィンドールと共同授業だ。リリーとの時間に水を差されたくない。
「そうか、そうか。グリフィンドールとの共同授業か」
「なっ」
「何故解ったか、と聞きたい顔だね。いいよ、教えてしんぜよう。種明かしするまでもないことだが、邪魔されたくない理由でもあるのかと思ってね。そんな理由、リリー・エバンズ以外にないと思ったのさ。どうやら合っているようだね」
説明を聞いているうちに皺のできた眉間を見て、自慢げに鼻を鳴らす。それがまた鬱陶しい。
「解ったなら来るな」
「いいじゃないか。恋愛に熱中するのも学生の本分だが、友人との縁を大切にするのも学生の本分だよ。ね?いいだろう?」
「年中頭の中にイタズラのことしかない奴と縁を結んだ覚えはない。僕にはリリーで充分だ」
すると奴は少し考える素振りを見せて、やがてにんまりと笑みを浮かべた。それに激しく嫌な予感を覚えたのは、僕の気の所為だろうか。
「そうか、そうか。ならば君に会いに行くのは辞めるよ」
いや、気の所為らしい。すんなり引いてくれて助かる反面、何か隠しているんじゃないかと疑う気持ちもなくならない。奴はひらりと赤い裏地のローブを翻らせ、背中を向けた。肩越しに視線を遣り。
「ではまた!親しい我が友人よ!」
無駄に演技がかった声量で高らかに言うと、ローブの中から箒を出した。校内で飛んではいけないという校則は知らないのか。だが、校則どころか決められたルールの一つも守らない彼女にそれを言うのもおかしな話だ。何を言う前に彼女は商品の前で群れをなしていた生徒に解散するよう命じて去っていってしまう。アリの群れみたいな生徒数が減っていく中、ぽつんと残された僕はさっきの言葉を脳内で再生させていた。そして一つのことに気付く。それに気付く頃には彼女はもう居なくて、時すでに遅しであった。リリー目当てに来るつもりだな!? 叫びたい衝動に駆られたのは、今日が初めてだった。
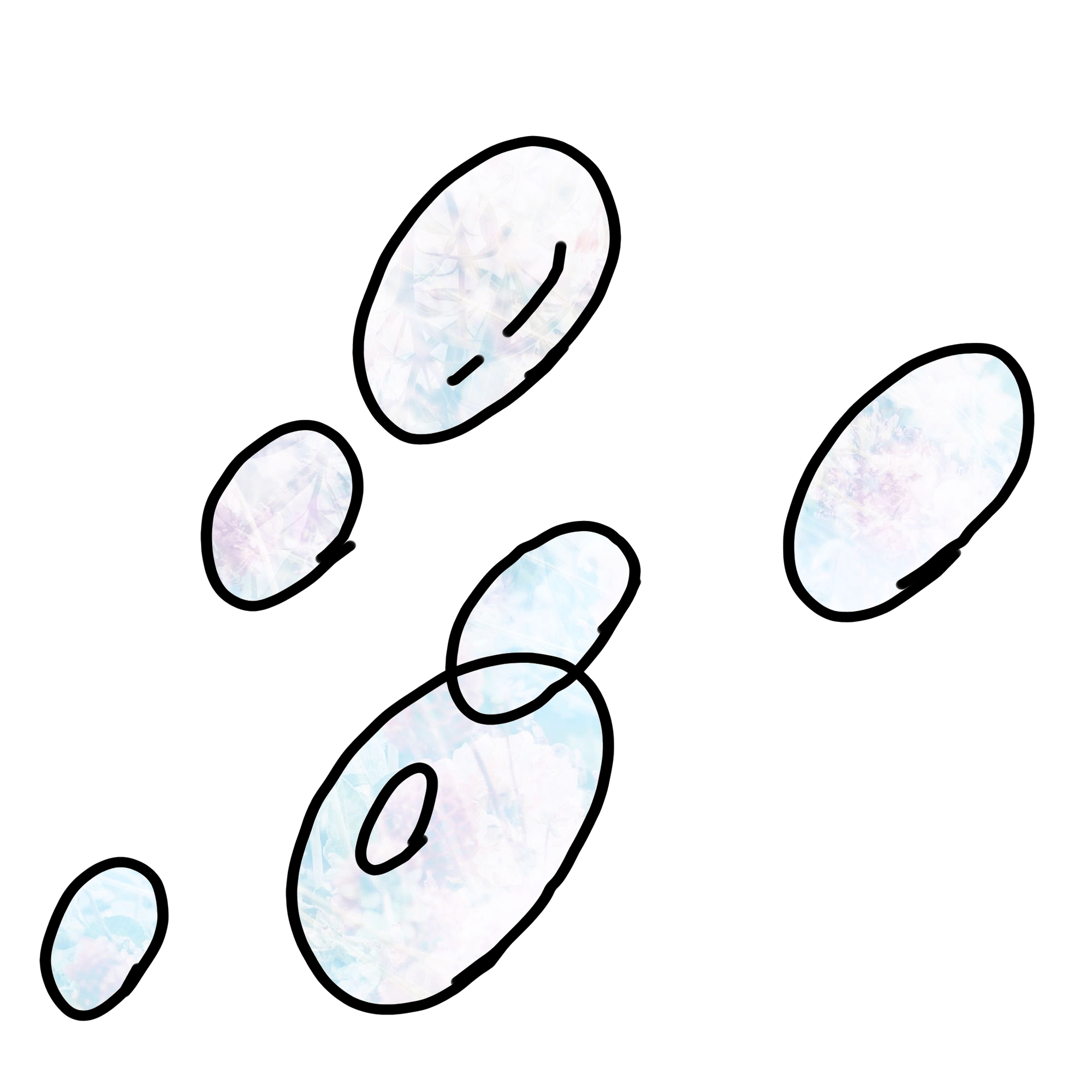
うるさい奴に絡まれる一日
、