イライラする。何に、ではなくただイライラする。無性に腹立たしい。今何か気に入らないことが起きれば、間違いなく私の声はドスを帯びるだろう。何かが起こるまでもなく、話しかけられただけで爆発しそうだ。つまり、それくらい限界を迎えているのだ。
「いつまでも本を眺めていないで、食事を摂ってください。いい加減食べないと夜中に起きるはめになります」
私の心境なんて全く知らない幼馴染のレギュラスが、目の前のテーブルに小さな皿をコトリと置いた。両手くらいの大きさの皿には九時を回って食べても明日の朝に響かない程度の軽い食べ物がいくつかあった。その傍にパンを置く。そして白い湯気を漂わせるトマトスープも。
「要らない」
怒りを顕にしないようになるべく感情を抑えて言ったら、その声はとても冷たくなってしまった。人の善意を一蹴するように突き放したにも関わらず、彼は傷付いた様子もないようで「食べてください」と言った。
「明日は大切なクディッチの練習がある日です。ビーターに求められるのは、強い腕力と当たっても怪我しない体の強さです。スリザリンの名を背負ったビーターがこれでは、明々後日の対グリフィンドール戦に負けるのは火を見るより明らかですね」
「うるさい。食べればいいんでしょ」
「最初からそうしてください」
イライラ度が増した。その気持ちをぶつけるようにパンを噛みちぎってアツアツのトマトスープで一緒に流し込む。いつもなら「熱っ」と飛び跳ねただろうが、そんなことにも気が向かないほど苛立っているので、飛び跳ねはしなかった。だが「チッ」と舌打ちが零れる。長いソファに座っていた私の隣に、静かに腰を掛けて本を読むレギュラスが、それを見兼ねて「熱いのは当然でしょう。水を飲みますか?」と尋ねてきた。私は首を横に振った。
「寝ないの?」
次こそはと声を調子を上げて聞くと、いつもに近い明るい声が出た。一瞬彼が眉を顰めたが、ぱちりと瞬きをしてみればいつもどおりの無表情に戻っていたので気の所為だと片付けた。
「眠くないので寝ません。それにまだ消灯時間ではないでしょう」
「ふうん」
「それより咀嚼して嚥下してください。丸呑みしては喉に詰まりますよ」
「解ってる」
なんでこう彼は時々お母さんになるのか。今も「ああもう。口の周りを汚さずに食べれないんですか」と険しい表情をしてティッシュで私の口の端を拭く。それが鬱陶しくて「やめて」と払った。
「世話される歳じゃない」
「世話されないように大人になってください」
「子供扱いしないで!」
ムキになってつい声を荒らげてしまった。しんと静まる談話室。幸い私とレギュラス以外誰も居ないので、他の寮生の視線を浴びずに済んだ。はっと意識を取り戻す時には遅く、レギュラスは私をじっと見ていた。恥ずかしくなって「ごめん」と謝る。さっきの威勢はどこか、今は萎れた花のように黙る他できなかった。
「早く食べ終えてください」
そう言って彼は再び本に目を向けた。カチャカチャと談話室にスプーンの音がする。時々隣からページをめくる音も。食べ終えるまで、私達に会話はなかった。やってしまった。彼は悪くないのについ当たってしまった。いやだけど子供扱いするレギュラスも悪い。ああでも。と頭の中で天使と悪魔が壮絶に鬩ぎ合ってうるさい。そして全て平らげるとそれを見計らったようにレギュラスが立って皿を手に取った。急いで彼の手に自分のを重ねる。
「どこに持ってくの?」
「決まっています。厨房ですよ。屋敷しもべ妖精に返すんです」
「いい、私が持ってく」
「座っていてください」
「はい」
強く言われて引き下がってしまった。有無を言わさないように言われてしまえば、これ以上粘るのも返って彼に迷惑をかけてしまう。ソファに腰を下ろして、談話室を出ていくレギュラスの背中を見つめていた。それから彼を待っていたが、がちゃりと扉を開けて入ってきたのはスネイプ先輩だった。私が談話室に居るのを見て目を瞬かせる。
「随分早いな」
「ここで食べたんです」
「ここで? 誰が食事を持ってきたんだ?」
「レギュラスが」
「ああそういえば、レギュラスは先に帰っていたな」
「あの、レギュラスと会いませんでしたか?」
「いや会っていない。おおかた皿を屋敷しもべ妖精に返しに行っているのだろう。少し待てばそのうち来る」
「はい」
スネイプ先輩は「おやすみ」と言って男子部屋に入っていった。それからというもの待てども待てどもレギュラスの姿はなかった。帰ってくるのは同じ寮の違う子ばかり。おそらく最後に入ってきた先輩にレギュラスは知らないかと尋ねれば「会っていない」と言われてしまった。
「遅いなぁ」
探しに行こうにも外出禁止の時間になってしまっては行くのは無理だ。罰則が明日のクディッチに関わるものならそれこそレギュラスにも怒られる。仕方ないと諦めて彼の帰りを、静まった談話室で待つことにした。それから消灯時間の間近、談話室の扉が開かれる音がした。本からばっと顔を上げると、今度こそレギュラスだった。
「レギュラス!」
「寝ていなかったんですか?」
「まだ謝ってないし礼も言ってないから待ってたの」
「謝る? 何に?」
「子供扱いされた時急に怒鳴ってごめん」
「ああ、それですか。気にしてないのでいいですよ」
「ほんと? あと食事持ってきてくれてありがとう」
「気は収まりましたか?」
「え?」
なんのことだと目を丸くした。レギュラスは私の顔をじっと見て、質問の意図を理解できていない私に断りもなく抱き寄せた。突然のことで頭が状況に追いつかない。抱き締められた腕の中で彼の名を呼んだ。
「れ、レギュラス? どうしたの?」
「貴女、苛立っていたでしょう」
「うん」
「何について苛立っていたかは知りませんが、」
彼に抱き締められたまま頭を優しく撫でられる。ぽかんとする私に彼は言葉を続けた。
「落ち着いたようで良かったです。自分に素直が取り柄の貴女が、人を慮って感情を抑えるなど、らしくない。怒鳴るなり泣くなりして鬱憤を吐いてください」
彼の声はどこまでも優しかった。見上げた時、私は息を小さく呑み込んだ。滅多に笑わないレギュラスが、口元を綻ばせたのだ。ふっと呆れるような、微笑みかけるような笑顔。それを見て、心をきつく縛っていた縄がゆるゆると解かれた気持ちになる。彼の胸板に頭をぐりぐりと押し付けた。
「ありがとう」
子供をあやす手付きで撫でられる間、私はそれに身も心も委ねることにした。言葉も目線も合わないけど食事中の気まづさや恥ずかしさは微塵も感じられなかった。
私が感じたのは暖かなぬくもりと彼の優しさだけ。思い起こせば彼には小さい頃から、気が立っていた時によくこうしてもらっていた。やっぱり幼馴染には適わない。暖かな時間を噛み締めるように、私はそっと瞼を閉じた。
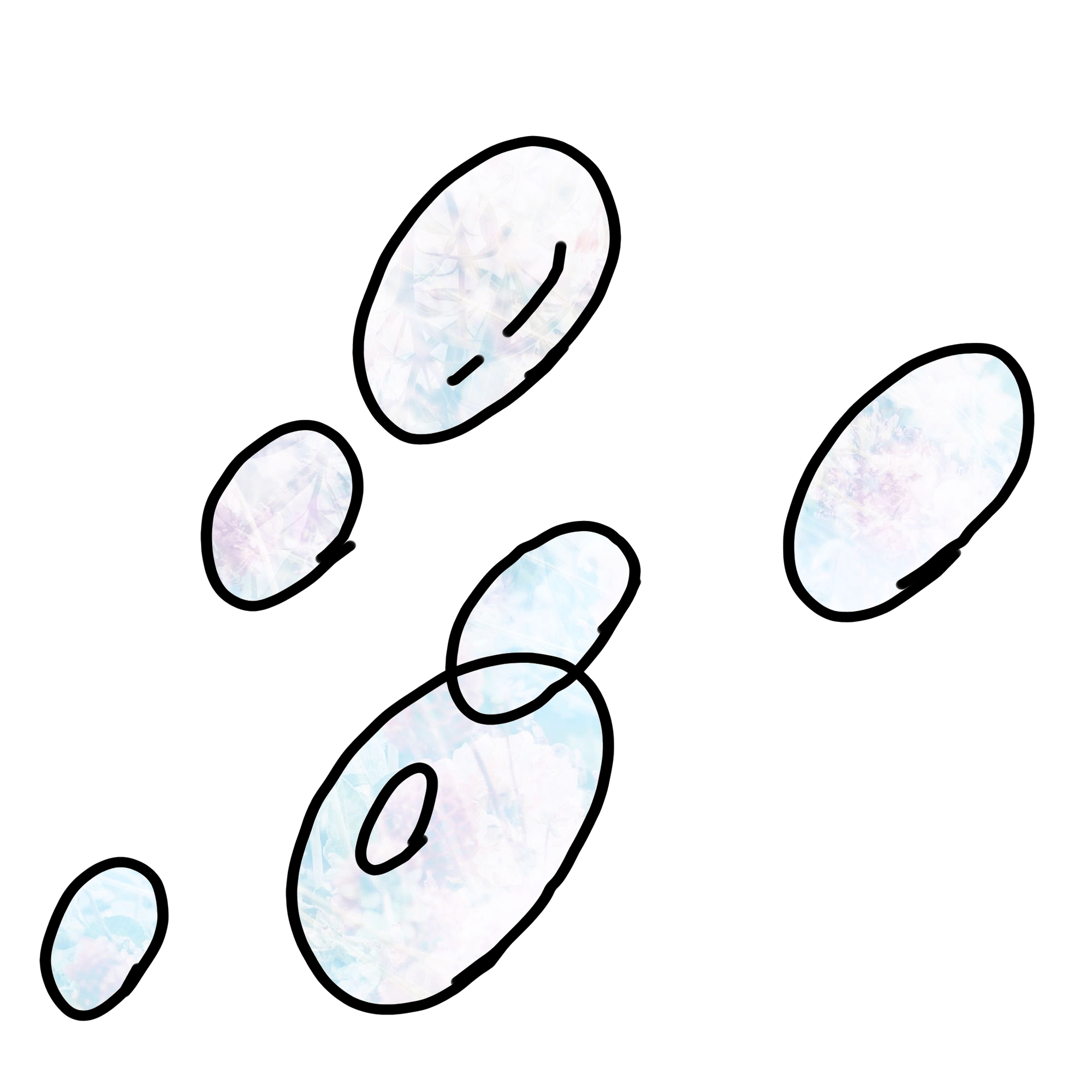
ひとときの休息
、