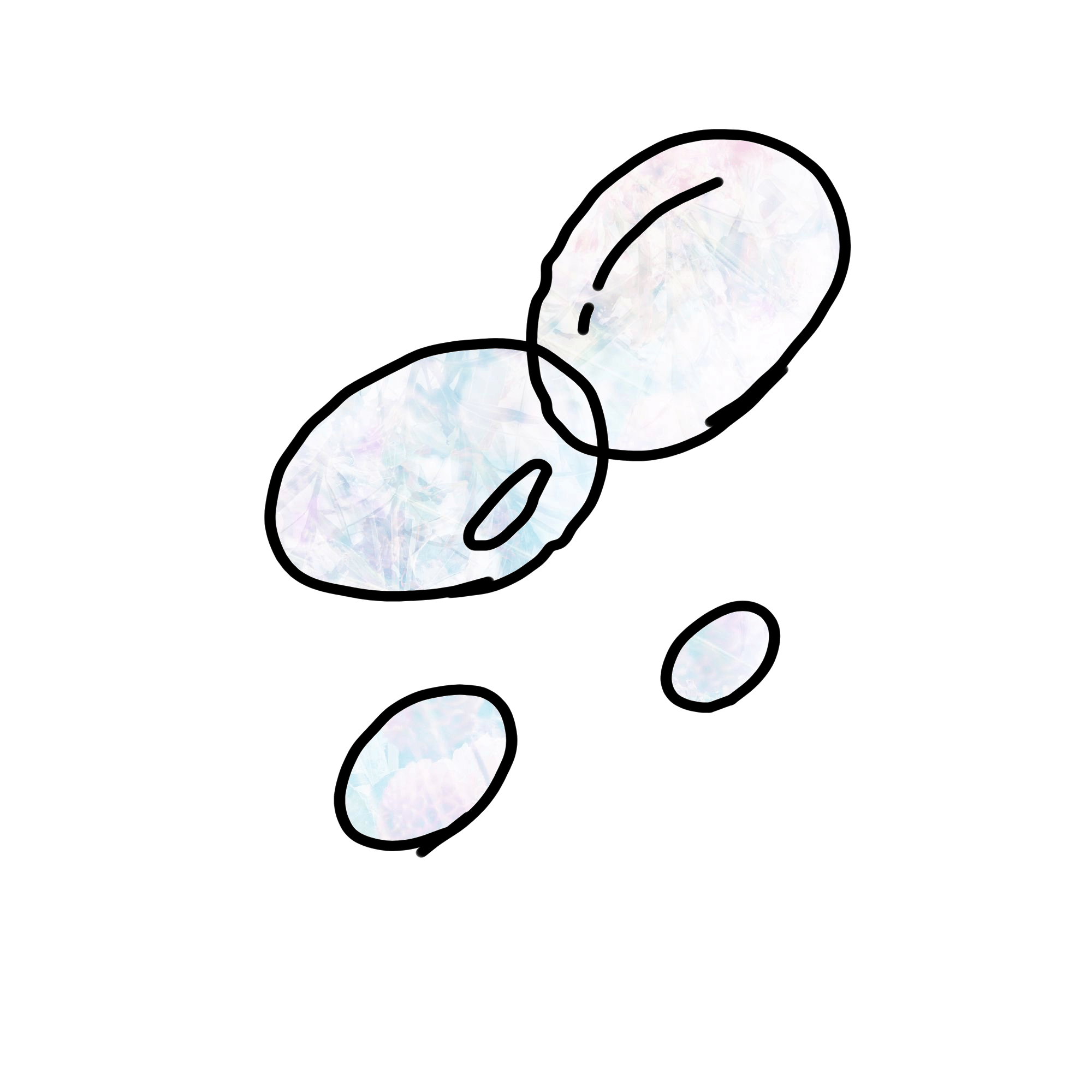
仮面を取り繕う怯懦
「気持ちは嬉しいけどごめんなさい。」
夕暮れ時の喫茶店。店内はモダンを意識していて、客の話に介入しない程度にジャズが流れている。外の喧騒と遮断されたここは、初めて来たにも関わらずすぐに気に入った。運ばれたシフォンケーキは甘い。美味しいと頬を緩ませていたが、それも数分後には暗鬱な色が浮かんでいた。ひとつのテーブルを挟んで向かい合う男と女。男は肩を落とし、手元のコーヒーカップを見つめる。女はシフォンケーキを一口かじるが、飲み込むとフォークを置いて水を飲んだ。男は続けざまにこう言う。
「理由を聞いてもいいかな」
わたしは、こくりと頷いて瞳を彼に向ける。彼はすっかり意気消沈していて、知りたいはずの理由さえ聞きたくないといった感じだった。気づいていても、わたしは言う。
「好きな人が居ます」
「そうか」
「ごめんなさい」
「いや、こちらこそ話を聞いてくれてありがとう」
傷心した事実を隠そうといつも笑顔な彼にしては不格好な笑みを浮かべて、手を振った。気丈な様を見せたいんだろうけど、なるほど、目は口ほどに物を言うとはよく言ったものだ。彼は席を立つ。その手には白い紙が握られていて。
「あ、すみません、お幾らでしょうか」
「ここは僕に持たせてくれないかな」
「ですが」
「いいから」
「解りました。ご馳走様です」
「ああ。じゃあね」
「はい」
彼は背を向けてレジへ一直線に進んだ。テーブル席にはわたしがぽつんと残されて、テーブルにあるシフォンケーキには食欲が促進されなかった。苦々しい珈琲は決してわたしの好むところではないが、それでもその珈琲に、視線を釘付けにされて傍から見れば飲みたくて堪らないといった表情になっているに違いない。
「ごめんなさい」
掻き消えるような声だった。自分でもびっくりする程の小さく、それでいてか細い声だった。まるで肌に触れるか触れないかの瀬戸際に居るハエのような。
「泣くくらいなら断らなきゃいいだろ」
その声はひとつの壁を隔てた隣席のものだった。声からして男性。だが、そんな情報よりも先に、頭には声の主の人像が浮かび上がっていた。その人物はわたしが小さい頃からよく知っていた者であったからだ。
「好きなやつだったんだろ」
声の主であるメロは、姿を現そうとはしなかった。隣席に座ったまま、声を投げてくる。
「いいんだよ、これで」
きゅっとスカートを掴む。お気に入りのスカートに皺ができるなんて、今はどうでもよかった。ただ、眦から溢れそうになるそれを止めることができれば、なんでもよかった。
「いいの。言ったじゃない、わたしは恋人を作らないって」
それは巣立つ時、わたしが自分に課した枷だ。一生恋人を作らない。想いを伝えない。純潔を捨てない。自分はその枷を枷と認識したことはなく、逆にそれはわたしを守る盾だった。と同時に相手を守る盾でもあった。
「それにね、メロはさっき好きなやつって言ったけど、わたしは多分、いや、確実にあの人を好きじゃないよ」
「嫌いって意味か」
「違うよ、もう。メロならそれくらい解るでしょ。あの人と話してて楽しかったし、一緒に居て気が楽で安心した。会うたびに胸がときめいて、凄く嬉しかった」
約束を取り付けれた日なんか、ずっと胸が踊って最初の日は、それこそ寝られなかった。約束の日が待ち遠しくて、早くその日にならないかななんて思ったりもした。
「会う時は化粧もして、あの人が好きそうな恰好もして、好きそうな店に行ったりした。だけどね」
ああ、店内に流れる曲がいきなり大音量になってくれないかな。そうすればわたしという人間は、音楽に隠れて消えてしまえるのに。
「あの人に告白されて、胸は満たされなかったの」
言うと同時に、胸に針で刺されたような痛みが走った。わたしはひとつずつ本音を紡ぐ。本音や弱いところなるべく見せないようにしていても、どうしてか、メロにだけはそれが通じない。話さなくていいこと、話す必要がないこと、話したくないことまで、流れの激しい川のように止めることができずに溢れてしまうのだ。それでも彼は何も言わず、そうかと流してくれるので、もしかしたらそこが気に入ってしまったのかもしれない。
「逆にすっと波が引くように冷えてしまったの」
あれだけ弾んでいた心が嘘みたいに一瞬にして冷えてしまった。その事実は、決して素通りできるものではなく、しかし気の所為だと流して彼との交際を始めるわけにもいかなかった。
「なんでだろうね。もしかしたらわたしは、あの人のことを友人として好きだったのかもしれない」
けれど、なら、どうしてあんなに楽しかったのだろうか。どうしてあんなに待ち遠しかったのだろうか。その質問は今になっても解答を迎えることはできていない。
「ほんと、最低だわたし」
好きかもしれないと思って、あの人に近づいてしまった。好きかもしれないと思って、あの人と何度も会ってしまった。それ故に、彼を傷つけてしまった。
「なんで、普通に人を好きになることができないんだろ」
普通とはなんだろう。そんなことは解らない。けど、わたしだって周りみたいに一人の人間に好意を抱いて、普通に交際を初めて、普通に結婚したい。けど、わたしはそれができない。人を愛することができないんだ。一時的に胸を踊らされても、両想いだと確信すれば冷めてしまう。愛したいのに愛せない。矛盾した人間は、人を傷つけることしかできない。ならばわたしは、恋人を作らないでおこう。それが好きな人であっても。それが両想いだとして、その時冷めなかったとしても。いつかくる “冷め” のために、相手を傷つけてはならない。わたしは何度泣いたっていい。自分が泣いて済むくらいなら、いくらでも泣いてやる。けど、相手を傷つけるのは、それ以上に辛い。
「ねえメロ」
「なんだ」
「メロはさ、ずっとわたしの傍に居てくれる?」
その質問に一般的な意味、所謂恋愛がないってことは、彼なら百も承知のはずだ。彼はわたし以上に頭の機転は利くし、理知的な思考だってできる。洞察力に長けている彼は、わたしの心情なんて手に取るように解ってしまう。静かに聞いていた彼は、やがてこう言った。
「気が向いたらな」
木で鼻を括ったような態度だが、今はそれが身に染みてありがたく感じる。泥に埋もれていた心が、少しだけ、ほんの少しだけ軽くなって、ふと笑みが出た。
「ちゃんと見届けてね」
「あいにくそんな暇じゃねぇよ」
「そっか」
シフォンケーキを口に含む。シンプルな生地と添えられたソフトクリームが、腔内で甘さと丁度良い冷たさを広げて、滅入った気分を持ち上がらせてくれた。ゆくりなくも軽快なメロディーを発した携帯が、空気を一転させる。呼び出しは友人からだった。ディスプレイに表示された友人とは、この後会う約束をしている。
「またね、メロ」
「ああ」
鞄を持って店を出る。ちゃりんと鈴の音が鳴った喫茶店を背にして、アスファルトにヒールを鳴らして歩く。ここへ来ることはもうないが、シフォンケーキの味を忘れることは、ないだろう。あんな塩っぱいシフォンケーキを忘れるなんて、できるわけがないのだから。
「怯懦な奴」
ガラス越しから、店に背を向けて去っていくあいつを見ながら、俺はチョコを齧った。
、