休日と言えば世間の恋人達は何をするのだろうか。デートだったり家で一緒に映画とか見たり、もしくはそれぞれの友人と遊んだりするのが、多いと思う。私の友人も例外ではなかった。付き合い始めて三年の恋人とは、土日のどちらかは必ず出掛けると言う。いや、正直に言って凄い。別に毎週毎週外へ行きたいとかは思わない。最近は暑くなってきたし、天下の大都会のここは人集りも多い。なんで彼はこんな二十三区内に住んでいるのか。
まあ、外がいくら暑かろうと人の喧騒が酷かろうと、彼の建てたこの建築物内では、それらは一切遮断される。常に一定の温度を保つこの部屋は、今までは格段涼しいとも暑いとも思わなかった。けど、例年真夏になる時のみこの部屋の凄さを痛感できるのだ。外は乾涸びてしまう程気温も湿度も高いというのに、ここに入った瞬間一気に暑さに対する殺意が削がれてしまう。常に冷房の効いたこの部屋は、どの場所を探しても代用が効かないくらいに私の肌に合ってしまっているのだ。
「まだ終わんない?」
ソファに座って、持参した三冊の本を読み終えてしまった私は、視線を彼に移した。目の前には、相変わらずの白いシャツにジーパンという見慣れたラフな格好をしている彼が私に背を向けて、手に持っている紙と机上のパソコンを交互に見ていた。
「まだ待ってください」
「それ一時間前も聞いたー」
いっそのこと、この本を投げてしまおうか。そしたら少しはその仕事ばかり見つめる彼が私を見てくれるかもしれない。好奇心に身を燻らせる私は本を持った。すると、彼はくるりと椅子を回して紙を持ったまま私を見て言った。
「正確には三十八分前です」
それだけ言ってまた背中を向けるなんて、ほんと憎たらしい。
「解ってんなら早くしてよ、ばか」
私は本を投げるのを止めて、そこら辺にあったクッションを掴んで顔を押し当てた。それこそ呼吸する隙間を与えない程に。全く! 見て欲しいって思った時にこっち向かないでよ!以心伝心というものを、ちょっぴり信用しかけてしまった。突然振り返るものだから、びっくりしてしまった。それに、やっぱり狡いと思う。ぐりぐりとクッションに顔を擦り付け、深く顔を沈める。これ以上は沈まないというのに。けれど、そうでもしないと、早くなった動悸を抑えることはできないのだ。
「そのクッションによく顔を埋めてますね」
「わあっ!?」
「そんなに驚きますか」
耳元でした声に、肩どころか全身で飛び跳ねてしまった。思わずクッションを床へ放り投げてしまい、声のした方からは大きく離れてしまった。広いこのソファは五人掛けになっているので、二人分のスペースを空けたとしても、落ちるなんてことはまずない。
「びっくり、させないでよ」
「すみません」
一瞬心臓が止まったかと思った。そうさせた元凶はというと、私の持ってきた本に関心を抱いたらしく、いつもの―親指と人差し指で挟む―持ち方で本の右上の角を掴んで、珍しいものを見つけた子供のように、目を瞬かせ首を傾げている。人を驚かせておいて無視ですか。少しのイラつきが生じたが、彼の淡泊さは今に始まったことではないので、まあいいかと流した。
「仕事終わったの?」
ようやく心臓も落ち着きを取り戻したので、彼の傍へと移動した。彼は本の表紙を見ながら言った。
「いえ、少しの休憩です」
休憩とかするんだ。思えば私は彼の仕事をしていない時を見たことがない。いや、正確に言えば、休憩している時にここへ来たことがない。私が居る時は自然とそういう事になるか、私が無理矢理休憩させるかしかなくて、もしかしたら私が居ないと一生この人は仕事をやり続けるのかもしれない。延々に黙々と。淡々と仕事をこなす様は、同期の生まれの私から見たら尊敬の念を抱く対象だった。
「竜崎のことだから、休憩とか言って三分しか休む気ないでしょ」
「バレましたか」
「もう」
何事も限度がある。適度がベストだ。彼―名を竜崎と言う―のように、真っ黒な隈を作って髪もぼさぼさにして、猫背になり内向的になってしまうのは、恋人から言えば絶対だめだ。
「そのクッション、好きなんですか?」
「え?ああこれ。うん、好きだよ。色もいいし、何よりビーズクッションだから柔らかいの」
手繰り寄せたピンクのクッションは、私が持ってきた物だ。機械と一つの客用の机と五人掛けのソファ。それしかないこの部屋に、ピンクのクッションは違和感しかなかった。だがそれも慣れてしまえば特に思うことは無い。
「そうですか」
「あ、竜崎も触ってみたいんだ?」
「え?」
まじまじと見つめる彼は、きっとそうなんだ。触りたくてこっちに来たんだ。可愛いなんて思うのも仕方のないことだろう。なにせ彼は大抵の物には関心を抱かない。それどころか見向きもしないので、その竜崎がこうして物に関心を抱く様は、一種の母性本能が働いて、恋人の私は喜ばしく思う。
「はい。ぎゅーって抱き締めてみて、凄い気持ちいいから」
「どうも」
クッションを半ば押し付ける形で渡した。どう扱っていいのか解らないのか、彼は幾度となく様々な位置からそれを見るだけで、抱き締める気配は伺えなかった。
「よく、凹みますね」
両の手で左右から力を加えると、クッションは物の見事にひょうたんみたいになる。なんか、凄いシュールな絵面だな。二十歳を過ぎた男性がクッション一つに、不自然な動作でそれを堪能するという、さながら研究員のような光景は、何度見ても慣れそうにない絵面だ。
「気に入ったようだね」
気づけば面白そうに私は笑っていた。
「いえ」
「え、気に入ってないの?」
「はい」
言うや否やそれを私に戻してきた。
「好きじゃなかった?」
「クッション自体は柔軟で、触り心地も決して悪くありません」
「じゃあなんで?」
時々彼のことが解らなくなる。単に私に理解できないのか、彼に解らせる気がないのか。うんうんと唸ったところで、打開するのは困難だってことは解ってるので、私はこうやって彼に聞くのだ。教えて、と。
「クッションを持つべき人は私ではないからです」
「なにそれ」
あっけらかんと言う彼がふざけているなんてことはないだろう。むしろ彼は大真面目だから冗談なんて言わない。筈。
「岩から剣が抜けないのと同じです」
「ぶはっ!」
「吹くほど変なことを言ったつもりはありません」
「いや、だって、竜崎の口からまさかエクスカリバーネタが出るとは思わなかった」
「失礼ですね」
今度友人と飲みに行く時にこの話をしよう。絶対お酒が進むだろう。ひととおり笑い終えると、私は改めてなんでか聞いてみた。
「じゃあさ、クッションを持つべき人とか居るの?」
「そうですね」
竜崎は頤に細い人差し指を曲げて宛てがい、そしてしばらく黙り込んでいた。多分二分くらいだと思う。結論に至ったのか、彼は指を離して私を見る。
「居ます」
「居るんだ。竜崎の思うクッションの持つべき人って誰?」
ワタリさんかな?とか思う私の頭に、銀髪の黒いスーツを着た男性が思い浮かんだ。ワタリさんは所謂竜崎の保護者のようなものだ。と言っても、私が勝手にそう決めつけているだけだが。竜崎のことはあまり知らない。それは思っていることや考えていることに留まらず、彼の生い立ちにも当てはまる。知っている彼のことと言えば、甘党で、急に突拍子もないことを言う変人で、そして名探偵ってことくらい。彼曰く、その界隈での知名度はそこそこあるらしい。
「貴女です」
「へ?」
竜崎について考えていたので、彼の言ったことに対し耳を傾けるのがワンテンポ遅れてしまった。
「なんで私?」
確かにそのクッションは私の私物ではあるけど、それだけが理由なのだろうか?
「クッションを持つ時、それは貴女が心恥ずかしい時です」
探偵の口振りで推理する彼に私は呆然としていた。一方彼はと言うと、どこか満足げであった。
「わ、私、そんなにクッション持ってた?」
「はい」
「嘘」
「嘘ではありません」
自分でも気づかなかった。触り心地いいなーとは思ってたけど、彼に気づかれる程触っていたとは。
「流石だね」
「単に貴女が解りやすいというのもあります」
「馬鹿にしてる?」
「気の所為です」
そっかー。私、そんなにクッション触ってたんだ。私は押し戻されたクッションを見下ろし、ふと疑問が湧いた。
「竜崎っていつも仕事してるじゃん。どうやって気付いたの?」
私がここへ来た時もワタリさんがお菓子を持ってきてくれる時も、私が知るところ殆ど仕事をしている。休憩だって全然ないし、あったとしてもほんの五分、十分程度だ。私だってたまに訪れた休憩という時間を全てクッションに費やしてるわけじゃない。なのに、どうして気付いたんだろう。
「好きな人のことを知りたいと言うのは、私らしくないと思いますか?」
机に並べられた色とりどりのお菓子を見ながら竜崎は言った。いつもは聞いてるこちらが小っ恥ずかしくなる言葉を、目を見て平静に言ってのけるのに、今は目を合わせようとしない。
「そ、か」
どうしよう。手を繋いでいるわけでもない、肌を密着させているわけでもないのに、彼の熱が移ったかのように頬が自然と熱くなっていく。隣で座っている彼もそれ以上は何も言わずに、お菓子に向かって手を伸ばしそれを口に放り込む。私は言葉の一つも投げれず、この居た堪れない空気をどう切り抜こうかと考えていた。でも、嬉しかった。彼のことを気になって知りたいと思うのは、私だけなんじゃないかと思っていたから。だから、竜崎も私のこと知りたいと思っているのを聞けば、これ以上の嬉しいことはないだろう。
「またクッションに埋めるんですね」
「恥ずかしいの」
でもやっぱりダメだ。嬉しいのはあるけど、面と向かってオープンに言われたら、恥ずかしすぎてクッションに埋める他ない。やっぱり私って、彼の言うとおり解りやすい人間かもしれない。
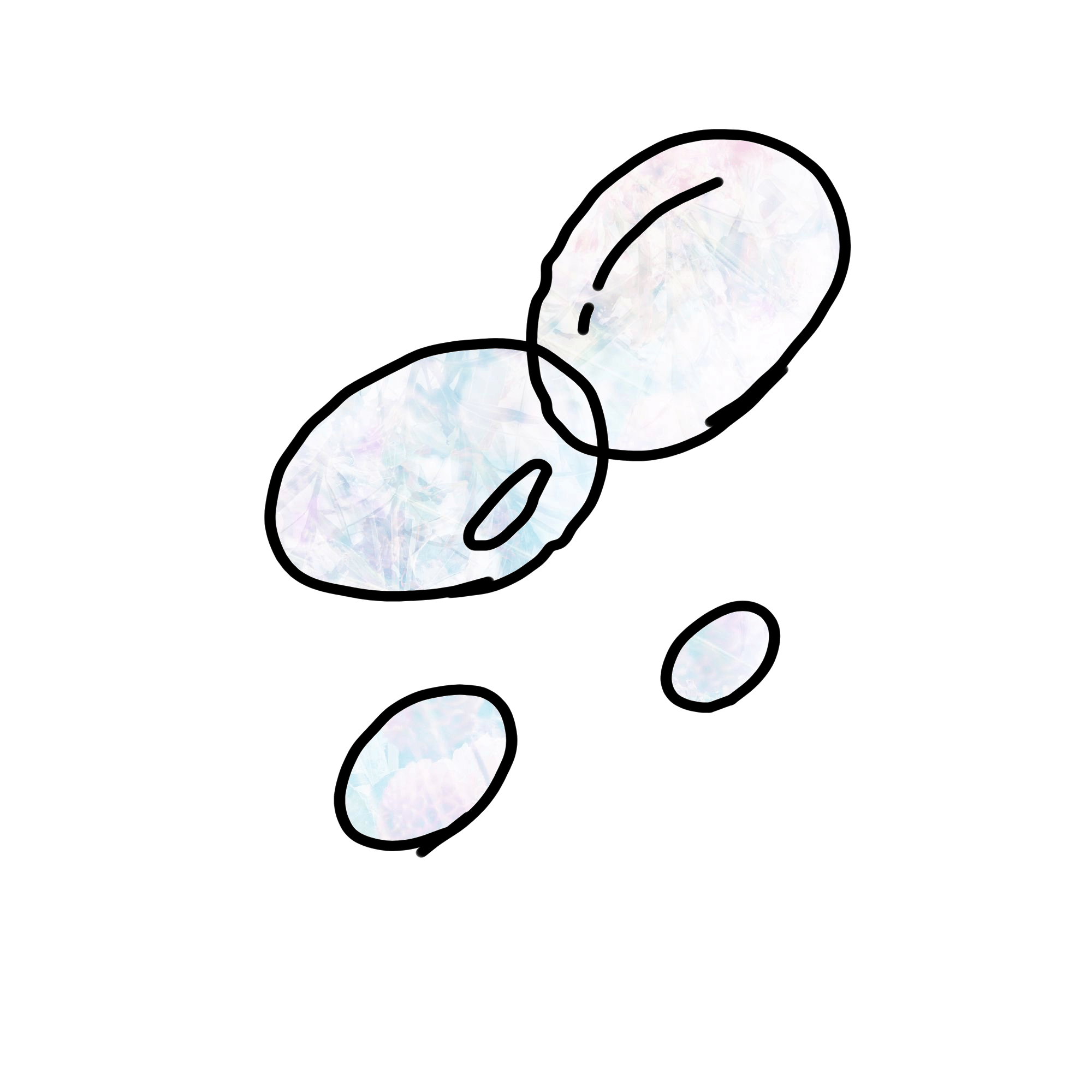
クッションに沈むひとつの愛
、