変光星・前篇
御幸一也様
お元気ですか? わたしは元気です。
突然なのですが、色々あって、鵜久森高校を受験することにしました。
成績的にはもうちょっと上の学校を目指せるって先生には止められるんだけど、お父さんとお母さんは好きにしろって言ってくれたから、受験頑張ろうと思います。
偏差値が高くて有名な学校に通って毎日勉強勉強になるより、勉強には余裕があって、やりたいことをめいっぱいやれる環境がいいなと思ったので、鵜久森にしました。
鵜久森に入って、野球部のマネージャーをやろうと思うの。
だからかずくん、もし青道に入ったら、青道の内部事情とか手紙に書かないでね。わたしも書かないから。東と西だから夏の大会で会うことはないけど、他で対戦する可能性はあるしね。
もしかしたら練習試合とか、大会とかで、かずくんに会えるかもしれないね。それはそれで楽しみです。
(中略)
今回もだらだら長くなっちゃった。読むの毎回めんどいでしょ、ごめん。
少しずつ暖かくなってきたけど、季節の変わり目は気温の上下があるし、かずくんもおじさんも体調を崩さないようにしてね。
それじゃあ、また。
天乃英様
元気ですか? 俺も父さんも元気です。
受験校決めるの早くないか? まだ四月……手紙が来た時点では三月だったけど。周りのやつらは受験なんてまだまだ先の話だと思ってるし、俺もそうです。
まあでも来週には進路希望調査があるって先生が言ってたし、そんなものなのかな。
鵜久森高校ってあんま名前聞いたことないなと思って、先生に聞いてみたけど、駅伝のほうがまだ有名だって? 野球はそんな聞かないって言ってたぞ。父さんは名前さえ知らなかった。英が選んだのならそれなりに理由があるんだろうけど。
まあ、英が後悔しないならそれでいいんじゃない
俺のほうは、今のところ気の早すぎるスカウトがあったのが青道ってだけで、監督たちにはこれからスカウトが増えてくるからゆっくり決めろって言われてる。俺、どこがいいとかあんま考えたことなかったけど、前手紙に書いたすごい捕手は青道に入ったみたいだし、やっぱ青道かな。兄ちゃんも青道だったし。
(中略)
べつに手紙長いのは読んでて面白いから気にしてないよ。俺そんなに書くことないけど。
江戸川のみんなは元気です。みっちゃんとかに、たまに英のこときかれるから、元気にしてるって答えてるよ。
じゃあまた。
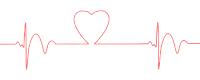
父と母の仕事の都合で、江戸川のあの家を離れてからはや五年──
高校二年生、初夏。
今朝コンビニで買った高校野球の雑誌を流し見していると、「英ちゃーん」とクラスメイトから声をかけられた。
「南朋くん、来てるよ」
「あ、はーい! ありがと!」
雑誌をぱたりと閉じる。目当てのページにはまだ辿りつけていないから、雑誌を小脇に抱えて、お弁当を手に立ち上がった。
「お待たせ」
「うん。なに読んでたの?」
「野球王国。……押すから持ってて」
中学二年生のときからの友人である松原くんは、交通事故の後遺症で下半身に麻痺が残り、現在は車いすで生活している。普段はハンドリムを操って一人でどこへでも行ってしまうのだけれど、一緒にいるときはわたしが押すというのがお決まりになっていた。
ブレーキを解除してハンドルを握る。
すっかり腕に馴染んだ重みに体重をかけると、察した生徒たちは道を開けてくれた。松原くんがニコ、とほほ笑むとみんなも笑って手を振る。学年全体の優しい気質もあるけれど、松原くん本人の人望の表れでもある。
「あ、御幸一也載ってる」
「ちょっと、そこはわたしより先に読んじゃだめ! あとにして」
「いいじゃないか少しくらい」
あとで一緒に読もうと思っていたのに。後ろから腕を伸ばして雑誌を奪い取ると、松原くんはけらけら笑いながら後頭部で頭突きをかましてきた。
「そんな英に今日はいい話を持ってきたよ」
「いい話? なぁに」
「うん。明後日、デートしない?」
ざわっ、と生徒たちの色めきだった視線が音を立てて集まってくる。
悪戯っぽく口角を上げた松原くんの表情は、例えば野球部のみんなにサーキット追加を指示するときや、試合のための作戦会議をしているときと全く同じだ。かわいらしい笑顔の裏側に見え隠れする強かな腹の底、中学生の頃とそっくり同じ。
──つまり、なにか企んでいる。
「なになに、南朋くんと英ちゃんがデート!?」
「ついに二人そういう関係に!?」
廊下にいた知り合いがわくわく顔で近寄ってくるので、松原くんは「いや」と肩を竦めた。
「そういうんじゃなくてさ。日曜日、英の初恋の君の試合があるから観に行きたいんだよね」
「「「初恋の君っ!?」」」
「まーつーばーらーくーん!!」
松原くんの形のよい頭を両手で掴んでギリギリ締め付ける。慣れっこの彼は「あはは」と軽く笑ってしれっと続けた。
「高校野球界では超高校級捕手ってけっこう有名なんだ。中学進学と同時に英が転校して離ればなれになっちゃったんだけど、当時からずっと手紙のやりとりを続けてて、いまだにメールじゃなくて文通してるんだよこの二人。しかも一切会わずに。もうじれったくて」
「「「キャー!!」」」
「人の事情をべらべら喋るなっ!」
鵜久森高校、野球部。
かずくんの青道から遠く離れたこの場所で、わたしはマネージャーをやっている。
松原くんが誘ってくれたのは、青道グラウンドで行われる練習試合だった。
鵜久森野球部には縁のない話だが、部員数が百名にも迫る青道野球部では、夏の大会までに厳しいレギュラー選抜があるらしい。そのため、春の都大会や関東大会のあとはほぼ毎週末、練習試合を組んでいるのだ。
「ね、御幸一也どれ?」
行きたくないと渋るわたしの自宅に朝っぱらから突撃してきた松原くんは、それはもう楽しそうな顔でグラウンドを眺めていた。
私立の強豪だから当然だけど、野球部専用のグラウンド、しかも二面、すぐそこに専用寮、室内練習場にウェイト室付き、専属の調理師さんまでいる。この設備の豪華さ。
現在、中堅に掠る程度の鵜久森には夢のまた夢だ。
「ねえ、どれってば」
部員数百名に対して、女子マネージャーは見える限りで四人。片岡監督をはじめ、OBからのコーチも何人かいるという。名ばかりの顧問兼監督とブレーンの松原くん二人で野球部を支えるうちとは大違い。
「ねえ英」
さすがに無視するのも忍びなくなってきた。
「……あそこのキャッチャーだと思うけど」
「そうなんだ。雑誌でよく見てたけど、防具つけてるとやっぱりわからないな。それで、現実逃避は終わったの? 別に意地悪で連れてきたわけじゃないんだよ」
眼下のグラウンドでは整列が始まっていた。
東東京の古豪・帝東高校 対 西東京三強・青道高校。練習試合とはいえ一見の価値がある。事実、OBさんのほかにも他校からの偵察は何人か来ていた。
「存じております。こんな好カードの練習試合、観に来ない理由がない。西東京とはいえ春や秋の大会では青道と当たる可能性もじゅうぶんにあるし」
「なんだ。わかってるじゃないか」
転校してからは一度も会っていないけれど、高校に上がって雑誌で取り上げられるようになってからは見かけるたびに買っていた。
わたしよりもずっと小さかったかずくん。
随分と身長が伸びて、体も大きくなって、すっかりイケメンに成長している。スポーツサングラスなんてこれまた洒落たものまでかけて。きっと女子人気も高いんだろうなぁ、「御幸くーん!」なんて黄色い歓声を浴びる姿が目に浮かぶようだ。
……実際人気キャラだったしなぁ……。
離れてみると改めて、人を惹きつける要素をいくつも与えられた男の子なのだということが判る。
そのかずくんが、キャッチャースボックスへ向かう途中で一瞬だけこちらを向いた。
なにか気になったのだろうか。
松原くんは比較的どこに行っても視線を集めてしまう。車いすに座った学ランの男の子が見学席にいるのなんて珍しいだろうし、それでつい見てしまったのかな。
「英を見てる」
「……え?」
「僕じゃない。英に気づいた」
どきり、と心臓がへんな感じに鳴るのがわかった。
グラウンドに目をやるけれど、かずくんはすでに所定の位置に腰を下ろしている。こちらには背を向けているから顔は見えない。
そうこうしているうちに試合が始まった。
関東大会に登板して注目を集めたという一年生投手や、去年までは粗が目立っていた三年生投手のピッチング。青道の強打線に堅い守備。それに立ち向かう帝東、こちらは大会でよく見るスタメンが半数程度しかいなかったから、メンバーを抑えているのだろう。
松原くんも、広げたノートを見下ろして満足げだ。
「うーん青道、いい投手だったね。それ以上に捕手がいい。アーリーにも観てもらえばよかった」
「御幸レベルを求めるのは酷だよ……。いいの、投手はうちのほうが優秀だから」
「そう思う? いつも梅宮とけんかばっかりのくせに」
「それは梅宮くんがいつまで経ってもズボン履かないからでしょ……。いい球投げるだけが、いい投手じゃないしね」
今頃、学校で松原くんの残したメニューをこなしているはずの部員たちを思い返す。
『南朋くんのために』──
その一念で集まった足立ロケッツ。
負けられない理由はどこの学校の、どのチームにもある。どの選手にも。
けれどこんなにも崇高な理由をわたしはほかに知らない。その一員に自分を入れてもらえたことが、どこか申し訳ないほど。
そしてわたしは、鵜久森野球部の梅宮聖一以上に、頑強な信念を持つエースを知らない。
帰ろうか、と声をかけようと松原くんを見ると、口角を上げた彼がグラウンドのほうに視線をやった。
第二試合へ向けた準備が始まるベンチで、防具を外したかずくんが、今度こそしっかりとわたしのほうを見つめている。ぐっと体を強張らせていると、「僕ここで待ってるから」と楽しそうな松原くんに腕を叩かれた。
それとちょうど同じタイミングで、かずくんも、青道のキャプテンに肩を叩かれる。
見学席から少し離れたところで、ネットを挟んで、五年ぶりに顔を合わせた。
手紙で文字のやりとりはずっとしていたけれど、直接言葉を交わすのは本当に久しぶりだ。なんとなく、本当になんとなくだけれど、電話も一切しなかったし。
松原くんや野球部のみんなや鵜久森の生徒たちと話すときとは違う、どこか身の竦むような緊張感に震える。
どうしようこの子、かっこいいな。
すっかり『御幸一也』だ。
「来てたんだ」
「……う、ん。うわ、かずくんだ」
「『うわ』ってなんだよ。失礼だな」
くしゃっと顔を歪めて笑ったその顔に、ようやく息ができたような気がした。こういう笑顔は子どものときとあんまり変わっていない。
知らないうちに見上げるほども大きくなってしまったことがなんだか寂しかった。
男の子って、一瞬で女の子を追い越してしまうよね。
「鵜久森でマネしてるって書いてたよな。一緒にいたのは? 野球部?」
「うん、一緒に鵜久森で野球しようって言ってくれた子、松原くん」
「あー、なんか覚えがあるな。手紙に書いてた」
「そうそう、その子」
どこかぎこちない会話を交わすわたしたちを、見学席のOBさんや、片づけで通りかかる青道の部員たちがちらちらと一瞥している。
なんだか居心地が悪いな。ますます早く鵜久森に帰りたい。
彼のほうも少しばつの悪そうな顔をして、足元に視線を落とし、意味もなく爪先で土を蹴った。
「えっと、……よくわかったね、わたしだって」
「わかるよ」
どこか不満そうに、かずくんは呟いた。
「わかるに決まってる。どこにいても、英なら」
「……、……うん、まあ、そりゃそーだ。わたしも、防具つけててもわかった、し」
なんだか凄いことを言われた、ような、気がするが……防具をつけていても遠目に歩き方でかずくんだと判別できた、自分も人のことを言えないのかもしれない。
「鵜久森ってセーラーなんだな」
「え、ああ、うん」
「……なあ、なんで青道来なかったの」
かずくんがネットに指をかけた。
なんにも考えずに、そうするのが当然のように、その武骨な指先に触れる。すぐにこの距離感は子どものときのそれだと気づいたから手を離した。
わたしたちはもう子どもじゃない。
高校二年生で、青道野球部の捕手で、鵜久森野球部のマネージャーだ。
「遠いから?」
「……来てほしいなら『来て』って言ってくれないと、わからないよ。大体、かずくんの青道より先に、わたしが鵜久森に行くって決めたのよ」
「ま、そうだけどな。……言ってみたかっただけ」
ネットにかかったままの彼の指がゆるくほどかれて、拳をつくる。
「なんとなくわかった。『松原くん』が、理由なんだな」
「……ん」
今度こそ、そうするのが当然だった。わたしも握りこぶしをつくってこつんと当てた。
手の大きさ、全然ちがうな。当たり前か。
……五年って、おおきい。
「きれーになった。変なのに絡まれたりしてねーか?」
「大丈夫、うちのエースがリーゼントの元ヤンだからいつも盾にしてる」
「なんだそれ面白いな。……いや元ヤンならうちにもいるけど」
「ああ、倉持くんだっけ? かずくんこそ女の子ファン増えたでしょ。あんまりぞんざいに対応してたら恨み買うわよ。野球以外のことには昔からドライだったけど、人間関係もうまく形成しなきゃ。ちゃんと野球部以外に友達できてる?」
「ははは……さすが英ちゃん……」
できてないんだな、さては。
昔から野球に対してだけはとにかく純粋だった。手紙には書いてこなかったけれど、中学時代だってトラブルの一つや二つあっただろう。高校に入ってからも、クリス先輩が故障で一線を離脱したあとは、いつもより精神的に余裕がなかったみたいだし。
まあ、でも、先輩になったことでなにか変わったのかな。
「でも、今日の試合観て、かずくん楽しそうで安心した」
「俺も、英が楽しそうでよかった。……このあとは?」
「もう帰る。学校でみんな練習してるから」
「そっか。また返事、書くから」
「うん、待ってるね」
……あれ、へんだな。
緑色の細いネット越しにあてた指と指を離したくなくて、お互いなんだか変な沈黙になってしまった。
「……じゃあね」
「ははっ、わかったって、行けよ」
「ちょっとかずくんから離れて」
「意味わかんねぇ、なんの譲り合いだよ」
「じゃあはい、せーのっ」
一斉に一歩ずつ後ろに離れた拍子に、ようやく磁石みたいにくっついていた指の背と背が弾かれる。
そうしたら自分たちの子どもみたいなやりとりがおかしくなってきて、わたしたちは肩を揺らして笑いながらさよならをした。
TIAM top