火星ソーダ・前篇
「英お腹へったなんか食べもの持ってないー?」
ずしり。
両肩や背中や頭のてっぺんに重みがかかり、聞き慣れた人の声が頭上から落ちてきて、そして周囲にいた生徒たちが一気にテンションを上げる。
背後から圧し掛かってくる人の正体なぞ振り返らなくても判るけれど、文句を言うために後ろを見ようと思ったら、両肩に回された腕は抱擁を通り越して拘束する勢いで首を絞めてきた。
ほぼ
もちろん力なんてほとんど入っていないから苦しくはないけど、真っ昼間の校舎のど真ん中で後輩女子にかける技じゃあない。
「ちょっとちょっとなに首絞めてるんですか鳴さん」
「お腹へった〜〜」
「それはさっき聞きました! 重い! 苦しい! いくら野球部のなかじゃちっちゃい方っていっても体重65キロもある人が……っ重い重い潰れるっ」
「なに? 誰がチビだって? 勝手に人の体重暴露してんじゃないよ」
「うわあああん原田センパイ平井センパイ助けてえええ」
「大体65キロなんて軽いほうだろーが!」
「ギャアアアア」
成宮鳴──関東No.1サウスポー。
稲実の
マネージャーとして入部した当初からちょっかいをかけられ、あの憧れの成宮鳴が気にかけてくれるというのが嬉しかった時期もあるけれど、度を越して意地悪されるようになってからは一切ときめかなくなった。いくら関東ナンバーワンでも甲子園投手でも、近くにいて一緒に過ごしていればいずれ夢は醒めるものだ……。
一見すると今をときめく超有名人に後ろから抱きしめられているように見えないこともない。
鳴さんに憧れる女子生徒たちのソワソワするような羨望の視線も、ちょっとやばいかもと感じる嫉妬の視線も、全部ぜんぶ勘違いですよー! この人私のことペット程度にしか思ってませんよー!! って大きい声で叫んでやりたい。
バックハグ、その実態は裸絞。
制服のポッケに忍ばせていたキャンディーを、つむじにぐりぐり顎を突き立ててくる鳴さんの眼前に差し出した。
「やっぱ持ってた」
「鳴さんがいつもいつも乞食しにくるからでしょうが」
「ん? 今なんて? 先輩に向かってなんて?」
「痛い痛い痛い!!」
今度は大事な大事な左手でガッと顔面を掴まれる。
ひどい扱いされるって解っているのに憎まれ口を叩かずにいられない自分の性格を恨んだ。
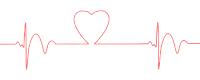
四月頭の始業式に先んじて、野球部ではすでに春の都大会が開幕している。
今回三年生の先輩に代わって私は記録員としてベンチに入れてもらっていた。起用の理由はよくわからない。来るべき世代交代のときに備えて、三年生の先輩たちの背中にしっかり学び秋以降へ生かせと、そういうことなのかなと自分では思う。
ちなみに記録員が私だと発表されたときの、鳴さんの反応が以下──
「いや〜出世したねぇ、あのヘナチョコ英が記録員か! ホントに大丈夫ぅ? ちゃんとスコア書けんの?」
「鳴さんは私をバカにしすぎでは!?」
「ヘナチョコだったのは事実じゃん」
ハハ〜ンとご機嫌に笑いながら、背番号1のゼッケンを手にした鳴さんは私に背を向けた。
常日頃から彼にいじられる私を愉快に見守る三年生の先輩たち、特にカルロス先輩と福井キャプテンは私の両脇にそっと近づいてきて、ぽんと肩に手を置く。
「あれで喜んでんだぜ。ガキだからあんな言い方しかできねーの」
「一年生の頃の天乃さんを一番構ってたのは鳴だからさ、きっと嬉しいんだよ」
幸か不幸か、先輩たちのフォローがけっして嘘でないと解る程度には、私は鳴さんのことを知っていた。
昨年秋に続いて2番を背負うこととなった多田野に絡むその背中へ目をやると、視線に気づいたとしか思えないような絶妙なタイミングで彼は振り返った。
ぱち、と視線がかち合う。
鳴さんはにんまり笑った。ナルシスト感満載、いつもの自信家の笑みだ。
「まぁせっかくベンチに入れることになったんだから、俺の輝かしい活躍、精々一番近いとこで目に焼きつけなよね!」
俺の輝かしい活躍……。
いや、鳴さんはそりゃもちろん注目されるし活躍するだろうけれど、自分で言うか。
彼に絡まれるのに辟易した頃、「成宮先輩のナルはナルシストのナル」とぼそっと多田野につぶやいたのを聞きつけた鳴さんに見事首をロックされたことを思い出してしまった。
カルロス先輩が小さく噴き出して、私の肩に顔を埋めて笑いを堪える。
「……もーちょっと素直に喜べませんかね、あの人」
「「それは無理」」
福井キャプテンまで。
でも実際、春にベンチに入れてもらったということは、夏は多分スタンド組だ。
これが、鳴さんの試合をすぐ近くで見ることができる最初で最後の機会。
有難くも恐ろしかった。
四月七日──
昨夏の甲子園準優勝校たる稲実と、今春のセンバツベスト4の薬師。今大会で注目度ナンバーワンといっても過言ではない対戦だ。キャパ五千の明治神宮第二球場は興奮する観客で埋め尽くされていた。
両チームとも先発はエース。
互いに実力を出し惜しみする相手ではないことを解っているから。
薬師ベンチはこれまでの試合でよく見ていた通り楽天的で明るい。楽しそうにバットを振って試合開始を待つ轟や三島などの要注意選手を、稲実ベンチのカルロス先輩たちはどこかつんとした様子で眺めている。
三年生の先輩たちは実力に見合っただけの自信をそれぞれ抱いている。それが相応しい人たちだと思う。
カルロス先輩も、白河先輩も、山岡先輩も──もちろん鳴さんも。
けれど、秋を惨敗に終えたのちようやく迎えた公式戦、あまりの迫力に怯えそうになるときがあった。
威圧感。貫禄。気迫。
闘志というよりは、矜持。
自分たちこそが王者だという自負、確信、それを裏付ける、長く辛い秋冬の記憶。
呑まれて、私まで食い潰されそうになるほど。
暴君は沈黙している。
タオルを肩にかけたまま、ベンチ最後列に腰を下ろし、底冷えする炎をその双眸に揺らめかせながら。
──異様な緊張感だった。
「天乃、緊張してるの?」
トン、と私の手の甲を指で叩いたのは多田野だった。「震えてるけど」その言葉を聞いて自分の手を見下ろすと、シャーペンを握る右手は僅かに揺れていた。
緊張。
確かに、記録員というプレッシャーに緊張もしているけど。
「なんか、……怖くて……」
「怖い?」
「……鳴さんが」
後ろにいる本人に聞こえないように声を潜めたつもりだったが、横に立つ国友監督には聴こえてしまったみたいだ。ちら、とこちらを一瞥してまたグラウンドに視線を戻す。
自分のチームのエースを怖がるなんて、呆れられてしまっただろうか。
重苦しい沈黙に包まれたベンチのなかで、福井キャプテンだけがそれを弾き飛ばすような笑顔を浮かべている。
試合が始まると、初回の稲実の攻撃は三人できっちり終わってしまった。
センバツ帰りでノっている真田投手が先発なのだ、初めのうちは彼の実力や進化を見極める必要があるし、スコアが動かないのも無理はない。むしろ昨年からほとんど一試合を投げ抜くことのなかった彼が疲労を見せはじめる、あるいは投手を交代する後半戦からが勝負。
静かに立ち上がった鳴さんがゆっくりと歩いてくる音がする。
冷たい気配は私の横でぴたりと止まった。
知らず知らずのうちに震えていた手を抑えながら見上げると、彼はひたとグラウンドを見据えたまま浅く息を吐く。
ぽんと頭の上に掌が乗っかった。
撫でるというよりはゆらゆらと頭を揺らされる。「う……」「なんですか」と控えめに抗議してみたものの、鳴さんの視線は前を向いたまま。
怖がるな、ちゃんと見てろ。
雑な手つきのなかに、そんな声が聴こえた気がした。
野手陣の準備が整って順番にベンチを飛び出していく傍ら、鳴さんは指先でわたしのキャップのつばを掴んだ。
しれっとした顔のまま勢いよく下へ引っ張られて、視界が塞がれる。
「わっ、もー、何するんですか!」
鳴さんはやっぱり何も言わなかった。
その代わり横目にこちらを見下ろし、フフンと目だけで笑う。なんか、バカにされた気がする。キャップを被り直しながら唇を尖らせる私を置いて、多田野と並んで歩きだした。
背番号1を戴くその後ろ姿は陽光の下、太陽に一番近い場所へ。
成宮鳴、関東No.1サウスポー。
──稲実のキング。
TIAM top