あの子の心臓窃盗罪・前篇
いつかこんな日がくるんじゃないかと思っていた。
「何の用だよ、こんなとこに呼び出して。──鳴」
高校生活最後の夏が過ぎ去り、進路に関する色々な手続きにひと段落ついた十二月も中旬。
メールで指定された、青道と稲実のちょうど中間地点にある公園に足を踏み入れると、ブランコに浅く腰掛けていた鳴がこちらを向いた。
「元気してた? 一也」
「オカゲサマで」
引く手あまたでドラフト一位確実と囁かれていた世代No.1サウスポー成宮鳴。
プロ志望届を提出せず大学進学を択んだというニュースは、世の高校野球ファンの多くや、ともにプレーしてその実力を嫌というほど知る俺たちを勢いよく引っくり返した。
鳴のことだから真っ直ぐにプロへ進むだろうと俺も思っていたのだ。
──まあ、それはそれで彼の選択なのでしょう。
ニュースを見た英が存外冷静にそう言ったから、俺たちもなんとなく、すとんと落ち着いてしまったが。
「一也ってさー」
「ああ」
「英のこと好き?」
ああ、ホラ。
……嫌な予感してたんだよな。
「好きだよ」
「好きなんだ」
「世界で一番幸せになってほしいって願ってる」
この三年間、色々な探りを入れてくる色々な人に腐るほど返してきた常套句だ。大抵の人はこう言うと、「なんかちょっと誤魔化したけどやっぱり好きなんだな」と引き下がってくれる。
だけど、こんなセリフが鳴に通用するとは元より思っちゃいない。
「世界で一番幸せにしたい、じゃないんだね」
「…………」
「じゃあ俺が英ほしいって言っても文句ない?」
無言で鳴を見下ろす。
ブランコに腰掛ける鳴に対して俺はわざとその前に立っていた。すでに日の落ちた暗い公園で、街灯のわずかな灯りを光源にして、鳴は迷いなくこちらを見上げる。
いつかこんな日がくるんじゃないかと思っていた。
応えない俺に、説明を求められていると解釈したのか、鳴は口元に笑みを浮かべる。
「悔しいことにさ、誰に何をどう言われるよりずっとずっと、英の言葉が効果あるんだよね」
「……わかるよ」
誰より俺が一番わかっている。
「なんなんだろうな、あれ。ド正論のときはめちゃくちゃヘコんだりムカついたりするし、遠回しに励まされたらあー情けねーってなるけど、あいつの声聞いてマイナスに働いたことないんだよね」
「あー。お前よく試合前に電話してきてたもんな」
「なんで知ってんだよ!!」
「英から逐一報告受けたわ。昨日鳴からこういう電話がかかってきたよ〜ってさ」
「ギャ──チクり魔かよあいつ!!」
こうしてマウンド以外の場所でキャンキャン喚いている鳴を見ると詐欺だなと思うのだが、こいつが投球する姿は、甲子園で投げた完吾兄ちゃんによく似ていた。
だからだろう昔から、英は、どれほど子どもっぽいケンカをしてもいがみ合っても、鳴のピッチングからは目を逸らさない。
だから鳴だけはだめだと思っていた。
だから、鳴から呼び出しを受けた中学三年の秋、英を連れて行かなかった。
連れて行って稲実に勧誘されればあいつは揺らぐに決まっている。相性が悪いのか似た者同士の同族嫌悪なのか、とにかく鳴とは言い合いが多かった英は、それでも誰よりも鳴のピッチングを見ていたから。
鳴だけはだめだと思っていたのは、鳴だけが俺からあいつを掻っ攫ってしまえるからだ、きっと。
「英の心は英だけのものだ。告白するなりなんなり好きにしろよ」
「あれ、意外と寛大? 一也の屍を越えていくくらいの気持ちではいたんだけどな」
「俺より厳しい壁があるから安心しろ」
言うまでもなく完吾兄ちゃんである。
鳴ははにかむように笑って、伸びをしながら立ち上がる。
「あー、人生最大の強敵な気がする!」
「手強いぜ、あいつ」
「一也は結婚式の友人代表スピーチの原稿でも考えときなよ!」
「あーハイハイ」
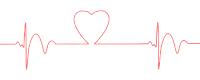
「そこのお嬢さん、野球部のマネやってよ」
大学の入学式を終えて帰宅しようと構内を歩いていたわたしは、傍若無人なその勧誘に立ち尽くした。
硬式野球部の新勧チラシをドヤ顔で押し付けてくるのは、高校時代嫌というほど敵対し見慣れていた世代No.1サウスポーの成宮鳴である。
「……なんでいるの?」
「言っとくけど先にここの大学受かってたの俺だから。英があとから合格したんだからね?」
「……そういえば秋口に志望大学あんたに教えた気がするわ」
「別に英がいるから受けたわけじゃないよ。ただ志望大学が重なってたから、同じ大学になったら絶対野球部に入れるって決めてたし先輩にも顧問にも監督にも有能マネが入部しますって言ってあるってだけ」
「この野郎!!」
思わずチラシを振り払ってしまった。
確かに、野球推薦で大学を決めた鳴と、内申点と小論文で推薦を受けたわたしでは、彼のほうが日程は先だ。謀られたわけではないが、その根回しの良さが心底いけ好かない。
鳴のことは嫌いじゃない。
同じ大学に知り合いがいるのはもちろん嬉しい。高校時代は熾烈な甲子園争いを繰り広げた相手だけど、そうであるがゆえに選手としては尊敬している。
ただ、なんというのだろう。
『成宮鳴』と『天乃英』として向き合うとどうしてもケンカになってしまうのだ。
「……大学では野球しないって決めてるの」
「一也がいないグラウンドになんて興味ない?」
「わかってるなら言わせないで」
「俺の投げる試合には興味あるだろ?」
入学式の大学構内は、新入部員獲得のために勧誘に力を入れる公認団体で溢れかえっている。
次々にチラシを押し付けられて戸惑う新入生たちのうち、何人かはこちらを見て「成宮鳴だ」と呟いていた。
桜の見守る麗らかな春の陽射しのなか、どこかそわそわした空気とは裏腹に睨み合うわたしたち。
鳴はニッと口角を上げた。
ドヤ顔。不遜な笑み。自分が王者だと信じて疑わない、そのための実力を持ち合わせた、誰がなんと言おうとわたしたちの世代では文句なし一番の投手。
「大学野球の日本一に連れてってあげるから、英は今度こそ俺のチームでマネージャーをやってよ」
「ッ何様だ!!」
「成宮鳴様でしょ」
しれっと返してきたのは紅子だ。
紅子もわたし(と鳴)と同じ大学に入学している。彼女は大学の吹奏楽団に所属することがすでに決まっていて、明日から早速練習に参加するそうだ。
ひとまず入学式お疲れ会と称して、大学通りのお洒落なカフェでお茶しているところ。
「いやー話には聞いてたけどマジで王様なんだね。一回生にしてすでに『大学野球の日本一に連れてってあげる』とは……」
「大学で野球やるのは自分だけだとでも思っているのか!? 言っておくけど哲さんや純さんや亮さんやクリス先輩や大学野球に進んだ偉大な先輩はみんな他大だし、倉持やノリくんや健二郎さんだってよそに散らばってるんだからっ!!」
「その代わり稲実の偉大な先輩や同輩たちも色々散らばってるんだろ?」
「そうよ!!」
「御幸から聞いてはいたけど、あんたホントに成宮鳴と相性悪いんだね……。こんな声荒げてる英初めて見た」
……ヒートアップしすぎた。
一度深呼吸してからコーヒーを一口飲む。おいしい。
「なんなのかしら……お互い小学生の頃から知ってるけど、いつもこうなの。向こうがいらんこと言うしわたしもいらんこと言ってケンカになるのよね」
「いいことじゃん。『ケンカするほど仲がいい』」
それを言われるとなんだかむず痒い。
確かに顔を合わせればいつも言い合いになってしまうけど、お互い嫌っているわけではないのだ。実際、高校時代は電話越しであればわりと穏やかに話せていた。
わたしは鳴のことを凄い投手だと思っているし、鳴もわたしを戦力として数えるに値すると思ってくれている。じゃなきゃわざわざマネージャーに勧誘なんてしないはずだ。
彼の描く勝利の道筋に、天乃英はいたほうがいいと判断された。
多分、かなりの名誉だ。
そう──マネージャーとして必要だと、思ってくれた。
味方ではなく、宿敵だった相手が。
しかもあの成宮鳴が。
「……全国の野球部マネが泣いて喜ぶレベルの話よね……」
「成宮鳴ってそんな凄いの?」
「まあ泣いて喜ぶは大袈裟かもしれないけど。マネとしての戦力に欲しいと思ってもらえる程度には、鳴はわたしを買ってくれているってことでしょ。プロ志望届を出していればドラフト一位確実だった世代No.1サウスポーが。……光栄な話よ」
テーブルの隅に置いていた携帯電話の小窓が光った。
周りが続々とスマホを手にするなか、わたしはまだガラケーのままでいる。まだ購入して四年目だし、使ううえで不便も感じていないからだ。
鳴からのメールだった。
《明日朝七時に野球部グラ集合ね! 監督たちにはもうマネ候補来ますって言ってるから!》
「…………わたし今日人生で初めて携帯を逆パカしたいと思った」
「落ち着け」
けっして鳴に勧誘されたからじゃない。
すでに話が通っているという監督さん方に失礼になるから、すっぽかすのだけはわたしの良心が許さなかった。断じてそれだけだ。
動きやすい服装で野球部専用グラウンドに向かう。
ちょうど朝練前のランニングのために部員たちが集まり始めたところだった。どこから入ればいいのかわからなかったのでネット越しに様子を見ていると、「あ!」と鳴の声が聞こえた。
「英ーっ、こっちこっち! なんだやる気満々じゃん」
「……スカートにハイヒールで来ればよかった」
「そんなことできないよ。お前にはね」
わかったようなことを言う。見透かされていることに腹が立つ。
“そう”だと当たり前のように信じてくれていることが嬉しいと、感じる自分が何よりむかつく。
駆け寄ってきた鳴に首根っこを引っ掴まれ、ずるずるとグラウンドの近くまで連行された。初めて入るグラウンドだ、入り口で立ち止まって脱帽し一礼すると、その行為さえ予想していたようなタイミングで鳴にまたシャツを掴まれる。
春休み中にどれほどわたしのことを言い触らしていたのか、監督さんや主将さんは「成る程この子が」「大会中継で見たことある」とふんふん頷いていた。
「すこぶる見た目はいいけど中身はわりとひねくれてて口も悪いです!」
「ちょっと」
「でも絶対戦力になります! 青道でも情報収集担当だったろ? あと会計とか事務系もしてたから、なんでもできます!」
「なんでそこまで知ってんのよ……」
「一也に聞いたー」
一也め。
しかしどうやら監督さんたちも、成宮が言うからといってハイじゃあ入部、というつもりではなかったらしい。朝練はとりあえず見学ということになった。
「今日は特別メニューなんだから光栄に思いなよ」
「特別メニュー? この間入部したばっかりのぺーぺーのくせに?」
鳴はなぜか微笑した。
憎まれ口を叩いたつもりが柔らかい表情を返されてしまい、ちょっと言葉に詰まる。
「そーそー、そういうトコ」なんて、何がそういうトコなのかよく解らないことを呟いて、わたしの手を引きブルペンへと歩いていく。
「お前を口説き落とすために今日の特等席を用意しましたー」
「……ブルペンじゃん」
「そ。英って、俺のピッチングを目と鼻の先では見たことないだろ。見てみたくない? 世代No.1サウスポーのピッチング、一番近くでさ」
「…………ナンバーワンって自分で言うな」
ああこれは、危ない流れだ。
だって鳴のピッチングはきれいなのだ。
わたしが人生で最も美しいと思った、あの夏、太陽を背に名だたる強豪校の打者を次々に倒していく兄の投球によく似ているから。
特別メニューに付き合ってくれるらしいキャッチャーが防具を装着している。コーチさん、主将さん、その他にも部員が何人か見に来ていた。
一つ上と二つ上の世代の有名選手は嫌でも頭に入っている。練習試合で当たった人の顔もある。
「『天乃英』が『成宮鳴』に口説き落とされるとこ、先輩たちが見たいってさ」
「……マネージャー獲得のために特別メニュー組ませる生意気な後輩を見定めに来たんじゃなくて?」
「あー、それ、そういうの。さすが英」
「さっきからなんなの?」
「俺が英をほしい一番の理由!」
不覚にもどきりとしてしまった。
その動揺を悟られないようにわざと顔を顰めると、鳴はニッと笑って「見てろよー」と正位置についた。
TIAM top