檸檬の気配・前篇
「硬式野球部どうですかー!?」
大学一年、春。
青道高校で青春をともにした仲間が誰もいない大学に入学した。硬式野球の強い大学だったけれど、同級生たちは皆よそへ。
一也も倉持も紅子もいない、一人ぼっちの新生活スタートだ。
『天乃英』の人生としては初めての試みなのでさすがに少し緊張している。
学内で腕のなかに捻じ込まれたチラシの山にうんざりしていると、一番上に乗っかったのは、わたしにとって最も馴染みの深い運動部だった。
「あれ、興味ある? よかったら説明だけでも聞いていきませんか?」
チラシを押し付けてきた部員がキラキラした目でこっちを見つめてきた。
大学のキャンパス内でビラ配りということは大学公式団体だ。説明を聞いたからといって入部が確定するわけではないはず、しつこい勧誘もないだろう。……話を、聞くだけなら。
強い春風に煽られて顔にかかった髪を掻き上げると、声をかけてきた部員が目を丸くした。
「あれっ……なんか見たことある……」
「そうですか?」
「なんだろ。モデルとかやってる?」
それは初めて言われた──わけでもないか。
沢村くんと初めて出会った日のことを思い出して少し笑ってしまった。
「芸能関係の仕事ならしていません。高校時代は野球部のマネージャーをしていたので、試合中継になら映ったかも」
「野球部のマネ! うちもちょうどマネ募集してんだよ! 経験者なら話早いや」
彼に誘導された先には、長机のそばに『硬式野球部』と幟を立てた新入生向けの説明ブースが設えてあった。
説明担当の部員が二名着席していて、対面には新入生用のパイプ椅子が二脚。ちょうど前の説明を受けていた二人組が席を立ったので、「タイミングいいじゃん」と彼が笑う。
「新規一名様ご案内! 高校時代に野球部マネ経験ありだって」
「へー。どこの高校?」
「青道高校です」
着席していた二名のうち、視線を落として手元のノートに何か書いていたほうがぴくりと反応した。
その隣に座っていたもう一人と、わたしを誘導してきた人のほうは『青道高校』という名前に驚いている。「強豪じゃん!!」「ってか青道って──」と同時に目を丸くし、そして視線を一人に集中させた。
顔を上げたその人は、眉間に皺を寄せていた。
「……亮さん!?」
「なんで居るの、お前」
「えっ、いや待ってください違うんです。何も知らなかったんです、でも大学合格したって報告したとき文さんと将さん変な顔してたなぁぁぁこのことか!!」
「クリスと哲がニヤニヤしてたのもこのことか……」
わたしたちは顔を見合わせてがっくし肩を落とした。
「……なに。御幸のいない野球部に何か心惹かれるものなんてあるの? 入る気がないなら説明なんてしないよ、面倒くさい」
「亮介おまっ、何言ってんだよ! 勧誘しろよ!!」
「そうだぞ美人マネだぞ! お前が言ってた高校時代の『やたら色んな偏差値の高い有能マネ』ってこの子だろ!?」
亮さんは手のなかでシャーペンをくるっと回すと、ややうざそうな表情でわたしを見つめる。
「勧誘しても別にいいけど、これ俺の(妹みたいなもの)だからね?」
亮さんの先制攻撃はよく効いた。
省略されたカッコの中身を理解したわたしは顔が緩みそうになっているのを必死に押さえて、理解しなかった二人は「「なんっだよ!!」」と撃沈した。
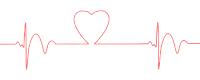
その後、入部するしないのすったもんだを亮さんと繰り広げた末、わたしは硬式野球部の女子マネージャーとして迎えられることになった。
「グラウンドのどこにも御幸はいないよ」と頑なだった彼に対して「でも亮さんがいます」そう答えると、諦めたように笑ってくれたのだ。「好きにしな」と。
勧誘時の亮さんの先制攻撃は部内中に広まり、おかげで入部してからというもの部内における恋愛トラブルとは無縁で過ごすことができた。そこはかとなく「結局小湊と天乃は付き合ってんのかそうじゃねーのか」と探りを入れられつつも、亮さんが詮索を許さないキャラであるため必要以上には触れられない。
「それではー、天乃ちゃんのハタチのお誕生日を祝してー」
入学式の日、わたしに声をかけてくれたあの先輩がグラスを掲げる。
「かんぱーい」という音頭とともに、集まってくれた野球部の面々が勢いよくグラスをぶつけ合った。
入部から二年が経ち、成人式も終えた三月末、『天乃英』は二十歳の誕生日を迎える。
そういえばこの体にお酒を入れるのは初めてだ。
あんまり強そうな感じはしないし、最初から飛ばすのはやめておこう。知らない人のいるような飲み会ではないし、部員みんないい人だから心配ごとは特にないけど。わたしの初飲酒を楽しそうに見守る先輩たちの前で苦笑しながらカシオレを一口、飲み込んだ。
この二年間ずっと一緒に野球をやってきた亮さんも、少し遠くの席からこちらを眺めている。
「はい天乃ちゃん初めてのお酒ー」
「アラちょっと、なに撮ってるんですか。事務所通してくださいよ」
「あー写真NGですか? すんませんそこのマネージャーさん許可くださーい」
雑なフリをされたマネージャーさん、こと亮さんがひらひら手を振った。
野球部内におけるわたしの保護者ポジがすっかり板についている。
「あとで俺に写真送ってくれるなら好きにして」
「亮さんっ!?」
「青道ラインに載せとくから。英のはじめての飲酒」
「はじめてのおつかいみたいに言わないでください」
飲み会はけっこう好きだ。
別にお酒を飲まなくてもいい。なんとなく雰囲気に酔って、おつまみを食べたりソフトドリンクを飲んだりしながら、いつもよりちょっと陽気にお喋りをするだけでも楽しい。
幸いにして女子に無理やりお酒を飲ませてくるような先輩はいなかったので、この日のわたしは調子に乗って、前の人生で好んでいたお酒を入れていた。
あー、懐かしいお酒の味。そういえばこんな味だったなぁ。
二十年ぶりだもんね、よく考えたら。
──そして見事に酔った。
顔に熱が集まって、心臓がドキドキして、目がちかちかする。
なんとなく体を左右に揺らしながら同期の女子マネの片腕に抱き着いた。「あら〜」とにやにやしながら頭を撫でてくれた彼女の肩に寄りかかると、わたしを見下ろした先輩たちが「あちゃー」と頭を抱える。
「あーしまった……」
「飛ばしすぎだって止めたんだけど……」
「とりあえず水頼もう水。亮介、天乃ちゃんの家知ってるっけ?」
「知ってる。……英」
お隣に座っていた先輩がどけたところに、亮さんがぽすんと座った。
今日ずっと遠いところにいたから、近くにきてくれたのが嬉しくてへらっと笑うと、亮さんはわたしの持っていたグラスを「はい没収」と取り上げる。
「あ」
「飲みすぎだよ。なにやってんの」
「でもまだ残ってます」
「俺が飲むからお前は水。顔真っ赤じゃん、りんごみたい」
ぷに、とほっぺたを抓られた。亮さんが愛情チョップ以外で触れてくるなんて、珍しいの。
いそいそと同期から離れて亮さんのそばに寄ると、こてんと首を傾げて顔を覗き込まれた。
「意識ハッキリしてんの?」
「してます」
「フワフワしてるだけか。気分は悪くないね」
「だいじょうぶです。でもちょっと眠い」
「寝てれば。その前に水飲んで」
ちょうどそのタイミングで運ばれてきたお冷やのグラスを渡される。氷できんきんに冷えたグラスを頬や首筋に当てると、少しだけ頭がハッキリするような気がした。
……飲みすぎだ。
前のわたしなら平気で飲めた量だけど、やっぱり『天乃英』はそんなに強くない(というか弱い)。精々カクテル三杯が限界だ。気をつけないと。
ふぅっと息を吐きだしてから口をつける。
三分の一ほど飲んでからテーブルに戻すと、亮さんは「よし」とわたしの頭を引き寄せた。彼の肩に頭を預けて目を閉じる。
「一人で帰れる?」
「……帰れないって言ったら送ってくれます?」
「いいよ。誕生日だしね」
「ふふ、亮さんが優しい。酔っ払ってみるものだなぁ」
「バカ言わないで。俺はいつでも優しいよ」
「……ですね。えへへ亮さん大好き」
「はいはい、知ってる」
ドカッ、と誰かがテーブルに引っかかって盛大に転んだような音が聴こえたが、わたしはもう瞼を上げるのも億劫になっていた。
お酒のせいで上がった体温と、こっそり亮さんが握ってくれた手の柔らかさに安堵して。
野球部の面々の話し声。店内を流れるBGM。橙色の照明。亮さんが飲み物を飲んだり、何か摘まんだりするたびに伝わる振動。
「寝たん?」「みたい」と、わたしに優しい配慮をした声量。
「それにしても『亮さん大好き』ねぇ」
「何その顔。こいつのことだから他意はないよ」
「でも悪い気しないだろ? 警戒心強い猫チャンのくせにさ、亮介にだけはデレデレなんだから」
「そのぶん苦労も多いよ。御幸は大変だっただろうなぁって心底思う」
「御幸って御幸一也? プロの」
「そ」
「じゃー亮介の最大のライバルだ?」
「勝負にもなんないよ。今も昔も英にとっての最優先は御幸。だから追いかけてくるなって言ったのに……」
ぽやぽやと表層を漂う意識はその会話の意味を理解しなかった。
ただ低く響く話し声が心地よくて、ずっと聴いていたかった。
「英。帰るよ、起きろ」
ぶに、と頬っぺたを挟んで起こされる。
「おー起きたか天乃ちゃーん」「気持ち悪くないかー」と、先輩たちがけらけら笑いながら見下ろしていた。うとうとする前よりは酔いが醒めた感じがする。顔を覗き込んできた亮さんに、ごめんなさい、とつぶやいた。
「肩、重かったですよね。すみませんわたし失礼なことしませんでしたか」
「あ、もう醒めちゃってるな。もうちょっとふにゃふにゃの天乃ちゃん見てたかったのに」
「こっから先は有料。ほら英、立って」
「わ、亮さん待って」
わたしの上着とカバン、そして会の初めに受け取ったプレゼントの紙袋を持った亮さんのあとを慌てて追いかける。
レジ横を通ると幹事の先輩がすでに会計をしているところだった。
お金払ってない、と真っ青になるわたしの後頭部をぺしっと亮さんが引っ叩く。
「今日はお前の誕生日会だろ。主役に金出させるバカどこにいるよ」
「あ、そうでした……」
「まだ酔ってるね。ぼけっとしてないで挨拶しな」
「うう、面目ない」
集まっていたメンバーが全員店の前に出てきたところで、主将が締めに入った。わたしもお礼を言わせてもらい、解散の流れとなる。「全員無事帰宅したら俺に連絡入れろー」とみんなを見送る主将自身は、何人かで二次会へ向かうようだった。
亮さんから受け取った上着を着て、カバンを持ったところで主将たちがこちらを見る。
「天乃ちゃんは亮介が送ってくか?」
「うん。まだふらついてるし」
「送り狼にならないように」
亮さんは無言でニコッと笑った。……また性質の悪いからかい方して。
キャーッと先輩二人がなぜか黄色い歓声を上げる横で、主将が「帰った帰った」と手を振る。
「行くよ英。襲わないでね?」
「亮さんが可愛いことしなきゃあ襲いませんよ」
「襲う側そっちなの?」
「天乃ちゃん対応手慣れてるな」
そりゃ、もうつきあいも五年になりますので。
二次会組に改めてお礼を伝えてから、とっとと帰路につこうとしている亮さんの後ろ姿を追いかけた。
この場所から大学付近のわたしのアパートまでは徒歩で十五分。四月も目前だがまだ風は冷たく、肌寒い。時刻は九時を少し過ぎたところで、通りにはまだたくさんの学生や社会人が行き交っていた。
「初めてのお酒はどうだった?」
「んー……思ったより弱かったですね。前はもうちょっと」
「前?」
あっ。
ハタと口に手をやったわたしに、亮さんは眉を顰める。口が滑った。お酒って怖いな。
「あのー、年末年始の親戚の集まりで……」
「ああ、そういうこと」
嘘だった。でも本当のことは、亮さんには言えない。
『天乃英』に生まれるより前の記憶があるんですなんて、そんな突拍子もないこと、一也以外には。
こんなにも信頼している大好きな先輩にまで、つかないといけない嘘があるなんて、わたし。
泣きたいくらい胸が痛いのはきっとお酒のせいね。
「英?」
「……ごめんなさい」
「何が。別に怒ってないよ、おいで」
飲酒歴があることを反省していると思ってくれたのか、視線を落としたまま亮さんの隣に並ぶと、ぽすぽす頭を撫でられた。
睫毛を上げて、ほんの少しだけいつもより近いところにいる亮さんを見つめる。
彼は飄々とした様子でわたしの髪の毛を撫でおろし、指先で頬に触れた。
呼吸をかぞえるようなその沈黙に耐えかねて、その肩に顔を埋める。
亮さんのにおい。
「……なに」
「……まだお酒残ってる、みたいで」
「気分悪いの?」
「眠いだけ、です」
嘘、だった。
きっとそんなものお見通しだったのだろう。彼はわたしの耳もとでくすりと笑った。
「酒のせいにするんだ。悪い女だね」
酒のせいにさせるような指をしているあなただって大概、悪い男だ。
TIAM top