檸檬の気配・中篇
ぴこん。
間抜けな通知音とともに、枕元に投げやっていたスマホの画面が明るく光った。
ベッドに寝転んだまま小説を読んでいたわたしは、文章から目を離さないまま手を伸ばしてスマホを引き寄せる。こんな時間になんだろう、野球部か青道か紅子か。きりのいいところまで読んでから視線を画面に映した瞬間、飛び上がってしまった。
亮さんだった。
《明日ひま?》
《ひまだろ》
《出かけるよ》
今年の三月に大学を卒業して現在は社会人となっている亮さん。卒業後もなんだかんだと連絡をとりあっていて、月一くらいでご飯に連れて行ってくれている。いつもお誘いは唐突だったけど今回はとびきり急だ。
「暇じゃなかったらどうするつもりだったんだろ……」
幸い予定はないけれども。
こんな勝手気ままなお誘いも嫌じゃないって、わたしもすっかり亮さんの……なんだろ。子分? 妹? ペット? 悲しいことにペットが一番しっくりきてしまった。
《ひまです!》
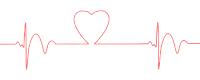
亮さんとはじめてお出かけしたのは、実は大学で再会するより前のことになる。
わたしが高校二年の二月。事故って亮さんに絶交されかけてなんとか仲直りしてもらったあとのことだ。あの頃の心臓に悪い日々のことはあんまり思い出したくないけど、とにかく、文さんがにやにやしながら「ここに二枚のチケットがあります」と話しかけてきたのだ。
卒業を目前に控えた三年生の先輩たちが、久しぶりに夕食後の食堂でわたしたちの相手をしてくれた日のことだった。
「映画の前売り券なんだけどさー。英、明日の午後オフだろ? 亮介と二人で行ってこいよ」
「……は?」
亮さんはたいへん嫌そうに振り返った。
この顔が、わたしとお出かけするのが本気で嫌というわけではなく、そこでなぜ自分に声がかかるのか心底理解できない、という意味であることくらいは察しがつく。文さんも承知の上で有無を言わさぬ笑みを浮かべた。
「英、最近色々と大変だったろ? しかも亮介に絶交されかけて半泣きだったし」
「いやそれ俺悪くないから」
「亮介と英の高校最後の思い出が大ゲンカなんて、亮介はともかく英がかわいそうじゃん。楽しい思い出つくってこいよ。あと俺ホラー映画ムリでさ」
「「「俺も」」」
「本音そっち?」
うんざり、といった表情の亮さんはそれでも文さんからチケットを受け取った。
一緒に覗き込んでみると、最近CMでよく見るホラー映画の前売り券だった。実在の心霊スポットを題材にしたもので、著名なホラー映画を多数手掛ける監督の最新作だ。
……ホラーかぁ。
「じゃあ英もムリじゃん。文化祭のお化け屋敷でガチ泣きだったし」
「あ、映画なら多分いけますよ。わたしでよければ御伴します」
じゃー決まりな、と文さんは押しの強い笑顔になった。
亮さんは形ばかり最後の抵抗といった感じで眉を顰める。
「ホラー映画ムリなくせに何で前売りなんて持ってんの」
「イトコが彼女と行く予定だったけど振られたらしい」
「あー……」
食堂が一気に同情的な空気になった。
翌日、午前練を終えたわたしは即行で帰宅し、先日兄から送りつけられたプレゼントのワンピースを引っ張り出した。
シャワーを浴びて、軽く昼食をとり、身支度を整えて出発する。亮さんとのお出かけははじめてなのでなんだか変な汗をかきそうだ。
集合場所には亮さんがすでに待っていた。
いくら部活があったからって先輩を待たせるなんて、わたしというやつは。慌てて駆け寄ると、足音で気づいた亮さんはいじっていた携帯電話を閉じて「お疲れ」と微笑んだ。
「お待たせしました!」
「まあ待ったけど、別に走らなくていいのに」
ああ、ここで「今来たとこだよ」って言わないの、なんか亮さんっぽい。
わたし相手だと若干意地悪度が増す人なので、本命の彼女ができたらそうやって優しく嘘をつくのかもしれないけど。……それもまたあんまり想像つかないなぁ。
「行くよ」と歩きだした亮さんの隣に並んで、目線の等しい彼の横顔を盗み見る。
なんか、変な感じ。
わたしっていつも亮さんのあとを追いかけてばかりだから、隣を歩くなんて初めてかもしれない。
「お前ホラー映画ほんとに平気なの?」
「人生で一度くらいは映画館で観てみたいと思ってたんです。映画って、脚本がある以上はある程度次の展開が予測できるじゃないですか。ここで怖がらせる仕掛けが待ってるぞ、幽霊出るぞ、みたいな。だから多分大丈夫です」
「なにそれ……。分析班やるようになったせいで分析癖でもついたわけ?」
「そうかもですね」
亮さんはぴたりと立ち止まった。
慌ててわたしも足を止めると、彼はこちらを見てほんの少し眉を寄せて胡乱げに首を傾げる。
なんだなんだ、何か変なところがあったかな。ぱたぱたと手を当てて髪型を確認したり、ワンピースを見下ろしたりしてみたけれど、変なものはついていない……と思う。
「……あー」
「どうかしましたか」
「なんか変だと思った、英が横歩いてるからか」
「……お嫌でしたらいつも通り、後ろから追いかけていきますが?」
「犬かよ」
ふっ、と笑ってまた歩きだす。
これはあれかしら。犬じゃないんだから隣歩いていいよ、ってことかしら。
わたしも違和感があったのは確かだけど、一緒のおでかけで後ろからついていくというのも怪しいし喋りにくい。開き直って亮さんの横に並んだ。
「冷静に分析しながらホラー観る女なんてモテないよ」
「そうですか? 亮さんは嫌いです?」
「キャーキャーうるさいよりはマシ」
「じゃあいいじゃないですか」
「……そーだね」
映画館に到着した頃には、開場までちょうどいいくらいの時間になっていた。
飲み物とポップコーンを買って少しの間ソファに腰掛ける。周りにはカップルや高校生のグループが待機していた。公開からしばらく経っているからか、そこまで客入りは多くないみたいだ。
「ムリになったら途中で出るから言いなよ」
「ありがとうございます」
「一年の頃のお化け屋敷みたいにべそべそ泣かれても困るからね」
「あれはですねー! 大きい音とか突然驚かされるのが苦手だっただけです!」
「映画館も一緒だろ」
確かに。
そう言われてみると、『天乃英』として生まれ直してまだ幼かった頃は映画もあんまり好きじゃなかったな。アニメ映画ならなんとかいけたけど、実写のアクション系は避けていた。最近は3Dメガネを掛けて観る映画も出てきているけど、ちょっと遠慮したいかも。
というか、映画館で映画を観ること自体何年ぶりだ……。
野球野球でここのところそんな暇なかったから。
「御幸と映画とか観たりしなさそう」
「え?」
「お前ら二人」
「んー、そうですね、二人で映画館に来たことはないかな。うんと小さい頃なら、うちの兄と母と、御幸家のおかあさんと、連れ立って観た記憶もありますけど」
そうこうしているうちに開場のアナウンスが流れたので、わたしたちは人波に乗って受付を済ませた。
真ん中あたりの列の、階段に近い席二つ。
「映画館ってなんかわくわくしますね。久しぶりだから余計に」
「上映中に足バタバタさせちゃダメだよ」
「子ども扱いですか。……でもポップコーンは急いで食べておかないと。ホラーだし」
「確かに」
ホラー映画だから無音のシーンも多いと踏んでポップコーンを一生懸命消費しつつ、電源を切るために携帯電話を開く。新着メールが一件。
文さんから一言、《亮介とデート楽しんで》というものだ。
……デートねぇ。
返信はしないまま電源を落とした。
同時に館内の照明が落とされ、映画のCMが始まる。
本編あらすじはこうだ。
某県某所に存在する心霊スポット。トンネルの向こうには、地図に乗らず、日本の憲法や法律が通用しない村が広がっているという。
そしてある晩、一組のカップルが肝試しでそこを訪れた。お手洗いのために彼氏と別れた彼女は恐ろしいものを目にし、発狂してしまう。
それからというもの主人公──発狂しその後自殺した少女の彼氏の双子の妹だ──の周囲でも様々な異変が起こりはじめ、やがては彼女の住む土地、そして血筋に伝わる呪いの全貌が明らかになっていく……。
というやつ。
先日読んだ本に書いてあったのだけれど、ホラー映画というのは基本、『安心』と『恐怖』の繰り返しらしい。
その理論さえ分かっていれば心構えができる。登場人物が気を抜いたり安心したりすれば、次のカットで何かが起きるわけだ。隣に座っている亮さんが泰然と座っていたこともあって、わたしも余裕をもってスクリーンに臨むことができた。
「病院のシーンが一番怖かった気がします」
「あー、布団の中にいるやつね」
二時間の恐怖に無事耐え抜いたわたしたちは、映画館の近くのカフェでちょっと遅めのおやつを食べていた。
「でも脚本が腑に落ちないですね。ホラーって意思疎通できない霊が相手だからこそ怖いのに、いきなり出てきた先祖霊がべらべら喋って道案内してくれるのが変な感じでした。あと最後のラスボス、変身シーンが長すぎませんか……」
「確かに。呑気に変身眺めてないで逃げたほうがよかったよね」
「でもそれ以外は面白かったです! 病院で主人公が幽霊を視るシーンぞわぞわっとしましたね。視える人ってあんな風に視えてるのかなーって感じで」
パンケーキを切り分けながら映画の内容を思い出すわたしを、亮さんは楽しそうに見つめている。
夕飯が入らなくなるという理由で彼は飲み物だけだ。なんだかわたしばかりパクパク食べているのも心苦しいので、頬杖をついている彼の顔を覗き込んだ。
「……亮さん一口食べます?」
「もらおうかな」
「どうぞー」
なんにも考えずにフォークで一切れ差し出すと、亮さんは一瞬だけ呆れたような顔になって、諦めたように笑いながら口を開いた。
「おいしいですよね」
「うん。けっこう甘いね」
そういえば亮さんは辛党だったっけ。
この人も大学生になったら同級生と一緒に激辛チャレンジとかしたりするのかな。前の人生で学生だったときの同期の男子なんて、激辛だの大盛だのにチャレンジしては瀕死になっていたものだけど、亮さんは大人っぽいからあんまり想像つかない。
相変わらず進学先の大学名を教えてもらえないわたしは、まだ見ぬ大学生姿の亮さんを想像してふふっと笑った。
そんなわたしを眺めていた亮さんもまた、にやりと口角を上げる。
「英」
「ハイ?」
「間接キスだね?」
ぱく、とわたしがパンケーキを口に放り込んだタイミングでそんなことを言うのだ。
思わずフォークを唇で挟んだまま動きを止めてしまった。
かん、せつ、きす。
「…………い、嫌なら食べる前に言ってもらわないと!」
「英ってけっこう直球に弱いんだよね。面白いな」
「いたいけな後輩をからかって遊ぶのも大概にしてくださいよー」
「可愛がってるんだよ」
それは、まあ、重々承知しておりますが。
反論もできずムムムと唇を尖らせたわたしに向かって、亮さんが音もなく手を伸ばしてきた。
唇のすぐ横を親指が這う。
あまりに唐突だったそれに目を丸くして硬直すると、口の端についていた生クリームを拭ってくれた指先が、ゆっくりと離れていった。
「で、意外と食べるのへたくそ」
「ね……念のために言いますけどその指すぐ拭いてくださいよ」
「なに舐めてほしいって?」
「亮さん!!」
「冗談」
にっこり笑った亮さんは、傍らに置いてあったお手拭きに指先を擦りつける。
「どうにかしなよ。その顔」と涼しい顔でカップに口をつける彼から姿を隠すように、ナイフを置いた手で顔を覆った。
……誰のせいよ。
TIAM top