青い夜のゆくえ・前篇
出会いは散々なものだった。
“程々に”“仲良く”しようと思ったら神田に対する初手を間違えて対アクマ武器を抜刀されたし、黒髪ポニーテールの後ろ姿を見つけて声を掛けたら人違いであこやには手首を捩じり上げられたし。
血のつながりは一切ないくせに、立ち居振る舞いや抜身の刃のような殺気はよく似ていて、記憶力には絶対の自信があるのにフとしたときに間違えそうになる。
異なる性質の孤独を抱えた、よく似たふたり。
……へんなやつら。
新入りエクソシストのラビは、大抵の場合はブックマンと二人セットで、ベテランのエクソシストを加え指導を受けながら任務をこなした。
もちろん神田とも組んだし、あこやとも組んだ。
だが人数の都合で二人のうちどちらかとの同行になったため、彼らが肩を並べているところを見たのは、ラビが入団してから三か月が経ってからのことだ。
修練場に顔を出そうと本部内をてこてこ歩いていると、「いけェ! やれあこや!」「仇をとってくれー!」という野太い歓声と、明らかに何かを破壊するような凄まじい戦闘音が聞こえてきた。
どうやらあこやが誰かと組手でもしているらしい。
どれどれ。
ギャラリーと化した探索部隊の壁の隙間から覗き込んでみると、砂地部分で対峙しているのは神田とあこやだった。「お、ラビ」とこちらに気づいた、科学班のジジの隣に移動する。
呼吸が途切れたのか、互いに構えたまま睨み合っている。──その手にあるのが真剣だと気づいて彼は思わず目を剥いた。
「うげっ」
「これぞ黒の教団名物、双子のガチンコバトルだ! 観とけ観とけ」
「ユウってぜってぇ手加減しねーだろ! あんなん止めなくていいんさ?」
あこやの実力はよく知っている。神田のそれも。いくらなんでも女の子のほうが不利に決まっているし、あこやには悪いが神田に勝てるわけがない。
するとジジはきょとんと目を丸くした。
「なに言ってんだ。あの二人は互角だぞ、神田の入団当初からずっとな」
「──はあっ!?」
白刃が煌く。
はっとした瞬間に二人の位置は入れ替わっていた。続けざまに一合、二合。火花が散り、風圧で足元の砂が散る。二人の黒髪が翻る残像に目を凝らしたが、剣士でないラビには追いきれなかった。
神田の黒髪の先が僅かに切れて宙を舞う。
あこやの頬に傷が入り、神田の二の腕に赤い筋が浮く。
うわユウのやつ女の子の顔に傷入れやがった、と引いた瞬間ギャラリーがどっと沸きあがった。──「神田何やってんだヘタクソか!」「俺らの大事なあこやに何やってんだァァ」「あこややれ! いけ! 神田の顔ボコボコにしてやれ!」
……ラビだったら絶対、やり辛くてかなわない。
神田は顔色ひとつ変えない。
というよりは、二人とも周りの声など耳に入っていないようだった。
「あこやの親父が凄腕のサムライだったんだ。娘は当然その一番弟子だし、神田も指導を受けた。エクソシストとしてのキャリアはあこやのほうが長くてな、神田が本部に来た頃の組手じゃ大体あこやの勝ちだったんだぞ。……まあケンカになると神田のほうが強かったが」
なぜか自慢げなジジの語りを耳に入れつつも、一瞬たりとも目が離せない二人の立ち合いに魅入った。
ひとつの型のように互いの刀を受け流し、弾く。任務ではたいてい剣腕で対アクマ武器を揮うことが多かった二人が、今は両手で柄を握っていることに気がついた。
……待ってこいつら任務でアクマ斃すときより本気なんじゃね?
ひく、と口の端が引き攣る。
兵士となって記録に入るのは初めてとはいえ、本来敵対しているものとの戦いよりも仲間との組手のほうがマジな戦闘狂はさすがに初めてだ。
「傍から見りゃヤベーケンカに見えるんだけどな。あれが二人のコミュニケーションなんだよ」
イヤイヤどんなコミュニケーションだよ。
そうこうしているうちに決着がついた。
低い姿勢から繰り出されたあこやの白刃が神田の鳩尾に迫る。
同時に見下ろしながら振り下ろされた神田の刀はあこやの喉元へ。
ふっ……と舞い上がった砂のなかで見つめ合う、ラビには到底理解しえない『双子』。
彼らは流れるような動作で刀を引くと、無言で頭を下げ合った。
「……あこやの親父さんてエクソシストだったん?」
教団史は創設期から頭に入れているところだ。近年の記録に入るまではまだまだ時間がかかる。
二人は刀身についた血を拭いて、ギャラリーから投げ渡された鞘に刀を納めていた。
「ああ。いい剣士だった」
「死んだんだな」
「二年前に任務で、探索部隊とイノセンスを庇ってな。……あのときのあこやも、神田も、俺ら見てられなかったよ」
ジジが切なげに零した後半の言葉に思わず視線を向ける。
所々から血を流しながらも笑顔のあこやと、相変わらず仏頂面の神田。ラビの見立てでは到底相容れるはずのない価値観を持ち合わせた二人なのに、肩を並べる姿は奇妙なほど自然だった。
あこやがラビに気づいてにこっと笑う。居心地の悪さを感じるくらいの親しげな笑みだ。
反対に神田はぎゅうっと顔を歪めた。こっちは気持ちいいくらい嫌われている。
「ラビだ。なに、ラビもやってく?」
「チッッ」
「いやー……勝てる気しねぇからいいや……」
…………へんなやつら!!
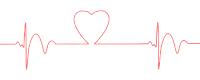
ラビたちの入団前から欧州で起きていた大規模な戦いがひと段落すると、本部内で神田とあこやの姿を見かけることも多くなっていった。
大聖堂に並んでいた夥しい数の柩はいつしか消え去り、戦士たちの体に絶えず付きまとっていた治療痕も減っていく。初めて教団に来た日に見た年下の少女の涙も、すっかり記憶の底へ沈んだ。
「ユウおっはよー!」
食堂で朝っぱらから天ぷら蕎麦を啜る神田の背中を叩くと、凶悪な目つきで睨まれる。
いちいち反応を返してくれる神田が面白くて、ラビは神田を神田と呼ぶことができなくなっていた。睨まれると怖いし、たまに命の危機に見舞われるが、慣れればどうということもない。「ユーくん」と呼ばない限り、余程のことがなければ抜刀を免れるということも学んだ。
「失せろ」
ただし辛辣。
「今日も蕎麦? 栄養偏んぜぇ」
「関係ねぇだろ隣に座るな」
「まぁそう言わずにぃ」
朝食のトレイとともに神田の隣に腰掛けると、ピリ、と気配が鋭くなる。
この神田ユウというエクソシストは実に不思議な人物だった。
戦争の本拠地である教団をホームと呼ぶリナリーや、彼女を中心とする科学班のアットホームな雰囲気、そしてこの場所で生まれ育ち団員皆が家族だと笑うあこや。
様々な戦地を記録してきたラビにしてみれば、戦争の最中にいてホームだの家族だのと馴れ合っている彼らのほうが奇妙に思える。神田も恐らくそちら側のはずだ。だから神田のそばは気が楽だった。教団はホームじゃないし団員は家族じゃない、そういう点では神田と気が合う。
だというのに、神田はなぜだかあこやと『双子』として語られる。
こんなにも正反対なのに。
そして人間嫌いを拗らせまくっているこの男がその扱いを受け入れているのだ。──まあ、ただ諦めただけかもしれないが。
「そういや、あこやは?」
「…………」
「無視すんなよユウ〜。昨日の夜はいたよな? いっつもメシ一緒に食ってんのに、今日はけんかでもしたんか? 駄目だぜユウ、女の子には優しくしなきゃ!」
ばちぃん! と凄まじい音がしたのは、神田が裏拳でラビの顔面をぶん殴ったせいだ。
ブックマンの跡継ぎとして師より戦闘訓練を受けたラビでさえ、神田の素早さにはわりと頻繁についていけない。とりわけあこやとの稽古中、そして怒ったときの神田には。
テーブルに突っ伏して悶絶するラビの耳に、「なにやってんの」と呆れたような声が届く。
「おはよう、二人とも」
「おはようさぁ、あこや……。朝からユウにいじめられてる……」
「ファーストネーム呼ぶからでしょ。原因解りきってるじゃないの。──おはよ、神田」
「…………」
「おはよう神田ー!!」
「うるっせェな朝っぱらから!!」
なんとあこやは神田の右耳を掴んで引っ張って大声で朝のあいさつを吹き込んだ。
神田はそれに対して拳ではなく怒声で返す。あこやは神田に「おはよう」だの「ただいま」だのしつこく声をかけて、あいさつをきっちり仕込むのが趣味らしい。
ラビは彼がまともに返事しているところを見たことがないが、リナリーや他の科学班に言わせると、まあ大抵の場合は素っ気なくもあいさつを返しているとのことだ。
ピザトーストを載せた皿を持った彼女は、団服を着ていた。
「任務?」
「うん。すぐ近くだけどね」
「気ィつけてなー」
「ありがと!」
神田と真剣の手合わせで引き分けるような猛者に対して、気をつけろも何もないとは思うが。
ちゃちゃっと朝食を終えて席を立ったあこやはまた「行ってきます!!」と大声で神田の耳に吹き込み、「うるせェとっとと行け!!」という“行ってらっしゃい”を受けて食堂を出ていった。
すぐ近くでの任務との言葉通り、彼女はその晩には帰還していた。
怪我もなく、団服には汚れさえついていない。談話室でジョニーやタップとチェスをしていたラビの隣にちょこんと収まり、膝で報告書を書きはじめる。
「そういや今日のユウすごかったぜ」
「神田? なにかしたの」
「組手で百人切り! 修練場に屍の山ができたさ……。うちのジジイとあんなにやれんのってスゲェよ」
「へーえ。ラビも?」
「オレは最初の一人さ……。ユウってなんであんな強いんかね?」
さすがに情けなくて虚ろな笑みを浮かべてしまった。
あこやは「ふふ」と肩を震わせながらペンにインクをつける。
「いいなぁ、ラビは」
「へ?」
思いがけぬ言葉を洩らした彼女を振り返ると、報告書に目を落としたまま、どこか翳のある微笑みを口の端に載せていた。
いつもニコニコと朗らかな表情を見せていたあこやのイメージからは少し遠い、大人びた笑みだ。
「ユウって呼べて」
「……えー? したらあこやだって呼べばいいじゃん。カッて目ん玉かっ開くけど、そんくらいだろ? オレ面白くってさ」
「わたしはだめなの。怒られちゃう」
「ユウってあこやに対して怒んの?……いや、常にイライラしてっけど」
「怒るよー。最近はあんまりだけど、昔は怒らせてばっかだったもん。大ゲンカして投げ飛ばされて額縫ったことあるし」
「エエッ」
そういえばジジも、ケンカになると神田のほうが強いと言っていたか。
型やある程度のルールを度外視して感情のままに戦えば、膂力のぶん当然神田のほうが強いだろう。小さなオオカミ二匹が全力で喉笛を咬み合う様を想像してしまい、ラビはそっと蒼くなった。
あこやはそれから報告書の作成に集中するようになり、ラビも対局が終盤に入ったこともあって会話は途切れた。
盤上の戦いがジョニーの勝利に終わった頃、こて、と背中に重みがかかる。
「……お?」
「あれ、あこや寝ちゃった?」
「みたいだな。日帰りのぶん慌ただしかったんだろうなぁ」
ジョニーとタップがラビの背中を覗き込む。
体勢を変えたら背中の彼女が倒れそうだったのでラビは顔だけ振り向いたが、確かにすよすよと穏やかな寝息が耳に届いた。
「オレ神田呼んでくるよ! ラビもうちょっとそのままにしてあげて」
「へ? わざわざ呼ぶくらいならオレ運ぶけど」
それとも神田以外には触らせてはいけない決まり事でもあるのか?
それはそれで興味深いなと思いながら自らを指さしたが、タップは「おお、その手があったか」と手を叩く。どうやらそういうわけでもないらしい。
「そういえばそっか。なんかあこやといえば神田って感じになっちゃってさー」
「あれだろ、ジジが運ぼうとしたら激怒して抜刀してからだろ、神田に運ばせるのが暗黙の了解みたいになったの」
「そうなの? 神田ってけっこうジジに心開いてるのに」
「付き合い長いし普段はそうだけど。どうもジジがあこやに触るのは嫌らしいって、ロブが言ってたぞ」
「へえぇ。なんかあったのかな?」
こてりと首を傾げたジョニーの後ろで、談話室の入り口を見覚えのある黒髪が通り過ぎた。
噂をすればなんとやら、神田だ。
「あっ、神田!」と結局呼び止めてしまったジョニーに連れられてやってきた神田は、ラビの背中で寝こける無防備なあこやを見て眉間に皺を寄せると、心底面倒くさそうに溜め息をつく。
「ラビが運ぶって言ってくれたんだけど、ちょうど通りがかったからつい呼んじゃったよ」
「……いちいち呼ぶんじゃねぇよ」
文句をつけつつもあこやの両腕を掴む。そんなに雑に扱っていいのかと驚くほどぞんざいな手つきで、神田はあこやを抱き上げた。
片腕に『双子』を抱く男の姿を見て、口が勝手に開いていた。
「ユウってあこやのこと好きなん?」
瞬間、談話室にブリザードが吹き荒れる。
絶対零度の蒼い双眸でラビを射殺さんとする神田の視線に、内心(ヤベェ怖えぇ)と冷や汗をかきつつも、気になるものは気になるという本能には逆らえなかった。
「いや今聞いたけどさ、ジジがあこやに触るのは嫌って、フツーに聞いたらそれ独占欲とか嫉妬とかじゃん。どうなんかなーって思って」
ぎろりと神田の視線が科学班二人へ。「ヒエッ」「ゴメンッ」と謝る二人はガクガク震えていた。
幸いにも帯刀していないうえ両手が塞がっていた神田は、『六幻』を抜くことはできなかった。
「興味ねェよ」
「えー。でもさ」
「カゲマサの墓に誓っただけだ。……あのクソジジには指一本触れさせねぇ」
「その発言んん……」
よっぽどグレーどころかやっぱフツーに聞いたらそれ独占欲とか嫉妬なんですけど……と思ったものの、神田はそれ以上口を開こうとはせず、黒い髪を靡かせながら談話室を出ていく。
足音が完全に聞こえなくなってからようやく、残された三人はぎこちなく動きを再開した。
「…………カゲマサって誰?」
「あこやのお父さんだね。二年前に任務中に亡くなったんだ」
「お父さんて。ガチじゃねーのユウのやつ」
ラビのこの無謀な尋問はすぐさま科学班やエクソシストに広がり、「自殺願望でもあるのか」「命が惜しけりゃ神田のことはそっとしとけ」と誠に心の籠った忠告をいくつも受けることとなる。
TIAM top