名もない痕ばかり・前篇
この春、青道高校の一年生になった僕はこの場所で憧れの人を見つけた。
青道高校三年生、野球部のマネージャーを務める天乃英先輩である。
立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花、成績優秀で人柄もよくなんと昨年のミス青道コンテストでグランプリを受賞。その隙のなさから一年生の時点でついた綽名が『高嶺の花』。
噂ばかりを聞いていた頃は、いやいやそんなマンガみたいな完璧超人いるわけないじゃん、なんて思っていたんだけど。
いたんだよ完璧超人──
否。
天乃先輩は完璧ではなかった。運動がやや苦手なのだそうだ。あざといけどそのあざとさが逆に可愛い。
げんに今グラウンドに見えている彼女は、クラスメイトと一緒に授業前のランニングをしながら苦笑いしている。
なんともはや幸運なことに窓際の席である僕は、長い黒髪をなびかせながらのんびりと走る天乃先輩をじっくりと見つめていた。
「今日も高嶺は高嶺の花だなぁ……」
天乃先輩の後ろから二つの影が近づいていく。
気安い様子で彼女の頭をぽんと叩いて抜かしていく彼らは、野球部の倉持先輩と御幸先輩だ。天乃先輩は一瞬怒ったように二人のあとを追いかけたが、すぐに引き離された。足おそいんだな。それとも長距離があんまり好きじゃないのかな。
そんな様子を観察している僕に近づいてきたのは、同じクラスの由井薫だ。
「なに見てるの?」
「天乃先輩を見てる。……いーなぁ由井、天乃先輩と同じ部活で」
「あー……そう、だね」
何やら意味ありげな返事を寄越した由井は人差し指で頬を掻いた。
生まれてこの方スポーツとは縁のない僕にはよく解らないが、どうやらこの由井は野球の界隈ではかなり有名な選手らしい。西東京三強とよばれる青道野球部で、入学直後からベンチ入りしているという。
「でも高嶺先輩、野球部の先輩のなかでは一番怖いよ」
「はああっ?」
思わず天乃先輩から視線を逸らしてしまった。由井は驚く俺に肩を竦めて、グラウンドを走る彼女を目で追う。
「すごくきれいな人で、仕事もできるし、あんなマネージャーに支えてもらえる俺たちは幸せだよ。でもなんていうか……選手を含めて先輩全員のなかでも一番厳しいし、怒ったら怖い」
「……あんなにおキレイなのに?」
「だからこそ怒ったら怖いっていうのもあるかも。三年生の先輩たちも、天乃先輩が怒ったら誰も逆らえないって言ってたし」
そう言われてみると、僕は学校にいる間の天乃先輩しか見たことがないのだ。
青道高校はもともと野球部が有名な学校で、夏や秋の大会では試合中継もしているし、春のセンバツだって全国中継だった。ただ僕が彼女を知ったのは入学後のことだから、『野球部の天乃先輩』は一切知らない。
眼下、グラウンド二周をようやく終えた彼女は、とっくに走り終わって二人で喋っている倉持先輩と御幸先輩のところに駆け寄っていく。
倉持先輩に後ろからタックルをかまして無邪気に笑う天乃先輩。
さっき頭をぐしゃぐしゃにされた仕返しなのか。あんな華奢な体じゃ、何をしたって野球部の屈強な二人は痛くも痒くもないだろうに。
「ああしていると部活のときとは別人だよ」と、由井はそう言いおいて席に戻っていった。
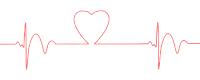
天乃先輩が『怖い』……。
由井はおかしな嘘を吹聴するような奴じゃないから、きっと本当のことなのだろう。なんだか納得いかないし、ちっとも想像つかないけど。
一体なにがそんなに怖いんだろう?
授業終わりに先生から雑用を言いつけられたため、集めた古典のノートを抱えた僕はのろのろと職員室までの道のりを歩いていた。
由井に言われたことが気になって注意散漫になっていたのだろう。
向かい側から走ってきた生徒を避けきれず肩がぶつかり、腕のなかに抱えていたノートを廊下に全部ぶちまけてしまった。
「あっ、ごめん!」
「いえ、大丈夫です……」
ボケッとしていた僕が悪い。いや、ボケッとしていなかったとしても避けられなかったかも。
ちょっと反省しながらしゃがみ込むと、ぶつかってきた女子生徒もノートを拾ってくれた。
同じ一冊に手を伸ばし、指と指がぶつかる。
スミマセン、と顔を上げた瞬間、時が止まった。
「天乃先輩……」
僕が名前を知っていたからか、天乃先輩は一度だけぱちりと瞬きをした。しかしすぐにニコリと微笑んで、「一年生だね」と花の綻ぶような声で話しかけてくれる。
一瞬不審に思われるかもと肝が冷えたが、もしかしたらこの人は、自分が有名人なことをよくわきまえているのかもしれない。
「あ、えっと、僕、由井と同じクラスで」
「そうなの。……ああ本当だ、由井くんのノート見っけ」
何冊か拾い集めた彼女が膝の上でノートの角を整えたとき、「何やってんの」と御幸先輩が現れた。
「ぶつかっちゃって」
「前見て歩けよ」
……うわ、近くで見るの初めてだけど、御幸先輩ってオーラある。
存在感っていうんだろうか。かっこいいし、体も大きいけど、喋り方や声が落ち着いていてなんだか余裕がある。眼鏡してるけど野暮ったさはなくて、一年の男子に比べると断然大人っぽい。
「あーあ」とぼやきながらも、御幸先輩までノートを拾ってくれた。
僕やばい、青道で一番有名なコンビと一緒にいる。やばい。死ぬかも。
「クラス全員分は重いわよね。今度から誰かに手伝ってもらったほうがいいよ」
「お前もよく一人で運ぼうとして腕プルプルさせてたもんな」
「いい筋トレになったわ」
お茶目な表情になった天乃先輩は右腕を曲げた。さすがにシャツを着ているから力こぶなんて見えない。
リアクションに困っている僕の目の前で、御幸先輩は躊躇なく掌を伸ばし、がしっと天乃先輩の二の腕を掴む。
そそそそんな、容赦のない……!
女子の二の腕って胸と同じ感触だとかいって男子にとっちゃタブーみたいなものなのに……!
なんだこの人たち距離感バグってんな!!
あのあと、チキンな僕は二人の醸し出すキラキラ青春オーラに耐え切れず「拾って頂いてありがとうございましたぁぁ」と悲鳴のようなお礼を述べて逃げ出した。
しかし、しかしである。
由井から聞いたあの話がどうしても気になってしまって、僕は放課後、ホームルームが終わってからそのまま野球部専用グラウンドへと足を運んだ。
初めて来た。
すぐそばに部員用の寮を構えた野球部グラウンド。高いネットに囲まれたグラウンドが二面。倉庫やプレハブ小屋や得点板、ベンチ、ブルペン。
野球なんて体育の授業でちょこっとやったくらいで、夏の甲子園もスポーツ漫画も興味ないけど、まさにこれに青春を懸けている人たちが同じ学校にいるんだなぁ。
本当にホームルーム後直行してきたから、グラウンドにはまだ部員の姿も多くない。
ちょっとどきどきしながらも、見学っぽいおじさんたちが屯していたベンチの端っこに腰掛けた。そうこうしているうちに寮のほうから練習着に着替えた部員たちが続々とやってきて、各々体を動かし始める。そのなかには由井もいた。
「来たんだ」
「うん、まあ、なんか気になってさ。……部員でもOBでもないけど見学っていいのかな。迷惑じゃないかな」
「平気だよ。いつもOBさんや取材陣はいるし、学生の見学も多いよ」
由井は爽やかな笑顔で走り去っていく。その言葉通り、青道の女子生徒が何人かベンチに腰を下ろしたのが視界の端に映った。彼女らはあれだろうか、僕が天乃先輩を見に来たように特定の先輩のファンとかなんだろうか。
部員やマネージャー、顧問の先生たちが全員揃ったところで整列する。
部員の多さに恐れ戦きながらひぃふぅみぃと数えてみたけど、多分これ百人くらいいる……。ベンチに入れるのって二十人くらいだよね。それで、スタメンは九人。
あれだけたくさんいる部員のなかで、球場でプレーできるのは一割。
「凄まじい世界だなぁ……」
正直その厳しい倍率にドン引きしているうちに、部員たちは二つのグループに分かれた。二・三年生の半分がAグラウンドで準備を始めて、残りの半分と一年生全員はBグラウンドへ移動していく。天乃先輩はコーチらしき中年男性と一緒にBグラへ行くようだ。
その様子を見ていて、由井の言葉が腑に落ちた。
──すごくきれいな人で、仕事もできるし、あんなマネージャーに支えてもらえる俺たちは幸せだよ。
──でもなんていうか……選手を含めて先輩全員のなかでも一番厳しい。
厳しいとか怖いっていうか、張り詰めている感じだ。
ノートを拾ってくれたときの優しい表情も、お茶目に力こぶを作ったときの悪戯っ子みたいな笑みも全て消え去って、練習に向かう三年生と同じくらい真剣な目をしている。
たらたら歩いている一年生の最後尾を見つけると、彼女はふぅと息を吐いた。
「見られてるわよ。わたしにもコーチにも監督にもOBさんにも」
痛烈な叱咤。ビクッと肩を跳ねさせた数名が慌てて駆け足になってBグラに向かう。「厳しいね」とヒゲを撫でたコーチに「始まったばかりなのにダラダラされると口出ししたくもなります」と、天乃先輩は淡々と答えた。
「補佐殿がいると締まるから助かるけどね」「落合コーチもたまにはビシッと言ってください」そんなやりとりをしながら、二人は見学席の横を通り過ぎていく。
「あちゃー」と隣に座っていたOBさんらしきお兄さんが苦笑した。
大学生くらいだろうか、五人くらいでBグラの天乃先輩を眺めている。
「今日も絶好調だなぁ鬼マネちゃんは」
「三年に上がって厳しくなったよな。まあ御幸の代はあんま後輩に厳しくしないほうだし」
「言葉より背中の男どもが多いんだよな、主力の三年。他は優しいタイプが多いから補佐殿が損な役回りになるんだなー」
言葉より背中……。
Aグラで実戦形式の練習を開始した御幸先輩を見つけた。確かにお兄さんたちの言う通り、後輩にあれこれ指示を出している感じはしない。というかこの野球部、部員一人一人が自分から動いているのだ。だから先輩が口うるさく言う必要もないのかも。
「まー後輩に厳しく言う以上に自分にも厳しいマネだし、御幸たちもわかってんだろ。そういう役割分担なんだって」
「あいつら二年の半ばまでメチャクチャ仲悪かったくせにな! ここにきて団結したよな」
「あーそうそう、バチバチ火花散らしてな。まあそれは今もか」
「マネ中心に回る代ってどーよとも思ったもんだが、最終的にはあるべき形になったよ」
「あいつらももう三年だもんな」とつぶやいたお兄さんの言葉は、しんみりと溶けて消えた。
三年生。
そっか。
御幸先輩や天乃先輩にとっては、この夏が最後なんだ……。
TIAM top