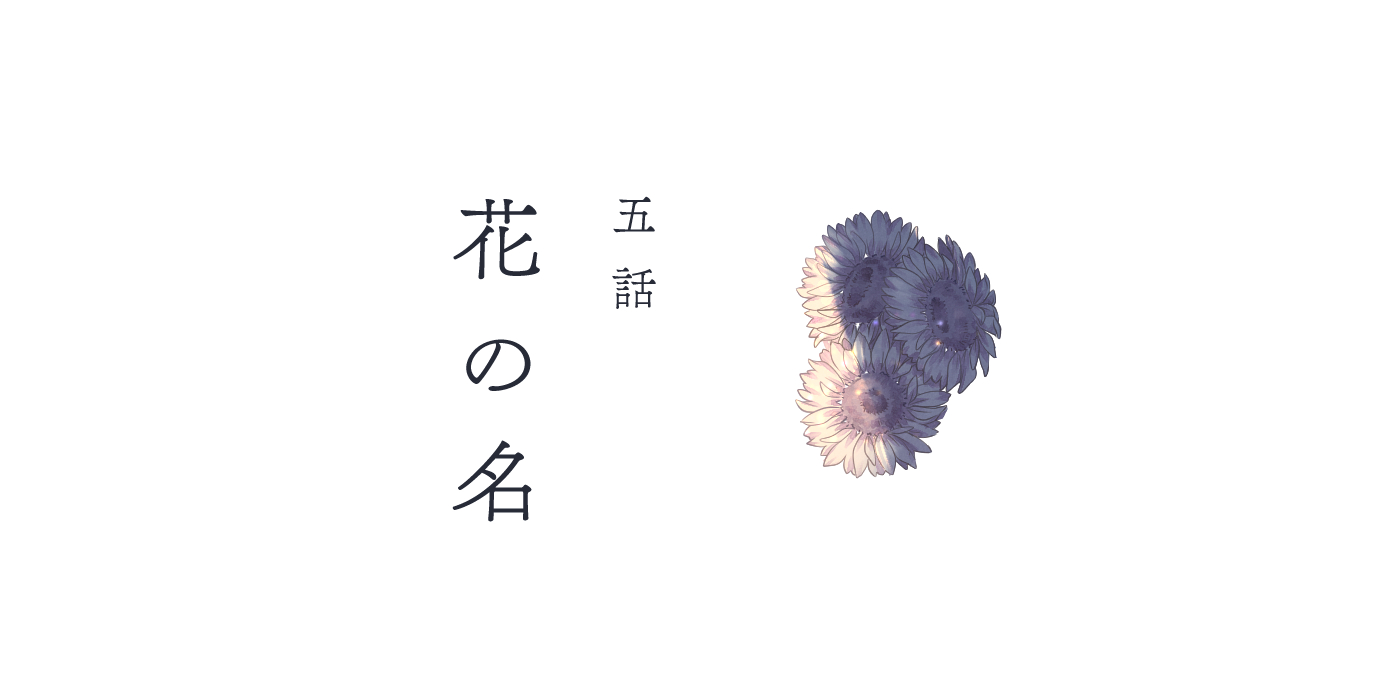
秋が深まって、庭のコスモスと銀木犀がぽろぽろときれいな花を咲かせるころ。
学校にいこうと紅色のランドセルを背負って自分の部屋をでると、二階奥の書斎の扉が開く。「おはよう、葵……」のっそりと緩慢な動きで出てきた文月さんの気だるげな表情は、すこし要さんと似ていて、やっぱり兄弟なのだなあと思う。暗い瞳に背筋が緊張するのを飲み下して、「うん、おはよう」と答える。
要さんはまだ寝ている。睦月は遠方の私立中学校に通っているので、わたしよりずっとはやく家をでる。しんと静かな廊下で文月さんの顔をみあげていると、文月さんはごく自然な動作で一冊の本を差しだす。白いハードカバーのまあたらしいものだ。受けとると、両手にずっしりと重みがかかる。
「新刊。わたしておく」
「……うん」
睦月いわく「それなりに人気作家」の新刊を家族という理由でもらえているのだし、お礼を言うべきだけれど、文月さんは言われても困ったように笑うだけだ。わかっているからうなずいて、ランドセルにそれをつめて足早に「いってきます」と背中を向ける。
横目で文月さんの顔をみる。
撃たれたひとの目がわたしをみつめていた。
花びらの輪郭をなぞるような視線が、どこか不気味だった。
まだわたしは書くに値する人間なのだなあと、顔がゆがんだ。
「葵ちゃん」
「……祐樹お兄ちゃん」
その日の帰りも、お兄ちゃんたちと会った。わたしは駅前をうろうろと歩きながらハードカバーを両手で開いていて、祐樹お兄ちゃんに声をかけられるとそれをランドセルにしまった。「今日は重たそうな本だね」と祐樹お兄ちゃんが覗きこんでくるので、わたしは首をかたむける。
「おじさんが書いた本なの」
「……葵のおじさん、小説家なんだ?」
つぶやいたのは楓お兄ちゃんだった。声がすこしの驚きを伴っていて、そういえば話をしたことはなかった、と思う。三人もわたしも長袖になってからだいぶ経っていて、会った回数も結構なものになっていたけど、言う必要がないから言わなかったのだ。
わたしはうなずき、「いつもあたらしいものを一冊くれる」と説明する。瞳お兄ちゃんがランドセルの中にしまわれた本の背表紙を軽くみて、「[#ruby花城_はなしろ#]、[#ruby立_りつ#]……」と作者名を口にだす。お兄ちゃんの声が淡々とその名前をなぞっただけなのに、いいようもなくなにかおそろしい気持ちになって、わたしは顔をあげた。
「お兄ちゃん、知ってるの?」
瞳お兄ちゃんをみあげるわたしの声はほんのすこしふるえていた。たずねてから、わたしはいったいなにがおそろしいのだろうと自分を奇妙に思う。おじさんが小説家で、話すまでもなく名前を知られているというのは、すくなからずよろこばしいことのはずだ。瞳お兄ちゃんが「いや、名前だけ」と簡素に答えることに安堵するのも、おかしなことだった。
「お前がたまに読んでるだろ」
「……あぁ、うん。そうだったかも」
わたしが自分で持っている本はとてもすくない。睦月がたまに買ってくれるものか、文月さんがわたしてくれる文月さんの本。迷宮のような書斎にある大量の本は、読むことはしてもあまり持ち出さない。だから会ったばかりのころ、たとえば瞳お兄ちゃんとふたりでいて会話がないときなんかには、わたしは文月さんの本を開いていることがあった。瞳お兄ちゃんの言葉も態度も、当然のものだ。
文月さんのことをお兄ちゃんが知っているといううれしさと、本を読んでいなくてよかったという安心は両立していた。要さんのことを知られるのは不安だし、想像するとかなしくなるけど、文月さんのことはどうにも一概に言い切れなかった。
ランドセルのふたを手早く閉めて、「いこう」と瞳お兄ちゃんの手を掴む。わたしの手足にはきょうも殴打の痕があるけど、お兄ちゃんたちがわたしのことを不気味そうに払いのけたことはないから、自分から手をとることも可能だった。
「……」
瞳お兄ちゃんはなにも言わずに歩きだし、祐樹お兄ちゃんがきょうのワンピースをほめてくれる。楓お兄ちゃんはいつもの黒々としたカメラを持ったまま、じっと、わたしの顔をみつめていた。
ランドセルの内側で、ぶあつくて重たい本がかたかたと揺れていた。
花城立という作家の書く小説は、ほとんどのヒロインに花の名前がついている。
桜、椿、野ばら、梔子、水仙。葵はみたことがない。
聡明でたおやかだけれど、どこかつかみどころのない言動と、あまり恵まれていない生い立ち。それらをまるで重荷に感じない、すこしだけ浮世離れした性格。長くうつくしい黒髪と白い肌をもつ花の名がつけられたヒロインは、作中で幸福を得たり安らぎを感じたりはするものの、大抵、終盤でいなくなる。霧が晴れるように、花が散るように。夢が覚めるように。少女は永遠に、どこにもいなくなってしまう。
古今東西、ひとが死ぬ話も消える話も山ほどある。本を読むことならちいさいころから絶えず続けてきたので、ひとひとりがいなくなる話なんてめずらしくもなんともない、と言いきれるつもりだ。それを作風にしている作家だってすくなくないだろう。
だからわたしは文月さんがぽつりとこぼした「モデル料」という言葉の意味を、ながいことくみ取れずにいたのだ。
なんせ、はじめて言われたのは小学二年生のときだった。無理もない。
「葵、おじさんの書く小説好きなの?」
公園のベンチに腰かけるわたしをぱしゃりと撮り、画面をこちらにみせながら楓お兄ちゃんはたずねた。ほがらかに微笑んでいる画面の中の女の子に反して、わたしの肩はこわばる。
「……きらい、じゃない」
「そっか」画面を自分でもみつめて、少し暗いな、とつぶやきながらなにかのボタンを操作する。わたしの隣で同じく画面を覗いていた瞳お兄ちゃんが、「曲がってる……」と髪にくくりつけたリボンを直してくれた。楓お兄ちゃんはすこし離れたところで、またカメラをかまえる。
「葵ちゃん、あんな分厚い本、読むの難しくない?」
「お前と一緒にしてやるなよ」
「ひどい! 確かに俺はばかだけど……」
瞳お兄ちゃんにばっさりと言い切られた祐樹お兄ちゃんは頬をふくらませて、「でも、葵ちゃんくらいの子が読むものじゃなさそうなのはほんとでしょ」と続ける。膝の上に置いたランドセルの中で、ハードカバーの本が眠っている。この本も読み進めれば、また、花の名の少女がいなくなってしまうのだろう。誰にもどうしようも出来ない不幸を抱えた、誰にもどうしようも出来ない人生。誰にもどうしようも出来ない彼女。
「……る、りょう」
「ん?」楓お兄ちゃんが、わたしの声に反応して顔を向ける。
「モデル料、なんだって。言われたことあるよ」
瞳お兄ちゃんが文月さんの小説を読んでいなくてよかった、と思ったのは、そこに描かれているわたしのような誰かを知らないことに安心したのだ。お兄ちゃんたちがわたしとヒロインの女の子をまぜて考えることは絶対ないのだし、気にするようなことはなかった。それでも、反射的によぎった不安をこらえられなかった。
わたしは笑顔をつくってなんでもなくつぶやいたつもりだったけど、もしかしたらへんな顔をしていたのかもしれない。三人でいるときは常に軽やかな笑顔を浮かべている楓お兄ちゃんが、さっと表情を変えた。リンドウの匂いがぴりっと苦くなって、わたしはランドセルのはしを握る。怒っているようにみえた。
「……ふうん」
楓お兄ちゃんの声は静かで、言葉もみじかくて。
わたしはどうしたらいいのかわからず、じっとうつむいてしまう。祐樹お兄ちゃんがあどけない顔で首をかしげて、「モデル料って、どういうこと……」と瞳お兄ちゃんにたずねている。わたしはなにも言わないまま、朝にみた文月さんの視線を思いだしていた。記憶の中の曇った瞳と目があいそうで、そっとまぶたを閉じる。
物語の中で、何度でも消える花の名の少女。
投影を鮮明に告げられた以上、わたしと無関係には出来ない。
同時に、その行いがどれほどよくないことなのか、わたしにはわからない。
文月さんはわたしを殴らない。いままで一度も、痣が出来るようなことはしなかった。
同時に、要さんに馬乗りにされているわたしのことを、助けずにみつめているときもあった。
恍惚としたような、渇望するようなあの目を、わたしはいつもちょっと憐れに思う。
やさしくない、わけじゃない。
多分、やさしいひとでもない。
それが普通なんだと思う。あるときはやさしくて、あるときは自分本位で、そういうのが人の普通のかたちなんだ。やさしいときの文月さんのことはすきだし、いざ目の前にすると、問題なんてなにもないような気がした。やさしい大人のやさしくない顔が、わたしの生活をつくっているのだから、甘んじるしかない。
わたしだって物語の少女たちのようになげやりになって、人生を放棄すれば、簡単になにもかもを台無しに出来る。物語は何度でも生まれ直すけれど、わたしは一回死ねばそれきりだ。一回、恐怖や苦痛をこらえきれれば終わる。そういった幕引きを選ばなかったのは、死ぬよりいいことがあるかもしれないという夢想をわたしが選んだからだ。夢をみること。きょうよりすてきなあしたを考えること。現実の殴打も視線も帳消しにしてくれないけど、夢に物理的な攻撃力も防御力も求めてはいない。夢をみるだけでも、わたしは十分生きていける。そういうところが文月さんの小説にうまくかみあってしまっただけ、なんだと思う。
――いままでは。
いままでは、ずっと。
まぶたをゆっくりあげると、心配そうな祐樹お兄ちゃんと目があう。眉をさげて「葵ちゃん……」とか細くわたしを呼ぶ声に、自然と口許がほころぶ。
「わたしはぜんぜんへいき」
「でも、そんな、こと……」
答える声がちいさくなって、泣きそうな目元と同じく糸のように細くなっていく。わたしは息をふかくすいこんで、もう一度「ほんとうに、だいじょうぶ」とつぶやく。言葉に力をこめながらランドセルを抱きしめると、瞳お兄ちゃんがだまって手を繋いでくれた。クレマチスの匂いがする。
「もう、わたしじゃないから。だいじょうぶなの」
きょう受けとった小説の中の少女は、前回までの少女たちとなんら変わらなかった。残酷なほど無垢で、透明にもみえる極彩で、恋を持たない。愛ばかりがある。誰もを憎まない。恨まない嫌わない。許すばかりのたおやかな、だからこそいなくなってしまうおんなのこ。
それはわたしじゃない。
明確に感じた。はじめてのことだった。モデル料という言葉の意味を理解してからはじめて、まったく知らない誰かのお話だと思った。読み進めるほど、きっと濃厚に差異を受けとることが出来るだろう。いなくなってしまうその子は、文月さんが罪悪感と空虚にまみれた瞳孔で映したわたしを書いたはずのそれは、わたしじゃない。文月さんにはわからなくても、わたしにはわかる。
わたしはそんなにきれいなおんなのこじゃない。
侵害されたくないものがある。
脅かされたら、ゆるせないと思うものがある。
以前はなかったけど、いまはあるのだ。
文月さんは知らない。
お兄ちゃんたちの話をしたことがないから。
わたしの手を握りつづける瞳お兄ちゃんの指のつめたさも、祐樹お兄ちゃんのまなざしも、首をかたむけながら楓お兄ちゃんがつぶやく「うん」も、文月さんは知らない。わたしがどれだけ三人にこだわって生きているのかも知らない。
描かれる少女は、いまだ透明できれいなままだ。
公園の中を風が吹きぬけて、わたしの髪がぶわりと舞いあがる。空を向く自分の黒い髪を追うように顔をあげると、楓お兄ちゃんがだまってそれを撮った。
ぱしゃ、ぱしゃり。
一瞬が切りぬかれる。
「葵」
「楓お兄ちゃん?」
「今のすげーきれいに撮れたよ。見る?」
「えっ、俺も見たい!」
祐樹お兄ちゃんが真っ先に身を乗りだし、はじけるような笑顔を浮かべる。楓お兄ちゃんはその顔を見て、やわらかく目を細める。まぶしいのでもいつくしむのでもない視線が数瞬祐樹お兄ちゃんの笑顔をなぞって、すぐ、いつものほがらかにほころんだ目元になる。こちらに歩み寄ってきてみせてくれる画面を、瞳お兄ちゃんと祐樹お兄ちゃんと一緒に覗きこむ。
画面の中で拡大された少女が、空を仰ぐように上を向いている。髪とからまって天にのぼるようなリボンが四角い景色をふちどるように舞って、一枚の絵のようだ。
「めちゃくちゃいいだろ? お気に入り」
心底うれしそうな楓お兄ちゃんの表情が、なんだかちょっと照れくさい。
「……アホ面」と瞳お兄ちゃんがつぶやいて、すぐさま祐樹お兄ちゃんがかみつく。わたしは笑った。その間も瞳お兄ちゃんはずっと手を握ってくれていた。
ランドセルの内側にある本のことは、いまはどうでもいい。
百日紅の匂いがすると、わたしはすぐに瞳お兄ちゃんの手を離し、ランドセルを背負って公園をでた。公園の土から整備された住宅街の道に踏み出す間際、ベンチのそばから動かずにわたしを見送ってくれる三人を振り返って、ちいさく手を振る。祐樹お兄ちゃんがひときわうれしそうに笑顔を浮かべて、ぶんぶんと手を振り返した。
道をふたつ曲がったところの塀に、要さんはじっともたれていた。疲れているような青ざめた表情だけれど、整った顔立ちは否応なしに他人を惹きつける。いまも道を歩いていく女性が、要さんの顔に視線を奪われながら歩き去っていった。わたしは目を細める。ばかばかしい、と思う。みためなんて所詮、みためでしかない。
注意深く表情をひきしめて、「要さん」とやさしく声をかける。薄ぼんやりと開いた瞳がわたしを捉えて、「……あぁ」とうめくようにつぶやく。だいぶ早まった夕時の紅い光が、きれいな輪郭線を照らしていた。
「具合がわるいの?」
「いいや、……なんでもない」
「かえろう。眠るなら家のほうがいいよ」
「うん」
要さんはわたしの手を掴んで、歩きだす。どこかこどものような返事からは想像も出来ない、ぎしぎしと骨が軋むほどの力で握ってくる。このひとの力加減の出来なさはいつもだ。痣が残るとすこし動きはにぶくなるけど、いたくもないので、わたしはなにも言わずに引っ張られて歩く。
瞳お兄ちゃんの手はやさしかった。
目を伏せて、歩く。要さんといると、いつだって途方もなくながいように感じられる。時間も道も、呼吸も。
まるで半分死んでいるみたいだ。
手を引かれて、歩くだけの人形。もういないものへ焦がれるための偶像。
家につくと、要さんは乱暴に扉を開けて、投げ捨てるようにわたしを玄関に放りだす。慣れっこなのでだまって立ちあがり、要さんがこれもまたこどものように脱ぎ散らかした靴と、自分の靴をそろえる。まだ睦月は帰っていないらしく、玄関には要さんとわたしの靴しかない。文月さんは天性のひきこもり体質でめったに外出しないから、大抵下駄箱にしまっているままだ。
いまにも死にそうな顔色の要さんは、「寝る」とつぶやいてふらふら奥の部屋に向かう。要さんの自室だけは一階にある。わたしはランドセルを背負ったまま「おやすみ」と無感情に答えて、二階にあがる。階段をのぼりきったところで、声がした。
「おかえり、葵」
「……ただいま」
文月さんが書斎から顔をだして、やんわりと微笑んでいた。持っているマグカップにコーヒーを注いできたところなのだろう。わたしは今朝受けとった本のことも、もちろんお兄ちゃんたちのこともなにも言わない。言わなければわからないから。わからなければ書かれないから。
挨拶だけして書斎に消えていく姿を見届けて、わたしも自分の部屋にはいる。つめたくしんとした白い部屋。紅色のランドセルを床におろして、中から教科書類とハードカバーの本を取りだす。
表紙に描かれた少女の後ろ姿を、指でなぞる。
文月さんの小説が愛情なのか贖罪なのか、わたしにはわからない。
ただ、許せないことじゃない、と思っていた。文月さんの行いはわたしにとっていたくなかったし、なんなら助けてくれるときもあった。要さんのことすら許して生きていけるのに、文月さんのことが許せないはずはない。そう思っていた。
けど、違ったのだ。
許せるのではなくて、わたしは。
どうでもよかっただけ、だった。
文月さんの小説も、要さんの拳も、同級生の態度も、どうでもいいから許せると思いこんでいた。なにもかもをわたしは受けとってすらいなくて、通り抜けていただけなのだ。
夏の終わりにお兄ちゃんたちと出逢って、それらがどうでもよくない、いやなことだと感じると、とたんに世界は息苦しく変貌した。
その嫌悪もまた、急速に薄れはじめている。
わたしは三人がいればそれだけで、ぜんぶどうでもよくなってしまう。気づくと簡単なことだった。わたしはこだわっていないからなにもかもを許せるだけで、いやなことすらどうでもいい。ほんとうに本物の透明な心なんて持っていない。
お兄ちゃんたちに会える時間が、要さんの迎えより文月さんの小説より同級生の態度よりなによりつよく、わたしの世界を占めていた。ほんのすこし一緒にいられれば、その日のぜんぶが花咲くほど、うれしくて楽しい。三人のやさしさにあまえているのをわかってても、いまのわたしは三人といられる自分の人生がすきで、毎日を誇りに思う。だから、ほかのあらゆるものはどうでもいい。傷も痣も言葉も物語も、わたしがこだわるものじゃない。
「……だいじょうぶ」
どんないたみも台無しになるほど、うれしいことがある。
百日紅の匂いがする手に掌を潰されても、きっとわたしは瞳お兄ちゃんの手を憶えている。クレマチスの匂いがする、やさしい感触を。祐樹お兄ちゃんがかけてくれた言葉も、楓お兄ちゃんが撮ってくれた写真も、わたしが憶えている。
だからだいじょうぶ。
何度花の名のおんなのこがいなくなっても。
それはわたしじゃない。
▶もうじき夏が終わるから