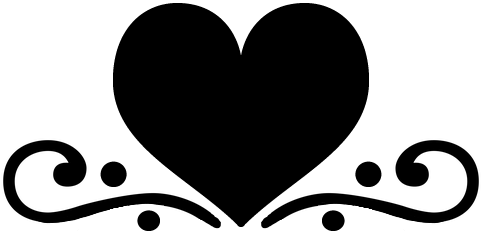
お嬢様の甘い選択
カレンは悩んでいた。この上なく迷っていた。この選択によって運命が決まると言っても過言ではない。
これは、ある種の賭けだ。どちらか一方を選べば、どちらか一方を諦めるしかない。選んでしまえば後戻りすることは出来ない。そう、失敗するわけにはいかないのだ。
「良いからさっさと選べよ」
苦悩するカレンの横から、面倒臭そうな呆れ声が聞こえてきた。その途端にカレンの集中力が霧散する。
「少し黙ってくださいます? わたくしは皆さんに美味しいケーキを持ち帰らなくてはなりませんの!」
「店で売ってんならどれだっておいしいケーキだろ……」
「これだから貴方という人は……よろしいこと? 乙女にとって、ケーキを買うのは重要なミッションですのよ」
ずらりと並ぶケーキ達をズビシッと指差し、カレンは言い切った。
確かにここにあるケーキはどれも全て美味しいに違いない。しかし、残念なことに全てを食べることは出来ない。金銭的な理由ももちろんあるのだが、最大の理由はそんなものではない。
「ケーキを食べれば太る、それが自然の摂理……! だからこそ、時間をかけてじっくりと食べるケーキを選びますの。アルティナは『食べたい、でもたくさん食べると太るから食べられない』という悩ましい乙女のジレンマを分かっていませんわ!」
「そんなの知るか……」
甘い物をたくさん食べたいなんてアルティナは思わない。というか、それ以前に乙女ではない。れっきとした男である。乙女の気持ちを分かれと言われて分かるわけがない。
アルティナは不機嫌に黙り込む。カレンがケーキを選び始めてから、かれこれ10分程は経過した。長時間待たされることはもちろん、ケーキ屋という甘い匂いの立ちこめる店内にいることも彼にとっては苦行だった。そして、チラチラ感じる視線が煩わしい。店には女性しかいない。男である自分は完全に浮いている。全力で帰りたい。
抵抗しか感じないケーキ屋になぜアルティナがいるかと言うと、それもこれも全てカレンのせいだった。
それは、リッカの宿屋へ帰ろうとしていた時のことだ。
カレンとアルティナは不本意にも二人でとあるクエストを引き受けていた。普段いがみ合ってばかりの二人だが――いや、だからこそか、「早く用(クエスト)を済ませて帰りたい」というその気持ちだけはピッタリと一致していた。二人のその思いが通じたのか、クエストは早々とクリア、依頼主から報酬ももらい、宿屋に戻るだけ――になったはずだった。
その帰り道に、カレンが見慣れないケーキ屋を発見するまでは。
「あら、あんなところにケーキ屋さんなんていつの間に……」
「ケーキ屋?」
好奇心に目を輝かせるカレンとは対照的に、アルティナはケーキという単語に顔をしかめる。アルティナは甘い物がどうにも苦手だった。食べられないわけではない。少量ならばどうということはないが、量が多くなってくると話は別だ。
「そうですわ! アルティナ、宿屋の皆様にケーキを買って帰りますわよ。いつもお世話になっておりますもの、それくらいしなくては」
「は?」
「わたくしもちょうど何か食べたいと思っていたところですし……疲れたら甘い物が一番ですわ。ああ、仕事終わりに食べるスイーツはどうしてあんなに美味しく感じるのかしら」
ケーキ屋の方を見ながら、カレンは片方の頬に手を添えてうっとりと呟く。完全に自分の世界に浸っている。当然ながらアルティナはついて行けない。
決定事項のごとく勝手にケーキの購入宣言をしたカレンは、勝手にケーキ屋へ颯爽と向かう。アルティナの意見を聞く気は毛頭無いらしい。
アルティナはアルティナで勝手に帰りたかったのだが――勝手に帰って後から文句を言われるのも面倒だ。仕方が無いので店の外で待機しよう、と考えていたところに数歩先で振り返ったカレンが声をかける。
「そこで何を突っ立っていますのアルティナ、貴方にもいらしてくださいませんと。自分のケーキは自分で選んでくださる? 勝手に決めて後から文句を言われてはかないませんもの」
そんなの別に何でも良いし、何なら自分の分は買わなくても良い――そんなアルティナの内心を見透かしたのか、カレンは目をすっと細めてとどめの一言を加える。
「ちなみに、来ないと言うのならば、アルティナの分のケーキはそこに書いてある『プリンセス・ストロベリーのドレスアップタルト』になりますわ」
カレンは店頭に掲げられた看板を指差す。そこには少女の夢をふんだんに詰め込んだかのような、かわいらしいデコレーションの施されたイチゴタルトの絵が描かれていた。いろいろと思うところはあるが、とりあえず男が食べるにはかなりの勇気を要する一品であることは確実だ。少なくともアルティナは注文しようとは思わない。
「…………」
そのイチゴタルトのあまりにも強烈なメルヘンぶりに、アルティナは呆れを通り越して閉口した。最早何も言うまい。
そんなやりとりを経て、かくしてカレンに強引に店内へ連れてこられたアルティナであった。
挙げ句、乙女の乙女による乙女の為のケーキ選定に付き合わされ、いい加減ゲンナリし始めた頃である。ようやく購入するケーキが決まったらしく、カレンは一人納得したように頷く。
「……決めましたわ、こちらのケーキにいたします!」
季節のフルーツタルトかロールケーキの二者択一で迷っていたのがようやく決まったらしい。正直どっちでも良いと思ったが、それを言うとうるさくなるのは目に見えているのでアルティナは黙っておいた。
そして会計を済ませてようやく外に出ると、カレンはふと気がついたように立ち止まり、呟いた。
「……ケーキといえば美味しいコーヒーか紅茶が必要ですわね。買って帰りましょう」
「は?」
そして、振り出しに戻る。
「……なんてことがありましたのよ」
チョコレートケーキの味を堪能しつつ、カレンは先程の出来事をリタに語った。
「新しいケーキ屋さんかぁ。全然気付かなかったよ」
カレンの買ってきた色とりどりのケーキに、リタは目を輝かせた。カレン同様、リタもケーキをはじめとする甘い物が大好きだ。
宿屋の面々におすそ分けをした後、カレンはリタを、そしてついでにアルティナをティータイムに誘った。
ちなみにレッセはというと、部屋で読書に没頭していたので、近くのテーブルにケーキを置いてそっとしておくことにした。ノックをして部屋に入り、ケーキを置いて外に出る――そんなカレンの一連の行動にレッセが全く気付いていなかったのはさすがというか何というか。
そういうわけで、現在テーブルを囲んでいるのはカレンとリタ、そしてアルティナの三人である。
「あのケーキ屋さん、ちょうどオープンしたばかりらしいですわ。内装も素敵で、いつまでも眺めていたいくらいでしたの」
店内を思い出してか、うっとりとため息をつくカレンだったが、ふとアルティナを一瞥して大げさに肩をすくめた。
「……だというのに、アルティナときましたら、『さっさと選べ』の一点張りでおちおちケーキも選んでいられませんでしたわ」
「場違いとしか思えない店に連れて行かれるこっちの身にもなれ」
割と強制的に店内に連れて行ったくせして文句タラタラなカレンに、アルティナもさすがに物申す。しかもその後にコーヒーと紅茶の店にまで付き合わされた。振り回される側としては堪ったものではない。
「それはまぁ、お願いしたのはこちらですけれど……余裕のない男は嫌われますわよ?」
「余計なお世話だ」
カレンがアルティナに対して何かと口出ししてくるのはいつものことだ。そしてアルティナが「余計なお世話」と切り捨てるのもいつものことである。
「またそんなことをおっしゃって……今後恋人と一緒にケーキ屋へケーキを食べに行くことになりましたらどうしますの。ねぇリタ」
「えっ、私?!」
ご機嫌にフルーツタルトをつついていたリタがパッと顔を上げた。タルトに夢中で今の会話を聞いていなかったらしい。アルティナ相手にささくれ立っていた心が和むのを感じる。リタには是非ともそのままでいて欲しいものだ、とカレンはしみじみ考えた。
「殿方がそのような店に抵抗を感じるのも分からなくはありませんけれど……今後のためにも慣れる必要があるのではないかと、わたくしは声を大にして主張したいのですわ!」
「だからそれが余計なお世話だと言ってるだろうが」
「全く仕方ありませんわねぇ。でしたらそのチーズケーキがケーキ選びに付き合っていただいた分のお礼ということにしてあげますわ」
「何が『仕方ない』だ。だいたいそれもお礼というよりケーキ屋に連れていく口実だっただろうが」
アルティナとカレンのケーキを巡った不毛な言い争いは、しかしリタが口を挟んだことにより終止符を打つこととなる。
「そっか、だからアルはチーズケーキなんだね。アルって結構好きだよね、チーズケーキ」
好きというか、あまり甘くなさそうなケーキを選んだ結果そうなるだけだが、アルティナもチーズケーキが嫌いなわけではないので特に否定はしない。
まれにどうしたと言いたくなるくらい甘いものもあったりはするが、基本的にはサッパリとしていて食べやすい。
今回はあのメルヘンチックなケーキを売る店のチーズケーキなのでどうだろうかと思ったが、一口食べてみたところ甘さ控えめで安心した。
「美味しい?」
「まぁそれなりに」
かなりそっけない感想ではあるものの、ケーキを食べる手は止まっていない。分かりにくいが、アルティナが美味しいと感じている証であることをリタは知っている。
「うぅ〜、いいなぁ。私も次食べる時はチーズケーキにしようかなぁ」
チーズケーキに熱い視線を送り、すでに次回のことを考えるリタを見て、アルティナは口に運ぼうとしたケーキをリタの方へ向けた。リタの目線が一口大のチーズケーキとアルティナの間を行き来する。
「へ……えっと、いいの?」
「早くしないと下に落ちるぞ」
「ま、待って待って!」
慌ててパクリと食べればいわゆる間接キスになるわけだが、リタもアルティナも特に気にしない。というかこの二人には間接キスなど最早今更感しかない、とカレンは思っていたりする。
「チーズケーキもすっごくおいしい〜。アル、ありがとうね〜」
それはそれは幸せそうな笑顔でチーズケーキを頬張るリタに、カレンもつられて頬が緩んだ。
「うふふ、良かったですわねぇリタ」
「うん、疲れた時はやっぱり甘いものが一番だよね!」
ねー、と共感する女子二人にしかしアルティナだけがついて行けない。別に否定はしないし、するつもりもない。ただ、甘いものに対する女子のこだわりに共感出来ないだけで。
とはいえ、こんなに喜ぶのならたまには買って帰っても良いのかもしれない。チーズケーキひと口でとびきりの笑顔を見せる少女を眺めながら、アルティナはふとそんなことを思う。
そして、もう一方のお嬢様はというと――。
ほら買っておいて良かっただろうとでも言うような視線を、カレンはアルティナに向けていた。その勝ち誇ったような表情に、アルティナの眉間にシワが寄る。
「何か文句でもあるか」
「いいえ、別に?」
むしろごちそうさまでした、とカレンは心の中で付け加える。甘いケーキも恋愛も、どちらも乙女の大好物なのである。
カレンは目の前の甘さを堪能しつつ、ティーカップの紅茶を優雅に口へと運ぶ。濃いめに淹れた味は少し渋いくらいだが、お砂糖たっぷりの甘さにはそれくらいが丁度良い。
「悩んだかいがあったというものですわね」
やはり、ケーキを買ってくるのは乙女の大事な使命である。
紅茶片手に、一人呟いたカレンは満足そうに頷いた。
お嬢様の甘い選択(終)
―――――
boundless凪瀬巴さんへ相互記念として捧げます。
長らくお待たせしてしまいまして大変申し訳ありませんでした。
カレンの文ということで、リクエスト承っていたのですが、「あれじゃない、これじゃない」とグルグル考えていましたら月日は無情にも経過してしまいました。相互していただいた日付が怖くて見返すことの出来ない私はクズです←
カレンのゴーイングマイウェイなお嬢様っぷりを発揮して欲しくてこのようなお話になりました。お気に召していただけますと幸いです。逆に気に入らないところなどございましたら遠慮なくお申し付けください。
短編をすぐに仕上げることもままならないダメ管理人ではありますが、これからもどうか仲良くしてくださると嬉しいです。それでは、どうぞよろしくお願いします。