──中島敦は、武装探偵社の新入社員である。
入社を果たしたのはつい此の間で。
同じくつい此の間発覚した、とんでもな自身の事情 を受け入れてくれた探偵社に敦は在籍しているのである。
と云っても此の会社。
入社試験からして真面 とは程遠い場所に在るんだろうなあと、既になんとなく敦は察し始めていたのであった。
否だって、真逆入社試験で命懸けの"度胸試し"をされるとは夢にも思うまい。
そうして今は、敦を拾い探偵社へと招いて──否済し崩しに連れ込んだ?──太宰治其の人の、前職当ての真っ最中で。
一向に当たる素振りもない、と云うか未知数過ぎて予想すら出来ない太宰治と云う人間そのものに、なんだか胡散臭さすら感じていた時だった。
まだ少ない太宰治其の人についての記憶を掘り起こしていた時に、ふと、入社試験の後の光景が脳裏を過ったのだ。
すると其れが如何にも思考に焼き付いてしまって、敦は思考を一旦取り止めて、素直に疑問を其の儘問いかけることにした。
こういう疑問は、とっとと解決させた方がいい。
「──そう云えば、太宰さん先刻 社の中で女の人と親し気にしてましたよね」
「うん?」
「ほら、着物姿の……給仕さん……?」
「……ああ、菫のこと」
──あの人、菫と云うのか。
なんとなく、上品な名前だなと思いつつ。
あの場で明らかに浮いていた格好の女性を思い出し乍ら、敦はちらりと周りの面々の様子を伺った。
敦の周りには、真正面に谷崎ナオミと谷崎潤一郎がいて。そこから右側に、奥から太宰と国木田が座っている。
つまり敦に一番近いのは一人だけ珈琲ではなくお茶を飲んでいる国木田だ。
そうして、そんな国木田はちらりと先程"菫"と口にした太宰のことを伺っていた。
其の様子に、敦は惘乎 としつつも不思議に思っていれば。
そんな国木田の視線など素知らぬ顔で、珈琲を降ろした太宰は、にんまりと笑みを浮かべてこう云ったのである。
「菫は私の妹だよ」
「……えっ! そ、そうなんですか?」
云われた言葉に、一瞬、敦は思考を止めた。
しかしそれもほんの瞬きの間のみで、太宰の言葉を脳内に納め切った敦は其の儘条件反射の様に驚きを口にする。
そんな敦に、太宰はまたも笑うのみ。
──しかし、なんだろうか。
其の横にいる国木田は何処か訝し気な顔をしていて。
真正面のナオミは特に変わった様子を見せないものの、其の隣にいる谷崎も、国木田と同じく何処となくなんとも云えない表情を浮かべている。
其の余りにも微妙な空気に一体なんだと少しばかり警戒しつつ。
敦は、こちらを見てにこにこと笑う太宰に、恐る恐る視線を向けた。
「ふふ、敦君てば。なにをそんなに驚いてるのさ」
「えっいやその、あんまり似てないなーって……」
「そうかい? 結構私たち、似てると思うけれど。ほら髪とか、あれも私と同じで癖っ毛だし」
「ああ、そう云われれば……確かに……?」
──寧ろ髪しか似ていないような?
まだ言葉すら交わしたことのない、妙齢の女性の姿を脳裏で思い描き乍ら敦はそっと疑問を浮かべていく。
と云うか抑も、癖っ毛と云ってはいるが髪そのものも彼女の方が其の"癖"は大分控えめな気すらする。
あと髪色も、彼女は見事な烏の濡れ羽色で、対する太宰はどこか淡くも焦げた茶色だ。
──あれ、思った以上に、共通箇所がないのでは?
なんて深淵を覗きかけている敦に。
思い出したように、太宰はこう声を掛けるのだ。
「因みにだね敦くん。菫の前職も私と同じだよ」
「えっ」
言葉を聞いて、一拍。
そうして頭が真っ白になって、また一拍。
「……、…………! 妹さんと、同じ、職場……!?」
「そうだよ。なぁに、そんなに驚くことじゃないでしょ」
そうのほほんと朗らかに笑う太宰に、しかし敦はいやいやと首を振る。
だって、其の言葉でより一層想像がつかなくなったのである。
此のちゃらんぽらんで心の内が読めない、しかし本気を出せば凄そうな人と、あのしずしずとお茶を運んできた大和撫子然としていた女性が、同じ職。
兄妹で働くと云うのはまあ、目の前の兄妹の例もあるし此のご時世なんら不思議ではないものの、其れが如何にも此の男とあの女性とでは繋がらない。
と云うか先ず兄妹と云う処から不思議でならない。
本当に、今の今まで語られたことは真実なのか?
──なんだか頭が痛くなってきたぞ。
なんてことを思い乍ら、敦は痛む額に手を当てて。
そうして、確認するようにこう問い掛けた。
「……太宰さん今幾つですか」
「自殺盛りの22歳」
「妹さんは」
「花も恥じらう20歳だね」
「探偵社に入社したのは」
「二年前だから、私が20歳で菫は18の頃かな」
「…………」
勤め人でもなく、研究職でもなく、工場労働者でもなく、作家でもなく、役者でもない。
それでいて、妹と同じ職場──?
──駄目だ、全く想像がつかない。
そうぐぬぬ、と呻く敦を余所に、谷崎の携帯に連絡が入った。
如何やら、探偵社の依頼が入ったらしい。
自然とお開きになる空気に、一寸悔しさを感じ乍らも着いていけば。
こそっと敦の横に並んだ谷崎が、こう慰める様に敦に話しかけてきた。
「あの二人、雰囲気もまるで違うし、"本当に兄妹なのか"って探偵社でもよく話題に上がるんだよね」
「へぇ」
それをお前が云うのかと思いつつ、取り敢えず黙って話を聞いておく。
なんたって、もしかしたら小さな処にヒントが隠れているかも知らないし。
まだまだ七十万を諦めていない敦である。
──まぁ、けれどそんな思考回路も。
次の谷崎の一言で、何処かへ飛んでいってしまうのだけれど。
「抑もあの二人、名字からして違うからね」
「えっ!?」
思わず出した大声に、なんだと前を歩いていた国木田が振り替える。
其れになんでもないですと誤魔化して、如何いう事かと無言で谷崎に迫る敦に。
谷崎は、頬をかき苦く笑い乍ら、なんでもなくこう言うのだ。
「彼女の名前は木下菫さん。探偵社の事務員にして給仕であり、専属看護士でもある。太宰さんと同じく過去が一切見えない人で、同じく商典は七十万。何処か浮世離れした品の善い人だよ。うん、たまにアレだけど、善い人だから……。探偵社の事もよく理解してるから、僕が居ない時とかは彼女を頼ると善いかもね」
「はあ……」
──其れはまた、太宰さんとはまるで違うような。
そしてなんか何処と無く、含みがあったような。
なんてことを思うも、谷崎は伝えることは伝えたぞとでも云わんばかりに、敦よりも一歩先に探偵社の中へと入っていってしまう。
そうなってしまえば、もう此の会話は打ちきりにも等しいもので。
嗚呼置いていかれるのは困ると、一番下っ端の敦は勇んで其の背中を追いかけるのであった。
因みに此の後の依頼により、敦は躯を切り裂かれ片足を切り落とされ再生すると云う大怪我からの超回復を体験し。
尚且つ、自分自身に対して七十万だなんて目じゃない、七十億と云う大金が懸けられている事を、敦はなし崩しに知るのだった。
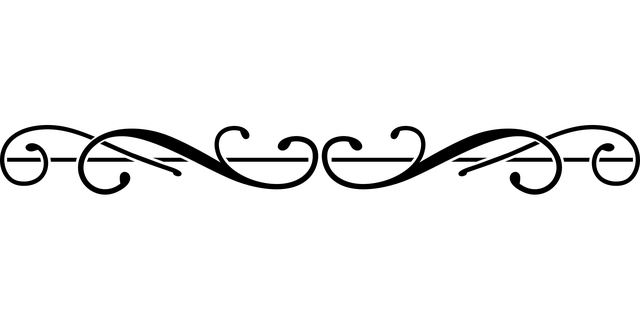
処変わって、探偵社にて。
太宰からの連絡により連れ帰った三人の──否二人の怪我の処置に、今探偵社はてんやわんやであった。
耳を澄まさなくとも聴こえるけたたましい悲鳴が鳴り響く様は、ある意味見事とも云えるもので。
女性だからと丁寧に麻酔剤を処方してから治療 を済ませたナオミの最終チェックを終えて、彼女──菫は今回の功労者へと労いの言葉を掛けに往ったのだった。
「お疲れ様ですお兄様 。素晴らしいご活躍だったそうで」
「まあねぇ。もう気持ち的には色々最悪だけれども! マフィアには逢っちゃうし、気絶してる人間って重いし服もこんなに血塗ろになっちゃったしさ」
「確かに。白昼堂々歩いていれば、うっかり通報されそうな汚れ具合ですわね」
此処は探偵社の資料室兼数ある太宰のサボりスポットのひとつで。
恐らくそろそろ国木田さんが探しに来るのでは、と思い乍らも菫はこそっと持ち込んだお茶菓子とお茶を机に置いていく。
詰まる処は、彼女もサボりだ。
といっても資料室なのにこんな風に椅子と机がある時点で、ぶっちゃけサボりを容認しているようなものだろう。
「それで。マフィアは何方がいらしたの?」
「芥川くんさ。元気そうにしてたよ。まぁ、お前がせっせと肥えさせた頃を思い出すとまた元の骨ガラ に戻ってたけど」
「……そう。折角の体質改善が、水の泡に…………」
──結構時間かけてじっくり遣ったのになぁ。
まあ離れたから仕方ないか、と菫が溜め息を吐いた処で、ふと腰に違和感が。
しかし其れに抵抗する間もなく、ぐい と引き寄せれて。
彼女は只でさえ小さい一人用の椅子に座る兄の膝に、ぽすんと其のお尻を乗せてしまった。
そうして其の儘、ぐりぐりと谷間に顔を埋められる。
「誰かに見られたら確実に事案ですよ。私たち、兄妹 なんですから」
「ん〜〜?事案 なら既に一組居るんだから、別にもう一組増えたっていいじゃない」
「……国木田様の胃に穴が空いちゃいますわよ、もう」
変な体勢の儘だった躯を整えるように、足を持ち上げ太宰の上に横向きに座るように降ろして。
そうして未だに戯れつくように自身に撓垂れ掛る"兄"の髪を指で梳き乍ら、なんとなしに菫は兄の服に触れてみる。
──濡れては、なさそう?
「ちゃんと乾いてるよ。お前の服汚れてないでしょ」
「……だって。血って落ちにくいんですもの」
思考を読まれた事は特に気にせずにしていれば、なにやら大きな物音が。
其の只事ではない物音に、なんだろうと思って菫が身を起こそうとすれば──しかし、背中に回った兄の手によって動きを止められる。
思わず兄を見遣れば、何やら含み顔。
「お前は往かなくていいよ」
「……あら。何故?」
真意がさっぱり掴めない。
そうして其の間にも過激さを増していく騒音に、真逆荒くれ者でも押し入ってきたんじゃないかと被害状況を確かめに往きたいのに、矢っ張り兄は腕を弛めようとはしない。
確かに菫は非戦闘員だけれど、其れ故に探偵社の物品等を管理するのは彼女の仕事なのだ。
其れに探偵社の、特に外回りの面々の実力は指折りつき。
例え荒事中に顔を覗かせ渦中に飛び込んだとしても、彼等は見事に此の身を守ってくれるだろうと云う確信すら菫は持っていた。
其れこそ、今迄だって何度もこういう事はあったのだ。
其の度に出歯亀する彼女の事を、太宰は悪趣味と笑い乍らも止めた事は一度もなかった。
大体が、止めるのは国木田の役目だ。
其れが、此の徹底振り。
此れはもしや、なにかある?と菫は躯を縮めて兄の顔を除き込んで見た。
影の中では真っ黒なのに、光に当たると色素が薄くなる瞳が、菫を見てゆっくりと瞬いている。
「ねぇ、何故なの。教えてくださいな」
そう強請れば、ゆったりと細められる瞳。
相変わらずの毛束の多い睫毛に、ほんと、何度怪我をしても顔だけは綺麗だと菫が感想を浮かべていれば。
そんな彼女の心情を知ってか知らずか、薄く笑い乍ら太宰はまるで悪戯を打ち明ける小さな子供のように、こう囁いたのだ。
「──今、黒蜥蜴 が来ているのさ」
「……!」
黒蜥蜴。
ポート・マフィアの過激で苛烈な実働部隊。
菫の記憶から変わっていないのであれば、確か広津が率いていた隊だった筈だ。
其れが今、武装探偵 社に。
「…………私、此処に居ますわ」
「うん。其れでいい」
躯を正して其の儘ぽすんと太宰に凭れ掛かれば、彼は笑い乍らそう答える。
"其れで"と云っている時点で、其れ以外の回答なんざさせない事は明白だ。
過激で苛烈な黒蜥蜴。
だけれども、正直にいって菫は武装探偵社が遅れを取るとは考えていない。
と云うよりも、実はあんまり異能力者の居ないポート・マフィアよりも、集団的な武力だけで云えば武装探偵社の方が勝ってるとも思っている。
とは云っても、其れも個人の異能力の脅威だけで換算すると結果はまた変わってしまうのだけど。
ポート・マフィアは組織全体の中でも異能力者が少ない分、其の数少ない異能力者たちが凶悪過ぎる。
なんたって、たった一人で数十数百分の"無能力者"の戦闘力を保有してたことを、菫は"外"に出て初めて知ったのだから。
──だけどまあ、そんな物騒なポート・マフィアの中で、黒蜥蜴だなんて前戦隊 は、其の実主力メンバー以外は"捨て駒"だらけの張りぼてだったりするのも確かで。
要は、主力の周りを数で固める事で敵を圧倒 しているのだ。
けれど蓋を開ければ、其の中身は正しく"蜥蜴の尻尾切り"。
詰まりは、主力以外は皆銃弾を放つくらいしか能がない。
だけど其れでも、顔を合わせるのは厄介だ。
なんたって、未だ菫達の存在は、ポート・マフィアにはバレていない筈なのだから。
──こんなに近くにいるのにバレないとは流石に捜査がザル なんじゃないか、と、思わないこともないけれど。
と、いうよりも。
むしろ今は、どっちかって云うと。
「……壁の修理費、以外と嵩みますのよねぇ」
思い出したようにぽつりと呟いた言葉は、我ながら草臥れていると菫は思った。
なんというか、自身の声に哀愁を感じる。
「此の前画鋲の穴を石鹸で塞いでたじゃない。あれでは駄目なのかい?」
「画鋲の穴と銃痕を一緒にしないでくださいな。石鹸なんかで塞いだら、逆に目立ってしまいますわ」
「じゃあ……漆喰 ?」
「……此の前使った残り、まだあったかしら」
倉庫を確認しなければ、と思わず呻けば、何故だか腕の中から笑い声が。
其れに今度はなに?と伺ってみれば、楽しそうに笑う太宰と菫はぱちりと目が合った。
なにやら、とても嬉しそうだ。
「いやぁ、お前も染まった なぁと思ってね」
「……そうかしら?」
「そうだよ。あっち に居た頃は、銃痕なんてあっても誰かに言いつけて終わらせてたでしょう? 自分で直そうだなんて、お前は一度も考えてなかった筈だよ」
──なのに今、お前は"自分で直す"事を真っ先に思い浮かべてる。
そう続ける兄の言葉に、菫はなるほど、と言葉なく呟いた。
確かに云われてみれば、そうかもしれない。
なんたってあの頃は、自分自身も"張りぼて"の権力者だったのだから。
だから確かに。
そう、思うとするならば。
「変わったのかも?」
「変わったんだよ」
ゆるりと、また兄が、太宰が笑みを浮かべる。
其の顔を見て、菫は変わったのはそっちもでしょと思いはするが、其れは特には口にしなかった。
だってなにしろ、此の男は不意にまた悪い顔 を浮かべるのだから。
──でも、変わったのか。
変わることが、出来てしまうのか。
そう思って、菫は瞳を伏せて、太宰の真似をするように惘乎と笑みを浮かべる。
だって、時間というものは、如何やら自分が思っていた以上に物事を変えてしまうようなのだから。
──ポート・マフィアを出て、丸二年。
自分が世界の中心でないことを、彼女はひそりと噛み締めて。
そうして矢っ張り、笑うのだ。
騒音は、いつの間にやら止んでいた。
入社を果たしたのはつい此の間で。
同じくつい此の間発覚した、とんでもな自身の
と云っても此の会社。
入社試験からして
否だって、真逆入社試験で命懸けの"度胸試し"をされるとは夢にも思うまい。
そうして今は、敦を拾い探偵社へと招いて──否済し崩しに連れ込んだ?──太宰治其の人の、前職当ての真っ最中で。
一向に当たる素振りもない、と云うか未知数過ぎて予想すら出来ない太宰治と云う人間そのものに、なんだか胡散臭さすら感じていた時だった。
まだ少ない太宰治其の人についての記憶を掘り起こしていた時に、ふと、入社試験の後の光景が脳裏を過ったのだ。
すると其れが如何にも思考に焼き付いてしまって、敦は思考を一旦取り止めて、素直に疑問を其の儘問いかけることにした。
こういう疑問は、とっとと解決させた方がいい。
「──そう云えば、太宰さん
「うん?」
「ほら、着物姿の……給仕さん……?」
「……ああ、菫のこと」
──あの人、菫と云うのか。
なんとなく、上品な名前だなと思いつつ。
あの場で明らかに浮いていた格好の女性を思い出し乍ら、敦はちらりと周りの面々の様子を伺った。
敦の周りには、真正面に谷崎ナオミと谷崎潤一郎がいて。そこから右側に、奥から太宰と国木田が座っている。
つまり敦に一番近いのは一人だけ珈琲ではなくお茶を飲んでいる国木田だ。
そうして、そんな国木田はちらりと先程"菫"と口にした太宰のことを伺っていた。
其の様子に、敦は
そんな国木田の視線など素知らぬ顔で、珈琲を降ろした太宰は、にんまりと笑みを浮かべてこう云ったのである。
「菫は私の妹だよ」
「……えっ! そ、そうなんですか?」
云われた言葉に、一瞬、敦は思考を止めた。
しかしそれもほんの瞬きの間のみで、太宰の言葉を脳内に納め切った敦は其の儘条件反射の様に驚きを口にする。
そんな敦に、太宰はまたも笑うのみ。
──しかし、なんだろうか。
其の横にいる国木田は何処か訝し気な顔をしていて。
真正面のナオミは特に変わった様子を見せないものの、其の隣にいる谷崎も、国木田と同じく何処となくなんとも云えない表情を浮かべている。
其の余りにも微妙な空気に一体なんだと少しばかり警戒しつつ。
敦は、こちらを見てにこにこと笑う太宰に、恐る恐る視線を向けた。
「ふふ、敦君てば。なにをそんなに驚いてるのさ」
「えっいやその、あんまり似てないなーって……」
「そうかい? 結構私たち、似てると思うけれど。ほら髪とか、あれも私と同じで癖っ毛だし」
「ああ、そう云われれば……確かに……?」
──寧ろ髪しか似ていないような?
まだ言葉すら交わしたことのない、妙齢の女性の姿を脳裏で思い描き乍ら敦はそっと疑問を浮かべていく。
と云うか抑も、癖っ毛と云ってはいるが髪そのものも彼女の方が其の"癖"は大分控えめな気すらする。
あと髪色も、彼女は見事な烏の濡れ羽色で、対する太宰はどこか淡くも焦げた茶色だ。
──あれ、思った以上に、共通箇所がないのでは?
なんて深淵を覗きかけている敦に。
思い出したように、太宰はこう声を掛けるのだ。
「因みにだね敦くん。菫の前職も私と同じだよ」
「えっ」
言葉を聞いて、一拍。
そうして頭が真っ白になって、また一拍。
「……、…………! 妹さんと、同じ、職場……!?」
「そうだよ。なぁに、そんなに驚くことじゃないでしょ」
そうのほほんと朗らかに笑う太宰に、しかし敦はいやいやと首を振る。
だって、其の言葉でより一層想像がつかなくなったのである。
此のちゃらんぽらんで心の内が読めない、しかし本気を出せば凄そうな人と、あのしずしずとお茶を運んできた大和撫子然としていた女性が、同じ職。
兄妹で働くと云うのはまあ、目の前の兄妹の例もあるし此のご時世なんら不思議ではないものの、其れが如何にも此の男とあの女性とでは繋がらない。
と云うか先ず兄妹と云う処から不思議でならない。
本当に、今の今まで語られたことは真実なのか?
──なんだか頭が痛くなってきたぞ。
なんてことを思い乍ら、敦は痛む額に手を当てて。
そうして、確認するようにこう問い掛けた。
「……太宰さん今幾つですか」
「自殺盛りの22歳」
「妹さんは」
「花も恥じらう20歳だね」
「探偵社に入社したのは」
「二年前だから、私が20歳で菫は18の頃かな」
「…………」
勤め人でもなく、研究職でもなく、工場労働者でもなく、作家でもなく、役者でもない。
それでいて、妹と同じ職場──?
──駄目だ、全く想像がつかない。
そうぐぬぬ、と呻く敦を余所に、谷崎の携帯に連絡が入った。
如何やら、探偵社の依頼が入ったらしい。
自然とお開きになる空気に、一寸悔しさを感じ乍らも着いていけば。
こそっと敦の横に並んだ谷崎が、こう慰める様に敦に話しかけてきた。
「あの二人、雰囲気もまるで違うし、"本当に兄妹なのか"って探偵社でもよく話題に上がるんだよね」
「へぇ」
それをお前が云うのかと思いつつ、取り敢えず黙って話を聞いておく。
なんたって、もしかしたら小さな処にヒントが隠れているかも知らないし。
まだまだ七十万を諦めていない敦である。
──まぁ、けれどそんな思考回路も。
次の谷崎の一言で、何処かへ飛んでいってしまうのだけれど。
「抑もあの二人、名字からして違うからね」
「えっ!?」
思わず出した大声に、なんだと前を歩いていた国木田が振り替える。
其れになんでもないですと誤魔化して、如何いう事かと無言で谷崎に迫る敦に。
谷崎は、頬をかき苦く笑い乍ら、なんでもなくこう言うのだ。
「彼女の名前は木下菫さん。探偵社の事務員にして給仕であり、専属看護士でもある。太宰さんと同じく過去が一切見えない人で、同じく商典は七十万。何処か浮世離れした品の善い人だよ。うん、たまにアレだけど、善い人だから……。探偵社の事もよく理解してるから、僕が居ない時とかは彼女を頼ると善いかもね」
「はあ……」
──其れはまた、太宰さんとはまるで違うような。
そしてなんか何処と無く、含みがあったような。
なんてことを思うも、谷崎は伝えることは伝えたぞとでも云わんばかりに、敦よりも一歩先に探偵社の中へと入っていってしまう。
そうなってしまえば、もう此の会話は打ちきりにも等しいもので。
嗚呼置いていかれるのは困ると、一番下っ端の敦は勇んで其の背中を追いかけるのであった。
因みに此の後の依頼により、敦は躯を切り裂かれ片足を切り落とされ再生すると云う大怪我からの超回復を体験し。
尚且つ、自分自身に対して七十万だなんて目じゃない、七十億と云う大金が懸けられている事を、敦はなし崩しに知るのだった。
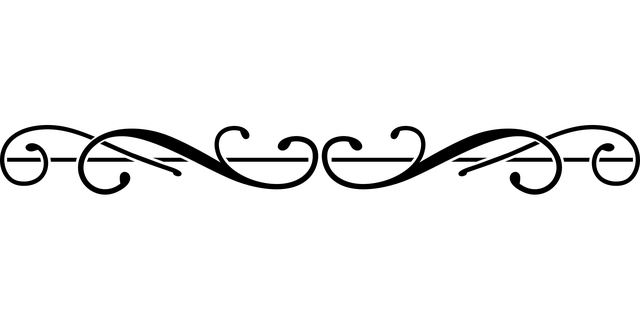
処変わって、探偵社にて。
太宰からの連絡により連れ帰った三人の──否二人の怪我の処置に、今探偵社はてんやわんやであった。
耳を澄まさなくとも聴こえるけたたましい悲鳴が鳴り響く様は、ある意味見事とも云えるもので。
女性だからと丁寧に麻酔剤を処方してから
「お疲れ様です
「まあねぇ。もう気持ち的には色々最悪だけれども! マフィアには逢っちゃうし、気絶してる人間って重いし服もこんなに血塗ろになっちゃったしさ」
「確かに。白昼堂々歩いていれば、うっかり通報されそうな汚れ具合ですわね」
此処は探偵社の資料室兼数ある太宰のサボりスポットのひとつで。
恐らくそろそろ国木田さんが探しに来るのでは、と思い乍らも菫はこそっと持ち込んだお茶菓子とお茶を机に置いていく。
詰まる処は、彼女もサボりだ。
といっても資料室なのにこんな風に椅子と机がある時点で、ぶっちゃけサボりを容認しているようなものだろう。
「それで。マフィアは何方がいらしたの?」
「芥川くんさ。元気そうにしてたよ。まぁ、お前がせっせと肥えさせた頃を思い出すとまた元の
「……そう。折角の体質改善が、水の泡に…………」
──結構時間かけてじっくり遣ったのになぁ。
まあ離れたから仕方ないか、と菫が溜め息を吐いた処で、ふと腰に違和感が。
しかし其れに抵抗する間もなく、
彼女は只でさえ小さい一人用の椅子に座る兄の膝に、ぽすんと其のお尻を乗せてしまった。
そうして其の儘、ぐりぐりと谷間に顔を埋められる。
「誰かに見られたら確実に事案ですよ。私たち、
「ん〜〜?
「……国木田様の胃に穴が空いちゃいますわよ、もう」
変な体勢の儘だった躯を整えるように、足を持ち上げ太宰の上に横向きに座るように降ろして。
そうして未だに戯れつくように自身に撓垂れ掛る"兄"の髪を指で梳き乍ら、なんとなしに菫は兄の服に触れてみる。
──濡れては、なさそう?
「ちゃんと乾いてるよ。お前の服汚れてないでしょ」
「……だって。血って落ちにくいんですもの」
思考を読まれた事は特に気にせずにしていれば、なにやら大きな物音が。
其の只事ではない物音に、なんだろうと思って菫が身を起こそうとすれば──しかし、背中に回った兄の手によって動きを止められる。
思わず兄を見遣れば、何やら含み顔。
「お前は往かなくていいよ」
「……あら。何故?」
真意がさっぱり掴めない。
そうして其の間にも過激さを増していく騒音に、真逆荒くれ者でも押し入ってきたんじゃないかと被害状況を確かめに往きたいのに、矢っ張り兄は腕を弛めようとはしない。
確かに菫は非戦闘員だけれど、其れ故に探偵社の物品等を管理するのは彼女の仕事なのだ。
其れに探偵社の、特に外回りの面々の実力は指折りつき。
例え荒事中に顔を覗かせ渦中に飛び込んだとしても、彼等は見事に此の身を守ってくれるだろうと云う確信すら菫は持っていた。
其れこそ、今迄だって何度もこういう事はあったのだ。
其の度に出歯亀する彼女の事を、太宰は悪趣味と笑い乍らも止めた事は一度もなかった。
大体が、止めるのは国木田の役目だ。
其れが、此の徹底振り。
此れはもしや、なにかある?と菫は躯を縮めて兄の顔を除き込んで見た。
影の中では真っ黒なのに、光に当たると色素が薄くなる瞳が、菫を見てゆっくりと瞬いている。
「ねぇ、何故なの。教えてくださいな」
そう強請れば、ゆったりと細められる瞳。
相変わらずの毛束の多い睫毛に、ほんと、何度怪我をしても顔だけは綺麗だと菫が感想を浮かべていれば。
そんな彼女の心情を知ってか知らずか、薄く笑い乍ら太宰はまるで悪戯を打ち明ける小さな子供のように、こう囁いたのだ。
「──今、
「……!」
黒蜥蜴。
ポート・マフィアの過激で苛烈な実働部隊。
菫の記憶から変わっていないのであれば、確か広津が率いていた隊だった筈だ。
其れが今、武
「…………私、此処に居ますわ」
「うん。其れでいい」
躯を正して其の儘ぽすんと太宰に凭れ掛かれば、彼は笑い乍らそう答える。
"其れで"と云っている時点で、其れ以外の回答なんざさせない事は明白だ。
過激で苛烈な黒蜥蜴。
だけれども、正直にいって菫は武装探偵社が遅れを取るとは考えていない。
と云うよりも、実はあんまり異能力者の居ないポート・マフィアよりも、集団的な武力だけで云えば武装探偵社の方が勝ってるとも思っている。
とは云っても、其れも個人の異能力の脅威だけで換算すると結果はまた変わってしまうのだけど。
ポート・マフィアは組織全体の中でも異能力者が少ない分、其の数少ない異能力者たちが凶悪過ぎる。
なんたって、たった一人で数十数百分の"無能力者"の戦闘力を保有してたことを、菫は"外"に出て初めて知ったのだから。
──だけどまあ、そんな物騒なポート・マフィアの中で、黒蜥蜴だなんて
要は、主力の周りを数で固める事で敵を
けれど蓋を開ければ、其の中身は正しく"蜥蜴の尻尾切り"。
詰まりは、主力以外は皆銃弾を放つくらいしか能がない。
だけど其れでも、顔を合わせるのは厄介だ。
なんたって、未だ菫達の存在は、ポート・マフィアにはバレていない筈なのだから。
──こんなに近くにいるのにバレないとは流石に捜査が
と、いうよりも。
むしろ今は、どっちかって云うと。
「……壁の修理費、以外と嵩みますのよねぇ」
思い出したようにぽつりと呟いた言葉は、我ながら草臥れていると菫は思った。
なんというか、自身の声に哀愁を感じる。
「此の前画鋲の穴を石鹸で塞いでたじゃない。あれでは駄目なのかい?」
「画鋲の穴と銃痕を一緒にしないでくださいな。石鹸なんかで塞いだら、逆に目立ってしまいますわ」
「じゃあ……
「……此の前使った残り、まだあったかしら」
倉庫を確認しなければ、と思わず呻けば、何故だか腕の中から笑い声が。
其れに今度はなに?と伺ってみれば、楽しそうに笑う太宰と菫はぱちりと目が合った。
なにやら、とても嬉しそうだ。
「いやぁ、お前も
「……そうかしら?」
「そうだよ。
──なのに今、お前は"自分で直す"事を真っ先に思い浮かべてる。
そう続ける兄の言葉に、菫はなるほど、と言葉なく呟いた。
確かに云われてみれば、そうかもしれない。
なんたってあの頃は、自分自身も"張りぼて"の権力者だったのだから。
だから確かに。
そう、思うとするならば。
「変わったのかも?」
「変わったんだよ」
ゆるりと、また兄が、太宰が笑みを浮かべる。
其の顔を見て、菫は変わったのはそっちもでしょと思いはするが、其れは特には口にしなかった。
だってなにしろ、此の男は不意にまた
──でも、変わったのか。
変わることが、出来てしまうのか。
そう思って、菫は瞳を伏せて、太宰の真似をするように惘乎と笑みを浮かべる。
だって、時間というものは、如何やら自分が思っていた以上に物事を変えてしまうようなのだから。
──ポート・マフィアを出て、丸二年。
自分が世界の中心でないことを、彼女はひそりと噛み締めて。
そうして矢っ張り、笑うのだ。
騒音は、いつの間にやら止んでいた。