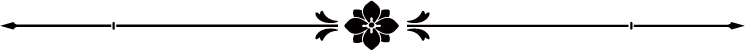花冠をつくりましょう
剣持さんが亡くなった。飲酒運転の車に轢かれた事故だったらしい。病院に運ばれる途中に息を引き取ったのだと。ご家族から会社へ、会社からスタッフへ、そして我々ライバーへと伝えられた。不老不死だと謳っていた彼も、猛スピードで迫り来る鉄の塊には勝てなかったらしい。歳を取らない十六歳ではあったけれど、不死なのは自称だったということだ。
重たい空気が部屋を包み込む。誰もその訃報に口を開けないまま時間だけが過ぎていく。誰も信じられなかった。信じたくなかった。ドッキリ大成功の看板を持って扉からやってくることを、期待した。そうしたら間抜けにも引っかかってしまったと笑ったのに。けれど、彼がそんなタチの悪い冗談を言う人ではないことを、知っている。だからこそ信じたくはなくて。悲しむよりも先に驚きの方が勝ってしまって。結局、何を口にすればいいのかわからなかった。人はこの状態を困惑していると言うのだと、変に冷静な頭が考える。ずっと、おはようございますと彼が顔を出すのを期待している自分がいる。きっとそれは全員が同じだった。その証拠に、誰だって涙を流していない。全員が、扉を見つめている。
嘘だと言ってほしかった。冗談だと笑ってほしかった。何引っかかってるんですか? って、からかうように、人を煽るように笑ってほしかった。誰もが期待して、だけども、絶対に有り得ないことを感じ取っていた。
一番に口を開いたのは、この中で誰よりも先にその報せを知っていたスタッフの一人だった。
「……とりあえず、」
今日はもう、解散にしましょう。
スタッフの言葉に異論を唱える人は誰もいなかった。突然の報せに感情の整理がままならないまま収録や打ち合わせを行うことはできないし、剣持さんがいなくなってしまった今、ROF-MAOというグループをどうするかの話し合いから始めなければいけない。背中にかなしみを背負ったまま、やっぱり誰も口を開けず帰宅することとなった。
次の予定は、まだ決まっていない。
▽
目が覚めたら一面真っ白な場所にいた。
何を言っているかわからないと思うが僕にもわからん。目が覚める前の記憶は曖昧だし、誘拐にしてはあまりにも白すぎる場所にそんなところを探す方が無理だと思う。いやバーチャルだからなんでもありだけれど。
ふと足元を見れば、自分の影がそこにはなかった。地面に立っているのかすら危うい場所で左右を見渡してもなにもない。ただ僕という存在だけが、そこにぽつんと在った。
「どこだここ……」
言葉を発してみても音が反響することはなかった。それだけでこの場所がいかに広いかを知ることができる。無闇矢鱈に動き回るのは得策ではないかもしれない。目印もなにもないのだから、何かあった時同じ場所へと戻ってこれる自信はなかった。
うーん。どうするべきか考えて、首を捻った。
制服を着たままだったのでブレザーをその場に畳んで置く。目印さえあれば、そう遠くまで行かなければ戻ってこれるはずだ。
しばらく歩いて気がついたことは、特になにもなかった。見つかったものさえ存在しない。ただ限りない広さの真っ白な空間であることだけが、改めて知れた現実だった。
目印を元に戻ってきた場所で、特に疲れを感じているわけではないけれど座り込む。考えるのはどうしてこの場所にやってきたのかであって、この場所の存在のことは後回しにした。
連れてこられたのであればきっと僕は抵抗するだろう。顔見知りであればその限りではないが、かといってこういった意味のわからない場所に連れてくるような知り合いはいないはずだ。だとすれば見知らぬ誰かであることはほとんど確定で。そしてそうならば、抵抗しないわけがなくて。抵抗をしたなら衣服は乱れているはずだけれど、その様子は見られなかった。
ますます深まる疑問に、今度はここへ来る直前の出来事を思い出そうと記憶の蓋をこじ開ける。モヤがかかって鮮明には思い出せないが、確か、ROF-MAOとは別の収録のためにスタジオへ行っていたはずだ。無事撮り終えたことははっきりと覚えている。その後――収録後だから、たぶん、日は暮れていた。
暗い夜に、ビル明かりが道を照らす中、一際強い光が、ちかづいてきて、
そして、そして……?
「あ、そっか」
僕は、死んだのか。
▽
簡潔に言うと、ROF-MAOは解散することとなった。当たり前だった。誰か一人欠けた状態で続けるなど、無理な話だった。彼の言っていた通り円満解散とはいかなかったけれど、それでもきっと、いつかはこうなっていたに違いない。彼の訃報はすぐに公式から知らされた。元々配信頻度の少ない彼ではあったが、さすがに一ヶ月と音沙汰がなければリスナーたちも不安に思うことだろう。だからこそすぐに発表された内容に、みな悲しんでいた。彼の同期の人たちは悲しみからしばらく配信を休んだりもしていて、しっかりと乗り越えようとしているのがわかる。悲しむばかりではいけないと、そう思っているのだろう。
ROF-MAOの動画は、貯まっている分をすべて公開するまで続く。全員で話し合って決めたことだった。中にはもう見れないという声だってあったが、それでも、何を言われても、すべて公開すると決めた。それは、ただの悪あがきだった。
長い活動の中でいえば、グループとして活動したのはほんの少しだけだろう。だけど確かに仲は深まっていたし、それなりに情もある。それでも個人の活動を休むことなく続けられているのは、なぜなのか。
ふとひとつのコメントが目に入り、口を閉ざしてしまった。
〝休まなくて大丈夫?〟
画面の中にいる自分の動きすら止まるのが見えた。ただじっとそこだけを見つめている自分が、目の前にいる。そういえば同期の二人からも似たようなメッセージが届いていたような。
大丈夫か、なんて。大丈夫だから今こうして配信を行っているのだろうに。心配される理由はわかるが、でも、だって、己の精神的疲労ぐらいは把握できている。こちとらいい歳した大人なのだから。
「心配をお掛けしてしまってすみません、大丈夫ですよ」
ほかの二人がどうかは、少し確認ができていないけれど。
ああ、そういえば、
「結局、大人にはなれなかったんですよね」
足元になにか軽いものが当たって、顔を俯かせる。すぐ下に落ちていたのは一輪の花だった。濃いピンクのような、見ようによっては赤のような小さな花が一本の茎についている。その花を、僕は見たことがなかった。いやもしかしたらどこかで目にしたことはあるだろうが、少なくとも、記憶からすぐに引っ張り出せるようなものではなかった。
真っ白な空間に、自分以外の色が増えた。綺麗な色だった。だけど僕はその花の名前を知らないし、なぜ今になって突然現れたのか理由もわからない。首を傾げて花を手に取ると、質量を感じないぐらいに軽かった。無重力というわけではないが、花一輪であればこのぐらいだろう。
どこから現れたのかわからない花を手にしたまま、数秒。次は頭になにかが当たる感覚がして、手を添えた。しかしそこにはもう何も無い。振り返るとまた足元に、同じ花が落ちている。それを拾おうとしゃがめば、次は視界の中に堂々と花が映りこんだ。
「なんだなんだ!?」
次々と色を足していく花は、どうやら上から落ちてきているものらしい。休むことなく降り続けた花は、現れたときのように突然ぴたりと止む。足元一面に広がる花を見下ろして、僕は訳も分からず呆然とすることしかできなかった。
「本当になんなんだよいったい……」
▽
グループが解散してからというもの、よりいっそう個人の活動に力を入れることができているかもしれない。あの時間が嫌いだったわけではないし、むしろ大切とすら思っていたけれど、それはそれとして。自分の時間が増えたからこそ休むこともできるし、その分ゆとりだって生まれた。
だから、だから、さあ、
「晴、顔やべーぞ」
そんなことを言われる覚えは、ない。
心配そうにしている彼には悪いが、生活にも心にも幾分か余裕が増えた自分の顔がひどいだなんて、そんなわけないじゃないか。反論しようとして、なんだかめんどくさく感じてやめた。代わりに次の仕事のことをほのめかせばやべ、と慌てた様子で家を出ていく背中は、いつも通りだった。
確かに、たしかに。大先輩で、最初よりも距離が近くなったかもって、そう思ってた人の突然の死に悲しくないわけがない。何も思わないわけがない。これからもずっと続くと思っていたグループ活動が突然の終わりを迎えたことに何も感じなかったわけではない。でも、少なくとも、不破さんや社長よりも人の死の近くに生きている僕は、泣くこともできやしなかった。ほかの二人が泣いたのかは知らないけれど。あれから、あの二人とは顔を合わせていないから。なんとなく、顔を合わせづらく感じているのは、きっと僕だけだ。
これは、ただの後ろめたさだ。
ふぅ、と息を吐き出した。手をつけて長い研究が、ようやっとひと段落するところまで進めることが出来たのだ。これも、集中する時間が長くなったおかげ。
別に、もちさんのせいだとか、おかげだとかは言うつもりは無い。結局僕が研究する時間が増えたことも、個人の活動に力をよりいれることが出来ているのも、ただの結果でしかないのだから。あのままグループが続いていたって、僕は別に良かったのだから。
……悲しくないわけじゃない。だけど、やっぱり、涙を流せるほどのものじゃないんだと。慣れて麻痺してしまった心では、たったひとつの命が消えたところで悲嘆に暮れることはできなかった。
でもほら、
「もちさんだって、泣かなかったし……」
「またかよ……!」
足元に散らばる花はずっとそこに在るままだ。それにも関わらず今度は違う花が宙から落ちてくる。色鮮やかな花の次は、オレンジがかった赤が、中心になるにつれ白へと変化している不思議な花だった。やっぱり僕はこの花を見たことは無いし、知らない。どうしてこの花が落ちているのかも、よくわからなかった。どうせならわかりやすく桜とか梅にしてくれたらいいのに。いや、どちらにせよどうすることもでかないから、なんだっていいんだけれど。
最初の花が埋もれてしまうほど落ちてくる新しい花たち。枯れることを知らないのか、ずっと鮮やかなままだった。広い空間であることは僕が自分の足で確かめているのに、なぜか花が落ちてくるのは自分の周りだけ。どういう理由で落ちてくるのか分からない花に囲まれる時間は、特に面白みもなかった。むしろ困惑が強まるだけである。頭の上に落ちてくる花の衝撃に思わず痛い、と声をこぼしたが、痛みは感じていない。死人に痛覚があるもんか。
自分の死は、思ったよりもあっさりと受け入れていた。まあそんなもんだよな、と思える辺り、あまり生に執着はしていなかったのかもしれない。でもまだやりたいことは沢山あったしなぁ、とは思う。死ぬまでの間で謳歌はしていたが、まだ足りない。足りないが、死んでしまったことに文句を言ったって生き返る訳でもないし。結局、仕方ないよな、で落ち着いてしまう。
そういえば、同期たちは僕の死をどう思ったろうか。尊敬する人たちは? 相方は? 幽霊にもなれぬこの状態で確認するすべは持ち合わせていない。一緒にグループを組んでいた彼らはどうなのだろうか。そもそも、グループはどうなったのだろうか。何も情報を手にすることが出来ないせいで気になることが増えてしまった。
悲しむなよ、とおもう。僕一人が死んだところで悲しんでいたって時間の無駄だろう、と。
だけど、だけどなぁ。
「みーんな無駄に優しいんだからさぁ……」
▽
からん、と空の缶が床をころがっている。どうにも片付けに手をつける気にならなくて放置していたが、中身が空っぽでよかった。
ROF-MAOのメンバーで、何も変わらず過ごしているのは自分だけだという確信があった。というより、個人の配信を覗いた感想とも言う。みんなそれぞれやつれていたり、無理していたりするのが見え隠れしている。たぶんリスナーも気づいてる。ちらほらコメントでも心配する声が見えるが、どれも見ないふりをしているように思えた。
明那に悲しくないの? と聞かれたことがある。たったの一度だけだったけど。それに俺は、笑ってかなしいよ、とこたえた。だって仲のいい人が死んじゃって、悲しくない人間がいるわけが無い。いたとしたら、そいつはよっぽと心のない人間に違いない。でも、かなしいけど。泣くのは違うんちゃうかな、と思う。無理にいつも通りを装うのも違うし、自分を追い詰めるのも違う。俺はあくまで自然体で、いつも通りを過ごしている。
それでいいと思った。それがいいのだと思った。だから、何も変わらない。いつも通りゲームして遊んで配信して、ホストの仕事をして、疲れたら眠る。その生活を崩すことはしなかったし、どれかひとつの時間を大きく取ることもしなかった。
だってさぁ、
「もちさん、望んでないと思うんよな、おれ」
新しい種類の花が落ちてきた。二つ目のものより小ぶりな花は、今までと違って青い色をしていた。三度目を迎えて慣れてしまったせいか、はいはいまたね、と特に気にすることもない。ただやっぱり、一度目や二度目に降ってきた花を覆い被さるように落ちてくるから、そっと場所を開けた。
そういえば、今回の花は見たことがあるかもしれない。どこで見たかも、名前もなにも知らないけれど。
大量の花は既に僕の周りじゃ収まりきらないようになっている。少し歩かなければ色付いた床の端に行けなくなってしまった。誰がこんなに大量の花を確保しているのか、どうやって宙から落としているのかいまだに理解はできない。上を向いてどこから落ちているのか確認しようとしても、すぐに視界いっぱいが花一面となるのだから確認のしようもなかった。
最近は、特に何もすることなく暇を持て余しているせいで、床に転がる枯れない不思議な花を使って手遊びにハマっていた。嫌だって他にやることないし。花と僕以外なにもない真っ白な空間だし。ちょっと女子っぽいかもしれないけど、今の僕にはこれしかやることがないのだから仕方がない。誰かがこの姿を見れば指さして笑いそうなものだけれど、お生憎様、ここには僕一人なので。そのせいで出来上がったお遊びが両手で収まらなくなってしまった。それでもまだ大量に残っているし、なんなら増え続けているのだから上限は無いのだろう。時折、一度落ちてきた花がもう一度落ちてくることもあったし。
誰に渡すわけでもないけれど、随分とつくるのが上手くなってしまった。こんな特技はいらないかもしれない。新しい種類の花でつくろうと手を伸ばした時、急に視界が揺れた。その揺れが睡魔からやってくるものだと理解する前に、まぶたが落ちてくる。
「こんどはなにぃ?」
今までこんなことは無かった。お腹も空かなければ眠たくもならないはずなのに。そもそも死人には必要ないだろうに、どうして、こんな、急に。
青い花を手にしたまま、僕は無理やり意識を落とされた。
図書館にいた。冷房の効いた部屋は心地よく、流れていた汗もかわいていく。種類別に置かれている中、図鑑のゾーンを見つけ出し、ひとつひとつタイトルを確認していく。目的のものを見つけ出した僕は、周りの目を気にせずに一心にその図鑑を読み込んだ。
まず探すのは、赤い花。
造形はしっかりと覚えている。五十音順に並ぶページをパラパラと捲って、目的の花が視界に入った。
「……ぜらにうむ」
まだしっかりと舌が回らずうまく発音が出来ない。しかし、読んだ名前の花は確かにあの時落ちてきたものと一致していた。
次は、中心が白くだんだんとオレンジがかった赤になる花。落ちてきた順に探しているから飛ばしてしまったが、こちらは既に見つけていた。記憶していたページを開けば、そこには予想通り載っている。
「これは、あまりりす」
聞いたことがあるような、ないような。あの花はそんな名前だったのか。
次は、最後。唯一違う色をしていた、あの青い、見たことがあるような花。パラパラとページを捲って見つけた花は、そういえばここへ来る途中にも見ていたかもしれない。
そんな花の名前は、
「おおいぬのふぐり」
全ての花の名前をしっかりと覚えた僕は、図鑑を元の場所へと戻す。司書さんにありがとうございますと言えば、優しく笑って手を振ってくれた。
あの真っ白な空間で花が落ちてきた理由を、僕は知った。知ってしまった。読み聞かせるように祖母が話していたのだ。きっと小さい子どもだと、理解ができないと思っていたのだろうが、残念ながら中身は剣持刀也である。しっかりとその意味を理解して、むず痒い気持ちになったのは記憶に真新しい。
帰宅して母にスマホを借りて、調べてきた花の名前を入力していく。あの場所で、祖母の話していた通りであるならば。花が落ちてきたこと自体ではなくて花言葉の方に意味があると踏んでいる。だって全て別の種類って、そういうことだろ。ひとつひとつ検索をして、花言葉を知って。なんとなく、あれらが誰からの贈り物なのか見当がついてしまった。
ああもう、最悪だ。好奇心は猫をも殺すとは言うけれど、まさかその猫に自分がなるなんて思ってもいなかった。
「――! 大丈夫? どこか痛いの?」
家事をしていた母親が、心配そうに駆け寄ってくる。怪我がないか全身確認するのをどこか遠くで見つめていた。
「どこもいたくないよ」
「じゃあ、どうして泣いてるの?」
泣いているのか、この僕が。
ああ、そうか、そうか。
僕が死んで、何年経ったかはわからない。そもそも異世界やら魔界やらが存在しているのに、同じ世界だとも限らない。
……しくったな。
母親には大丈夫だと伝え、確かに濡れている頬を拭った。これぐらいで泣くなんて、幼子は涙腺が弱すぎないか。もっと頑丈になれよ。頑張れよ。
世界は変わっている。僕が剣持刀也として生きていた世界は既に終わっている。
不老であった僕とは違って正しく歳を重ねる彼らが生きている希望なんてどこにもない。
死んだ僕へ贈り物を届けていた彼らは、きっと、もう、どこにもいない。
――〝生きている人が故人を思い返す時、天国で故人の上から花が降り注ぐ〟
本当かどうかは身をもって知っている。あの場所が天国であるのかどうかはわからないが、花が降り注いだのは、つまりそういうことだろ。
それなら、今度は僕が彼らに贈り物をしようじゃないか。突然落ちてくる大量の花に、困り果ててしまえばいい。
その様子を想像して、涙が止まらないまま笑った。