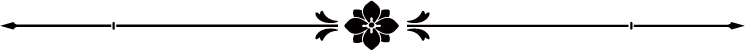うたかたのゆめ
太陽が半分ほど顔を隠して空をあかく染めている。大きいビルの隙間から差し込んだ光が眩しくて剣持は目を細めた。じっとりと湿度を多く含んだ風は気持ち悪く、制服のシャツが肌に張り付いて、剣持は空気を入れ替えるようにシャツを扇ぐ。暑い暑いと言い合う仲間は隣にはいなかった。竹刀の入ったケースが背に引っ付いてそこだけ異様に汗を流していた。夏の大会が終わった。
剣持はまだ二年生だが惜しいところで負けてしまい、お世話になった先輩たちが引退する姿を見るのはつらいものがある。涙を流すことはなかったが、剣持の中にわかだまりが生まれたのもまた事実だった。
実力を認められた者として出場した剣持に残るのは、ただの後悔だった。自分のせい、だとは思わなくても、もっと出来ることはたくさんあったとは思う。少なくともやりようによっては決勝へ行けたはずだった。しかし、悔しそうな顔をしながらもやりきったと言い切る先輩を前に、言葉を口にすることはできなかった。
あれ、と、不意に剣持は足を止める。
どこからか聞こえる歌声は聞き馴染みのある声だった。しかし誰の声だったかは思い出せないまま、足は誘われるように声のする方へ向かっていく。
きちんとした歌詞はないようで、ふふん、と鼻歌の調子で聞こえる歌はなぜか心地よかった。小鳥が囀るような大きさしか聞こえないものの、剣持は声のする方へずんずん進んでいく。場所が分からず左右に何度も曲がり続けても、その歌声はどこにかに留まっているわけではないのかなかなか辿り着くことが出来ない。
やっとここだ、と思えた場所にやってきた剣持はかなりの距離を歩いたような気もするが、実際には路地をひとつ裏手に入っただけだった。
声はだんだん大きくなっていくとともに、剣持はその声をよく知っているものだと認識していく。ただし記憶の限り、この声の主を浮かべることは出来なかった。そこそこ記憶力に自信はあるのだけれど、どうして思い出せないのだろうか。
不思議な感覚に、しかし足が止まることは無い。自分の意識の外で動いているように感じる体は不気味だった。
「……あれ、もちさん?」
歌声が止んだ。
次いで聞こえてきたのは、歌っていた声と同じもの。
こちらに話しかけるような声を発したのは、薄汚い壁に背を持たれかけていた、やけに絢爛豪華な装いをした男だった。白い髪に、ピンクと紫のメッシュが入っていてとても派手。少なくとも、まだ日が沈み切っていない時間帯に出歩くような人物では無い、と思う。
「やっぱもちさんじゃないっすか〜!」
男の言う〝もちさん〟が自分を指しているのだと理解をするのに数秒時間を使う。確かに己の名前に基づいたあだ名であっても違和感は無いだろう。
ただ、剣持は、そう呼んでくる人を知らないだけで。
「えっと、どちら様……?」
剣持にとって目の前の男は、完全に初対面であるはずだった。慣れ親しんだように呼ばれたとしても、その声をなぜか知っていたとしても、剣持は彼の名前を知らないし顔だって見たことは無い。
男が背を離して近づいてくる度に揺れる髪が綺麗だな、と思った。白銀の髪は太陽の光を反射してキラキラと輝いて見える。あまりの眩しさに目を細めていると、ビルの影に入った男から眩しさは消えた。
「ア〜、初めましてぇ、不破湊です」
「はじめまして……」
「部活帰りっすか?」
「……大会終わりです」
「勝った?」
「残念ながら」
「あちゃー、それはしゃーないっすね、うん」
失礼なことを言う男だな、と思った。ベラベラと初対面の男に話した自分も自分だけれど。ただ、彼に言われても特別腹を立てていないことが、自分でも不思議で仕方がなかった。
感情のコントロールは同じ歳の人間に比べてできる方だと自負している。だからきっとここで腹を立てていたって、この場限りだと怒りを顕にすることは無いだろう。しかしそもそもの怒りが湧いてこないのだから、剣持は内心首を傾げるしかなかった。
「まぁそういうこともあるもんで。そろそろ俺は行かんとあかんから行くけど、もちさんも気ぃつけて帰れよ〜」
「ああはい……。あの、ひとつだけ聞いてもいいですか?」
「おん? お兄さんがなんでも答えたりましょ!」
「うた、……歌を、歌っていましたよね?」
「わはは、聞こえてた?」
「まぁ、」
「やー、恥ずかしいな。いやええんやけどね」
「上手いんですね」
そう言えば嬉しそうに笑った彼が口を開いて――剣持は、目を開けた。
耳元で鳴るうるさいアラームをとめて体を起き上がらせる。腕を天井に伸ばしてぐっと力を入れてすぐに脱力すると一気に目が覚めた感覚になった。
(そういえばあの人……、あれ、…………あの人?)
夢を見ていた。
その事実ははっきりと認識しているのに、中身がまるで思い出せない。ほんの数秒前までは覚えていたはずなのにぽっかりと穴が空いたように消えてなくなってしまっていた。まるで泡沫のようだ、なんて。
(らしくもない)
剣持を頭を振って浮かんだ考えを切り捨てた。今日も朝から部活があるのに、そうのんびりはしていられない。薄手のタオルケットを勢いよく剥いだ剣持は、エアコンによって冷やされた床へと足をつけた。